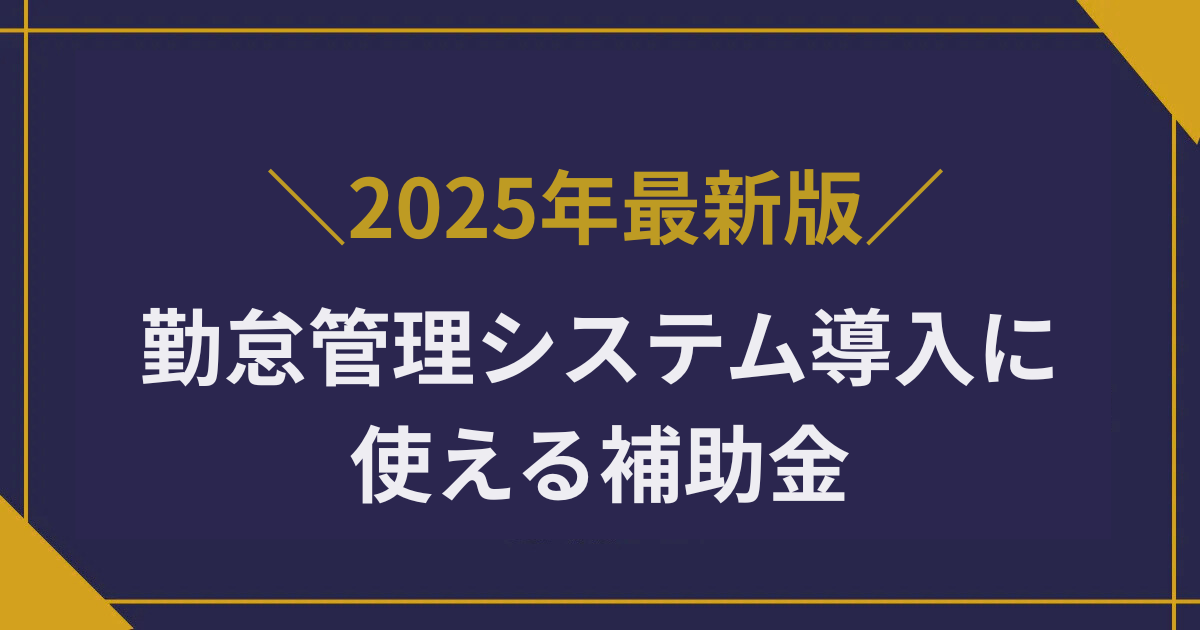働き方改革やリモートワークの普及により、勤怠管理のデジタル化が急速に進んでいます。従来のタイムカードや紙の管理表では、労働時間の正確な把握や法令遵守が難しくなっており、企業にとっては業務効率とリスク管理の両立が課題です。
そこで注目されているのが「勤怠管理システム」です。本記事では、勤怠管理システムの基本から導入メリット、さらに導入時に活用できる補助金・助成金について詳しく解説します。
- 勤怠管理システムとは
- 勤怠管理システム導入で得られるメリット
- 勤怠管理システム導入で使える補助金はIT導入補助金
- 勤怠管理システムで使えるIT導入補助金の基本条件
- 補助金活用の注意点と成功のコツ
- 自社独自の勤怠管理システムを開発する際に使える補助金
- まとめ
勤怠管理システムとは
勤怠管理システムとは従業員の出退勤や休憩時間、残業、休暇申請などの情報をクラウド上で一元管理する仕組みです。ICカードやスマホ、PCログを用いた客観的記録により打刻の正確性を高め、就業規則や各種労働時間制度に基づく自動集計を実現します。
承認ワークフローやアラート機能を備え、未打刻や36協定超過の兆候を可視化し、給与計算ソフトとの連携で転記ミスと作業時間を削減できます。多拠点やテレワークにも対応し、リアルタイムで労働実態を把握できる点が強みといえます。
導入の目的は工数削減だけにとどまりません。法令遵守の担保、労務トラブル予防、人的資源の最適配置、長時間労働の抑制と健康配慮など、経営課題の解決に直結します。次項では導入効果をコスト、コンプライアンス、データ活用の観点から整理します。
勤怠管理システム導入で得られるメリット

勤怠のデジタル化は現場と管理部門双方の負担を軽くし、精度とスピードを同時に引き上げます。紙やエクセル運用で発生していた集計や照合作業、差し戻し対応を自動化し、締め処理のリードタイムを短縮します。
さらに客観記録による実態把握は是正措置の迅速化にも資するため、労務リスクとコストの同時低減が可能です。以下で主要な効果を3点に分けて解説します。
コスト削減と業務効率化
申請から承認、集計、給与連携までをワンフロー化することで、人手に依存した転記やダブルチェックを大幅に削減できます。シフトや変形労働時間制、フレックスタイム制といった複雑な制度にも自動対応し、締め日変更や月跨ぎ勤務の計算も安定運用できます。
未打刻や乖離値の自動検知で差分確認が速まり、問い合わせ往復が減少します。ワークフローの電子化により紙コストや保管費用も抑制され、監査時は検索とエクスポートで証跡提示が迅速になります。結果として締め処理の短縮、残業抑制、間接部門の工数圧縮が重なり、総コストの最適化につながります。
法令遵守と労務リスクの低減
労働時間の客観的把握はガイドラインに適合し、残業上限や割増賃金計算の誤りを防ぎます。36協定や就業規則の条件をシステムに反映すれば、超過の予兆段階でアラートが発動し、管理者と本人が即時対応できます。
年5日の年休取得管理や勤務間インターバル、育児介護関連の制限勤務などもルール化でき、制度運用の抜け漏れを抑えます。改正対応はクラウド更新で反映されやすく、法改正のたびに手作業で帳票や計算式を直す負担を減らせます。証跡が整備されることで労使紛争時の説明責任を果たしやすく、監督署対応や監査リスクの軽減にも寄与します。
データ活用による経営判断のスピード化
打刻と申請のデータは人員配置や要員計画の精度を引き上げます。部署別や職種別の稼働状況、繁閑差、残業の発生源をダッシュボードで可視化し、要因分析に基づく配置転換やシフト最適化が可能になります。プロジェクト別工数を紐付ければ採算性の早期把握が進み、見込み残業の見直しや原価管理の改善に結びつきます。
拠点横断の指標を定点観測し、異常値やトレンドを早期検知できるため、労務是正や人員補充の意思決定が迅速になります。勤怠データは採用計画や教育投資の根拠にもなり、人的資本の開示準備や生産性指標の継続改善に役立ちます。
勤怠管理システム導入で使える補助金はIT導入補助金

勤怠管理システムの導入には一定のコストがかかりますが、国や自治体の補助金・助成金を活用すれば費用負担を大幅に軽減できます。ここでは、代表的な3つの制度を紹介します。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がデジタル化や業務効率化を進めるためのITツール導入を支援する制度です。勤怠管理システムや会計ソフト、受発注システムなどの導入費用が対象となり、クラウド利用料やサポート費用も補助されます。申請には、事務局に登録された「IT導入支援事業者」と連携して進めることが必要です。
補助枠には通常枠のほか、インボイス対応類型やセキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠などがあり、目的に応じて選択できます。補助率は最大で2分の1から3分の2程度となり、採択後に導入・実績報告を経て補助金が交付されます。
勤怠管理システムで使えるIT導入補助金の基本条件
勤怠管理のデジタル化を進める中小企業にとって、IT導入補助金は費用負担を抑えて導入効果を高める有力な選択肢です。対象ツールや申請要件は枠ごとに異なるため、公募要領を踏まえて自社の課題と合致させる設計が重要になります。以下では制度の要点を整理し、勤怠管理システム導入時に押さえるべき条件を解説します。
IT導入補助金とは
IT導入補助金は中小企業・小規模事業者の生産性向上を目的に、業務効率化やDXに資するITツール導入費を支援する制度です。勤怠管理システムを含むソフトウェアやクラウドサービス、導入時のサポート費等が対象となり、原則として事務局に登録されたITツールを選定します。
申請者は事務局登録のIT導入支援事業者と連携し、課題整理から導入・効果検証まで一体で進めます。枠は通常枠に加え、インボイス対応類型や電子取引類型、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠があり、目的に応じた選択が可能です。
補助率・補助額
補助率・上限額は申請枠や経費区分で変動します。一般にソフトウェアやクラウド利用料、導入支援費用が対象となり、補助率は枠により1/2〜2/3以内の範囲で設定されます。複数年分のクラウド利用料が対象となる類型もあり、勤怠管理のように継続利用が前提のツールでは費用対効果の観点で有利に働きます。
上限額は公募回や類型で異なるため、最新の公募要領で上限と対象経費の細目を必ず確認します。加点要素の活用で採択性が高まるため、賃上げ計画やクラウドツール選定などの要件整備が有効です。
補助対象者
対象は国内で事業を営む中小企業・小規模事業者で、業種ごとに資本金または従業員数のいずれかが基準以下であることが条件です。医療法人や社会福祉法人、学校法人等も所定の従業員規模内で対象になります。勤怠管理システムの導入は多くの業種で汎用性が高く、店舗・現場・本社が分散する事業形態でも効果が期待できます。
自社が対象か不明な場合は、業種分類と組織形態に応じた基準表で確認し、グレーゾーンはIT導入支援事業者と照合します。複数拠点を持つ企業は全社の従業員数で判定される点に留意します。
申請の流れとスケジュール
申請は①公募要領の熟読②GビズIDプライムの取得③SECURITYACTION宣言④IT導入支援事業者とツール選定⑤共同で交付申請書作成⑥審査・交付決定⑦導入・実績報告という順序で進みます。特にGビズIDは発行に日数を要し、SECURITYACTIONは宣言IDの取得が必要なため、早期着手が必須です。
申請書では勤怠管理導入による工数削減や法令遵守強化の数値目標を設定し、導入後の運用体制とデータ活用計画まで具体化します。公募は回次制のため、締切逆算で見積・要件定義・必要証憑の準備を進め、採択後はスケジュールに沿って納品・検収・支払い・実績報告を漏れなく行います。
補助金活用の注意点と成功のコツ

勤怠管理システム導入時に補助金や助成金を活用することで、費用負担を抑えながらDXを進めることができます。しかし、補助金申請には多くの条件や注意点があり、正しい手順を踏まなければ採択されないケースも少なくありません。ここでは、失敗を防ぎ採択率を高めるための実践的ポイントを解説します。
補助金対象外となるケース
まず注意すべきは、補助対象外となるケースです。補助金の多くは「新規導入」を前提としており、既に導入済みシステムの更新や保守契約の継続費用は対象外となります。また、業務効率化と関連しない汎用的な機器やソフトウェア(例:PC購入、オフィス家具など)も対象外です。さらに、導入目的が曖昧で生産性向上の効果が示されていない場合や、事業計画の根拠資料が不足している場合も不採択となる傾向があります。
見積書や契約書の不備、経費区分の誤り、スケジュール未遵守も多い失敗例です。制度ごとに対象経費や要件が細かく定義されているため、事前に公募要領を熟読し、自社の導入計画が該当するかを確認することが重要です。
採択率を高めるポイント
採択率を上げるためには、単なる「システム導入」ではなく「経営課題の解決策」としての位置づけを明確にすることが鍵です。勤怠管理システムによってどのように労働時間の削減、生産性向上、法令遵守が実現するのかを数値で示すと説得力が高まります。例えば「集計時間を月20時間削減」「残業時間を15%削減」など、定量的な効果を設定しましょう。
また、賃上げ計画や働き方改革への取組を事業計画に盛り込むと加点対象となるケースもあります。さらに、クラウド型ツールの選定やセキュリティ対策の実施は審査評価を高める要素です。申請書は形式的な記載ではなく、課題・目標・手段・効果の一貫性を意識して構成することで、審査官に伝わりやすい内容になります。
コンサルタントを活用した申請サポート
補助金申請は書類量が多く、制度ごとに要件が複雑です。そのため、経験豊富な補助金コンサルタントや認定支援機関のサポートを受けることで成功率を大幅に高められます。特にIT導入補助金や働き方改革推進支援助成金は、過去の採択実績や最新の審査傾向を把握している専門家の助言が有効です。
コンサルタントは書類作成の代行だけでなく、経営課題に沿った導入効果の定量化やスケジュール設計、採択後の報告手続きまで一貫して支援します。
採択率の高い申請書は、制度要件を満たすだけでなく、補助金を活用して企業の成長を実現するストーリー性を備えています。専門家と連携しながら、制度の特性を理解した上で戦略的に申請を進めることが、補助金活用成功の最大の近道です。
自社独自の勤怠管理システムを開発する際に使える補助金
自社の就業形態や管理体制に合わせた独自の勤怠管理システムを開発する場合も、補助金の活用が可能です。標準的なクラウドサービスでは対応できない機能や連携を実現するための開発費を支援する制度として、中小企業省力化投資補助金や経営基盤強化事業(一般コース)が利用できます。
中小企業省力化投資補助金(一般型)
中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足を解消し生産性を高めるために、IoT機器や勤怠管理システムなどの省力化設備導入を支援する制度です。補助上限額は従業員5人以下で750万円、101人以上で最大8,000万円(大幅な賃上げを行う場合は1億円)まで引き上げ可能です。
補助率は中小企業が1/2、小規模・再生事業者は2/3で、1,500万円を超える部分は1/3となります。設備導入やシステム構築費を中心に、クラウド利用費や専門家経費も対象です。

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)は、ポストコロナなど社会情勢の変化に対応し、中小企業が自社の強みを活かして経営基盤を強化する取組を支援する制度です。既存事業の「深化」では品質向上や高性能設備導入、「発展」では新商品・新サービス開発などが対象となります。
助成率は原則3分の2以内で、賃上げ計画を実施した場合は最大4分の3、小規模事業者は5分の4まで拡大されます。助成上限は800万円で、機械装置費やシステム導入費、専門家指導費など幅広い経費が対象です。申請は電子システム「Jグランツ」から行い、GビズIDの事前取得が必要となります。

まとめ
勤怠管理システムの導入は、業務効率化だけでなく、法令遵守や経営改善にもつながる重要な取り組みです。さらに、国や自治体の補助金・助成金を活用することで、コストを抑えながら導入が可能になります。
「IT導入補助金」や「働き方改革推進支援助成金」など、条件を満たせば高い補助率で支援を受けられるため、まずは自社の状況に合った制度を確認しましょう。適切な準備と専門家のサポートにより、勤怠管理のDXを実現することができます。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。