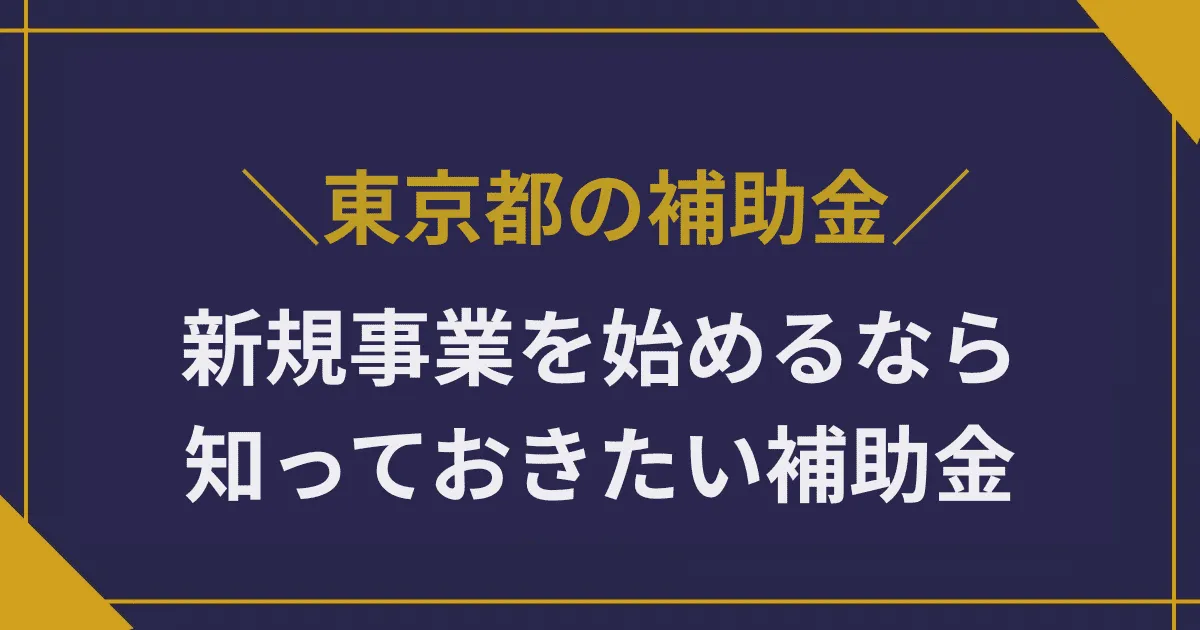補助金は、主に設備投資やシステム開発投資を促進する目的として、事業者が行う「事業」を支援するものです。返済不要である点が大きな特徴で、創業初期の資金繰りや成長の後押しにつながります。
一方で、東京都が提供する「助成金」は、この補助金と同様の性質を持ちながら、地域や分野ごとの特色に応じた制度が多く用意されています。つまり、国の補助金とは別に、東京都独自の支援を活用できるのです。
東京都内で新たに事業を立ち上げる場合、自己資金だけでは設備投資や人材確保に制約が生じることも少なくありません。そのような場面で心強いのが、これらの補助金・助成金です。本記事では、東京都で申請できる助成金を中心に解説します。仕組みを正しく理解し、適切に申請することで、事業のスタートをより有利に進められるでしょう。
- 東京都の新規事業補助金とは?
- 東京都で活用できる主な新規事業補助金
- 新規事業で補助金を活用するメリット
- 新規事業で補助金を活用する際の注意点
- 東京都の新規事業補助金を選ぶポイント
- 補助金の申請手順とスケジュール
- 補助金申請を成功させるための相談先
- まとめ
東京都の新規事業補助金とは?

東京都で新規事業を始める場合、補助金や助成金を理解しておくことは資金戦略上の大きなポイントです。返済不要の資金であるため、資金繰りの安定化に直結します。まずは補助金と助成金の違いを整理し、東京都が支援を強化している理由を確認していきましょう。
補助金と助成金の違いを理解する
補助金と助成金は同じように見えても、性質や運用の仕組みが異なります。補助金は主にシステム開発投資や設備投資を後押しする目的です。採択件数が限られており、審査を経て選ばれた事業者だけが受給できます。
助成金は厚生労働省系の制度で多く用いられ、雇用や働き方の改善に関連する取り組みに対して支払われることが特徴です。採択枠に余裕がある場合も多く、条件を満たせば受給できる可能性が高くなります。
東京都では、創業支援の文脈で展開される制度をまとめて「助成事業」と呼ぶことが一般的です。どちらも返済不要である点が魅力であり、事業資金の確保や初期負担の軽減に直結します。違いを理解したうえで、自社の状況に最適な制度を選択することが成功への第一歩です。
東京都が新規事業を支援する背景
東京都が新規事業支援に注力する背景には、地域経済と雇用の活性化という明確な狙いがあります。全国的に見ると、日本の開業率は欧米諸国と比較して低く、新しい雇用や産業の創出に課題があります。既存企業だけでは人口減少や社会構造の変化に対応しきれないため、若い企業やスタートアップの育成が欠かせません。
さらに、東京は国内外の資本や人材が集まる中心地であり、新規事業が生まれやすい環境を整備することが都市の競争力向上にもつながります。助成事業や補助金は、こうした背景を踏まえた政策の一環として用意されています。
創業助成事業では、賃借料や広告費、人件費、専門家指導料など、創業期に発生しやすい経費を対象としており、資金調達のハードルを下げることができるでしょう。また、商店街起業支援では地域商業の再生を目指し、空き店舗の活用や商店街の活性化も同時に進められます。
支援制度を理解して活用することで、東京都での新規事業はより現実的かつ持続的な成長を期待できるでしょう。
東京都で活用できる主な新規事業補助金
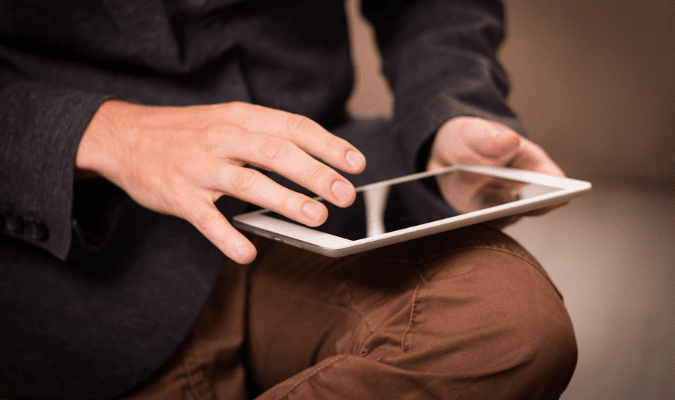
東京都には、新規事業を後押しするための補助金や助成金が複数存在します。それぞれ対象者や対象経費、助成率が異なり、適用できる制度を正しく選ぶことが重要です。ここでは主要な補助金の内容を整理し、特徴や活用のポイントを確認していきましょう。
創業助成事業
創業助成事業は、東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する代表的な創業支援制度です。創業予定の個人や、創業から5年未満の中小企業を対象とし、創業初期に必要な経費の一部を助成します。
対象となる経費には、オフィスや店舗の賃借料、広告宣伝費、従業員人件費、器具備品購入費、産業財産権の出願費用、専門家指導費、そして市場調査・分析費が含まれます。助成率は2/3以内で、最大400万円です。
商店街起業・承継支援事業
商店街起業・承継支援事業は、都内商店街の活性化を目的として新規開業や事業承継を支援する制度です。対象となるのは、都内の商店街で新たに店舗を開業する個人事業主や法人、または既存店舗の承継を行う事業者です。
助成対象となる経費には、店舗改装費、内外装工事費、設備導入費、看板や広告費、必要に応じた専門家指導料などが含まれます。助成金額は事業内容によって異なりますが、初期投資の負担を軽減できる点が大きな利点です。
さらに、申請には商店街内での専従体制が求められ、採択後は定期的な報告や実績確認も行われます。商店街の空き店舗解消や地域の回遊性向上にも直結する事業であり、地域に根ざした店舗経営を目指す起業者に適しています。
スケジュールに沿って申請書類を整え、面接審査を通過することで、開業準備を加速させることができるでしょう。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、東京都が実施する起業家育成支援の一つであり、39歳以下の男性または女性起業者が対象です。とくに商店街での新規開業や新たなサービス展開を支援することを目的としており、地域商業の活性化にも寄与します。
助成対象となる経費には、店舗の内外装工事費、設備購入費、広告宣伝費、デザイン費用、専門家への相談費用などが含まれます。助成金の上限は事業計画や対象経費により変動しますが、創業初期の資金負担を大幅に軽減する効果が期待できるでしょう。
申請にあたっては、開業予定地の選定や事業計画書の完成度が審査に直結します。採択後は助成金の交付だけでなく、商店街連携イベントや販促活動の機会を得られる場合もあり、経営基盤の強化に直結します。
新製品・新技術開発助成事業
東京都中小企業振興公社が実施する新製品・新技術開発助成事業は、都内に拠点を持つ中小企業や個人事業主が新たに開発する製品・技術に対して、開発費用の一部を支援する制度です。
対象となるのは、独自性や市場性のある新規技術や製品の開発であり、試作、設計、検査、外注費、設備費、原材料費、特許関連費用など多岐にわたる経費が対象とされています。支援額は最大2,500万円で、助成率は2分の1以内に設定されており、採択されれば高額な研究開発費の一部を補うことが可能です。
ただし、助成対象は既に製品化されていないアイデア段階の技術開発に限られ、過去に同種の支援を受けている場合は対象外となることがあります。加えて、技術の完成度や社会的な波及効果、収益化の見込みなどが審査で重視されるため、申請には具体性のある開発計画と事業実施能力の証明が不可欠です。
先進的な取り組みで競争力を高めたい事業者には、有効な資金支援となり得ます。
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)
東京都では、経営環境の急激な変化に直面する中小企業を支援するため、「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)」を設けています。この制度は、既存事業の見直しや業務改革を進める企業を対象に、経営の安定化と発展を目的とした取り組みに助成を行うものです。
たとえば、設備の入れ替えによる生産性向上、デジタル化への対応、販路の多角化、業務改善や働き方改革などが対象になります。助成金額は最大800万円で、通常の助成率は3分の2以内です。
ただし、都の定める賃上げ計画を実施することで、助成率は4分の3または5分の4まで引き上げることができます。法人の場合は都内に本店または支店を有すること、個人事業主は都内に納税地があることが要件です。
応募は通年で受付されていますが、予算上限に達した時点で締切となりますので、早めの準備が推奨されます。
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(小規模事業者向けアシストコース)
東京都が展開する「小規模事業者向けアシストコース」は、事業環境の急激な変化に適応しようとする小規模企業の取り組みを後押しする制度です。既存事業の「深化」や「発展」に取り組む企業が、業務の効率化や生産性向上を目的として行う設備導入やシステム改修に対し、最大200万円の助成が受けられる点が特徴です。
助成率は原則3分の2以内ですが、賃金引上げ計画を策定・実行した場合は5分の4まで引き上げられます。対象経費には、機械装置・工具器具費、設備等導入費、システム等導入費などが含まれます。
申請にはGビズIDプライムの取得が必須で、申請手続きはJグランツ上で完結します。募集期間は年間で複数回設定されており、各回ごとに定められたスケジュールに従って申し込みが可能です。先着順ではないため、期間内での準備が重要です。過去に同様の支援を受けた事業者が再度申請することはできないため、要件をよく確認する必要があります。
新規事業で補助金を活用するメリット

新規事業の立ち上げには、設備投資や人材確保、販促活動など多くの費用が発生します。補助金を上手に活用すると、資金面の負担を減らしながら、事業の成長を加速させることが可能です。ここでは補助金を活用する3つの主なメリットを整理します。
初期費用の負担を大幅に軽減できる
新規事業を開始する際には、オフィスや店舗の賃借料、内装費、設備購入費、人材採用費、広告宣伝費など、多岐にわたる初期費用が発生します。補助金を活用すると、こうした費用の一部を公的資金でまかなえるため、自己資金の消耗を抑えることが可能です。
資金面に余裕が生まれれば、開業後の運転資金に回せる割合が増え、事業継続の安定性が向上します。さらに、余剰資金を成長投資に充てることで、競合に対する優位性を早期に確立することも可能です。補助金は後払いが基本となるため、一時的に立て替えが必要になるものの、返済不要であることが大きな魅力です。
採択された場合には、経費精算と実績報告を通じて、計画的に補助金を受け取ることができます。初期費用の負担軽減は、資金不足による事業断念のリスクを下げ、挑戦の幅を広げる手段として非常に有効です。
返済不要で資金繰りの安定につながる
金融機関からの融資は、返済義務が伴うため、売上の変動が大きい創業期には資金繰りの圧迫要因となることがあります。補助金は返済不要であるため、収益が安定する前でも経営を支える強力な資金源となります。
毎月の返済負担が発生しないことで、売上の上下動があっても資金繰りに余裕が生まれるでしょう。資金の自由度が高まれば、販路拡大や商品開発、人材育成など、攻めの投資にも着手しやすくなります。さらに、補助金を受給すると、自己資本比率の改善や金融機関からの信用向上にも寄与します。
事業の持続性が高まることで、追加融資や他の支援制度へのアクセスも容易になるでしょう。資金面の安定は、新規事業の成長だけでなく、長期的な経営基盤の構築にも直結します。返済負担のない資金を得られることは、創業者にとって大きな安心材料となるでしょう。
事業計画のブラッシュアップにも役立つ
補助金の申請では、事業計画書や収支予測を精緻に作り込むことが必要です。この過程を通じて、事業内容の整理や収益モデルの検証を行うことができ、結果として事業計画の質が高まります。
採択を目指すためには、事業の独自性や市場性、成長性を明確に示す必要があるため、自然と計画の完成度が上がります。計画を第三者の目線で評価してもらう機会も得られるため、改善点や潜在的なリスクに気づきやすくなる点も利点です。
さらに、精緻な事業計画は金融機関からの融資や投資家への説明資料としても活用できます。補助金申請の経験を通じて、自社のビジネスモデルを論理的に説明できる状態になれば、資金調達やパートナー獲得にも有利です。資金支援を受けるだけでなく、事業運営全体の質を底上げする効果が期待できるため、補助金活用は計画力強化にも直結します。
新規事業で補助金を活用する際の注意点
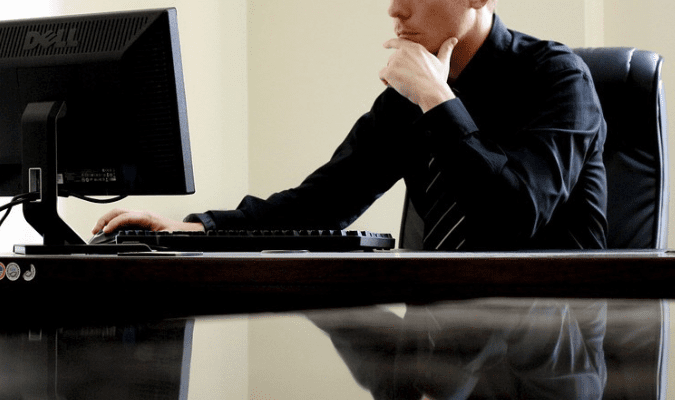
補助金は新規事業の力強い支援策となりますが、活用には複数の注意点があります。申請書作成や対象経費の管理、採択後の対応などを誤ると、受給できなかったり返還を求められたりする場合があります。事業を円滑に進めるためには、事前の準備と制度理解が不可欠です。ここでは、補助金利用時にとくに注意すべきポイントを整理します。
申請要件と対象経費を事前に確認する
補助金を申請する際には、対象となる事業者や経費の条件を正確に把握する必要があります。対象外の経費を計上すると、不備として申請が受理されない場合があります。
たとえば、創業助成事業では賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権の出願費用、従業員人件費、市場調査費などが対象となりますが、私的利用や交際費、申請前に発生した費用は認められません。また、対象者要件として、創業から5年未満や特定の創業支援事業の利用実績などが求められます。
条件を満たさずに申請すると、時間と労力が無駄になります。申請前には、募集要項や公式サイトを熟読し、自社の事業内容や経費が適合しているかを確認しましょう。必要に応じて、専門家や支援機関への相談も有効です。事前確認を徹底することが、採択への第一歩となります。
採択後は実績報告や事後対応が必要になる
補助金は採択された後も、交付までに複数の手続きが必要です。経費を支出した後には領収書や契約書、振込記録などの証憑を整理し、実績報告書として提出しなければなりません。報告内容に誤りがあると、支給が遅れたり、場合によっては助成金の一部返還が求められることもあります。
さらに、補助金は後払い方式が多いため、一時的に自己資金で立て替える必要が生じます。資金計画を立てずに事業を進めると、キャッシュフローが圧迫されるリスクもあるでしょう。事後対応では、経費の適正使用だけでなく、期限内の報告や証憑管理も重要です。
採択後に気を緩めず、計画的に手続きを進めることで、補助金を確実に受給し、事業成長につなげられます。
申請準備は早めに開始し、専門家活用も検討する
補助金申請は書類作成に時間がかかり、必要資料の準備も煩雑です。申請書や事業計画書の完成度が採択の可否を左右するため、早めの準備がポイントです。
募集開始直前に取りかかると、情報収集や計画の精査が不十分になり、採択率が低下するリスクがあります。とくに創業助成事業のように申請要件に創業支援事業の利用実績が含まれる場合、事前に数カ月以上の準備期間が必要です。
また、採択率を高めるために、認定支援機関や行政書士などの専門家に相談することも効果的です。第三者の視点で計画を確認してもらうことで、説得力のある申請書に仕上がります。十分な準備期間を確保し、必要に応じて外部サポートを活用することで、補助金活用の成功率を大きく向上させられます。
専門家を活用するメリットについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ものづくり補助金の申請を専門家に任せるべき理由と業者選びのポイント
東京都の新規事業補助金を選ぶポイント
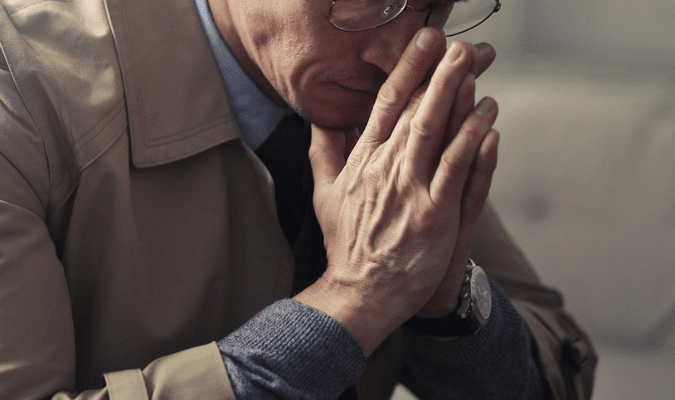
複数の補助金制度が存在しても、すべての事業者に適しているわけではありません。事業のステージや経費の種類、申請スケジュールを見極めることが重要です。適切な補助金を選ぶことで、資金の有効活用と事業成長のスピードアップが可能になります。ここでは、補助金を選定する際に意識すべき三つの視点を解説します。
自社の事業ステージに合った補助金を選ぶ
補助金を効果的に活用するには、事業の進行段階に合わせた制度選びが不可欠です。創業直後の段階では、初期投資や販促費を支援する創業助成事業や商店街起業・承継支援事業が適しています。まだ売上基盤が安定していない時期は、返済不要の資金を確保することで運転資金に余裕が生まれます。
一方、製品開発や技術革新に取り組む段階では、スタートアップ向け新製品・新技術開発助成事業のように開発費を重視する制度が効果的です。事業ステージに合わない制度を選ぶと、対象経費に合致せず申請が不可能になることもあります。
成長段階や経営目標を整理し、最適な補助金を選ぶことで、採択率の向上と資金の効率的な活用が実現できます。
対象経費や助成上限額を比較する
補助金の選定では、対象経費と助成額のバランスを見極めることが重要です。制度ごとに認められる経費の種類は異なり、設備投資、賃借料、広告費、人件費、知的財産関連費用などのどれが含まれるかを確認する必要があります。
助成上限額や助成率も制度によって差があり、創業助成事業では最大400万円、新製品・新技術開発助成事業では約1,000万円の支援が可能です。経費総額と補助率の関係を整理すれば、必要資金に対してどの程度の補助を受けられるかが明確になります。
十分な金額を確保できない制度を選ぶと、自己資金の負担が大きくなり、事業計画に影響することがあります。対象経費と上限額を比較したうえで、資金計画に最も適合する補助金を選択しましょう。
申請要件とスケジュールを把握する
補助金は、申請時期と要件を満たさなければ受給できません。制度によっては、創業支援事業の受講やインキュベーション施設の入居実績など、特定の条件を事前にクリアする必要があります。準備には数カ月を要する場合もあるため、スケジュールを逆算して計画を立てることが重要です。
また、申請期間は10日前後と短い場合が多く、直前の着手では必要書類の作成が間に合わない可能性があります。採択後も実績報告や経費精算の期限が定められているため、全体の流れを理解しておくことが欠かせません。
スケジュール管理を徹底し、事前要件の確認を怠らなければ、申請チャンスを逃さず、補助金を確実に活用できます。
補助金の申請手順とスケジュール
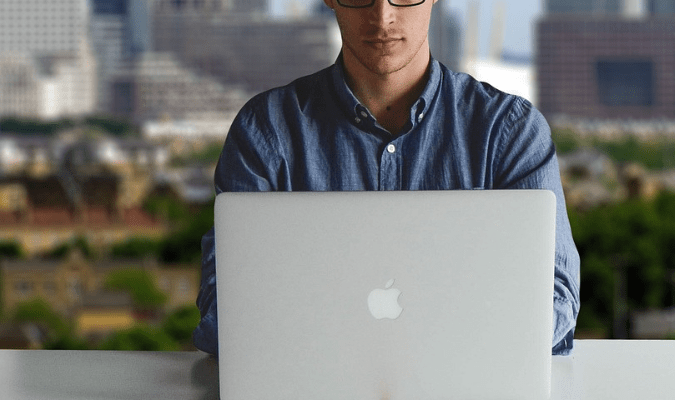
補助金を確実に受給するためには、申請手順とスケジュールを正しく理解する必要があります。書類作成や支援機関の活用、電子申請の準備など、事前準備が整っていないと期限内に提出できません。
さらに、採択後には実績報告や交付手続きが待っています。全体の流れを把握しておけば、無理のない計画で申請から受給までを進められるでしょう。ここでは、申請前の準備から採択までの流れを整理します。
申請前に必要な創業支援事業の利用や事業計画書作成
補助金の申請には、事前に創業支援事業の利用や事業計画書の完成が必須となる場合があります。創業助成事業の場合、TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援や、区市町村の認定創業支援事業を受講した実績が求められることがあります。
これらの支援を利用すると、計画の妥当性や収益性を客観的に整理でき、審査でも説得力を高められるでしょう。事業計画書には、事業内容や市場分析、収支計画、資金使途などを明確に記載する必要があります。
作成過程では、自社の強みや差別化要素を洗い出すことも重要です。申請準備を早めに始めれば、専門家や支援機関からのフィードバックを受ける時間も確保できます。審査での高評価を狙うなら、事業計画の完成度を徹底的に高める取り組みが不可欠です。
電子申請の流れと必要書類の準備
近年の補助金申請は電子申請が主流となっています。郵送での提出に対応している場合もありますが、電子申請を選ぶと受付期間内にスムーズな提出が可能です。申請では、法人登記簿謄本、確定申告書、事業計画書、見積書、経費内訳書など、多数の書類が必要となります。
誤りや不足があると受理されず、審査の対象外となる恐れがあります。電子申請の操作方法や必要書類のフォーマットは、事前に公式サイトで確認し、締切に余裕を持って作業を進めることが重要です。
また、PDF化や電子署名、添付容量の上限など、オンライン申請特有の注意点もあります。書類準備を並行して進めれば、申請期間が短い制度でも落ち着いて提出できます。正確な書類作成と迅速な電子申請は、採択への第一歩となります。
審査・採択・交付までのタイムラインを理解する
補助金の受給には、申請から交付までの一連の流れを理解しておくことが不可欠です。多くの制度では、まず書類審査が行われ、内容に問題がなければ面接審査や追加資料の提出を求められることがあります。
審査を通過すると採択通知が届きますが、実際の助成金は後払いであり、交付決定後に対象経費を支出したうえで実績報告を提出する流れとなります。助成対象期間は1年から2年程度の場合が多く、支払いのタイミングに合わせて資金計画を組むことが欠かせません。
さらに、報告内容や証憑に不備があれば交付が遅れる可能性もあります。スケジュール全体を把握しておけば、資金ショートや提出遅延のリスクを避けられます。計画的な進行管理を徹底すれば、補助金を事業成長に効果的に結びつけられるでしょう。
補助金申請を成功させるための相談先

補助金は申請手続きや書類作成が複雑であり、自己流で進めると不採択や提出不備のリスクが高まります。専門的な知識や経験を持つ相談先を活用すれば、採択率の向上や手続きの効率化が可能です。
東京都では、行政機関や認定支援機関、民間の申請支援サービスなど、多様なサポート先が用意されています。ここでは、主な相談先と活用方法を整理します。
東京都中小企業振興公社やTOKYO創業ステーション
東京都中小企業振興公社とTOKYO創業ステーションは、創業支援や補助金申請における公的サポートの中心的存在です。中小企業振興公社では、創業助成事業や商店街起業支援などに関する説明会や個別相談を受けられます。
制度の最新情報や申請要件の確認、必要書類のチェックを公的機関の職員から直接受けられるため、申請の精度が向上します。TOKYO創業ステーションでは、事業計画書策定支援や専門家による個別相談、セミナー参加などが可能です。
創業初期の課題整理や計画作成を通じて、採択につながる申請書作成力を養えます。公的機関の支援は無料または低コストで利用できるため、初めて補助金を申請する事業者にとって有益です。事前相談を重ねることで、提出前に不備を減らし、採択の可能性を高められます。
認定支援機関・行政書士への相談
補助金申請では、認定支援機関や行政書士などの専門家に依頼する方法も有効です。認定支援機関は国や自治体から公式に認定された機関であり、経営計画の策定や資金繰りの助言に強みがあります。
補助金申請に精通した担当者に依頼すれば、要件に沿った書類作成や実績報告まで一貫してサポートを受けられるでしょう。行政書士も補助金申請の代行に対応しており、必要書類の整備や電子申請の操作までを任せられます。
専門家を活用すると、複雑な申請書作成にかかる時間を削減し、申請の精度を高められます。報酬は成功報酬型の場合もあり、採択されなければ費用が発生しないサービスも存在するので、比較検討してみましょう。
自力申請に不安がある場合や時間を効率的に使いたい場合は、専門家の協力が採択成功への近道となります。
申請支援サービスを利用して採択率を高める
民間の補助金申請支援サービスを利用すると、採択率を高める効果が期待できます。これらのサービスでは、制度ごとの傾向や審査基準に精通した担当者が、事業計画書や申請書のブラッシュアップを行います。過去の採択実績に基づく添削や模擬審査により、申請書の完成度を大幅に向上可能です。
さらに、電子申請や実績報告のサポートも提供されるため、初めての申請でも安心です。成功報酬型や着手金ゼロ型のプランを選べば、コスト負担を抑えながら専門的な支援を受けられます。
申請書作成の負担を減らし、審査通過の可能性を高めるには、経験豊富な支援サービスの利用が有効です。事業の成長に直結する資金を確保するためにも、効率的な申請体制を整えることが望ましいでしょう。
まとめ
東京都で新規事業を立ち上げる場合、補助金の活用は大きな資金的後押しとなります。創業助成事業では最大400万円、商店街起業・承継支援事業や若手・女性リーダー応援プログラム助成事業など、事業規模や目的に応じた多彩な制度が用意されています。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として、東京都内の中小企業や個人事業主を対象に補助金申請支援を行っています。書類作成から電子申請、面接対策、実績報告までを一貫サポートし、高い採択率が特長です。
着手金0円・完全成功報酬型で安心して依頼できる体制を整えており、初めての申請でもスムーズに進められます。新規事業の立ち上げを加速させたい方や、資金調達の不安を解消したい方は、ぜひお問い合わせください。
【事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)にも対応!無料相談はこちら】
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。