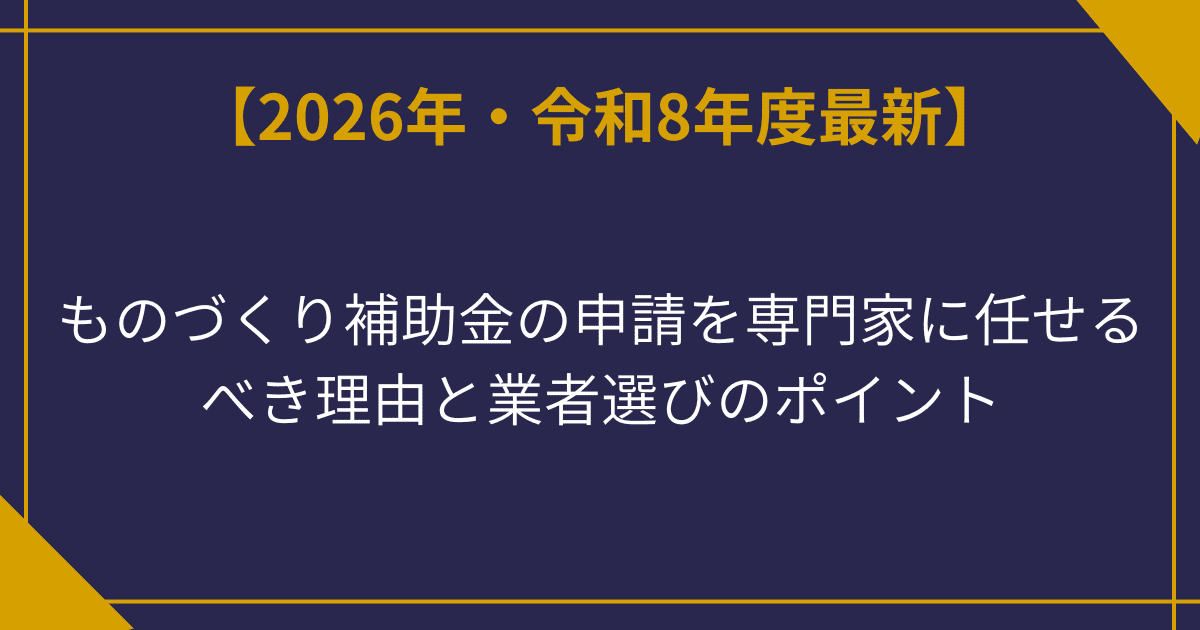ものづくり補助金の申請代行を検討中で、どの専門家に依頼すべきか迷っていませんか?
最大数千万円規模の補助金獲得を目指す際、自社のみでの申請はハードルが高く、多くの企業が専門家のサポートを活用しています。「ものづくり補助金 申請代行」の活用は、採択率を高め、事業を加速させるための賢い投資です。
この記事では、失敗しない代行業者の選び方や適正な費用相場、2025年の最新傾向について、補助金のプロが徹底解説します。
- まずは結論!申請代行を利用すべき理由と自社申請との違い
- 2025年版 ものづくり補助金の申請代行の費用相場
- 失敗しない申請代行業者選びの5つのポイント
- 株式会社イチドキリが選ばれる3つの理由
- ものづくり補助金 申請代行に関するよくある質問
- まとめ:信頼できる専門家と二人三脚で採択を勝ち取ろう
まずは結論!申請代行を利用すべき理由と自社申請との違い

ものづくり補助金は、要件を満たせば必ずもらえるものではなく、厳しい審査を通過する必要があります。申請代行を利用することで、採択の可能性を最大限に高められるのが最大の理由です。
専門家を活用する場合と自社で申請する場合の主な違いは以下の通りです。
- 採択率(合格率)の差
- 書類作成にかかる時間と労力
- 最新トレンドへの対応力
それぞれ具体的に解説します。
1. 採択率(合格率)の差
専門家による申請代行を利用すると、採択率が大幅に向上する傾向があります。過去の公募結果を見ると、全体の採択率は概ね30%〜50%程度で推移していますが※1、実績豊富な専門家が支援した場合、その採択率は80%〜90%に達することも珍しくありません。
審査員が評価するポイントを熟知したプロが事業計画書を監修するため、説得力が格段に増します。せっかくの優れた事業アイデアも、伝え方が悪ければ不採択になるリスクがあるため、プロの知見は不可欠です。
2. 書類作成にかかる時間と労力
ものづくり補助金の申請には、公募要領の読み込みから事業計画書の作成、必要書類の収集まで、膨大な時間が必要です。慣れていない方が自社で行う場合、100時間以上かかることもあり、本業に支障をきたす恐れがあります。
申請代行を利用すれば、ヒアリングや資料提供など最低限の工数で済み、経営者は本業に集中できます。時間はコストであると考え、面倒な作業をアウトソーシングすることで、経営資源を有効活用できるのです。
3. 最新トレンドへの対応力
ものづくり補助金は、年度や公募回ごとにルールや加点項目、申請枠(省力化枠やグローバル枠など)が頻繁に変更されます。最新情報を常に追い続けるのは、多忙な経営者にとって容易ではありません。
専門家は常に最新の公募要領や審査傾向を分析しています。「賃上げ要件」や「省力化投資」など、その時々の政策意図に合致した計画を作成することで、採択への近道を歩むことができます。
※1 出典:採択結果|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
2025年版 ものづくり補助金の申請代行の費用相場

申請代行を依頼する際に最も気になるのが費用です。料金体系は業者によって異なりますが、相場から大きく外れた業者には注意が必要です。一般的な費用構造と相場観を理解しておきましょう。
- 着手金の相場
- 成功報酬の相場
- その他にかかる費用
費用の内訳について詳しく見ていきます。
1. 着手金の相場
着手金は、採択・不採択に関わらず、契約時や業務開始時に支払う費用です。相場は10万円〜30万円程度が一般的です。
着手金が安い、あるいは無料の業者は、初期リスクを抑えたい企業にとって魅力的です。ただし、その分成功報酬が高めに設定されている場合もあるため、トータルのコストバランスを見て判断することが大切です。
2. 成功報酬の相場
成功報酬は、補助金が採択された場合にのみ支払う費用です。一般的には補助金交付予定額の10%〜20%程度が相場となっています※2。
例えば、1,000万円の補助金が採択された場合、100万円〜200万円が報酬となります。報酬率が低すぎる業者はサポート範囲が狭い可能性があり、逆に20%を超える場合は高額すぎる可能性があるため、サービス内容との見合いで検討しましょう。
3. その他にかかる費用
着手金と成功報酬以外にも、追加費用が発生する場合があります。例えば、採択後の「交付申請」や「実績報告」のサポート費用、数年間にわたる「事業化状況報告」の支援費用などです。
また、加点措置を得るための「事業継続力強化計画」等の策定支援が別料金になることもあります。契約前に「どこまでの作業が含まれているのか」見積書を詳細に確認し、後出しの請求がないよう注意してください。
失敗しない申請代行業者選びの5つのポイント

数多くの申請代行業者が存在するため、どこに依頼すればよいか迷うことも多いでしょう。安易に選ぶと「書類の質が低い」「連絡が取れない」といったトラブルになりかねません。
信頼できるパートナーを選ぶためのポイントは以下の5つです。
- 「認定経営革新等支援機関」であるか
- 具体的な採択実績と専門性
- 採択後のアフターフォロー体制
- 料金体系の透明性
- 担当者との相性と熱意
それぞれのポイントを解説します。
1. 「認定経営革新等支援機関」であるか
「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」とは、中小企業支援に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上あるとして、国が認定した機関(税理士、中小企業診断士など)のことです※3。
ものづくり補助金の一部の枠では、認定支援機関の確認書が必要になるケースもあります。国の認定を受けている専門家であれば、一定の質と信頼性が担保されているため、安心して依頼できる一つの基準となります。
2. 具体的な採択実績と専門性
HP等で「採択率〇〇%」「採択件数〇〇件」といった実績を公開しているか確認しましょう。特に、自社と同じ業種や、導入したい設備に近い事例での採択実績があるかが重要です。
「ものづくり補助金」は製造業だけでなく、建設業、歯科、システム開発など幅広い業種で利用可能です。自社の業界事情に詳しく、専門用語を理解してくれるコンサルタントであれば、事業計画書の解像度が高まり、採択率向上につながります。
3. 採択後のアフターフォロー体制
補助金は「採択」されて終わりではありません。その後の「交付申請」、設備の導入、そして「実績報告」を経て初めて入金されます。これらの手続きは非常に煩雑で、ミスがあると補助金が減額されるリスクもあります。
採択後の手続きまで一貫してサポートしてくれる業者を選ぶことを強くおすすめします。 申請支援のみで契約が終了する業者に依頼すると、採択後に自社で膨大な事務作業を抱え込むことになりかねません。
4. 料金体系の透明性
契約前に、発生する費用が明確に提示されているか確認しましょう。「着手金」「成功報酬」だけでなく、不採択時の再申請費用や、採択後のサポート費用が含まれているかが重要です。
中には、成功報酬の計算方法が不明瞭だったり、中途解約時の違約金が高額だったりするケースもあります。見積もりの段階で総額をシミュレーションし、不明点は納得できるまで質問する姿勢がトラブル回避の鍵です。
5. 担当者との相性と熱意
事業計画書の作成には、経営者の想いやビジョンをコンサルタントと共有するプロセスが不可欠です。ヒアリングが丁寧で、自社の事業に興味を持ってくれる担当者であれば、より良い計画書が完成します。
無料相談などを活用し、「話しやすいか」「レスポンスは早いか」を確認してみてください。補助金申請は数ヶ月から数年にわたるプロジェクトになるため、信頼関係を築けるパートナー選びが成功の土台となります。
※3 出典:認定経営革新等支援機関|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
株式会社イチドキリが選ばれる3つの理由
ものづくり補助金の申請代行をお探しなら、私たち「株式会社イチドキリ」にお任せください。認定経営革新等支援機関として、多くの中小企業様の補助金獲得を支援しています。
当社が選ばれる理由は主に以下の3点です。
- 着手金0円・完全成功報酬
- エンジニア出身×補助金のプロによる支援
- 高い採択率と豊富な実績
それぞれの強みについてご紹介します。
1. 着手金0円・完全成功報酬
当社は、申請時のリスクを最小限に抑えるため、「着手金0円」の完全成功報酬型を採用しています。万が一不採択だった場合、費用は一切いただきません。
これは、私たちの支援品質への自信の表れでもあります。初期費用を気にせず挑戦できるため、資金繰りが心配な事業者様でも安心してご依頼いただけます。
2. エンジニア出身×補助金のプロによる支援
代表自身がエンジニア出身であり、システム開発やIT導入に関する深い知見を持っています。ものづくり補助金は設備投資だけでなく、システム構築も対象となるため、技術的な内容を正確に計画書に落とし込めるのが強みです。
一般的な士業では理解が難しい専門的な技術やビジネスモデルも、的確に言語化し審査員にアピールします。ITや先端技術を活用した事業計画でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
3. 高い採択率と豊富な実績
当社は認定経営革新等支援機関として、補助金申請支援に特化したサービスを提供しており、高い採択率を実現しています。単なる代行ではなく、事業の成長を見据えたコンサルティングを行います。
売上向上や大規模案件の獲得を視野に入れた計画策定をサポートします。「採択されること」はもちろん、「事業が成功すること」をゴールに見据え、貴社の挑戦を全力でバックアップします。
ものづくり補助金 申請代行に関するよくある質問
申請代行を検討されている方からよくいただく質問をまとめました。不安や疑問を解消して、申請への一歩を踏み出しましょう。
- Q1. 申請代行は「丸投げ」しても大丈夫ですか?
- Q2. 自分で申請(電子申請)する必要がありますか?
- Q3. 採択されなかった場合の再申請は可能ですか?
それぞれの質問に回答します。
Q1. 申請代行は「丸投げ」しても大丈夫ですか?
完全に丸投げすることはできません。補助金は事業者が主体となって計画を実行するものであり、ヒアリングへの回答や必要書類の準備は行っていただく必要があります。
また、電子申請の操作自体は、セキュリティの観点から申請者自身が行う必要があります。専門家はあくまで「支援」の立場であり、二人三脚で計画を作り上げる姿勢が採択への近道です。
Q2. 自分で申請(電子申請)する必要がありますか?
はい、電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」への入力・送信操作は、原則として事業者様ご自身で行っていただく必要があります※4。GビズIDのアカウント管理も厳格に行う必要があります。
ただし、入力内容の準備や操作方法のサポートは専門家が行います。初めての方でもスムーズに申請できるよう、画面共有などで丁寧にナビゲートしますのでご安心ください。
Q3. 採択されなかった場合の再申請は可能ですか?
はい、不採択となった場合でも、次回以降の公募で再申請(リベンジ申請)が可能です。一度作成した事業計画書をベースに、審査員のコメント等を分析してブラッシュアップすることで、次回採択されるケースも多くあります。
当社のような成功報酬型の業者であれば、不採択時の費用負担がないため、再チャレンジもしやすい環境です。諦めずに計画を磨き上げることで、採択を勝ち取るチャンスは十分にあります。
※4 出典:jGrants(Jグランツ)|デジタル庁 https://www.jgrants-portal.go.jp/
まとめ:信頼できる専門家と二人三脚で採択を勝ち取ろう
ものづくり補助金は、最大数千万円の資金調達が可能となる強力な制度ですが、その申請難易度は年々上がっています。自社のリソースだけで挑むのではなく、実績のある申請代行業者を活用することが、採択への最短ルートです。
- 採択率の大幅な向上が期待できる
- 着手金0円の業者ならリスクなく挑戦できる
- 採択後のアフターフォローまで見据えて業者を選ぶ
株式会社イチドキリでは、エンジニア出身のプロが、貴社の技術や強みを最大限に引き出す事業計画書作成をサポートします。まずは無料相談で、補助金獲得の可能性を確認してみませんか?
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。