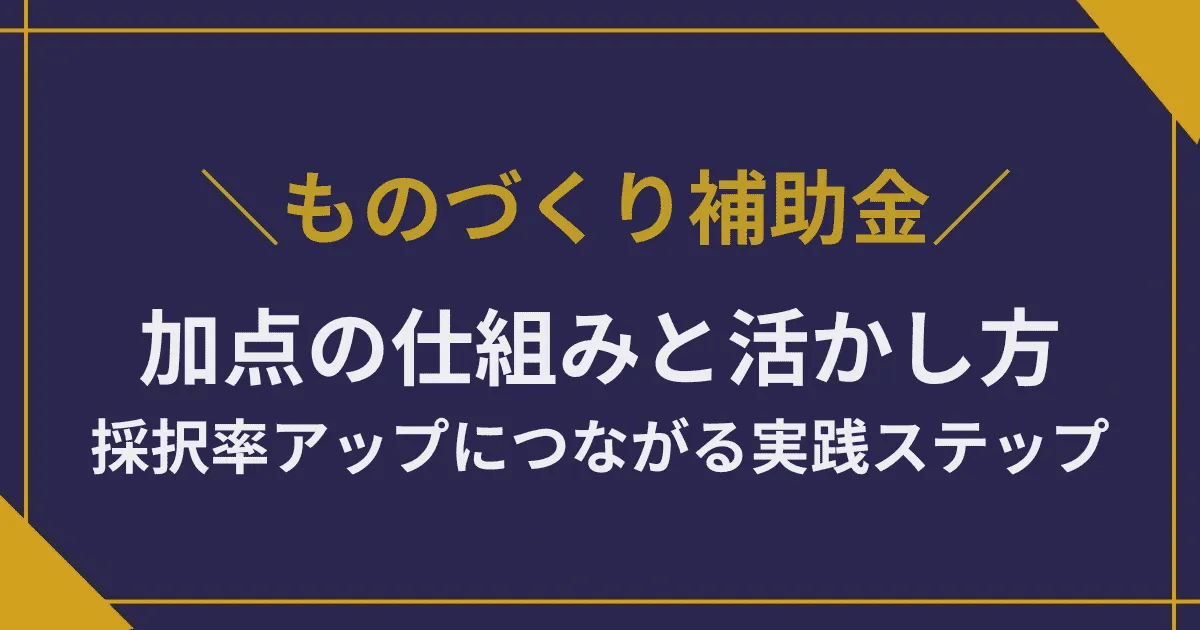ものづくり補助金を活用しようと考える中小企業にとって、採択率を左右する大きなポイントが「加点」です。加点は審査時の評価を押し上げ、申請の成功確率を大幅に高めます。
しかし、どの加点が取りやすく、どの項目に時間がかかるのかを正しく理解しなければ、効果的に活かすことはできません。さらに、加点は取得するだけでなく、達成状況を維持することも求められるため、戦略的な取り組みが不可欠です。
本記事では、ものづくり補助金における加点の仕組みや種類、獲得のステップ、注意すべき減点リスク、さらには採択後に意識すべきポイントまでを体系的に解説します。申請準備を進める経営者や担当者の方にとって、採択率を高めるための実践的な指針となるでしょう。
- ものづくり補助金の加点仕組みを理解する
- ものづくり補助金で活用できる加点項目の種類
- ものづくり補助金の加点を獲得する実践ステップ
- ものづくり補助金における加点と減点の注意点
- ものづくり補助金で加点を活かす採択率アップのコツ
- ものづくり補助金の加点を得た後に意識すべきポイント
- まとめ
ものづくり補助金の加点仕組みを理解する
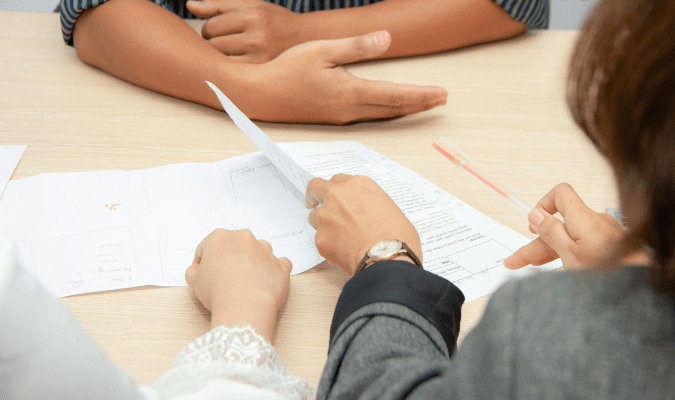
ものづくり補助金を申請する際に、加点の有無は採択結果に大きな差を生みます。採択率を上げるためには、制度の基本構造を把握し、加点の意義や仕組みを理解しておくことが不可欠です。
ここでは、制度の概要、加点が与える効果、仕組みと上限数について順に解説します。
ものづくり補助金とは何か
まず制度の全体像を整理しましょう。ものづくり補助金は中小企業や小規模事業者が革新的な取り組みを行う際に活用できる支援制度です。新製品や新サービスの開発、あるいは海外展開などの取り組みに必要な設備投資や関連経費を対象として補助が行われます。
対象経費は機械装置やシステム導入費、外注費、専門家活用費など幅広く設定されています。制度の目的は単なる資金援助ではなく、事業環境の変化に柔軟に対応できる体質を整え、生産性を高めることにあります。
さらに、採択された事業者には付加価値向上や賃金引上げなど具体的な数値目標の達成が求められる点も特徴です。言い換えれば、単なる補助金ではなく経営改善を促す仕組みと理解することが求められます。
ものづくり補助金について、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ものづくり補助金の条件を徹底解説|申請基準の詳細と満たすためのポイント
加点が採択率に与える影響
採択率を高めたいと考える場合、加点項目の存在は見逃せません。公式データでは、加点を一つでも取得した企業は採択率が大きく向上する傾向が示されています。審査で優先順位をつける際、政策的に推奨される取り組みを進める事業者を後押しするためです。
加点項目は労働環境の改善やデジタル化推進など、経済産業省が掲げる政策課題と深く結びついています。したがって、申請準備においては「どの加点を取得するか」を戦略的に選定し、審査上の優位性を確保することが採択の近道となります。
加点の仕組みと上限数
加点は申請内容に直接加算される仕組みで、審査における総合評価を押し上げます。申請者は複数の加点を申請できますが、認められる上限は6項目です。
すべての加点を満たす必要はなく、自社の現状に合致したものを選び、確実に取得することが重要です。加点項目の中には短期間で取得できるものもあれば、認証手続きに数か月を要するものも存在します。
したがって、スケジュール管理と優先順位付けが求められます。加えて、加点を申請する際には必要書類を事前に整備し、締切日時点で有効な状態にしておく必要があります。
形式的に申請するだけでは加点は認められないため、確実性を重視した取り組みが不可欠です。総合的に考えると、加点は採択の可能性を高める強力な要素として位置づけられます。
ものづくり補助金で活用できる加点項目の種類

加点は採択率を押し上げるための大きな武器となります。制度で設定されている項目は数多く存在しますが、取り組みやすさや準備にかかる時間はそれぞれ異なります。短期間で取得できるものから、数か月単位の準備が必要なものまで幅広いため、戦略的に組み合わせていくことが望ましいです。
以下の一覧表で種類と特徴を確認した上で、加点の種類をタイプ別に整理して理解を深めましょう。
| No | 加点項目 | 概要 | 取得難易度・期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 経営革新計画 | 新事業活動に取り組む計画を都道府県知事が承認する制度 | 難易度:高 |
| 2 | パートナーシップ構築宣言 | サプライチェーン全体の付加価値向上を宣言する仕組み | 難易度:低 |
| 3 | 再生事業者 | 再生計画を策定・承認済の企業 | 難易度:対象企業限定 |
| 4 | DX認定 | デジタル活用体制を国が認定 | 難易度:中 |
| 5 | 健康経営優良法人認定 | 従業員健康管理に積極的な企業を認定 | 難易度:高 |
| 6 | 技術情報管理認証 | 技術情報の管理体制を整備する制度 | 難易度:中〜高 |
| 7 | J-Startup/地域版 | 経産省が選定するスタートアップ支援 | 難易度:非常に高 |
| 8 | 新規輸出1万者支援プログラム | グローバル枠限定、輸出支援登録 | 難易度:低 |
| 9 | 事業継続力強化計画 | 災害対策計画を認定する制度 | 難易度:低 |
| 10 | 賃上げ | 給与総額や最低賃金を一定以上引き上げる | 難易度:中 |
| 11 | 被用者保険 | 短時間労働者を被用者保険に加入 | 難易度:中 |
| 12 | えるぼし認定 | 女性活躍推進に優れた企業を認定 | 難易度:高 |
| 13 | くるみん認定 | 子育てサポート企業を認定 | 難易度:非常に高 |
| 14 | 事業承継/M&A | 過去3年以内に事業承継やM&Aを実施 | 難易度:対象企業限定 |
| 15 | 成長加速マッチングサービス | 中小企業庁サイトで課題登録 | 難易度:低 |
| 16 | グローバル枠関連要件 | 海外事業体制や調査実施など | 難易度:中 |
取り組みやすい加点項目
短期間で整備できる加点項目として代表的なのがパートナーシップ構築宣言です。これは大企業と中小企業が共存共栄できる関係を築くための方針を宣言し、専用サイトに登録して公開する仕組みです。申請から反映まで1週間程度で完了し、書類作成の負担も軽いため、多くの中小企業が活用しています。
もう一つ注目すべきなのが事業継続力強化計画です。災害時や緊急時に備えた体制を整える計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けるもので、手引きを参考に進めれば比較的スムーズに仕上げられます。認定まで数週間で済むため、応募締切までに間に合う可能性が高い点が利点です。
これらの項目は労力に対して効果が大きく、初めて加点を狙う事業者にとって非常に有効な選択肢といえるでしょう。
時間がかかる加点項目
計画書のボリュームや審査プロセスの長さから準備に時間を要する加点もあります。経営革新計画は、新しい事業活動を通じて経営の向上を図るための計画を都道府県知事の承認を受ける仕組みです。計画内容の精緻さや提出書類の量が多く、承認まで2〜3か月を見込む必要があります。
DX認定も同様に、デジタル技術を活用した経営変革を行う体制を整えた企業に与えられる認定制度です。国の認定を得るために審査に3〜4か月かかることが一般的であり、直近の公募締切に合わせるのは難しいケースもあります。
こうした項目は準備に時間がかかる反面、取得できれば企業の信頼性を高める効果もあります。長期的な補助金活用や経営基盤強化を目指す場合には積極的に検討すべき選択肢でしょう。
グローバル枠で有効な加点項目
海外展開を視野に入れている事業者にとって有効なのが、グローバル枠特有の加点です。代表例が新規輸出1万者支援プログラムで、輸出に挑戦する企業を対象に情報提供やマッチング支援を行う仕組みです。
登録作業自体は比較的簡単で、1週間程度で完了するため短期間での取得ができます。さらに、海外市場の調査やパートナー探しを後押しする役割もあるため、補助金申請だけでなく実際の事業活動においても役立ちます。
グローバル枠を申請する場合、こうした加点を組み合わせることで採択率を一段と高めることが可能です。加えて、海外需要開拓を進める意思を示す証拠としても活用できるため、国際展開を本格化させたい企業にとって有効な一手となるでしょう。
認定制度による加点
認定制度に基づく加点も存在します。代表例は健康経営優良法人で、従業員の健康を重視した取り組みを行う企業が認定されます。企業価値向上にもつながる制度ですが、申請受付が年1回と限定されており、認定までにおよそ1年かかる点が課題です。
また、女性の活躍推進に関する取り組みが優良であると評価される「えるぼし認定」も対象となります。取得には最低4か月程度を要し、一定の基準を満たす必要があります。これらの認定は準備期間が長い分、社会的評価を得られる効果も大きいです。
短期的に活用するのは難しい一方で、中長期的な戦略に組み込むと企業のブランド力向上と補助金採択の両立を実現できます。採択率だけでなく企業価値も高めたいと考える場合には有効な選択肢でしょう。
ものづくり補助金の加点を獲得する実践ステップ
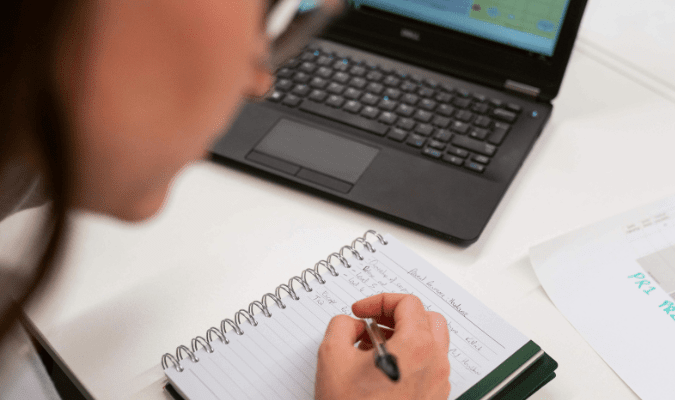
加点は採択率を大きく押し上げますが、闇雲に取り組んでも効果は限定的です。効果的に加点を得るためには、自社の現状把握から始まり、短期で取りやすい項目と長期準備が必要な項目を組み合わせる戦略が欠かせません。
さらに、専門家との連携により申請精度を高めることも重要です。ここでは実践に役立つ具体的な流れを紹介します。
まず確認すべき自社の状況
加点取得の第一歩は自社の現状把握です。資金力や人員体制、過去の補助金利用実績を整理することで、どの加点項目に取り組めるかが明確になります。たとえば、既に最低賃金を一定以上上回る水準で運用している企業は、賃上げ関連の加点に取り組みやすい立場にあります。反対に、デジタル化への取り組みが不足している場合はDX認定に挑戦する前に基盤整備が必要です。
自社が置かれている環境を正しく認識すれば、短期間で成果を出せる加点と時間をかけるべき加点の優先順位を判断できます。最初に全体像を把握しておくことで、無駄な作業を避け、効率的に申請準備を進められるでしょう。
短期間で準備できる加点の取り方
申請直前でも間に合う加点を選択することは重要です。代表的な例としてパートナーシップ構築宣言や事業継続力強化計画があります。前者はウェブ上で宣言内容を登録し公開する形式で、数日から1週間程度で完了します。
後者は自然災害や緊急時に備えた行動計画をまとめるもので、ガイドラインを活用すれば数週間以内に認定を得られる場合があります。短期で取得できる加点を組み合わせることで、採択率を引き上げる効果をすぐに得られます。
限られた時間の中で成果を最大化したい場合、短期取得可能な項目に優先的に取り組むことが効果的です。短期と長期の加点をバランスよく取り入れる姿勢が成功につながります。
中長期的に備えておくべき加点対策
長期的に安定して採択を狙うには、時間をかけて整える加点への準備が欠かせません。経営革新計画やDX認定は代表例で、承認や認定までに数か月を要します。計画策定には詳細な市場分析や経営戦略の整理が必要で、経営層の意思決定や社内の協力体制も不可欠です。
加えて、健康経営優良法人やえるぼし認定なども時間を要しますが、認定を得ると社会的信頼度が高まり、補助金申請以外の面でも大きな効果を発揮します。中長期的に準備を進めれば、採択率の安定化に加えて企業の成長戦略とも結びつきます。先を見据えた取り組みが、持続的な資金調達と経営基盤強化の両立を実現するのです。
認定支援機関と連携して進める方法
専門知識を持つ認定支援機関との協力は、加点取得の確実性を高めます。認定支援機関は補助金制度の要件や審査基準を熟知しており、適切な加点選択や書類作成をサポートします。たとえば、経営革新計画の承認申請にあたっては、計画の精緻さや実現可能性を高めるアドバイスを受けられるでしょう。
さらに、申請者が見落としやすい必要書類や期限管理についてもサポートしてくれるため、申請ミスを防ぐことができます。採択後の報告やフォロー体制についても相談できるため、補助金活用を長期的に継続するための強力なパートナーとなります。専門家との連携により、自社だけでは難しい加点取得をスムーズに進められるでしょう。
ものづくり補助金における加点と減点の注意点
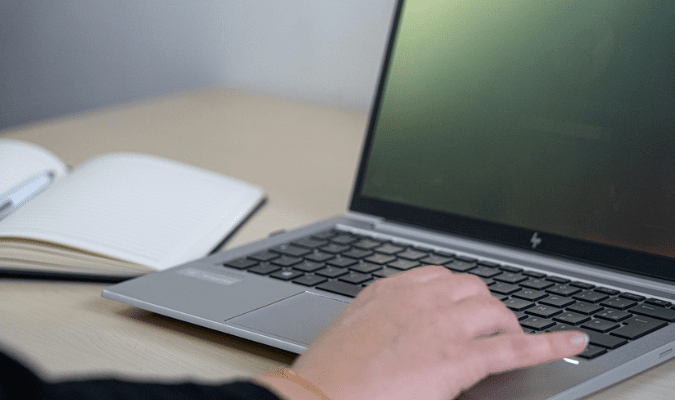
加点を上手に活用することで採択率は飛躍的に高まりますが、同時に注意すべき点も存在します。要件未達による減点や複数回利用の影響などを理解せずに申請すると、思わぬ不利を招く可能性があります。
採択を確実に引き寄せたいのであれば、加点と減点の両面を正しく把握し、リスクを避ける工夫を実行することが欠かせません。ここでは、ものづくり補助金における加点と減点の注意点について解説します。
加点要件を未達成だった場合のペナルティ
加点を申請し、審査で評価を得ても、その後に目標を達成できなければ大きなペナルティを受ける場合があります。たとえば、賃上げに関する加点を選択した企業が計画通りに給与総額を伸ばせなかった場合、次回以降の申請で大幅な減点が課されます。
これは制度の信頼性を保つためであり、表明した内容を遵守する姿勢が強く求められているのです。とくに、正当な理由が認められないまま未達成となったケースでは、一定期間の間、採択率が著しく低下するリスクが伴います。
加点を狙う際には、達成可能性を慎重に見極める必要があります。短期的な採択を優先して無理な加点を選ぶと、結果として長期的な不利益につながる恐れがあるでしょう。
補助金を複数回利用している場合の扱い
過去にものづくり補助金を活用した経験がある企業は、新規申請時に減点を受ける可能性があります。制度では、過去3年間に複数回採択された事業者や、以前の採択で成果を十分に出せなかった事業者に対して減点が適用される場合があるのです。
背景には、補助金を公平に分配し、多くの企業に利用機会を与えるという考え方があります。すでに支援を受けた企業が再び申請する場合には、過去の成果や実績を明確に示し、資金が有効に活用されたことを説明することが重要です。
利用歴があるからといって不利が避けられないわけではなく、実績を強みとして示せば逆に信頼を得られる可能性もあります。複数回利用する際には、採択実績と改善効果を裏付ける資料を準備することが欠かせません。
他補助金の事業化が進んでいない場合のリスク
申請者が他の補助金を受給している場合、その事業化状況が評価に影響を及ぼします。たとえば、過去に事業再構築補助金や同じものづくり補助金を受けた事業が、報告時点で計画通りに進展していない場合は減点対象となります。
制度側としては、補助金が成果に結びついていない事業者に追加の支援を行うことを避けたいという意図があるのです。したがって、新たに申請する際には、過去の補助金活用の進捗を丁寧に整理し、計画の実現度を数値や事例で示すことが求められます。
もし成果が限定的であった場合でも、原因を明確にし、改善策を提示すれば一定の評価を得られる可能性があります。事業化が進んでいない状況を放置したまま申請すると、採択は難しくなるでしょう。
ものづくり補助金で加点を活かす採択率アップのコツ

加点を取得するだけでは十分とはいえません。審査においては、加点と基本要件の両立や書類の完成度など総合的な観点が重要です。採択率をさらに高めたいと考える場合、複数の工夫を組み合わせる必要があります。
ここでは、加点を効果的に活かすための実践的なコツを紹介し、申請の完成度を高める視点を整理します。
加点と基本要件を両立させる工夫
補助金の審査では、加点項目が評価される一方で、基本要件の達成可能性も厳しく見られます。付加価値額や賃金の引き上げ、最低賃金水準の維持などを満たす計画を示すことが不可欠です。加点を狙う際には、基本要件の達成が現実的であるかを確認することが大切です。
たとえば、賃上げ加点を選んだ場合、従業員への給与増加をどのように実現するのか、売上や利益の成長計画と関連づけて示す必要があります。加点だけに注目して数字を設定すると、審査時に実現性の低さを指摘されかねません。
加点と基本要件の双方を満たす戦略を立てることで、信頼性の高い申請書を仕上げられるでしょう。最終的には、加点と要件が一体となって相乗効果を生むように設計することが重要です。
採択率をさらに高める審査対策
審査では、計画の具体性と独自性が大きな評価ポイントになります。市場動向や競合状況を分析し、自社の取り組みがどのように差別化されるかを明示することが求められます。また、費用対効果の説明も欠かせません。設備投資やシステム導入によりどの程度の売上増加やコスト削減を見込めるか、数値を用いて根拠を提示することが効果的です。
さらに、地域経済や雇用への波及効果を説明すると、政策面での評価が高まります。単なる加点取得だけではなく、全体として完成度の高い計画を示すことで、審査員にとって「選びたい案件」として印象づけることができます。採択率をさらに引き上げたい場合は、加点に加えて審査基準全般を意識した対策を講じましょう。
専門家を活用して書類精度を高める
申請書の質を高めるためには、専門家のサポートを受けることが有効です。認定支援機関やコンサルタントは制度の仕組みに精通しており、加点取得の適切な選択や申請書の表現方法をアドバイスしてくれます。
たとえば、事業計画の市場性や実現可能性を強調する際に、第三者の視点を取り入れることで説得力が増します。また、必要書類の漏れや期限管理の不備を防げる点も大きなメリットです。採択後のフォローや報告の体制まで支援を受けられる場合もあり、長期的に安心して補助金を活用できます。
自社だけで取り組むよりも効率的かつ精度の高い申請を実現できるため、専門家との連携は採択率向上に直結します。結果的に、加点を最大限に活かす体制を整えられるでしょう。
ものづくり補助金の加点を得た後に意識すべきポイント
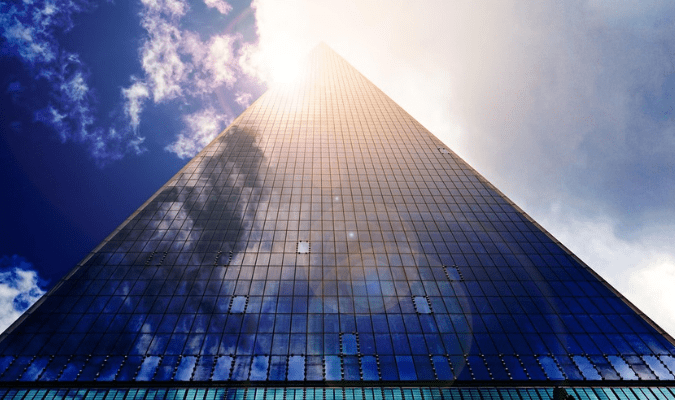
加点を取得して採択に成功した後も、企業には重要な取り組みが求められます。補助金は資金面の支援にとどまらず、計画実行や経営改善を進める責任が伴います。
採択後の行動次第で補助金の効果は大きく変わるため、事業化報告や経営改善への活用方法を意識することが重要です。ここでは、採択後に実行すべき具体的なポイントを整理します。
採択後の事業化状況報告で注意すべき点
採択された事業者には、補助金を受け取った後も複数回にわたり事業化状況報告を提出する義務があります。報告では、計画通りに付加価値額や賃金を増加できているか、設備投資の効果が出ているかなどが確認されます。
とくに、給与支給総額や最低賃金水準の達成度は審査の基準として重視されるため、日常的に数値を把握し、報告に備える体制を整えることが不可欠です。報告を怠ると補助金の返還や将来の申請に不利が生じる可能性もあります。
したがって、採択後は会計管理や人事データの整備を徹底し、透明性を確保することが望まれます。補助金を確実に活かすためには、報告の準備を日常業務の一部として組み込む姿勢が重要でしょう。
加点項目と実際の経営改善のつながり
加点を取得する過程で取り組んだ施策は、採択に役立つだけでなく経営改善の実効性を高める要素にもなります。たとえば、パートナーシップ構築宣言を行った企業は、取引先との信頼関係を強化し、安定したサプライチェーンを築ける可能性が高まります。
また、事業継続力強化計画を認定された企業は、防災やリスクマネジメントの体制を整え、危機に強い経営基盤を確立できるでしょう。さらに、DX認定や健康経営優良法人の取得は、従業員満足度や生産性の向上に直結します。
加点は単なる採択率アップの手段ではなく、自社の持続的な成長につながる経営改善策と理解することが大切です。採択後も積極的に加点の取り組みを発展させ、経営戦略に組み込む姿勢が効果を最大化させます。
加点を次回申請や別補助金に活かす方法
加点を取得した実績は、次回以降の申請や他の補助金活用にも有効です。経営革新計画やDX認定などは有効期間が複数年にわたるため、一度取得すれば継続的に活用できます。
また、採択後の事業化報告で加点要件を着実に達成していれば、信頼性の高い事業者として評価され、次の申請で優位に立てるでしょう。さらに、健康経営優良法人やえるぼし認定のような社会的評価につながる認定は、補助金申請以外にも取引先や金融機関からの信頼を高める効果があります。
実績を積み重ねることで、補助金の申請に限らず幅広い経営支援を得やすくなるでしょう。したがって、加点を一度きりの要素として終わらせず、継続的な成長戦略に組み込むことが重要です。
まとめ
ものづくり補助金における加点は、採択率を大きく押し上げる要素として非常に重要です。制度の基本を理解したうえで、短期間で取得できる項目と長期的に準備すべき項目をバランスよく選択することが採択成功の近道になります。
加えて、基本要件との整合性や審査基準全般を意識し、説得力のある申請書を仕上げることが欠かせません。さらに、採択後は事業化状況報告を適切に行い、加点取得を経営改善に結びつけることで補助金の効果を最大化できます。
株式会社イチドキリは、中小企業の補助金申請を完全成功報酬型で支援し、書類作成から採択後のフォローまで一貫したサポートを行っています。補助金を活用して事業成長を加速させたい経営者の方は、専門家の力を活かすことで安心して申請に臨めるでしょう。
採択率を高めたい方や経営基盤の強化を目指す方は、ぜひご相談ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。