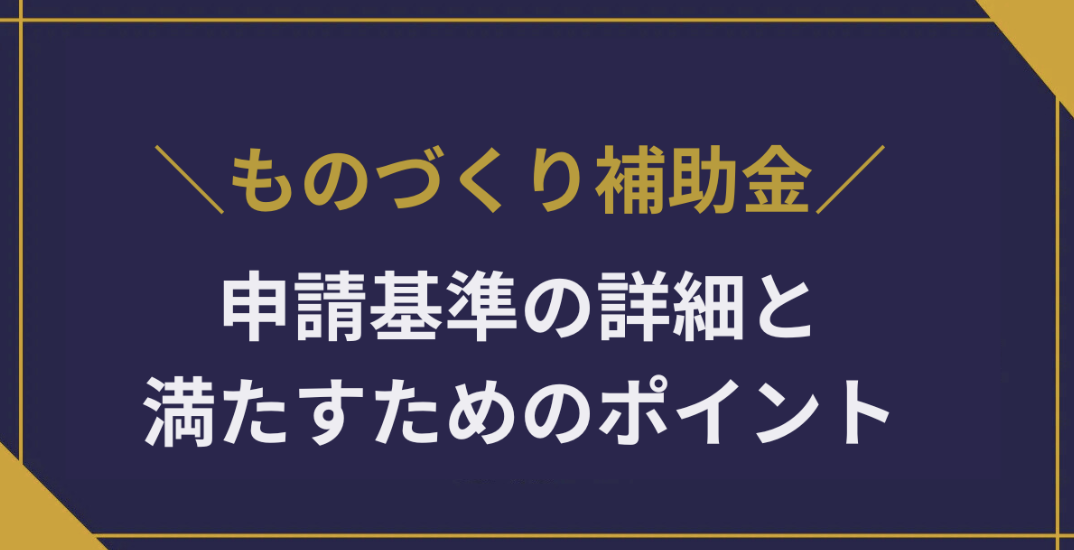革新的な設備投資や新サービス開発を後押しするものづくり補助金は、中小企業や個人事業主にとって事業成長の大きな支援策です。しかし、申請には細かな条件があり、基準を理解していなければ不採択となる可能性もあります。
本記事では、事業者の規模や業種、事業計画の目標、賃金に関する基準など、採択されるために知っておきたい要件をまとめました。スムーズに準備を進めるために、確認すべきポイントを押さえましょう。
ものづくり補助金の申請条件を正しく理解する

ものづくり補助金は、申請時に満たすべき条件が細かく設定されています。申請後に基準を満たしていないことが判明すると、不採択や返還のリスクが生じます。採択率を高めるために、自社がどの条件に該当するかを把握し、計画的に準備を進めることが欠かせません。ここでは申請可能な事業者や事業内容、数値目標の確認方法について詳しく解説します。
申請対象となる事業者か確認する
申請できるのは、中小企業や小規模事業者に該当する法人または個人事業主です。業種により資本金や従業員数の上限が異なり、製造業や建設業、ソフトウェア業は資本金3億円以下、従業員300人以下が上限です。サービス業や小売業ではさらに厳しく、資本金や従業員数の規模が低く設定されています。
自社がどの業種区分に属するかを調べ、現在の経営状況が基準を超えていないか確認することが重要です。基準を満たしていない場合は申請自体が無効になるため、準備段階で経営者自身が必ずチェックする必要があります。
開業前には申請できない理由
申請には、すでに事業を開始している法人や個人事業主であることが求められます。法人の場合は設立登記が完了していること、個人事業主の場合は開業届の提出が完了していることが確認できる書類が必要です。この要件は、申請者が実際に事業を運営し、計画を実行できる状態にあることを担保するためのものです。
申請時には登記簿謄本や開業届の控えが必要になるため、提出のタイミングまでに必ず準備しておきましょう。書類が不足していると申請が不備扱いとなり、不採択につながる可能性が高まりますので注意が必要です。
地域ごとの最低賃金水準に注意する
従業員を雇用している事業者の場合、地域ごとの最低賃金に対して一定の水準を上回る設定が求められます。具体的には、事業所内の最低賃金が地域別最低賃金に対して30円以上高い水準にする必要があります。
補助金の活用が雇用環境の改善にも貢献するために定められている条件です。申請前に給与規定を見直し、現行の賃金が条件を満たしているかを確認しましょう。地域によって最低賃金額は異なるため、都道府県別の最新データを参考にしてチェックすることが大切です。必要に応じて給与の調整も検討するべきでしょう。
個人事業主が満たすべき要件とは
個人事業主でも申請可能ですが、法人同様に条件を満たす必要があります。開業届を提出済みであることに加え、補助事業を遂行できる能力があるか、設備や人員の体制が整っているかが問われます。
さらに、審査では事業計画の収益性や実現性も評価対象です。個人事業主の場合、資金や規模に不安を感じることもありますが、事前に計画を見直し、可能であれば専門家に相談してブラッシュアップすると良いでしょう。実現可能性の高い計画を立てることで、採択の可能性は十分に高まりますので、諦めずに準備を進める姿勢が重要です。
条件未達時のリスクも知っておく
申請が採択された後も、設定された条件を達成できなければ補助金の返還が求められる場合があります。たとえば、付加価値額や従業員賃金の引き上げが目標に届かなかった場合などが該当します。不測の事態を避けるためには、計画段階から達成可能な数値を設定し、実現性を重視した内容にすることが必要です。
過度に野心的な計画を立てるのではなく、現実的で着実に実行できる計画を意識しましょう。返還免除の可能性や例外規定も存在しますが、基本的には未達によるリスクは事前に理解しておくべきです。
補助対象となる事業内容の条件を押さえる
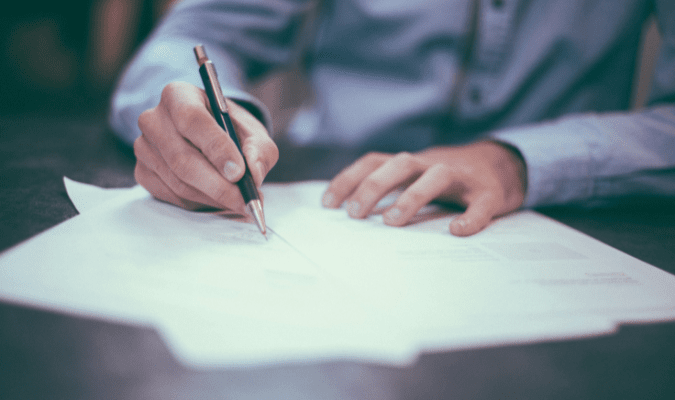
ものづくり補助金は、申請すれば誰でも受け取れる制度ではなく、事業内容にも厳格な条件が設けられています。革新性や生産性向上に寄与する取り組みであることが求められ、従来の延長線上にある単なる更新や維持だけでは不十分です。
ここでは、申請を検討するにあたり、どのような事業が条件を満たすのかを具体的に理解するためのポイントを解説します。
新製品や新サービスの開発が求められる理由
制度の目的は、既存の市場での競争を続けるための支援ではなく、新しい価値を生み出す取り組みを後押しすることにあります。したがって、既存製品の増産や老朽設備の単純な更新といった内容では、審査で高い評価を得ることは難しいでしょう。
新規顧客の獲得や市場拡大に資する新製品や新サービスの開発が不可欠です。その際、どのように顧客のニーズに応え、どの部分が業界内で独自性を持つのかを明確に示すと良いでしょう。さらに、開発の背景にある課題や期待される社会的意義も記載することで、計画の説得力が大きく高まります。革新性と実現可能性の両立を意識した提案が重要です。
生産性向上につながる投資が対象になる
補助金を活用するためには、事業の実施によって生産性が向上することが前提となります。単に設備を入れ替えるだけではなく、その結果どのように作業効率が高まり、コスト削減や収益増加につながるかを示す必要があります。
たとえば、作業時間をどれほど短縮できるのか、生産コストが何パーセント低減できるのかといった、具体的な数値で効果を示すと良いでしょう。業務効率化や従業員の負担軽減につながる改善はとくに評価されやすいです。
具体的な効果を明文化し、実現可能な計画であると審査側に伝えることが肝心です。定量的な根拠がある計画は、信頼性が高くなり採択の可能性も上がります。
革新性のある取り組みが条件になる
補助金を申請する際は、従来の業務を踏襲するだけではなく、新しい価値や視点を取り入れた計画が求められます。業界初の技術や独自性の高い工程改善など、競合他社との差別化が明確であることが重要です。革新性を伝えるためには、事業の背景にある課題やそれを克服するための手段を、具体例を交えて記載しましょう。
さらに、関連する技術や市場動向に関する調査結果を添えることで、計画の裏付けが強化されます。結果、単なる自己評価に留まらず、第三者の視点でも革新的と判断される計画になります。準備段階から徹底した分析と資料整備を進めると安心です。
グローバル枠に求められる追加条件
グローバル枠を選択する場合は、国内向け事業以上に具体的な準備が重要です。現地市場の需要調査結果や、どの国に進出するのか、輸出計画や拠点整備の見通しなどが明確になっている必要があります。
さらに、現地規制や認証取得の進捗状況も確認されることがあります。ただ海外展開を目指すというだけでは説得力に欠けるため、具体的な数値やスケジュールまで示すと効果的です。
事業の実現性や、現地パートナーとの関係性、輸送体制や販売網の整備状況なども伝えると良いでしょう。審査側に安心感を与える準備を進めることが採択につながります。
持続的な賃上げを見据えた事業計画が重要
ものづくり補助金は、単なる売上拡大だけでなく雇用改善を目的としているため、事業計画の中に従業員の賃上げに関する目標を盛り込むことが必要です。
従業員と役員、それぞれ給与支給総額ベースで年平均2%以上の賃上げを見込む計画が求められるため、経営状況を踏まえ無理のない目標設定を行いましょう。売上予測と支出計画をしっかりと練り、持続可能な水準で計画することで返還リスクを減らすことが可能です。
さらに、賃上げが従業員のモチベーション向上や人材定着に寄与することも明記すると、事業の社会的意義が伝わりやすくなります。実効性の高い計画が採択につながるポイントとなります。
基本要件に基づく具体的な数値目標を設定する

ものづくり補助金の申請では、単に革新性や事業の方向性を示すだけではなく、実現可能な具体的な数値目標を設定することが不可欠です。数値が曖昧な計画は、審査段階で信頼性を欠くため、採択されにくくなります。
ここでは、申請時に盛り込むべき基本的な数値目標について詳しく解説します。
付加価値額の年3%成長を達成する方法
付加価値額の向上は、補助金活用の成果を示す重要な指標となっています。具体的には、営業利益、人件費、減価償却費の合計が年平均3%以上成長するよう計画を立てる必要があります。
まずは現在の付加価値額を算出し、事業実施後にどの程度の上積みが可能かを予測しましょう。予測の際には、設備投資による生産性の向上やコスト削減効果など、根拠のあるデータをもとに数値を積み上げると説得力が高まります。
無理に高い目標を掲げるのではなく、実現可能な範囲で計画することが重要です。達成可能性が高い計画は審査においても信頼を得やすいでしょう。
給与支給総額または1人あたり給与の成長基準を守る
補助金の目的のひとつに、従業員の待遇改善を通じた雇用の安定があり、従業員(非常勤を含む)や役員の給与に関する明確な成長基準が設定されています。
申請にあたっては、給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上とするか、もしくは1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、都道府県の最低賃金の過去5年間(2019年度基準)の年平均成長率以上とする、いずれかを選択して計画に盛り込みます。
どちらの基準も賃上げを促進するためのものであり、申請前に自社の実績を分析し、無理のない範囲で目標を設定することが重要です。計画書には根拠や算定方法を明記し、達成可能性を示すことが採択のポイントとなります。
最低賃金を地域比+30円以上にする
地域ごとの最低賃金に加え、さらに30円以上上回る水準に設定することが補助金の条件として定められています。理由は、補助金の活用が単なる利益の確保だけでなく、地域経済や雇用改善にもつながることを重視しているためです。
現状の賃金体系を把握し、申請までに必要な調整が行えるか確認しましょう。都道府県ごとの最低賃金は毎年更新されるため、最新の金額を確認して計算する必要があります。とくに複数地域で事業を行う場合は、それぞれの拠点で条件を満たしているかの確認が重要です。無理のない調整計画を立てることが求められます。
子育てと仕事の両立支援策を計画する
仕事と家庭の両立支援も、補助金の申請において加点要素として注目されています。育児休業制度の充実や時短勤務制度の導入、テレワーク環境の整備など、従業員が安心して働ける環境づくりに向けた取り組みが必要です。
計画書には、どのような制度を導入し、従業員の負担軽減や就業継続率の向上につなげるのかを記載すると良いでしょう。制度の導入は、雇用の安定と企業イメージの向上にもつながるため、積極的に検討する価値があります。実施にかかるコストや運用方法についても併せて記載すると、計画の実現性が高まります。
特例措置の条件をうまく活用する
積極的な賃上げや最低賃金の大幅な引き上げに取り組む場合、特例措置を活用することで補助上限額の引き上げや期限の猶予といった優遇を受けられることがあります。特例を適用するためには、通常の基準を超えた目標設定や計画内容が必要になるため、申請前に自社が該当するかを確認してください。
特例を利用することで、より大規模な投資や挑戦的な計画を実現しやすくなります。制度の詳細を調べ、該当する場合は積極的に検討しましょう。しっかりと準備を整えれば、採択の可能性をさらに高めることも可能です。
申請時に見落としがちな条件と対策
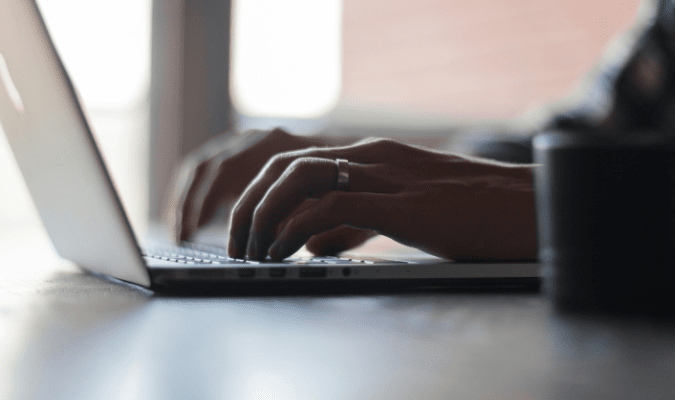
ものづくり補助金の申請においては、基本的な条件を満たしていても、見落としがちな点や予想外の落とし穴が原因で不採択や返還のリスクを招くケースがあります。とくに、制度の運用上のルールや補助事業の実施後の制約などは、事前の理解が欠かせません。
ここでは、申請時にありがちな見落としや注意点と、それに対する具体的な対策を詳しく解説します。
不適切な支援業者を選ばないために
補助金申請のサポートを行う支援業者の中には、経験や知識が乏しいにもかかわらず、高額な報酬を請求するところや、不適切な方法で申請を進めるケースがみられます。不適切な業者に依頼してしまうと、採択されても要件を満たせず返還となるリスクが高まります。
支援業者を選ぶ際には、実績や認定支援機関であるかどうかを確認し、過去の成功事例やサポート体制について十分にヒアリングを行いましょう。契約内容についても、報酬体系や成果に対する責任範囲が明確であるか確認しておくと安心です。
財産の処分制限や目的外使用に注意する
補助金を活用して購入した設備や導入したシステムには、補助金交付後も一定期間、処分や用途の変更に制限が課されます。設備やシステムを目的外で利用したり売却したりすると、補助金の返還を求められる可能性があります。
たとえば、補助事業終了から一定期間内に設備を廃棄したり第三者に譲渡した場合には違反と見なされるため、計画書の段階で運用計画を明確にしておくことが重要です。従業員にも周知し、導入した設備が計画通りに活用されているか定期的に確認する体制を整えると良いでしょう。
交付決定後の減額・返還リスクに備える
採択後に交付決定が行われても、補助金の全額が支払われるとは限りません。事業実施中に要件未達や不備が発生すると、交付額が減額されたり返還を求められる場合があります。
とくに、計画に記載した目標が著しく未達となった場合や、経費の使途が認められない場合が該当します。定期的に進捗を確認し、当初の計画通りに進められているか社内でチェックする仕組みを用意して、未然に防ぐことが重要です。問題が発生した場合には早めに事務局に相談し、是正措置を検討しましょう。
計画未達の場合の救済措置も知っておく
事業を進める中で、やむを得ず当初の計画を達成できないことがあります。そのような場合でも、一定の条件を満たせば返還が免除される場合や、猶予措置が認められる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
たとえば、自然災害や予測不能な社会的変化による影響などが該当します。事業計画が困難な状況に陥った場合は、速やかに事務局に報告し、必要な手続きを踏むことで救済措置を受けられる可能性があります。無断で計画を変更するのではなく、必ず相談して対応する姿勢が重要です。
事業計画書の整合性と条件の整備を確認する
申請書類の中でも、とくに重要なのが事業計画書です。計画書の内容に矛盾があったり、数値の根拠が不明確だったりすると、審査で大きく減点される原因になります。提出前には必ず複数人で内容を確認し、申請条件をすべて反映しているか、論理的に破綻していないかチェックするようにしましょう。
計画書に記載する目標や施策の内容についても、根拠データや背景資料をそろえておくと信頼性が高まります。第三者の視点で読み直し、改善点がないか確認する習慣が大切です。
条件を満たすために今すぐ始めるべき準備

ものづくり補助金の申請に向けては、条件を十分に理解するだけでなく、早い段階から準備を始めることが重要です。申請開始までに必要なアカウントの取得や、社内体制の整備、専門家との相談など、今すぐ取り掛かれる具体的なステップを押さえておくことで、申請時に慌てることなく対応できます。ここでは、事前準備として効果的なポイントを紹介します。
GビズIDプライムアカウントを早めに取得する
申請手続きは電子申請システムを利用して行われるため、GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。取得には事前の申し込みや本人確認書類の提出が必要で、発行までに時間がかかることもあります。申請期限が迫ってから手続きを始めると、間に合わない可能性があるため、申請を検討する段階で早めに申請しておくと安心です。
アカウントの取得後は、ログインできるか、システムの利用環境が整っているかも併せて確認しておくとスムーズでしょう。初めての利用者は、事務局が用意している操作マニュアルを一読しておくと申請時に迷わず進められます。
自社の数値を現状分析して課題を洗い出す
申請書類には、事業計画の根拠となる現状分析や数値目標が必要です。現状の付加価値額や従業員給与総額、最低賃金水準などを正確に把握し、申請時の条件を満たしているかを確認しましょう。条件を満たしていない場合は、どの項目をどの程度改善する必要があるのかを明確にすることが重要です。数値が曖昧だと説得力が低下し、不採択のリスクが高まります。
社内で定期的に数値の更新を行い、計画と現状とのギャップを可視化しておくと、申請書の作成がスムーズになります。必要に応じて、経理担当者や外部の専門家と連携してデータを整えておくと良いでしょう。
従業員との意識共有と協力体制を整える
補助金申請は経営者だけの作業ではなく、従業員全体の協力が必要です。なぜなら、事業計画に沿った業務改善や生産性向上、賃金引き上げの計画を実現するためには、現場の理解と協力が不可欠だからです。
申請前に従業員向けの説明会や個別面談を行い、計画の目的や内容を共有すると、実施後のスムーズな進行につながります。とくに最低賃金の見直しや業務フローの変更に関わる部分は、従業員の理解を得ておくことが重要です。計画の実現性を高めるためにも、定期的なミーティングを設けて情報共有を継続しましょう。
公的支援機関を活用して計画をブラッシュアップする
申請書類の完成度を高めるためには、公的な支援機関を活用するのが効果的です。商工会議所や中小企業診断士、認定経営革新等支援機関などは、計画の作成や添削、制度の解説を行っています。
とくに初めて申請する事業者にとっては、専門家のアドバイスを受けることで、条件に沿った書類作成がしやすくなります。事業計画の弱点や改善点を客観的に指摘してもらい、計画のブラッシュアップに役立てましょう。支援を受ける場合は、予約が必要なことが多いので、早めに相談の予定を立てると安心です。
専門家との無料相談で不安を解消する
補助金申請に関する不安や疑問点があれば、専門家との無料相談を活用して解消しましょう。認定支援機関やコンサルタントの多くは初回相談を無料で行っており、申請条件や事業計画の立て方、書類作成のポイントまで幅広くアドバイスを受けられます。
申請期限が近づくと相談が混み合うため、早めに予約するのが理想的です。相談を通じて、計画の改善点を明確にし、申請に自信を持てる状態に仕上げることが大切です。専門家の知見を活用することで、採択の可能性が高まります。
まとめ
ものづくり補助金は、中小企業や個人事業主が事業成長を実現するための重要な制度です。しかし、申請には厳格な条件があり、十分な準備がなければ不採択や返還のリスクを抱えてしまいます。
本記事では、事業者の基準、事業内容の革新性、生産性向上の視点、具体的な数値目標、さらには見落としやすい注意点や準備の進め方まで幅広く解説しました。ぜひ貴社の事業推進にお役立てください。
株式会社イチドキリでは、経営革新等支援機関として、条件確認から書類作成、面接対策まで一貫してサポートします。着手金不要の完全成功報酬型で、採択率80%超の実績を誇り、専門知識を活かしてお客様の事業を支えます。
申請に不安がある方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。