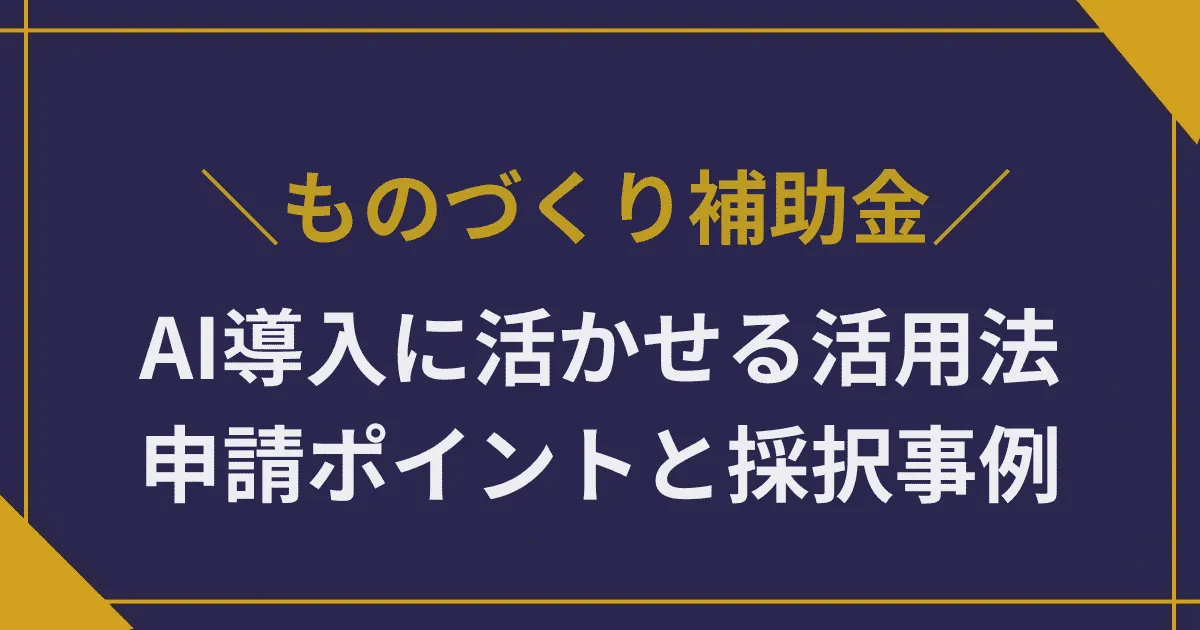AI技術は、製造業やサービス業の生産性向上や業務効率化に直結します。しかし、導入には高額な初期投資が必要で、中小企業にとっては大きな負担となりがちです。国が支援するものづくり補助金を活用すれば、AI開発やシステム導入にかかるコストを大幅に軽減できます。
さらに、申請のポイントを押さえれば採択の可能性を高めることが可能です。本記事では、補助金の概要からメリット、成功事例、申請の流れや注意点まで徹底的に解説します。
ものづくり補助金でAI導入は可能か?

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的なサービス開発や生産プロセス改善を行う際に活用可能です。AI開発やシステム導入も対象であり、条件を満たせば導入費用の一部が補助されます。ここでは、補助金の概要、補助対象経費、補助額・補助率、対象となる事業者条件について詳しく解説します。
ものづくり補助金の概要と目的
ものづくり補助金は、経済産業省が推進する中小企業向け支援策であり、生産性向上や競争力強化を目的としています。革新的な商品・サービスの創出や海外需要の獲得を目指した機器投資・システム導入を図る事業計画を策定することで申請対象となります。
支援対象は製造業に限られず、飲食業や小売業など幅広い業種が対象です。申請の際は、革新的な取り組みや新規性が求められる点に注意が必要です。ただの既存業務の置き換えでは採択されにくいため、データ分析や自動化などを通じて付加価値向上が明確な計画を作成しましょう。
補助金は事後精算で支給される仕組みのため、先行投資の準備も欠かせません。AI導入にかかるハードウェアやソフトウェア費用を有効に活用し、企業の成長戦略に直結させることが重要です。
AI導入で申請できる経費の種類
AI導入に関連する申請可能経費には、ハードウェアやソフトウェアの購入費、クラウド利用料、外注費、専門家経費などが含まれます。たとえば、画像検査AIを稼働させる専用機器や、AIモデルを構築するための開発環境も対象となります。また、データ収集用センサーや業務システムと連携するソフトウェアも補助対象です。
さらに、外部のシステムインテグレータへ依頼する開発費用や技術導入費も認められる場合があります。重要なのは、補助対象経費を明確に区分し、申請書に根拠を添付することです。
誤って対象外経費を計上すると審査に不利となる可能性があります。申請前には、経費分類や見積書の整備を徹底し、AI導入の効果を最大化できる計画として整理しておきましょう。
補助金額と補助率の最新情報
ものづくり補助金の補助額は、事業規模や申請類型によって異なります。製品・サービス高付加価値枠では最大3,500万円、グローバル枠では最大4,000万円です。補助率は中小企業で1/2、小規模事業者では2/3となります。
AI導入プロジェクトは高額になりやすいため、補助率を考慮した自己負担額の計算が欠かせません。また、最低賃金引上げや付加価値増加を条件とする加点措置も存在し、条件を満たすと補助上限の引き上げが期待できます。
申請にあたっては、想定する補助額に応じた事業計画書を作成し、資金繰りをシミュレーションしておくことが採択後の円滑な事業実施につながります。採択率向上にも直結するため、補助金額の上限や加点条件は必ず最新情報を確認しましょう。
補助対象となる中小企業の条件
ものづくり補助金の申請には、対象となる事業者の条件を満たす必要があります。製造業やサービス業を問わず、資本金や従業員数が中小企業基本法に定める範囲内であることが前提です。さらに、賃上げや雇用維持に関する要件が設けられており、給与支給総額や最低賃金の引き上げを事業計画に盛り込む必要があります。
また、過去に不正受給や重大な法令違反がある場合は申請が認められません。AI導入を含む事業は、単なる業務改善ではなく付加価値向上や生産性向上を明確に示すことが求められます。
ものづくり補助金でAI導入するメリット

AIを活用したプロジェクトは、補助金を用いることで経済的負担を軽減しながら実施できます。資金面の支援に加え、業務効率化や新規事業開発など、企業価値を高める効果が期待できるでしょう。ここでは、補助金を活用してAIを導入することで得られる主なメリットを整理し、実際の業務改善や収益向上につながる可能性を具体的に示します。
人手不足解消と生産性向上につながる効果
AI導入は、人材不足に悩む中小企業にとって強力な改善策となります。画像認識や自然言語処理を活用したシステムは、従来人手に頼っていた業務を自動化し、作業時間を大幅に短縮します。
たとえば、製造ラインでの不良品検知や在庫確認などの単純作業は、AIによる連続稼働で効率化が可能です。人手を削減できるだけでなく、従業員はより付加価値の高い業務に専念できるため、組織全体の生産性も向上します。
補助金を活用すれば、高額なAIシステムや専用設備を導入しやすくなり、投資回収までの期間を短縮できます。業務改善による成果は売上や利益にも波及し、長期的には企業競争力の強化にも直結するでしょう。現場の人手不足解消と生産性向上を同時に実現できる点は、補助金活用の大きな魅力です。
品質管理・検査精度の向上事例
AIは品質管理や検査業務でも力を発揮します。製造業では、従来の目視検査では見逃しがちな微細な不良も、AIを活用した画像認識で高精度に検出可能です。たとえば、金属部品や食品製造の分野では、微小な傷や異物混入をリアルタイムで判定できるAIシステムが導入されています。
導入初期は学習用データの収集や調整が必要ですが、運用が軌道に乗ればヒューマンエラーが減少し、品質のばらつきが抑えられます。補助金を利用することで、こうした先進的な検査装置やソフトウェアの導入コストを大幅に削減可能です。
品質安定は顧客満足度の向上やクレーム削減にも直結します。結果として、企業ブランドの信頼性が高まり、受注拡大や取引先評価向上にもつながることが期待できます。
データ活用と業務効率化の加速
AIは膨大なデータを解析し、業務改善に役立つ可能性を示します。製造現場で収集した稼働データや販売実績をAIで分析すれば、生産計画の最適化や在庫管理の高度化が実現できます。これにより、無駄な在庫や余分な作業が減少し、業務の効率化が加速するでしょう。
さらに、補助金を活用することで、データ基盤の整備やAI解析システム導入に必要な費用を抑えられます。AIの導入は単なる自動化にとどまらず、意思決定の迅速化や将来的な新規事業の開発にもつながるでしょう。過去のデータをもとに需要予測を行えば、設備稼働率や納期管理の精度も高まります。
結果として、利益率の改善や経営リスクの低減が期待できます。データを資産として活かす体制を整えることが、長期的な競争優位性につながるでしょう。
新規事業やサービス開発の後押しになる理由
補助金を活用したAI導入は、既存業務の改善だけでなく、新規事業の創出にもつながります。たとえば、製造データを活用した遠隔監視サービスや、顧客行動を分析するマーケティングツールなど、AI技術を応用したサービス展開が可能です。
開発や検証には高額な投資が伴いますが、補助金を活用することで初期リスクを低減可能です。さらに、新規事業は補助金審査においても評価されやすく、付加価値向上や市場拡大が明確であれば採択率が高まります。
AIを組み込んだサービスは他社との差別化にも直結し、中長期的には新たな収益源の確保にも貢献します。補助金を用いたAI導入は、事業拡大や市場競争力の強化を目指す中小企業にとって重要な成長戦略となるでしょう。
AI導入でものづくり補助金に採択された事例

補助金を活用したAI導入は、多くの企業で成果を上げています。実際の採択事例を知ることで、事業計画作成の参考になり、採択率向上にもつながるでしょう。ここでは、製造業やサービス業で成功した事例を紹介し、どのようにAIが業務改善や新規事業に貢献したのかを解説します。
画像検査AIを導入した製造業の事例
金属加工を行う中小製造業では、従来の検査工程が熟練作業者の目視に依存していました。長時間作業や人員不足により、不良品の見逃しや検査遅延が課題となっていました。補助金を活用して導入した画像認識AIは、高精度カメラと組み合わせることで微細な傷や異常を瞬時に検出できます。
結果として、検査時間は従来の半分以下となり、不良品率も大幅に低下しました。さらに、夜間も自動稼働できるため、人員配置の最適化が進み、残業削減にもつながっています。補助金により初期費用を抑えられたことで、短期間で投資回収が可能となり、企業全体の収益改善にも寄与しました。
このような事例は、審査においても生産性向上の具体例として評価される傾向があります。
生産計画最適化システムで効率化に成功した事例
食品製造業の企業では、受注変動に対応する生産計画が複雑化しており、現場の負担が大きな課題でした。補助金を活用して導入したAI生産計画システムは、過去の受注データや在庫情報をもとに最適なスケジュールを自動生成します。
導入後は、製造ラインの稼働率が向上し、在庫過多や欠品の発生が減少しました。さらに、業務担当者は手作業による調整作業から解放され、分析や改善活動に時間を充てられるようになりました。補助金がなければ難しかった大規模システムの導入が、経済的負担を軽減した形で実現できた点も大きな成果です。
生産計画の効率化は利益率向上に直結し、審査においても経済的効果を示せる優れた事例となりました。
既存業務をDX化したサービス業の事例
サービス業でもAI導入による補助金活用事例は増えています。清掃業を営む企業では、現場の作業報告や品質確認が紙ベースで行われており、情報共有の遅れや記録の漏れが課題でした。補助金を活用して開発したAI搭載の管理システムは、清掃状況を画像で自動認識し、クラウド上で進捗を共有できる仕組みです。
導入後は、報告業務の自動化によって管理者の負担が軽減され、現場の作業効率も向上しました。さらに、データを分析することで作業時間や人員配置の最適化が可能となり、経費削減にも成功しました。補助金により初期開発コストが低減されたため、導入ハードルが下がり、DX推進を加速できた事例です。
業務の可視化と効率化を同時に実現したことで、企業価値の向上にもつながりました。
申請方法と採択率を上げるポイント
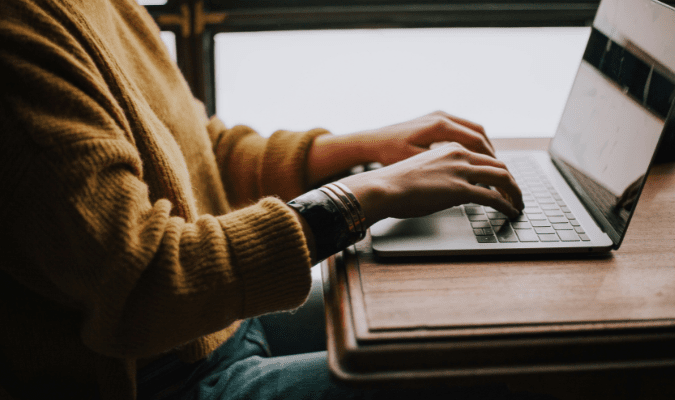
ものづくり補助金を活用してAIを導入するには、正しい申請手順と採択されやすい計画づくりが重要です。申請書類の不備や計画内容の不足は採択率を下げる要因となります。ここでは、申請の流れ、審査で評価される計画の作成方法、採択率向上のための工夫、専門家を活用した成功事例について解説します。
申請手順と必要書類
ものづくり補助金の申請は、事業計画書の作成から始まります。まず、事業の目的や導入するAIシステムの概要、期待される効果を整理します。次に、補助対象経費や資金計画を明確にし、見積書や仕様書などの裏付け資料を揃えることが必要です。申請は電子申請システムで行われ、提出後は審査委員による書類評価が行われます。
採択後は交付申請や実績報告が求められ、補助金は事業完了後に精算払いで支給されます。書類は正確さと整合性が求められるため、数字の矛盾や記載漏れは避けましょう。スケジュールに余裕を持ち、申請締切の1〜2週間前には最終チェックを行うと安心です。手順を理解し、段階ごとに必要な書類を整えることで、スムーズな申請が可能となります。
ものづくり補助金の申請手順について、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ものづくり補助金の手続きの流れを完全解説|申請から補助金受給までの全ステップ
審査で評価されるAI活用計画の書き方
採択される申請書には、AI導入による付加価値向上が明確に示されています。事業計画では、AIをどの工程に適用し、どのような改善効果を生むかを具体的に記載しましょう。たとえば「画像検査AIで不良品率を30%削減」「生産計画AIで在庫を20%圧縮」など、数値を用いた効果予測が有効です。
さらに、収益改善や新規事業展開といった経済的効果も盛り込むと評価が高まります。単なる業務効率化ではなく、企業全体の成長につながる計画であることを強調することが大切です。
また、AI導入の背景や市場ニーズも説明すると、審査側に納得感を与えられます。文章は簡潔に整理し、図表を用いることで視覚的にも理解しやすい計画書に仕上げましょう。
採択率向上のための加点項目の意識
ものづくり補助金には、審査で有利になる加点項目があります。代表的なものに、最低賃金の引き上げ計画、給与総額の増加、環境対応やDX推進への取り組みなどです。これらを事業計画に反映させると、審査評価が高まり採択率向上につながります。とくにAI導入はDXの一環として位置付けやすく、加点対象になりやすい傾向があります。
また、地域経済への貢献や雇用維持・拡大など、社会的意義を示すことも評価されやすいです。計画書には、補助事業の成果を定量的に示すだけでなく、加点項目を意識した取り組みを明確に記載しましょう。
加点は単なる形式的な記載ではなく、実際の事業方針と整合することが重要です。採択率を高めるための戦略として、初期段階から加点要素を意識した設計を行うことを推奨します。
専門家サポートを活用した成功事例
初めて申請する企業にとって、書類作成や事業計画の策定は大きな負担になるでしょう。専門家のサポートを活用した企業では、採択率の向上や申請負担の軽減に成功した事例が多く見られます。
たとえば、補助金コンサルタントや認定支援機関に依頼することで、審査基準に沿った計画書作成や加点項目の整理がスムーズになります。ある製造業では、専門家の助言をもとにAI活用による付加価値向上策を具体化し、初申請で採択に成功しました。
サポートを受けることで、審査に必要なデータ整理や数値計画の精度も向上します。補助金申請は専門知識と時間を要するため、早期段階から外部の力を取り入れることで、採択の可能性を最大化できるでしょう。
ものづくり補助金の申請を専門家へ依頼するメリットについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ものづくり補助金の申請を専門家に任せるべき理由と業者選びのポイント
ものづくり補助金でAI導入するときの注意点
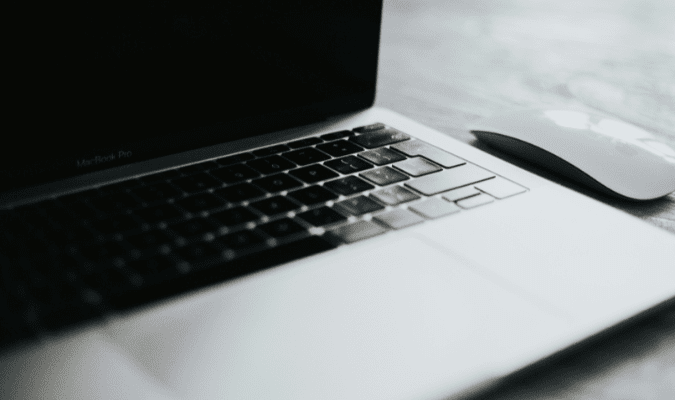
補助金を活用したAI導入は魅力的ですが、注意点を理解せずに進めると不採択や計画遅延につながります。申請段階だけでなく、事業実施後の運用も含めてリスクを把握することが重要です。ここでは、補助対象外となる可能性やコスト面の確認、人材・セキュリティ対策、事業計画の作り方に関する注意点を整理します。
AIを導入しただけでは補助対象外になる場合がある
AIシステムを導入するだけでは補助金の対象とならない場合があります。審査では、導入によりどのような付加価値が生まれるか、どの工程が改善されるかが重視されます。ただの既存業務の置き換えや、効果が不明確な導入は不採択のリスクが高まるでしょう。
たとえば、外部ベンダーのクラウドAIサービスを利用するだけでは、事業計画としての新規性や革新性が不足すると評価されがちです。補助金の趣旨は、生産性向上や収益改善に資する設備投資を支援することにあります。
AI導入が事業成長に直結することを明確に説明できる計画書を作成することが必須です。導入後の成果を数値化し、経営改善や新サービス開発につながることを示すことで、補助対象として認められやすくなります。
導入コストと自己負担額の把握が必要
補助金は導入コストの一部を負担してくれますが、全額を補填できるわけではありません。補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3が一般的であり、残りは自己負担となります。
また、補助金は事業完了後の精算払いとなるため、先行投資の資金繰りを確保しておくことが欠かせません。AI導入は、ハードウェア・ソフトウェア・外注費用を含めると高額になる傾向があります。
見積段階で補助対象経費を正確に把握し、自己負担額を明確にしておくことが重要です。資金調達を誤ると、採択後に事業が進まないリスクもあります。事業計画策定時には、補助金交付までのキャッシュフローも含めて検討し、実行可能な計画に仕上げましょう。
専門人材・セキュリティ対策を確保しておく
AI導入には専門知識が必要です。システム開発や運用を内製化できない場合は、外部のシステムインテグレータや技術者の協力が欠かせません。補助金申請では、外部連携や保守体制の有無も審査対象となることがあります。
また、AIシステムはデータを扱うため、セキュリティ対策が不十分だと情報漏洩リスクが高まります。具体的には、アクセス制御や暗号化、バックアップ体制などを整備し、安全な運用計画を立てることが重要です。
対策を計画書に反映させることで、審査でも信頼性が高い事業と評価されます。専門人材とセキュリティの確保は、事業の持続可能性を高め、導入後のトラブルを未然に防ぐために欠かせない要素です。
事業計画で効果を定量的に示すことが重要
採択を目指すには、AI導入の効果を定量的に示すことが必要です。たとえば、生産ラインの稼働率向上、作業時間削減率、在庫圧縮率、売上や利益率の改善見込みなどを数値で提示すると、審査員に伝わりやすくなります。
曖昧な表現や定性的な説明だけでは、事業の実効性が疑問視される恐れがあります。また、数値化は補助金受給後の実績報告にも役立つでしょう。実績報告では、事業計画で示した成果との比較が求められるため、計画段階で指標を設定しておくことが重要です。
定量的な効果を明確にすることは、補助金採択だけでなく、AI導入の社内説得や投資判断にも有効です。計画と実績の一貫性が確保されれば、次回以降の補助金申請にもプラスにはたらきます。
関連記事:AIが人件費をどこまで削減できるのか?電話営業・テレアポ自動化の未来|AIテレサポ
まとめ
AI導入は中小企業の生産性向上や業務効率化に直結しますが、初期投資の負担が課題となりがちです。ものづくり補助金を活用すれば、AIシステム開発や導入にかかる費用を大幅に抑えつつ、事業拡大や新規サービスの創出を実現できます。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として、ものづくり補助金をはじめとした補助金申請のサポートを行っています。着手金0円・完全成功報酬型で、事業計画書作成から申請、交付、実績報告までフルサポートが可能です。
AI導入を検討中の中小企業や小規模事業者は、補助金を活用した投資戦略を進める絶好の機会です。
補助金を活用して事業成長を加速させたい方は、まず無料相談をご利用ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。