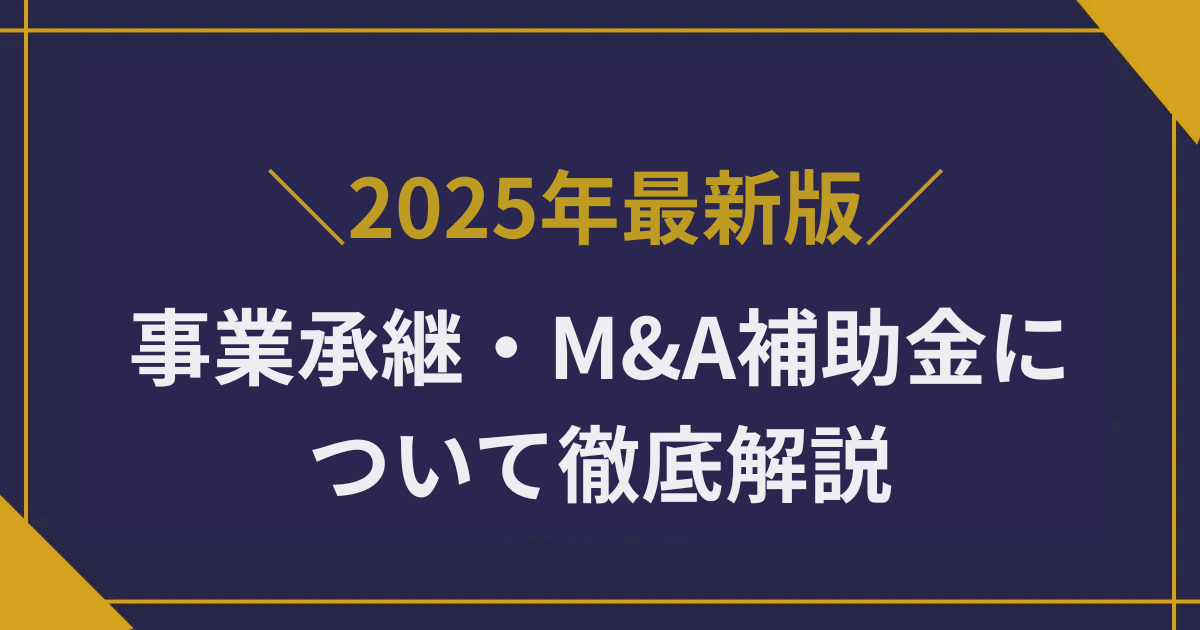中小企業の経営を次世代へと引き継ぐ「事業承継」や「M&A(合併・買収)」は、日本経済において極めて重要なテーマです。近年では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化し、事業の継続を危ぶむ声も増えています。
こうした状況を背景に、国は中小企業の事業承継を支援するために「事業承継・M&A補助金」を設けています。この制度を活用することで、承継や統合にかかる費用負担を軽減し、円滑な経営引継ぎを実現できます。本記事では、補助金の概要から最新の2025年度情報、採択のポイントまでを詳しく解説します。
- 事業承継・M&A補助金とは
- 事業承継・引継ぎ補助金の目的や背景
- 事業承継・M&A補助金の支援枠
- 2025年度の事業承継・M&A補助金
- 事業承継・M&A補助金の事例
- 事業承継・M&A補助金に採択されるためのポイント
- まとめ
事業承継・M&A補助金とは
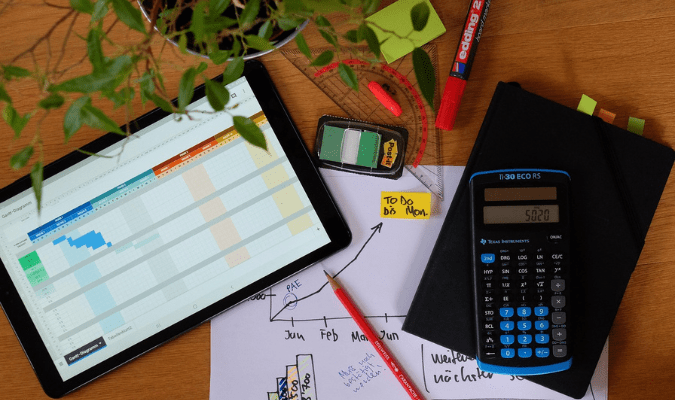
事業承継・M&A補助金とは、中小企業が事業承継やM&Aを契機として経営革新を図る際に、必要となる設備投資や専門家費用などを支援する国の制度です。補助率は1/2〜2/3以内、補助上限額は最大2,000万円と高額な支援を受けることができます。
この補助金は単なる経営支援にとどまらず、M&A後の統合(PMI)や廃業に伴う再チャレンジまでカバーする幅広い内容が特徴です。次に、この補助金が設立された目的や背景を見ていきましょう。
事業承継・引継ぎ補助金の目的や背景
日本では中小企業が全企業の99%を占めており、その多くが経営者の高齢化によって事業承継の時期を迎えています。しかし、後継者不足や承継費用の負担が大きく、黒字廃業に追い込まれるケースも少なくありません。
この課題に対応するため、国は「事業承継・M&A補助金」を創設し、経営資源の円滑な引継ぎを支援しています。補助金の目的は、単なる事業存続ではなく、承継をきっかけにした経営革新と生産性向上の促進です。承継を機に新規投資やデジタル化を進めることで、持続可能な企業経営を目指すことが期待されています。
事業承継・M&A補助金の支援枠
事業承継・M&A補助金には4つの支援枠が設けられており、企業の状況や目的に応じて選択できます。それぞれの枠には補助上限・補助率・対象経費が定められており、申請内容に応じて採択可否が決定されます。
事業承継促進枠
この枠は、5年以内に親族内承継や従業員承継を予定している企業が対象です。設備投資や店舗改修費などの経費が補助され、上限は最大1,000万円です。
特に、一定の賃上げを実施する場合は補助上限が引き上げられるため、従業員の待遇改善と経営基盤の強化を両立できます。事業の安定承継を目指す企業にとって、最も基本的な支援枠といえるでしょう。
専門家活用枠
M&Aの実施に伴い、ファイナンシャルアドバイザー(FA)や仲介業者などの専門家を活用する際の費用を支援する枠です。買い手・売り手双方が対象となり、上限は最大2,000万円。
補助率は1/2〜2/3以内で、M&A支援機関登録制度に登録された専門家による支援が条件です。DD(デューデリジェンス)費用や表明保証保険料も対象となるため、安心して取引を進めることができます。
PMI推進枠
PMI(Post Merger Integration)とは、M&A後の経営統合プロセスを指します。PMI推進枠では、統合に伴う設備投資や専門家費用を補助し、上限は最大1,000万円です。M&A後の生産性向上や組織融合を円滑に進めるための支援であり、買収後の混乱を防ぎ、経営シナジーを最大化することを目的としています。
廃業・再チャレンジ枠
事業承継やM&Aに伴い、既存事業を廃業して新たなビジネスに挑戦する場合に適用されます。補助上限は150万円で、解体費・在庫処分費・原状回復費などが対象です。他の枠と併用申請が可能であり、廃業後の再スタートを後押しする柔軟な支援策となっています。
2025年度の事業承継・M&A補助金

2025年度(令和7年度)も、事業承継・M&A補助金は引き続き実施される予定です。政府は中小企業の生産性向上と賃上げ促進を掲げており、前年同様に多くの中小企業が対象となります。
また、申請はすべて電子申請(Jグランツ)で行われ、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。最新情報は公式サイトや中小企業庁の発表で随時確認することが重要です。
2025年事業承継・M&A補助金の特徴
2025年度は、従来の補助内容に加え「生産性向上」と「賃上げ実施」がより強調されています。これにより、補助上限の引き上げ対象が拡大し、設備投資型の事業に有利な制度設計となっています。また、M&Aにおける専門家活用の条件も見直され、より透明性の高い支援が期待されています。
申請スケジュール
直近の第12次公募期間は2025年8月22日(金)~2025年9月19日(金) 17:00まででした。
2025年10月17日に第13次公募要領が公開され、公募期間は2025年10月31日(金)〜2025年11/28(金) 17:00までとなります。
スケジュールがタイトにならないよう、GビズIDの取得や事業計画書の準備は早めに行うことが望ましいです。
事業承継・M&A補助金の事例
実際に補助金を活用して成功した事例を紹介します。これらは、事業承継をきっかけに新しい挑戦を実現した中小企業の好例です。
あたらしや旅館
奈良県天川村にある老舗のあたらしや旅館は、先代の体調不良をきっかけに後継者不在となったため、従業員であった現事業主が養子縁組によって2022年に事業を承継しました。事業承継・M&A補助金を活用し、地域観光のニーズに合わせた改修を実施。
設備費を中心に補助を受け、浴場のろ過器更新や浴槽の改修、広間の畳入替、脱衣所拡張工事などを完了しました。これにより施設の快適性が向上し、宿泊客からも高評価を得ています。公衆浴場の許可取得後は、日帰り入浴と食事付きプランを新たに展開する予定です。
今後は観光客の増加に対応し、地域の飲食・温浴需要を取り込むことで、天川村全体の観光満足度向上と地域経済の活性化を目指しています。
参照:令和5年度 補正予算7次公募 事業承継・引継ぎ補助金事例集 | 事業承継・M&A補助金
株式会社カキモト
奈良県に本社を構える製造業の株式会社カキモトは、事業承継・M&A補助金を活用し、次世代型のものづくり体制への転換を進めています。現経営者が76歳と高齢であり、2029年に長男への承継を目指す中、補助金を活用して工場の自動化・省力化を推進しました。
具体的には、半導体加工機部品や金属工芸品のバリ取り工程に最新式メタルエステを導入し、生産速度と品質の大幅な向上を実現しています。
さらに工場内の電気配線や照明をLED化することで、省エネルギー化と安全性の強化を両立しました。これらの取り組みにより、従業員の意識改革が進み、次世代製造施設への移行が着実に進行しています。今後は銅やアルミなど新素材を活用した製品開発にも挑戦し、自社ブランドの確立と環境負荷の低減を目指しています。
参照:令和5年度 補正予算7次公募 事業承継・引継ぎ補助金事例集 | 事業承継・M&A補助金
株式会社アクシュワン
福岡県の食料品製造業である株式会社アクシュワンは、事業承継・M&A補助金を活用し、地元企業のマルボシフーズ株式会社を承継しました。2021年11月に株式を取得し、冷凍食品と液体調味料の製造ノウハウを融合させたことで、両社の強みを活かした新たな製品開発を実現しています。
補助金を活用して小袋充填機を導入し、「一食単位の小袋調味料」の開発・量産体制を整備しました。これにより、飲食チェーンやEC販売事業者への営業範囲が拡大し、商談件数も増加しています。
さらに、地域特産品を活用した小袋商品のサンプル開発にも着手し、地元産業との連携強化を推進中です。今後は取引先の独自ニーズに合わせたオリジナル調味料の開発を進め、ブランド価値と販路拡大の両立を目指しています。
参照:令和5年度 補正予算7次公募 事業承継・引継ぎ補助金事例集 | 事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金に採択されるためのポイント

補助金の採択率を高めるには、制度理解と計画的な準備が欠かせません。以下の4つのポイントを意識することで、申請成功の可能性を高められます。
書類の不備がないようにする
補助金申請では、書類不備が理由で不採択になるケースが多く見られます。申請様式や必要書類の記載ミス、添付漏れ、提出形式の誤りなど、基本的な確認不足が原因となることが少なくありません。特に電子申請(Jグランツ)では、ファイルの拡張子やデータ容量に制限があるため、事前に仕様を確認しておくことが重要です。
また、経費見積書や契約書の発行日・金額が補助事業期間と整合しているかを確認する必要があります。提出前には第三者によるチェックを行い、複数人で誤りを防ぐ体制を整えましょう。書類の正確性は、事業計画の信頼性にも直結します。
採択基準に沿った構成にする
採択審査では、事業の新規性、波及効果、地域経済への貢献、生産性向上への具体的な成果が重視されます。単に「設備を更新する」だけではなく、「承継を契機にどのように成長戦略を描くか」を明確にすることが鍵です。
例えば、事業承継促進枠では生産性向上の定量的な目標を、PMI推進枠では統合によるシナジー効果を数値で示すことが求められます。採択者の多くは、事業の社会的意義や持続可能性を説得的に説明しています。補助金の目的である“経営革新”を自社の計画にどう反映するかを意識し、申請書の構成を審査項目に合わせて整理しましょう。
最新の制度を把握する
補助金制度は年度ごとに見直しが行われ、補助率や上限額、対象経費が変更される場合があります。2025年度は「賃上げ実施企業の優遇」や「PMI支援の拡充」など、新たな要素が追加される予定です。そのため、過去の情報を流用せず、必ず最新の公募要領を確認しましょう。特に、申請期間や電子申請システムの仕様変更には注意が必要です。
GビズIDプライムアカウントの取得にも1〜2週間かかるため、早めの準備が不可欠です。最新制度を正確に理解することは、採択されるだけでなく、補助金の適切な活用にもつながります。常に中小企業庁や事務局サイトをチェックし、最新動向を把握しましょう。
専門家の支援も視野にいれる
初めて補助金申請を行う企業にとって、書類作成や採択戦略を独自で進めるのは難易度が高い場合があります。中小企業診断士、公認会計士、M&Aアドバイザーなどの専門家に依頼することで、申請内容の精度を大幅に高めることができます。
特に、採択実績のある専門家は審査員が重視するポイントを把握しており、説得力のある事業計画書の作成をサポートしてくれます。
また、承継後の経営改善や財務管理の体制づくりにも助言を得られるため、補助金を“資金調達”だけで終わらせず、経営基盤強化のチャンスとして活かせます。外部の知見を取り入れることで、採択率と実行力の両面で成果を上げやすくなります。

まとめ
事業承継・M&A補助金は、後継者問題に直面する中小企業を支援し、新たな成長への道を開く重要な制度です。承継・統合・廃業といった経営転換の場面で活用できるため、自社の状況に合った支援枠を選択することが成功の鍵となります。
2025年度も補助金は継続される見込みであり、採択に向けた準備を早めに進めることが求められます。公募要領の確認や専門家への相談を通じて、円滑な申請と事業成長を目指しましょう。
株式会社イチドキリは認定支援機関として、着手金0円・完全成功報酬で制度選定〜計画・申請まで伴走します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。