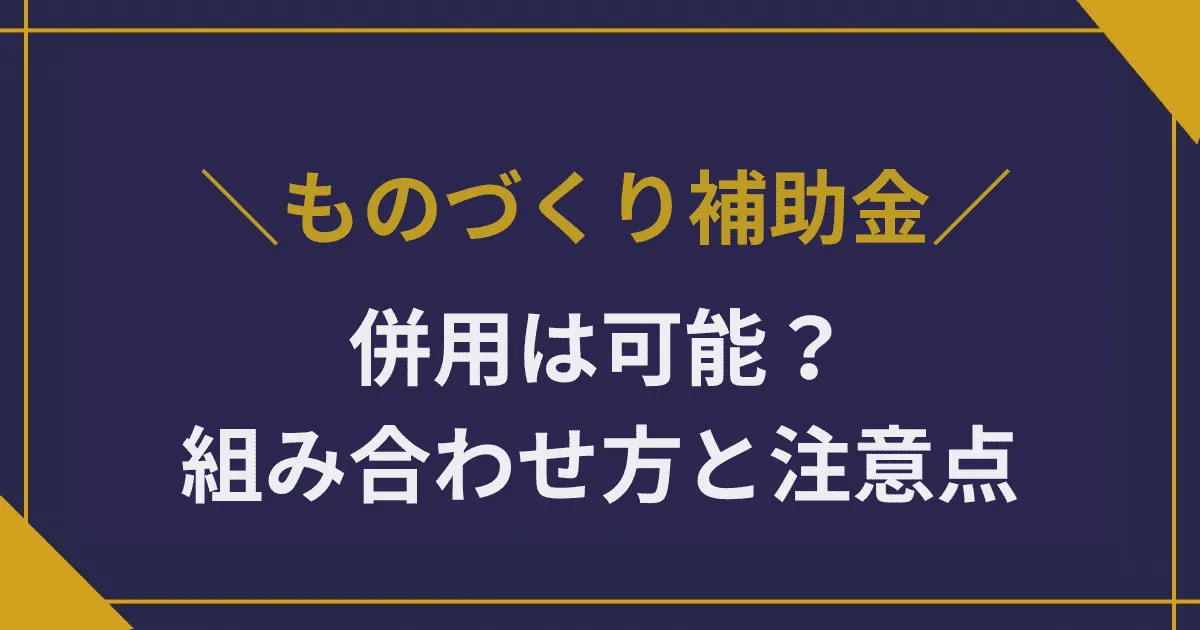中小企業や個人事業主にとって、補助金は事業成長や設備投資の大きな支えとなります。ものづくり補助金はとくに人気の高い制度であり、製造業だけでなく幅広い業種で生産性向上を目指す事業に活用できます。
しかし、併用には明確なルールや注意点があり、誤ると不正受給となる場合もあるので注意が必要です。ここでは、ものづくり補助金と他補助金の併用条件、組み合わせ例、メリットとデメリットを整理し、安全かつ効果的な活用方法を解説します。
- ものづくり補助金と併用できる補助金の基本
- ものづくり補助金と相性の良い補助金の組み合わせ例
- 併用申請を検討する際の注意点
- 補助金を併用するメリット
- 補助金を併用するデメリット
- ものづくり補助金の併用活用を成功させるコツ
- まとめ
ものづくり補助金と併用できる補助金の基本
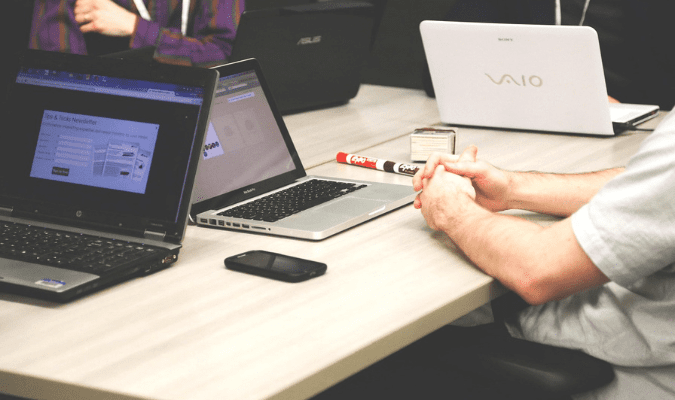
ものづくり補助金を活用する際、多くの事業者は他補助金との同時利用を検討します。併用が可能であれば、設備投資や新規事業への資金確保がより容易になります。
ただし、すべての補助金が自由に組み合わせられるわけではありません。ここで、対象事業や申請条件を理解し、どの補助金が併用できるのかを整理しましょう。
ものづくり補助金の概要と対象事業
中小企業の競争力強化を目的とするものづくり補助金は、革新的な製品開発やサービス改善、設備導入などを支援する制度です。国による支援施策として位置づけられており、経済産業省が管轄しています。応募対象となるのは、付加価値の高い商品を生産しようとする製造業だけでなく、一定の基準を満たす小売・サービス業も対象です。
主な支援内容は、機械装置費やシステム構築費などの設備投資に対する補助で、補助率や上限額は企業規模や申請枠により異なります。
また、申請には経営革新の要素が求められ、既存業務の延長線上ではなく新たな挑戦であることの証明が必要です。審査では、革新性、市場性、収益性といった観点から計画の実現性が問われます。戦略的に内容を設計すれば、事業成長の強力な後押しとなる補助制度です。
併用可能な補助金の種類と条件
ものづくり補助金は、他の国や自治体の補助金制度と併せて活用することが可能です。ただし、すべての補助金が自由に併用できるわけではなく、それぞれの制度に応じた条件や制限が定められています。
併用が可能とされている主な制度には、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金などがあります。たとえば、IT導入補助金ではソフトウェア導入に関する支援が中心であり、製造設備を補助対象とするものづくり補助金とは経費の対象領域が異なるため、明確に分けることが前提です。
一方、併用不可となる例として、同一設備に対して2つの補助金を申請するケースが挙げられます。これは二重受給とみなされ、申請の時点で却下または採択後に返還指示を受ける可能性が高くなります。
補助金ごとの公募要領に併用可否や注意点が明記されているため、申請前の確認が必要です。
併用できるケースとできないケースの違い
複数の補助金を活用する際、併用が認められるケースと禁止されるケースが存在します。併用が可能なケースは、補助金ごとに事業の目的や対象経費が明確に分かれている場合です。
たとえば、製造機械の導入をものづくり補助金、販路開拓を小規模事業者持続化補助金、業務システム構築をIT導入補助金といった形で役割を分けて申請する構成であれば、重複が発生しないため併用が認められる傾向にあります。
反対に、併用不可となるケースは、同一の経費や支出を複数の制度で申請した場合です。たとえば、同じ製造設備の取得に対して複数の補助金を適用する行為は、制度上のルール違反となります。
さらに、時期的な重なりによって事実上の併用と判断される例もあるため、計画段階で対象経費・時期・成果を明確に区分する必要があります。
ものづくり補助金と相性の良い補助金の組み合わせ例

ものづくり補助金の採択率や補助上限を最大限に活かすには、他の補助金との組み合わせを考えると効果的です。費用負担をさらに軽減できるうえ、異なる目的の施策を同時に進めることが可能です。ここでは、併用しやすい代表的な補助金との組み合わせ例を紹介します。
事業再構築補助金との併用パターン
ものづくり補助金と事業再構築補助金は、対象範囲や目的が異なるため、条件を満たせば併用が可能です。事業再構築補助金は業態転換や新市場の開拓を支援する制度であり、大胆なビジネスモデル変更に取り組む企業を対象としています。
一方、ものづくり補助金は設備導入や製品開発を通じた業務効率化や生産性向上が目的です。たとえば、事業再構築補助金で新規工場の建設を支援し、その工場に設置する最新設備をものづくり補助金で導入するパターンが併用例として考えられます。
ただし、両補助金が対象とする経費が明確に分かれていなければ、併給は認められません。交付決定前後のタイミングや費用の出所が混在していると、重複と見なされ不採択のリスクが高まります。
実行計画では経費の切り分けと導入タイミングの明確化が重要です。併用を検討する際は、スケジュールと支出計画の調整を十分に行う必要があります。
IT導入補助金との活用例
ものづくり補助金とIT導入補助金の併用は、経費の性質が異なることから併用しやすい組み合わせのひとつです。IT導入補助金は、中小企業が業務改善のためにITツールやシステムを導入する費用を支援する制度です。
一方、ものづくり補助金は生産設備の導入や製品開発にかかる費用が対象となっており、物理的な装置とデジタルソリューションを組み合わせた形で併用できます。たとえば、製造ラインを自動化する機械をものづくり補助金で導入し、その稼働を管理するシステムをIT導入補助金で整備するような構成です。
この活用方法により、製造現場のDXを実現しながら、両制度の補助対象範囲を最大限に活かすことが可能になります。申請時には、事業目的や経費項目を明確に分離し、導入プロセスを段階的に説明することが必要です。要件を満たせば、高い相乗効果を得られる併用パターンといえるでしょう。
小規模事業者持続化補助金との同時活用のポイント
小規模事業者持続化補助金とものづくり補助金の併用には、申請内容の切り分けが重要です。持続化補助金は、販路開拓や販売促進にかかる費用を補助する制度であり、広告宣伝費やホームページ制作費などが対象となります。
一方で、ものづくり補助金では、業務の効率化や生産性向上に資する機械装置の導入が支援されます。たとえば、製造機器を導入して生産能力を強化し、その後に新たな販路開拓のためのWeb広告を出すという流れで活用すると、両制度の目的が明確に分かれた併用が可能です。
ただし、同時期に重複する経費が見られると併給不可となるため、対象事業の範囲を分けた上で、それぞれの計画書に具体的な内容を記載しなければなりません。採択後の報告においても、支出のトラッキングや領収書の整理が求められます。計画段階で全体像を描き、経費と目的を明確に設定することがポイントです。
併用申請を検討する際の注意点

補助金を複数申請する場合、魅力的な資金調達方法に感じられますが、注意点を無視すると大きなリスクにつながります。二重受給や書類不備は不採択や返還の原因となりかねません。安全に併用するためには、事前の確認と計画的な準備が求められます。ここでは申請時にとくに重要なポイントを整理します。
同一事業での二重受給が認められない理由
補助金制度において、同一の事業内容で複数の補助金を同時に申請する行為は原則として認められていません。二重受給と呼ばれ、重大な規定違反と判断されます。
国や自治体の補助金は、事業者が一定の目的に対して必要な経費を補う形で交付されます。同一経費に対して複数の公的資金が投入されると、過剰な支援につながり、予算の公平性が損なわれる恐れが生じるのです。
さらに、交付元ごとに成果報告や実績検証が必要になるため、支出のトラッキングが困難になり、監査の際に不備が見つかるリスクも高まります。実際に二重受給が発覚した場合は、補助金の返還だけでなく、以後の制度利用に制限がかかる可能性も否定できません。
補助金制度の信頼性を維持するためにも、申請段階で事業の範囲を明確に定義し、それぞれの補助金が支援する対象と経費を分離して設計することが欠かせません。
費目を分ければ併用できるケース
複数の補助金を組み合わせる際、対象となる費目をしっかり分けていれば併用が認められるケースも存在します。これは「経費の切り分け」が明確であることが条件となり、制度ごとの目的と支援対象が重複していないことが必要です。
たとえば、製造設備の導入をものづくり補助金、業務管理ソフトの導入をIT導入補助金で申請する構成では、費目が異なるため併用が成立します。両制度の補助対象がはっきり区分されていれば、支援内容の競合は発生しません。
ただし、計画書内での記述が不明確であったり、関連性の高い費目が混在していた場合は審査時に不備とみなされる場合もあります。スムーズな採択を目指すには、導入時期・費用負担・成果物の説明を詳細に記載する必要があります。
複数制度を安全に併用するためには、費目の整理と情報の一貫性に注意を払い、制度の趣旨に適合する構成に整えることが重要です。
公募要領・FAQを必ず確認する重要性
補助金を申請する際、公募要領やFAQ(よくある質問集)を確認することは極めて重要です。制度ごとの詳細ルールや併用の可否、経費の定義などが明記されており、トラブルの回避に直結します。
たとえば、併用が認められる条件やNGとなる行為、提出書類の形式、採択後の流れなどはすべて公募要領に記載されています。FAQには過去の申請者から寄せられた質問と回答が掲載されており、実務で見落としがちなポイントにも事前に対応可能です。
また、制度は年度ごとに改訂される場合があるため、過去の情報だけに依存すると誤認や申請ミスの原因になります。必ず最新版の資料を参照し、内容に変更がないかを確認する姿勢が大切です。
申請の正確性や採択の可能性を高めるためにも、制度の原文を精読し、疑問点があれば事務局に問い合わせるなどして準備を万全に整えておきましょう。
補助金を併用するメリット

補助金を同時に活用する最大の魅力は、資金調達の幅が広がる点です。複数の制度を組み合わせることで、単独利用よりも大きな投資を実現でき、事業の成長スピードが加速します。ここでは、併用によって得られる具体的なメリットを整理し、戦略的な活用の可能性を示します。
資金調達を最大化できる利点
複数の補助金を組み合わせると、単独申請では得られない規模の資金を確保できます。ものづくり補助金は最大4,000万円前後の支援が可能ですが、事業再構築補助金やIT導入補助金を組み合わせれば、さらに数千万円規模の資金調達も実現可能です。
たとえば、新規工場の建設を事業再構築補助金で支援し、製造設備の導入をものづくり補助金で補填することで、自己資金の負担を大幅に軽減できます。加えて、IT導入補助金を利用すれば、生産管理システムや在庫管理クラウドまで一度に整備できます。
資金調達力が高まることで、大規模投資や同時進行のプロジェクトを進められるため、事業スピードが向上するでしょう。とくに中小企業にとっては、金融機関への借入依存を減らしながら成長戦略を描ける点が大きな強みとなります。
設備投資や新規事業のスピードを加速できる
補助金を併用すると、設備導入や新規事業展開のスピードが一気に高まります。資金を段階的に確保する必要がなくなるため、計画立案から実行までのリードタイムを短縮可能です。
たとえば、ものづくり補助金で生産ラインを自動化し、IT導入補助金で生産管理システムを整備すれば、稼働開始と同時に効率的な運営ができるでしょう。
さらに、販路拡大に小規模事業者持続化補助金を組み合わせれば、製造と販売の双方を同時に強化できます。事業計画を複数補助金で並行的に進めることで、競合他社よりも早く新製品を市場投入できる点は大きな優位性です。
スピード感のある経営戦略は、変化の激しい市場環境で生き残るために欠かせません。補助金併用は、このスピードを生む強力な手段となります。
複数の施策を同時に進められる効果
併用のもう一つの利点は、複数の経営課題に同時対応できる点です。単一の補助金では対象経費が限定されるため、事業の一部分しか改善できません。しかし、併用すれば生産、販売、デジタル化など複数の領域で同時に投資が可能です。
たとえば、ものづくり補助金で製造工程を改善し、IT導入補助金で業務効率化、さらに小規模事業者持続化補助金で広告宣伝を行うケースがあります。これにより、生産性向上と販路拡大を同時に実現できるでしょう。
施策を一度に進めることで、事業全体の相乗効果が生まれやすくなります。売上増加、コスト削減、顧客満足度向上など、経営指標全体にプラスの影響が期待できます。限られたリソースで最大の成果を得るためには、補助金併用は非常に有効な手段です。
補助金を併用するデメリット
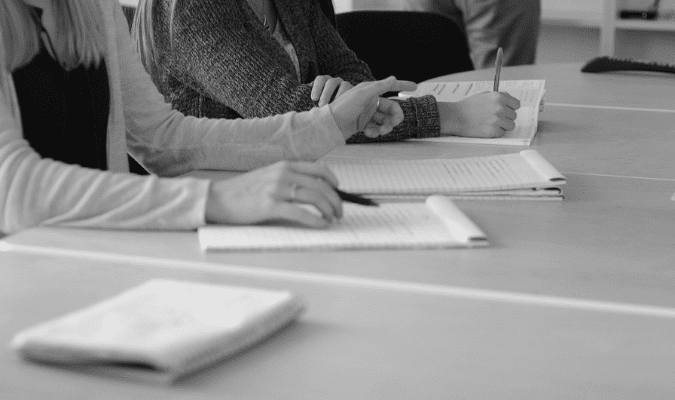
補助金の併用は魅力的ですが、必ずしもメリットだけではありません。申請や事務作業の負担、スケジュール調整の難しさ、そしてリスク管理の必要性があります。ここでは、実際に併用を検討するうえで理解しておきたいデメリットを整理します。
申請書類やスケジュール管理の負担
複数の補助金を同時に申請すると、書類作成や手続きの負担が大幅に増加します。補助金ごとに求められる事業計画書、経費明細、見積書、交付申請書、実績報告書が存在し、提出期限も異なるのです。
とくに、ものづくり補助金や事業再構築補助金は採択後に交付申請、実績報告、精算手続きまで求められるため、複数申請ではスケジュールが複雑化します。管理が不十分だと、提出遅延や不備により採択取り消しや返還のリスクが生じます。
負担を軽減するには、ガントチャートなどで全体スケジュールを可視化し、担当者や専門家と連携して進める方法が有効です。計画的な事務処理体制を整えなければ、併用のメリットは十分に発揮されません。
採択後に辞退が必要になる場合のリスク
複数の補助金に申請した結果、同一事業と判断されるケースでは、どちらかの補助金を辞退しなければならない状況が発生します。辞退手続きは想像以上に手間がかかり、計画していた事業進行に影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
たとえば、同一の生産設備に対して二つの補助金で申請した場合、採択後にいずれかを辞退し、事業内容を修正する必要があります。辞退によって補助金額が減少すれば、自己資金や借入金の追加が必要となり、資金繰りに負担がかかります。
こうしたリスクを避けるには、申請段階から事業内容や費目を完全に分離し、同一事業と誤解されない計画を策定することが大切です。準備段階の丁寧さが、後のトラブル回避につながります。
不正受給とみなされるリスクへの注意点
併用の際に最も注意すべきは、不正受給と誤解されるリスクです。補助金は国や自治体の財源で賄われているため、適正利用が強く求められます。わずかな申請不備や費用の重複でも、意図せず不正と判断される可能性も否定できません。
たとえば、領収書の日付や費目の記載が不明確で、二重計上の疑いを持たれる事例があります。また、補助事業完了後の実績報告で誤記や証憑不足があると、返還命令や今後の申請資格停止につながる可能性もあります。
リスクを避けるためには、経理管理を厳格に行い、領収書や契約書は補助金ごとに整理することが重要です。さらに、申請内容の妥当性を専門家に確認してもらうことで、安心して併用申請を進められます。
ものづくり補助金の併用活用を成功させるコツ

補助金を併用して最大限の効果を引き出すには、戦略的な進め方が求められます。資金調達の幅を広げられても、計画や管理が不十分だとメリットを活かせません。ここでは、併用申請を成功させるために押さえておきたい具体的なポイントを整理します。
事業計画を複数補助金で整理する方法
補助金を併用する場合、事業計画を複数の補助金に対応させて整理することが重要です。各補助金は目的や対象経費が異なるため、申請内容を分かりやすく切り分ける必要があります。
まず、ものづくり補助金でカバーする設備投資、IT導入補助金で対応するシステム構築、小規模事業者持続化補助金で行う販路拡大など、役割分担を明確にします。さらに、補助対象となる費目や事業内容を一覧化し、重複がないことを確認すると安全です。
事業計画書には、補助金ごとに異なる成果目標を設定すると審査にも有利です。たとえば、生産性向上、業務効率化、売上拡大など複数の成果を組み合わせ、相互に補完し合うストーリーを描きましょう。事業全体を俯瞰した計画を準備することで、複数補助金の併用がスムーズに進みます。
スケジュール管理と申請タイミングの工夫
補助金併用を成功させるには、スケジュール管理が極めて重要です。複数の補助金を申請する場合、応募開始日や締切日、交付申請、実績報告などの時期が異なるため、混乱が生じやすくなります。
まず、年間カレンダーやガントチャートを作成し、各補助金の手続きを一元管理すると安心です。複数補助金を同時に進める場合は、早期に交付決定を受けやすいものから着手すると効率的です。
また、工事や機器納入の遅延が発生すると補助金が無効になる場合もあるため、納期や施工計画も含めた詳細スケジュールを作成しましょう。加えて、書類作成は締切直前に集中しないように段階的に準備することが大切です。計画的なスケジュール管理により、併用のメリットを十分に引き出せます。
専門家への相談で採択率を高める方法
補助金併用を成功させるには、専門家のサポートを受けることが非常に有効です。複数の補助金を同時に申請すると、要件確認や書類作成、経理管理の難易度が高まります。経験豊富な専門家に相談することで、採択率を高めつつリスクを軽減できます。
認定経営革新等支援機関や補助金申請サポート会社は、事業計画の作成支援や必要書類のチェック、採択後の実績報告支援まで幅広く対応可能です。さらに、補助金ごとのスケジュール調整や費目整理も依頼できるため、二重受給や不備による不採択を防げます。
専門家と連携することで、複数補助金を組み合わせた資金計画を安全かつ効率的に実行できます。限られたリソースで最大の成果を得るためには、早い段階で専門家に相談し、全体像を共有して進めることが成功の近道です。
補助金申請を専門家に依頼するメリットについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ものづくり補助金の申請を専門家に任せるべき理由と業者選びのポイント
まとめ
ものづくり補助金は、事業再構築補助金やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金などと条件を満たせば併用可能です。対象経費や事業内容を丁寧に分けることで、二重受給のリスクを避けつつ、資金調達の幅を大きく広げられます。複数補助金の活用により、設備投資・業務効率化・販路拡大を同時に実現できるため、事業成長のスピードを飛躍的に高めることが可能です。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として中小企業の補助金申請を全面的にサポートしています。着手金0円・完全成功報酬型で、事業計画作成、書類準備、実績報告までを一貫支援し、採択率の高さと迅速対応が強みです。
さらに、販路開拓やIT導入、事業再構築支援まで幅広く対応しており、複数補助金の併用戦略にも精通しています。資金確保と事業成長を同時に実現したい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。