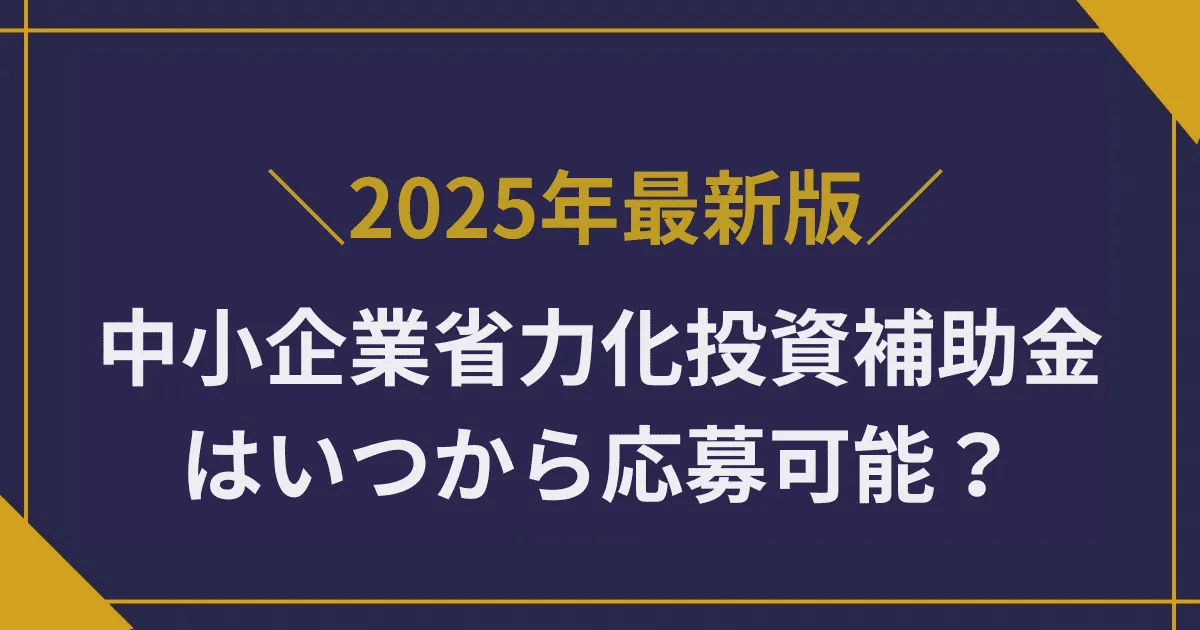中小企業省力化投資補助金は、人材不足や生産性の停滞といった課題に直面する企業にとって、業務改善を後押しする強力な制度です。IoTやロボットなどの省力化設備を導入することで、業務効率を高めながら賃上げの実現も視野に入れることができます。
さらに、導入後の成果を効果的に活かすためには、事業計画と賃上げ計画を連動させる視点も不可欠です。本記事で補助金の仕組みを正しく理解し、実際の活用事例から得られる知見を取り入れることで、事業の成長につなげましょう。
- 中小企業省力化投資補助金はいつから始まる?
- 中小企業省力化投資補助金の対象者と条件
- カタログ注文型と一般型の違い
- 中小企業省力化投資補助金の申請フロー
- 中小企業省力化投資補助金を活用するメリット
- 中小企業省力化投資補助金の活用事例
- 中小企業省力化投資補助金を効果的に活用するポイント
- まとめ
中小企業省力化投資補助金はいつから始まる?

省力化投資補助金は、公募開始日や申請期間が年度ごとに設定されています。2025年9月時点では第3回公募がすでに締め切られており、第4回以降のスケジュールが公表されています。
ここでは、それぞれの公募スケジュールや最新の募集状況を整理します。
カタログ注文型は随時受付で応募可能
カタログ注文型は、登録済みの省力化製品を選んで導入する方式です。手続きの簡便さが大きな魅力となっており、設備や機器をスピーディーに導入できます。2025年8月9日以降は公募が随時受付に移行しており、必要な製品がカタログに含まれていれば、準備が整い次第すぐに申請できる点が特徴です。
採択と交付決定も随時行われるため、従来のように締切日を待つ必要がなく、タイミングを柔軟に選べます。販売事業者のサポートも受けやすいため、初めて申請する事業者にとっても安心感が高い方式です。
導入効果を早期に得たい企業や、限られた人員で業務効率化を急ぐ事業者には特に適しているでしょう。計画を前倒しで進めれば、競争を意識せずに利用できる制度だといえます。
一般型は年3〜4回の公募が予定されている
一般型は、オーダーメイド性の高い投資やシステム構築を対象としています。既製品導入にとどまらず、業務に適した独自設備や複数機器の組み合わせを取り入れることができ、柔軟性の高さが特徴です。
公募は年に3回から4回程度設定され、各回で受付期間と採択発表日が設けられています。2025年は第1回と第2回がすでに終了し、第3回も8月29日で締切済となりました。採択結果は11月下旬に公表される予定です。
中小企業省力化投資補助金の対象者と条件
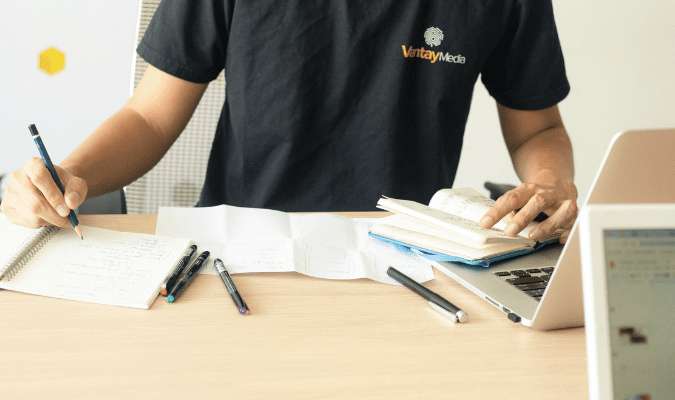
補助金を利用できるかどうかは、制度の要件を正しく理解することから始まります。対象範囲に含まれる事業者であっても、細かな条件を満たさなければ申請は認められません。反対に、条件を的確に把握することで申請資格を得られるケースも少なくありません。
ここでは対象となる中小企業や小規模事業者、さらに特定の法人がどのような基準を求められるのかを整理します。
中小企業者と小規模事業者の定義
中小企業者の範囲は業種ごとに資本金や従業員数の基準が定められています。たとえば製造業や建設業では資本金3億円以下または従業員300人以下、商業やサービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下が目安です。
小規模事業者についてはさらに基準が厳しく、製造業などは20人以下、商業やサービス業は5人以下、宿泊や娯楽に関しては20人以下とされています。これらの定義に合致した場合、補助率が2/3に引き上げられる特例もあります。
つまり、規模の小さな事業者ほど支援を受けやすく、資金面での後押しを強く受けられる仕組みです。自社がどの区分に該当するのかを確認することが申請の第一歩になります。制度を活かすためには、定義を正しく理解して計画に組み込みましょう。
NPO法人や社会福祉法人も対象になる場合
対象範囲は営利法人だけに限定されていません。特定非営利活動法人であっても、中小企業の振興や発展に資する活動を行い、従業員が300人以下である場合は申請資格があります。
ただし、経営力向上計画の認定を受けていることが条件として課されています。社会福祉法人については、所管庁の認可を受けて設立され、従業員が300人以下であることが前提です。
さらに収益事業の範囲内で補助対象の取り組みを行う必要があります。つまり、公益性の高い活動を行う法人であっても、規模や計画性が一定の基準を満たすことが必要です。非営利組織や福祉法人にとっても、業務効率化や人材不足解消に取り組むきっかけとなる可能性が広がっています。
対象外となる事業者の特徴
補助金制度には明確に除外される条件が設けられています。代表的なものとして、大企業の子会社にあたる「みなし大企業」があります。発行済株式の半分以上を大企業が所有している場合や、大企業から役員が派遣されている場合は対象外です。
また、直近3年間の課税所得の平均額が15億円を超える場合も申請資格がありません。さらに、暴力団関係者や公序良俗に反する事業活動を行う団体も除外対象です。過去にものづくり補助金や事業再構築補助金の支払いが完了していない事業者や、3年間で2回以上交付を受けた事業者も応募できません。
これらの基準に該当するかどうかを事前に確認することが重要です。資格を満たさないまま申請しても不採択となるため、無駄な労力を避けるために理解を徹底しましょう。
補助金返還が発生するケース
交付を受けた後でも、条件を達成できなければ補助金の一部返還が求められる場合があります。具体的には、労働生産性や給与総額の成長率が計画で示した数値に届かなかったときが該当します。
たとえば、従業員一人あたりの給与総額が設定された基準を下回ると、達成率に応じて返還額が算定されるのです。
さらに、効果報告を怠った場合や虚偽報告が発覚した場合にも返還を求められるので、注意が必要です。もっとも、天災や経営者の責めに帰さない事由がある場合は返還が免除されるケースもあります。返還リスクを避けるためには、無理のない事業計画を立て、賃上げや効率化の実行を継続的に進める姿勢が求められるでしょう。
カタログ注文型と一般型の違い
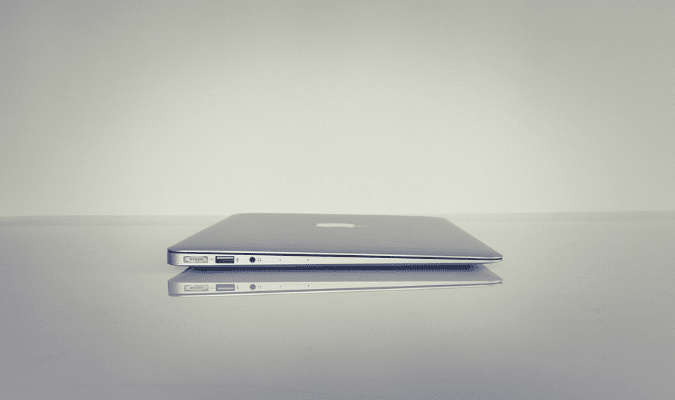
中小企業省力化投資補助金は、導入方法や対象範囲に応じて二つの類型が用意されています。カタログ注文型は簡便な手続きで導入できる一方、一般型は自由度が高く幅広い投資に対応可能です。
両者の特性を理解することで、自社の経営課題に合った類型を選択できます。ここでは、それぞれの特徴、補助上限額や補助率、さらに選び方のポイントを整理します。
カタログ注文型の特徴と補助上限額
カタログ注文型は、あらかじめ登録された省力化製品の中から選択し、導入する方式です。対象となるのは清掃ロボットや自動券売機、厨房機器、無人搬送車など多岐にわたり、幅広い業種で利用されています。
最大の特徴は、製品がすでに事務局によって登録・承認されているため、審査が簡易化されている点にあります。小規模事業者や初めて補助金を申請する企業にとって、取り組みやすい形式だといえるでしょう。
補助上限額は従業員規模によって異なり、5人以下は200万円、6人から20人は500万円、21人以上は1000万円が目安です。さらに大幅な賃上げを実施する場合は上限が引き上げられ、最大1500万円まで活用できます。手続きの負担を抑えつつ、省力化の効果を早期に得たい企業に適しています。
一般型の特徴と大幅賃上げ特例
一般型は、各事業者の現場や業務内容に合わせたオーダーメイド投資を可能にする仕組みです。既製品の導入にとどまらず、複数の機器を組み合わせたシステム構築や自社の業務に最適化した設備開発など、柔軟な取り組みに対応できます。
最低投資額は50万円と設定されており、比較的低いハードルで応募できる点も注目されているのです。補助上限額は従業員規模に応じて設定され、最大で8000万円に達します。
さらに大幅賃上げを実施した場合は1億円まで拡大されます。要件として給与支給総額の年平均成長率を6%以上にし、事業場内最低賃金を地域の水準より高めることが必要です。高額な投資を計画している企業にとっては、資金負担を大幅に軽減できる制度として有効です。
補助率の違いと特例の条件
補助率は類型や事業規模によって異なります。カタログ注文型は一律で1/2と定められており、条件がわかりやすく計画を立てやすいでしょう。一般型では、通常の中小企業であれば補助金額1500万円までが1/2、超える部分は1/3に設定されています。
一方で、小規模事業者や再生事業者は1500万円まで2/3の補助を受けられる仕組みです。さらに、最低賃金引上げ特例を満たすと、中小企業でも1500万円まで2/3の補助率が適用されます。
補助率を最大限活用するためには、賃金制度の見直しや雇用状況の把握が欠かせません。適用条件を理解したうえで戦略的に申請を進めましょう。
自社に適した類型を選ぶポイント
自社の課題に応じてどちらの類型を選択するかが成功の分かれ道です。小規模で人手や資金の余裕が限られている場合は、簡易な手続きと導入支援が受けられるカタログ注文型が適しています。導入する製品がカタログに登録されていれば、短期間で成果を出しやすいでしょう。
一方、業務特性に合わせた高度な自動化やシステム構築を求める企業には一般型が適しています。より大規模な投資を行い、生産性向上と賃上げを同時に実現したい事業者に向いています。
導入目的を明確化し、必要な投資額や期待される効果を比較検討することが重要です。さらに、補助率や特例の条件も加味することで、自社に最も有利な申請方法を選択できます。目的とリソースのバランスを見極め、最適な制度を選びましょう。
中小企業省力化投資補助金の申請フロー
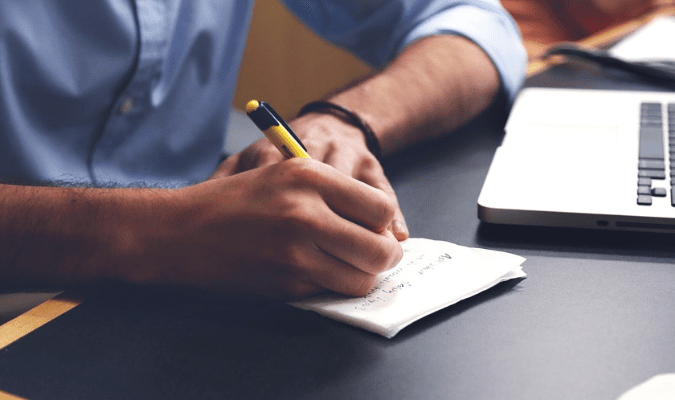
省力化投資補助金を円滑に活用するには、採択後の流れだけでなく、公募開始前からの準備が大切です。申請から補助金の受け取りまでには複数のステップが存在し、それぞれに必要な書類や確認事項があります。
ここでは、応募開始前に進めておくべき事前準備も含めて、申請フローを段階ごとに整理します。
GビズIDの取得から準備を始める
申請に必須となるのが、GビズIDプライムアカウントです。電子申請を行うための共通認証システムであり、これを持たなければ申請手続き自体を開始できません。取得には申請書類の郵送や審査を経るため、通常2週間から1か月程度の時間が必要です。
したがって、補助金を検討する段階で最初に進めておくことが望ましいでしょう。アカウントを取得することで、電子申請システムを利用できるだけでなく、他の補助金や助成制度の申請にも活用できる利点があります。
準備を後回しにすると締切に間に合わないリスクが高まるため、最優先で対応すべき工程です。事前に時間を確保し、余裕を持って申請を行いましょう。
事業計画書の作成と注意点
申請の成否を大きく左右するのが事業計画書です。省力化効果や労働生産性向上をどのように実現するのかを明確に示す必要があります。計画書には、投資の目的、導入する設備の概要、期待される効果、賃上げ計画などを具体的に記載しましょう。
さらに、投資回収期間や費用対効果を示す数値的根拠を添えることで、説得力が高まります。注意点としては、曖昧な表現を避け、実現可能性を裏付ける資料を用意することです。
審査では政策的な観点や地域経済への波及効果も評価対象となるため、広い視点から事業の意義を説明することが求められます。計画の不備や根拠不足は採択率の低下につながるため、専門家の助言を受けるのも有効です。
応募から採択までの流れ
事業計画書が整ったら、電子申請システムを通じて応募を行います。申請受付期間は限られているため、締切を過ぎないよう余裕を持った提出が重要です。申請後は事務局による形式審査を経て、技術面、計画面、政策面の観点から審査が行われます。
必要に応じて口頭審査が追加され、経営者や担当者が事業内容について説明する場が設けられる場合もあります。審査期間は数か月に及ぶため、結果が出るまでの間に資金計画や導入準備を並行して進めると効率的です。
採択が決まると公表され、次の交付申請に進むことができます。不採択の場合でも再挑戦が可能なため、フィードバックを活用して次回に備えることが望ましいでしょう。応募から採択までの一連の流れを理解することが、制度を円滑に活用するポイントです。
交付申請・補助金受け取りまでの手順
採択後は、交付申請を行い正式に補助事業を開始します。この段階では、導入予定の製品やサービスの詳細な見積もりを提出し、事務局の審査を受けます。交付決定が下りると、実際の発注や納品、検収、支払いといった一連の流れを進めることになるのです。
補助事業の実施期間は採択からおおむね18か月以内と定められており、この間に全ての工程を完了させる必要があります。終了後は実績報告を行い、事務局による確定検査を受けます。その後、補助金請求を行うことで実際に資金が支払われます。
さらに、補助事業の効果については5年間の報告義務が課せられており、継続的なフォローが必要です。計画的にスケジュールを管理することで、受給までを円滑に進められるでしょう。
中小企業省力化投資補助金を活用するメリット
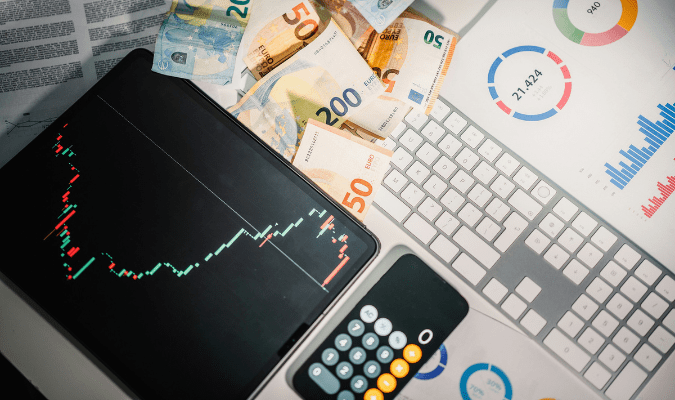
制度を利用することで得られるメリットは多方面にわたります。人材不足の緩和や生産性の底上げだけでなく、従業員の待遇改善やモチベーション向上など、経営基盤に直結する効果も期待できるでしょう。
さらに、導入段階では販売事業者からの支援を受けられるため、専門知識が不足している場合でも安心して取り組めます。ここでは代表的なメリットを4つの観点から解説します。
人手不足解消と生産性向上につながる
補助金を活用して省力化設備を導入すると、慢性的な人材不足の解消につながります。たとえば、単純作業を担ってきた従業員が自動化機器によって代替されることで、限られた人材をより付加価値の高い業務へ配置転換できるようになります。
結果として、全体の労働生産性が向上し、少人数で多くの成果を生み出せる体制が整うでしょう。従業員一人あたりの業務負担が軽減されるため、業務の質を維持しながら効率を高めることが可能です。
さらに、生産性向上は売上や利益の拡大に直結するため、企業の競争力を強化する効果も期待できます。持続的な成長を目指す中小企業にとって、労働力不足を補う手段となるでしょう。
従業員の労働環境改善と定着率向上
省力化投資は単に効率を高めるだけでなく、従業員の労働環境を改善する役割も担います。重労働や長時間労働を伴う作業が自動化されることで、身体的な負担が軽減され、労災リスクの低下にもつながります。
また、残業時間が削減されることでプライベートの時間を確保でき、ワークライフバランスの改善にもつながるでしょう。従業員が快適に働ける職場環境を整備することは、離職率の低下や人材定着の促進につながります。
加えて、働きやすさが向上すれば新たな人材採用の際にもプラスに作用し、採用競争における優位性を高められます。労働環境を整えることは、経営者にとっても従業員にとっても双方に利益をもたらす重要な取り組みになるでしょう。
賃上げによるモチベーション向上と人材確保
補助金制度の基本要件には賃上げ計画が含まれており、給与水準を引き上げる取り組みが推奨されています。給与が上昇すれば従業員のモチベーションが高まり、生産性向上への意欲も高まります。
さらに、給与条件の改善は人材確保の観点からも効果的です。求人市場において競争力を持つためには待遇面の充実が不可欠であり、補助金を活用して実現することで企業の魅力を高められます。賃上げによって従業員の生活が安定すれば、離職の抑制にもつながり、長期的な人材育成が可能になります。
制度を利用することは単なる資金支援にとどまらず、人材戦略の一環としても大きな価値を持つのです。結果として、企業全体の安定した成長に結びつく効果が期待できます。
販売事業者のサポートで導入がスムーズになる
カタログ注文型を中心に、販売事業者から申請サポートや導入支援を受けられる点も見逃せません。専門知識を持つ事業者が補助金の仕組みを理解したうえで助言を行うため、初めて申請に取り組む企業でも安心して進められます。
導入時の設定や操作方法の指導も受けられるため、設備を効果的に活用する環境が整いやすくなります。また、導入後のフォローアップも提供されることがあり、長期的な運用において不安を軽減できるでしょう。
外部からの支援は社内リソースが限られている中小企業にとって大きな助けとなります。補助金の申請や運用を単独で進めるよりも、専門的な知識や経験を持つパートナーを活用することで、成果を最大化できる可能性が高まるでしょう。
中小企業省力化投資補助金の活用事例

補助金の活用効果を理解するうえで、実際に導入を進めた事業者の取り組みを知ることが大切です。導入前後の変化を把握すれば、自社での活用イメージも描きやすくなります。
ここで飲食業、宿泊業、製造業、燃料小売業などの事例を通して、省力化投資がもたらす具体的な成果を確認してみましょう。
飲食業でのスチームコンベクションオーブン導入
飲食業では、スチームコンベクションオーブンを導入することで調理作業の効率が大きく向上しました。従来のフライパン調理では少量ずつしか対応できず、火加減の調整や立ち仕事による負担が大きな課題となっていたのです。
導入後は一度に20個以上の調理が可能となり、待機時間が削減されるだけでなく作業の安定性も高まりました。
製菓店においても焼成時間が半減し、余った時間をSNS発信や販路拡大に活用することが可能となりました。結果として売上拡大や新規顧客獲得に結びつき、単なる効率化にとどまらず経営基盤強化にも貢献しています。
宿泊業での清掃ロボット導入
宿泊業の事例では、清掃ロボットの導入がフロントやロビー業務の効率化につながりました。従来はスタッフ2名で2時間程度かけて清掃を行っていましたが、導入後は自動化により業務負担が解消されています。
清掃頻度を増やすことが可能となり、衛生環境の向上にも直結しました。人手不足が深刻化する宿泊業界において、限られた人員を接客や顧客対応に集中させることができ、サービス品質の向上にもつながります。
さらに、スタッフの身体的負担軽減による労働環境の改善効果も期待されるのです。自動化機器の導入は単なる作業削減ではなく、顧客満足度の向上やリピーター確保にも影響を及ぼします。宿泊施設が抱える慢性的な課題を解決する実例として注目されています。
製造業での無人搬送車(AGV・AMR)導入
製造業では、無人搬送車の導入によって生産ラインの効率化が実現しました。従来は2名体制で行っていた部品運搬作業が自動化され、人員を他の重要な業務に振り分けられるようになりました。
結果として、作業時間の短縮と人件費の削減が同時に達成されています。自動搬送は安全面にも寄与し、重量物の移動による従業員の身体的負担や事故リスクを軽減しました。さらに、搬送の正確性が高まったことで部品管理の精度が向上し、製造工程全体の品質も安定しています。
自動化機器の導入は単なる省人化にとどまらず、作業現場全体の最適化を促す効果があります。人材不足や生産性向上を同時に解決する手段として、製造業の実例は多くの事業者にとって参考となるでしょう。
燃料小売業でのタブレット型給油許可システム導入
燃料小売業では、タブレット型の給油許可システムを導入した事例が確認されています。以前は事務所スタッフが常駐し、給油許可を逐一確認する必要がありました。しかし導入後はシステムが自動で制御する仕組みとなり、常駐業務が不要となりました。
空いた時間を別の業務に充てられるようになり、たとえばレンタカー事業の清掃や点検など新しいサービス領域に人員を配置できています。これにより収益機会の拡大と業務効率化が同時に進みました。
省力化投資は単に負担軽減を実現するだけでなく、新たな事業展開への時間創出につながる点が特徴です。経営資源の最適配分を可能にする制度活用例として、燃料小売業の取り組みは非常に参考になります。
中小企業省力化投資補助金を効果的に活用するポイント

補助金を申請するだけでは十分な成果につながりません。効果を最大化するためには、計画段階から導入後の運用までを一貫して考える必要があります。
省力化の目的を明確化し、長期的な経営戦略に結び付けることで、単なる資金調達を超えたメリットが得られるでしょう。ここでは、効果的な活用に欠かせない観点を整理し、具体的な取り組み方法を示します。
導入目的を明確に定めて計画を立てる
補助金活用を成功させるためには、まず導入目的を具体的に定めることが欠かせません。単に新しい設備を入れるのではなく、どの業務を効率化したいのか、どの程度の人員を削減したいのかを明確にすることが重要です。
目的を定めることで事業計画書の説得力が増し、審査における評価も高まります。また、目標が具体的であれば導入後の成果を測定しやすくなります。たとえば、調理時間を半分に短縮する、搬送作業を完全自動化するなど、数値で示せる目標が望ましいでしょう。
さらに、目的が明確であれば社内での理解や協力も得やすくなり、現場レベルでの導入効果が高まります。曖昧な目的では成果が限定されるため、最初の段階で方向性を固めることが大切です。
事業計画と賃上げ計画を連動させる
補助金の根幹には賃上げを実現する狙いがあります。したがって、事業計画と賃上げ計画を切り離して考えるのではなく、連動させることが必要です。省力化によって生まれた余力をどのように活用し、給与水準の向上につなげるかを明確にすることで、審査で高く評価されるでしょう。
たとえば、業務削減による人件費の一部を給与に反映する仕組みを設計すれば、持続的な賃上げにつながります。さらに、給与改善を通じて従業員の意欲が高まれば、生産性がさらに向上する好循環が生まれます。
計画段階で賃上げの根拠を示すことは、返還リスクの回避にも有効です。制度の目的を正しく理解し、事業計画と賃上げ計画を一体化させることで、経営の安定性を強化できるでしょう。
専門家の支援を活用して採択率を高める
補助金申請は専門的な知識が求められるため、外部の専門家支援を取り入れることも効果的です。認定支援機関やコンサルタントは制度の要件を熟知しており、事業計画書の作成や数値根拠の整理をサポートします。
経験豊富な専門家が関与することで、申請書の完成度が高まり、採択率を向上させられます。また、過去の採択事例を参考にした助言を受けられる点も大きな強みです。
さらに、採択後の実績報告や効果報告の段階でも支援を受ければ、返還リスクを軽減し、制度を安心して活用できます。限られたリソースで申請を進める中小企業にとって、外部支援は大きな助けとなるでしょう。コストをかけてでも専門家を活用する価値は十分にあります。
まとめ
中小企業省力化投資補助金は、人手不足の解消や生産性向上を目的とした有効な制度です。カタログ注文型では手続きの簡便さを活かし、一般型では大規模かつ柔軟な投資を進められます。対象となる事業者の条件や返還要件を理解し、計画的に申請を進めることが採択率を高めるうえで重要です。
さらに、導入後の効果測定や賃上げ計画を明確化することで、長期的な成果を確保できます。活用事例が示すように、業種を問わず多様なメリットが得られる制度であり、経営改善の有力な手段として注目されています。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として中小企業向けに補助金申請支援を行っています。経営基盤の強化や新規事業への挑戦を考える企業に対し、書類作成から面接審査まで丁寧にサポートし、高い採択率を実現しています。
着手金ゼロ・完全成功報酬型の仕組みで、安心してご相談いただけます。事業成長を後押しするための第一歩として、ぜひお問い合わせください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。