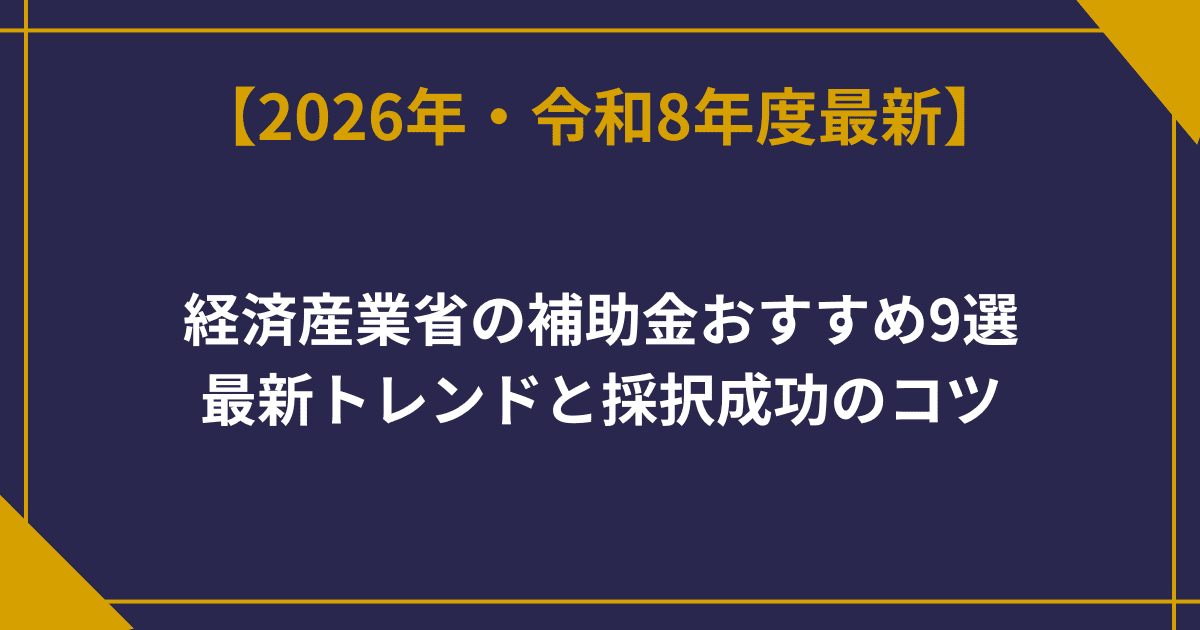設備投資や賃上げの資金確保にお悩みではありませんか?経済産業省の補助金は、2025年も中小企業の強力な味方です。しかし、種類が多く「どれが自社に合うのかわからない」という声も少なくありません。
本記事では、2026年の最新トレンドや、「省力化投資補助金」をはじめとするおすすめ制度9選、採択率を高めるコツを徹底解説します。自社に最適な補助金を見つけ、事業の飛躍にお役立てください。
- 経済産業省の補助金がおすすめされる理由と概要
- 2025年に注目すべきおすすめ補助金の最新トレンド
- 自社に合った補助金の選び方【3ステップで解説】
- 【一覧比較表】2026年おすすめの経済産業省補助金
- 2026年に活用したいおすすめの経済産業省補助金9選
- 補助金を活用するための申請ステップ
- 補助金採択を成功に導くための4つのコツ
- 補助金活用で注意すべきリスクと対策
- 経済産業省の補助金についてよくある質問
- 補助金申請なら株式会社イチドキリへ
- まとめ
経済産業省の補助金がおすすめされる理由と概要

経済産業省の補助金は、中小企業や小規模事業者の「攻めの経営」を後押しする制度です。厚生労働省の助成金と違い、採択には競争がありますが、補助金額が大きく、設備投資や新規事業への挑戦を強力にサポートしてくれます。
返済不要の資金を調達できるだけでなく、国が認める事業計画を有する証明にもなり、対外的な信用力向上にもつながります。
中小企業や個人事業主にとっての活用意義
金融機関の融資と異なり、原則として返済不要な資金を調達できるのが最大のメリットです。これにより、リスクを伴う新規事業や高額な機械設備の導入にも挑戦しやすくなります。
また、補助金に採択されることは、国が認める事業計画を有しているという証明にもなり、企業のブランド価値を高める手段としても有効です。資金面だけでなく、信用力の向上にも貢献します。
2025年に注目される補助金の傾向
2025年度は、人手不足解消のための「省力化」や「デジタル化(AI導入)」が大きなテーマです。従来のIT導入補助金が「デジタル化・AI導入補助金」といった名称で扱われるなど、AI活用への支援が手厚くなる見込みです。
物価高騰に対応するための賃上げや、環境配慮型経営(GX)への投資も引き続き重要視されています。
※出典:人気の補助金 | 経済産業省 中小企業庁
※出典:令和7年度補正予算案の概要|経済産業省
2025年に注目すべきおすすめ補助金の最新トレンド

2025年の補助金トレンドを一言で表すなら、「生産性向上と賃上げの好循環」です。単に設備を買うだけでなく、それによって従業員の給与を上げられるかどうかが、採択の可否を分ける重要な鍵となります。
賃上げ要件の強化傾向
多くの中小企業向け補助金で、「給与支給総額の年平均上昇率」などの賃上げ目標が必須要件、あるいは加点項目になっています。
例えば、大規模成長投資補助金では、事業終了後に給与支給総額を年率4.5%以上引き上げることが求められます。国は賃上げを行う企業を優先的に支援する姿勢を鮮明にしており、申請時には実現可能な賃上げ計画の策定が不可欠です。
デジタル化・省力化・GX関連投資の優遇
人手不足が深刻化する中、IoT、ロボット、AIを活用した「省力化投資」への配分が厚くなっています。
また、脱炭素社会に向けたグリーントランスフォーメーション(GX)も重要テーマです。省エネ性能の高い設備への更新や、電気自動車(EV)の導入、再生可能エネルギー設備の設置などに対して、高額な補助金が用意されています。
地域経済や外需獲得に注目が集まる
地域経済を支える取り組みや、海外市場への展開も注目ポイントです。地域の資源を活用した商品開発や、円安を背景としたインバウンド需要の獲得、輸出拡大を目指す事業への支援が強化されています。
特に「地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)」のように、地域金融機関と連携して行う事業には手厚い支援が用意されています。
大型補助金の新設と終了動向
コロナ禍で主力だった「事業再構築補助金」は枠組みの見直しが進んでいます。代わって注目されているのが、「中小企業省力化投資補助金」や「大規模成長投資補助金」といった新制度です。
特に省力化投資補助金は、カタログから選ぶだけで申請できる簡易な「カタログ注文型」も用意されており、手続きの簡素化が進んでいます。
※出典:中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 経済産業省
※出典:中小企業省力化投資補助金
自社に合った補助金の選び方【3ステップで解説】

数ある補助金の中から自社に最適なものを選ぶには、正しい手順で情報を整理することが大切です。いきなり公募要領を読むのではなく、まずは自社の現状分析から始めましょう。
ステップ1:事業の目的と課題を明確にする
「何に」お金を使いたいのかを明確にします。「新しい機械を入れたい」「ECサイトを作りたい」「M&Aをしたい」など、投資の目的によって選ぶべき補助金は決まります。
例えば、汎用的な製品で人手不足を解消したいなら「省力化投資補助金」、革新的な新製品開発なら「ものづくり補助金」といった具合に、目的と補助金の趣旨をマッチさせることが第一歩です。
ステップ2:対象となる補助金の種類を絞り込む
目的が決まったら、対象となる補助金を絞り込みます。このとき、「補助対象経費」と「補助率・上限額」を確認してください。
自社が個人事業主なのか、中小企業なのか、あるいは中堅企業なのかによっても申請できる枠が変わります。経済産業省の「ミラサポplus」や、専門家のサイトを活用して、条件に合うものをリストアップしましょう。
ステップ3:公募要領を確認し、申請準備を進める
候補が決まったら、必ず最新の「公募要領」をダウンロードして詳細を確認します。補助金は公募回ごとにルールが変わることがあるため、古い情報はあてになりません。
特に「申請締切日」と「GビズIDプライムアカウント」の取得状況は要注意です。ID発行には時間がかかるため、申請を決めたらすぐに手続きを行う必要があります。
※出典:人気の補助金 | 経済産業省 中小企業庁
※出典:経済産業省が実施する人気の補助金・助成金一覧 | スマート補助金
【一覧比較表】2026年おすすめの経済産業省補助金

2026年に活用をおすすめする主要な補助金を一覧表にまとめました。自社の目的に近いものを探してみてください。
| 補助金名 | 主な目的・用途 | 補助上限額(目安) | 補助率 |
| 1. 中小企業省力化投資補助金 | ロボット・IoT等の導入による省力化 | 1億円(一般型)1,500万円(カタログ型) | 1/2 ~ 2/3 |
| 2. ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービスの開発、設備投資 | 4,000万円~1億円 | 1/2~2/3 |
| 3. 新事業進出補助金 | 新市場への進出、事業転換 | 6,000万円~9,000万円 | 1/2~2/3 |
| 4. IT導入補助金 | 業務効率化ITツール、インボイス対応 | 450万円(通常枠) | 1/2~4/5 |
| 5. 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓(広告・店舗改装など) | 50万円~250万円 | 2/3~3/4 |
| 6. 大規模成長投資補助金 | 工場新設等の大規模投資、賃上げ | 50億円 | 1/3以下 |
| 7. 中小企業成長加速化補助金 | 飛躍的成長を目指す設備投資 | 5億円 | 1/2 |
| 8. 事業承継・M&A補助金 | 事業承継、M&A時の専門家費用 | 800万円~2,000万円 | 1/2~2/3 |
| 9. 省エネ・非化石転換補助金 | 省エネ設備への更新、脱炭素化 | 数千万円~億円単位 | 1/3~2/3 |
※金額や補助率は枠や公募回によって変動します。詳細は各公募要領をご確認ください。
2026年に活用したいおすすめの経済産業省補助金9選

ここからは、一覧表で紹介した9つの補助金について、それぞれの概要や金額、スケジュールの詳細を解説していきます。
1. 中小企業省力化投資補助金
人手不足に悩む中小企業にとって、今最も使いやすい補助金の一つです。IoT機器やロボットなどの「効果が検証された製品」を導入し、業務の効率化を図る事業者を支援します。大きく「カタログ注文型」と「一般型」の2種類があり、「カタログ注文型」は登録された製品を選ぶだけで申請でき、手続きが簡易です。
補助上限額と補助率
- カタログ注文型:上限1,500万円(従業員数により変動)、補助率1/2
- 一般型:上限1億円、補助率1/2 〜 2/3(賃上げ要件等により変動)
小規模な投資から大規模なシステム導入まで幅広く対応可能です。
申請スケジュール
カタログ注文型は「随時受付」となっており、準備ができ次第申請可能です。一般型は公募期間が設けられており、第1回~第5回(2025年12月中旬~2026年2月下旬)と断続的に実施される予定です。
2. ものづくり補助金
長年続く経済産業省の看板施策で、革新的な製品開発やサービスの生産性向上に必要な設備投資を支援します。新製品開発のための機械装置、システム構築費、技術導入費などが対象です。製造業だけでなく、サービス業や小売業でも「革新的なサービス開発」であれば対象となります。
補助上限額と補助率
・枠構成:現在は主に「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2枠。
・製品・サービス高付加価値化枠:従業員数に応じて上限最大2,500万円。
・グローバル枠:上限3,000万円(大幅な賃上げ等の要件を満たす場合は上限4,000万円まで引き上げ)。
・補助率:中小企業は1/2、小規模事業者は2/3。
申請スケジュール
2025年も継続的に実施される見込みです。第19次公募(2025年2月~4月)、第20次、第21次と四半期ごとに公募が行われるスケジュールが予測されています。
3. 新事業進出補助金
本業の市場縮小などに直面し、新たな分野へ挑戦したい企業向けの補助金です。既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。例えば、「ガソリン車の部品製造からEV部品製造へ転換する」「飲食店が冷凍食品の製造販売を始める」といったケースが該当します。
補助上限額と補助率
- 上限額:6,000万円~9,000万円(枠により異なる)
- 補助率:1/2~2/3
事業再構築補助金の後継的な位置づけとしても注目されています。
申請スケジュール
申請に関して、事業計画の策定に時間がかかるため早めの準備が必要です。
- 第1回公募:2025年4月22日公募開始、7月10日締切。
- 第2回公募:2025年9月12日公募開始、12月19日締切。
- 第3回公募:2025年12月23日に公募要領が公表され、応募締切は2026年3月26日18:00まで。
いずれの回も、事業計画の策定や金融機関・認定支援機関との調整に時間を要するため、早めの準備が重要です。
4. IT導入補助金
業務効率化やインボイス制度への対応のために、会計ソフト、受発注システム、PC・タブレット等を導入する費用を補助します。2026年は「デジタル化・AI導入補助金」といった名称への変更やAI重点化の可能性があります。ソフトウェアの購入費だけでなく、導入コンサルティングやクラウド利用料(最大2年分)も対象です。
補助上限額と補助率
- 上限額:通常枠で最大450万円、インボイス枠等は内容による
- 補助率:1/2~4/5(枠により異なる)
安価なツール導入から大規模なシステム刷新まで対応可能です。
申請スケジュール
通年で公募されており、随時締切が設けられています。IT導入支援事業者(ベンダー)を通じて申請する必要があるため、まずはベンダーへの相談から始めましょう。
5. 小規模事業者持続化補助金
従業員数が少ない小規模事業者(宿泊・娯楽業除く商業・サービス業は5人以下、その他は20人以下)が対象です。販路開拓や業務効率化の取り組みを支援します。チラシ作成、Webサイト制作、店舗改装、展示会出展など、使い勝手の良さが魅力です。商工会議所や商工会のサポートを受けながら経営計画を作成して申請します。
補助上限額と補助率
- 上限額:通常枠50万円、賃上げ枠や創業枠などは最大200~250万円
- 補助率:2/3(赤字事業者は3/4に引き上げ等の特例あり)
インボイス特例などの上乗せ措置もあります。
申請スケジュール
年に数回の公募があります。2025年も第12回以降の公募が継続的に行われる見込みです。災害支援枠などは随時募集されることもあります。
6. 大規模成長投資補助金
中堅・中小企業が、地域経済に波及効果をもたらすような大規模な投資を行う場合に活用できる補助金です。持続的な賃上げを目的としています。工場や物流拠点の新設など、投資額が10億円以上(新規公募分は20億円以上の可能性あり)となるビッグプロジェクトが対象です。
補助上限額と補助率
- 上限額:最大50億円
- 補助率:1/3以下
非常に規模が大きいため、しっかりとした事業計画と資金調達計画が求められます。
申請スケジュール
3次公募(3月~4月)、4次公募(7月~8月)といったスケジュールで実施されています。審査にはプレゼンテーションも含まれるなど、厳格なプロセスを経ます。
7. 中小企業成長加速化補助金
「売上高100億円」を目指すような、急成長を志向する中小企業を支援する制度です。大規模投資まではいかないものの、飛躍的な成長に必要な投資をサポートします。工場の新設・増築や、生産性を抜本的に向上させる自動化設備の導入などが対象です。大規模成長投資補助金とものづくり補助金の中間的な位置づけと言えます。
補助上限額と補助率
- 上限額:最大5億円
- 補助率:1/2
「100億宣言」など、高い成長目標を掲げる企業が対象となります。
申請スケジュール
2025年3月中旬から公募開始、6月締切といったスケジュールが公表されています。準備期間を十分に確保しましょう。
8. 事業承継・M&A補助金
事業承継やM&A(企業の合併・買収)をきっかけとした経営革新や、M&Aにかかる専門家の活用費用を補助します。後継者が新しい取り組みを行うための設備投資費用(経営革新枠)や、M&A仲介業者への手数料、デューデリジェンス費用(専門家活用枠)などが対象です。
補助上限額と補助率
- 上限額:600万円~2,000万円(枠により異なる)
- 補助率:1/2~2/3
M&A後の統合作業(PMI)にかかる費用も支援対象になります。
申請スケジュール
2025年も複数回の公募が予定されています(例:11次公募 5月~6月)。事業承継のタイミングに合わせて申請時期を検討しましょう。
9. 省エネ・非化石転換補助金
エネルギー価格高騰への対策と脱炭素化を同時に進めるための補助金です。工場やビルの省エネ改修を支援します。高効率な空調、照明、ボイラー、工業炉などへの更新費用が対象です。単なる更新だけでなく、省エネ診断の結果に基づいた設備投資を行うと採択されやすくなります。
補助上限額と補助率
- 上限額:数千万円~億円単位(設備の種類や事業規模による)
- 補助率:1/3~1/2程度
長期的なランニングコスト削減にもつながるため、非常に人気があります。
申請スケジュール
1次公募(3月~4月)、2次公募(6月~7月)など、年度前半に集中する傾向があります。早めの省エネ診断受診をおすすめします。
※出典:【2025年12月10日更新】経産省&都道府県別補助金情報
※出典:中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金
※出典:中小企業省力化投資補助金
補助金を活用するための申請ステップ
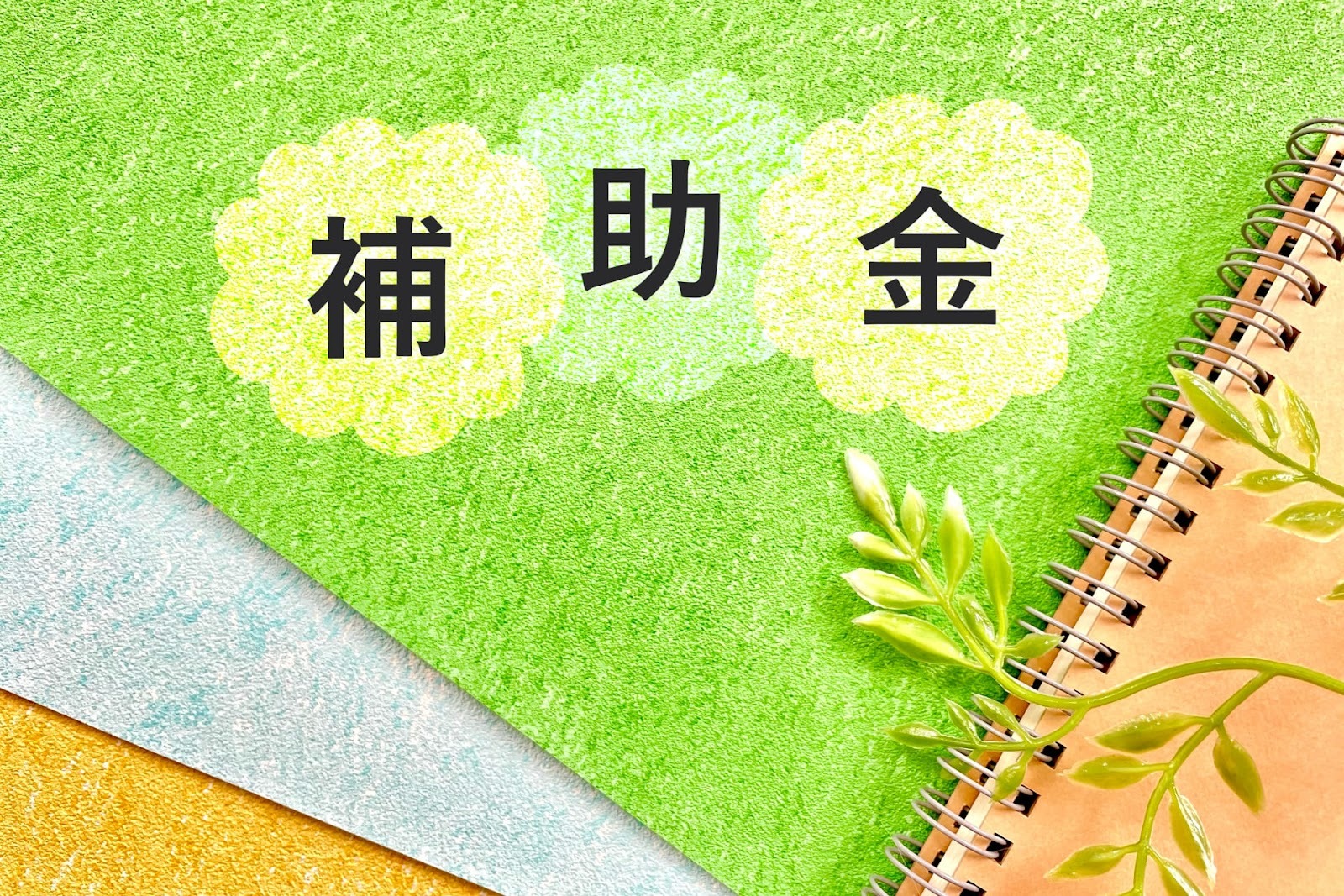
補助金は「申請すればもらえる」ものではありません。厳格な審査を通過し、正しい手続きを経て初めて入金されます。
公募情報を確認し事業計画を立案する
まずは公募要領を熟読し、要件を満たしているか確認します。その上で、「具体的で実現可能性の高い事業計画書」を作成します。なぜこの投資が必要なのか、どうやって利益を出し、賃上げにつなげるのかを論理的に説明する必要があります。
必要書類を準備し期限までに提出する
現在はほとんどの補助金が電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を使用します。申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。決算書や履歴事項全部証明書などの必要書類を漏れなくスキャンし、期限内に送信します。
審査から交付決定までのプロセスを理解する
申請後、書面審査(場合によっては面接)が行われ、採択かどうかが発表されます。採択されてもすぐには発注できません。「交付申請」を行い、事務局から「交付決定通知」が届いて初めて、契約・発注が可能になります。
補助金交付後の実績報告に注意する
補助金は原則「後払い」です。事業終了後、領収書や成果物を添えて「実績報告」を行い、検査に合格して初めて補助金が入金されます。この間、つなぎ融資などの資金確保が必要です。
※出典:中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金
※出典:公募情報 (METI/経済産業省)
補助金採択を成功に導くための4つのコツ

競争率の高い人気補助金で採択を勝ち取るには、審査員の視点を意識した対策が必要です。以下の4つのコツを押さえましょう。
- 補助金制度の目的と要件を理解する
- 自社の事業計画と整合性を持たせる
- 補助対象経費を正しく把握する
- 審査で評価されるポイントを押さえる
それぞれ解説していきます。
1. 補助金制度の目的と要件を理解する
各補助金には「政策的な目的」があります(例:賃上げ促進、DX推進など)。自社のやりたいことだけを主張するのではなく、「この事業が国の目的にどう貢献するか」をアピールすることが重要です。
2. 自社の事業計画と整合性を持たせる
「補助金がもらえるからやる」という動機は見透かされます。自社の強みや経営課題に基づいた、一貫性のあるストーリーを描きましょう。「なぜ自社が」「なぜ今」「なぜこの設備で」やるのかを明確にします。
3. 補助対象経費を正しく把握する
対象外の経費を含めていると、減額されたり不採択になったりします。例えば、汎用性の高いパソコンや車両は、特定の枠以外では対象外になることが多いです。公募要領の「補助対象経費」の欄を細かくチェックしましょう。
4. 審査で評価されるポイントを押さえる
公募要領には「審査項目」が公開されています。「革新性」「実現可能性」「費用対効果」など、何が点数化されるかが書かれています。これらの項目を網羅的に満たす記述を心がけましょう。
※出典:中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金
補助金活用で注意すべきリスクと対策

メリットの大きい補助金ですが、リスクやデメリットも存在します。これらを事前に把握しておくことで、トラブルを回避できます。
後払い制度による資金繰りのリスク
補助金が入金されるのは経費を支払った「後」です。数ヶ月から1年以上先になることもあります。金融機関と連携して資金繰り計画を立てておく必要があります。
採択率の低さと競争の厳しさ
人気の補助金は採択率が30%~50%程度になることも珍しくありません。手間をかけて申請しても不採択になるリスクは常にあります。不採択の場合でも事業を実行できるか、あるいは再申請するかを考えておきましょう。
詐欺や不正業者への注意
「絶対に採択されます」と謳う業者や、法外な手数料を請求する業者には注意が必要です。政府公式サイトのドメインは「.go.jp」です。怪しいサイトや勧誘には乗らないようにしましょう。
専門家を活用するメリット
申請書類の作成は専門知識が必要で、膨大な時間がかかります。認定経営革新等支援機関などの専門家を活用することで、採択率を高めつつ、本業への負担を減らすことができます。成功報酬型の支援会社を選ぶのも一つの手です。
経済産業省の補助金についてよくある質問
Q1. 補助金と助成金の違いは何ですか?
一般的に、経済産業省の「補助金」は予算枠があり、審査で優れた計画が選ばれる競争的な制度です。一方、厚生労働省の「助成金」は要件を満たせば原則受給できるものが中心です。
Q2. 赤字決算でも申請できますか?
多くの補助金で申請可能です。むしろ、経営を立て直すための計画(V字回復)が評価されることもあります。ただし、債務超過の状態などは審査で不利になる場合もあるため、金融機関の支援確約書などが必要になることがあります。
Q3. 補助金はいつ入金されますか?
事業完了後の「実績報告書」を提出し、事務局の確定検査が完了してからです。交付決定から入金までは、早くて半年、長いと1年以上かかるケースもあります。
Q4. 不採択になった場合、再申請は可能ですか?
可能です。不採択の理由を分析し、計画書をブラッシュアップして次回の公募に再チャレンジする企業は多くいます。事務局によっては不採択理由を聞ける場合もあります。
Q5. 補助金は課税対象になりますか?
はい、法人税(個人事業主の場合は所得税)の課税対象となります。ただし、「圧縮記帳」という会計処理を行うことで、課税を繰り延べることができる場合があります。詳細は税理士にご相談ください。
補助金申請なら株式会社イチドキリへ
2025年の補助金申請をご検討中の方は、ぜひ株式会社イチドキリにご相談ください。
当社は、難易度の高い経済産業省の補助金申請において豊富な採択実績を持っています。お客様の事業課題を深くヒアリングし、最適な補助金の提案から、採択されやすい事業計画書の作成支援、交付後の実績報告までトータルでサポートいたします。
「自社が使える補助金を知りたい」「申請の準備をしたいが時間がない」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
2025年の経済産業省の補助金は、「省力化」「賃上げ」「DX/GX」がキーワードです。中小企業省力化投資補助金や大規模成長投資補助金など、企業の成長段階に合わせた多様な制度が用意されています。
補助金は返済不要の資金調達手段として非常に有効ですが、後払いの仕組みや審査の厳しさといった注意点もあります。最新の情報をキャッチし、自社の事業計画にマッチした補助金を活用することで、さらなる事業拡大を目指しましょう。確実な採択を目指すなら、専門家のサポートを活用することも成功への近道です。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。