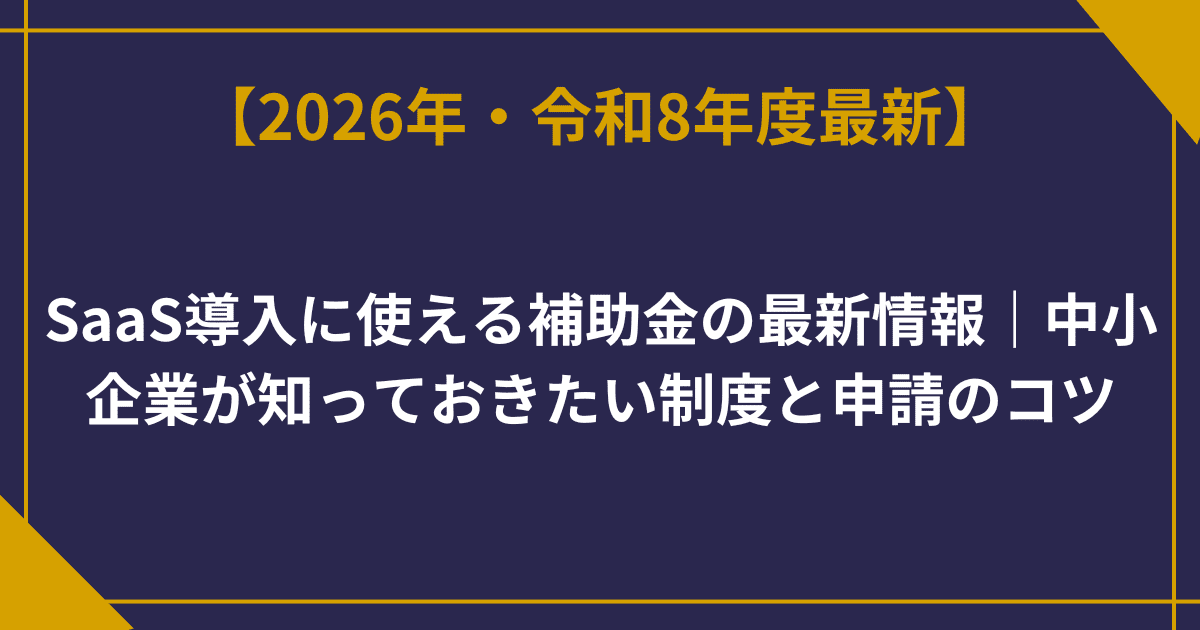「業務効率化のためにSaaSを導入したいが、コストや選び方がわからない」とお悩みではありませんか?
SaaS導入支援と補助金を活用すれば、専門家のサポートを受けながら、リスクを抑えてDXを実現できます。
本記事では、2025年最新の補助金情報と、失敗しないSaaS導入のポイントを解説します。自社に最適な支援制度を見つけ、企業の生産性を飛躍的に高める第一歩を踏み出しましょう。
SaaS導入支援とは?専門家が解決する企業の課題

SaaS導入支援とは、企業がクラウド型のソフトウェア(SaaS)を導入する際に、選定から定着までを専門家がサポートするサービスです。
単にツールを契約するだけでなく、業務フローの見直しやデータ移行など、プロジェクト全体を成功に導くための伴走支援を行います。
多くの企業が導入でつまずく原因は、ツール選びの難しさや導入後の定着不足にあります。ここでは、専門家の支援によって解決できる具体的な課題について解説します。
自社に最適なSaaSがわからない
膨大な数のSaaS製品の中から、自社の課題や規模にぴったりのツールを見つけ出すのは容易ではありません。
機能が豊富すぎて使いこなせない、逆に必要な機能が不足しているといったミスマッチは頻繁に起こります。SaaS導入支援では、専門家が客観的な視点で業務分析を行い、数ある製品の中から「本当に必要な機能」を備えたツールを選定します。
ベンダーの営業トークに惑わされることなく、費用対効果の高い最適な選択が可能です。
導入後の運用・定着に不安がある
どんなに優れたSaaSを導入しても、現場の社員が使いこなせなければ宝の持ち腐れです。
「使い方がわからない」「従来のやり方の方が楽だ」といった現場の反発により、導入したシステムが放置されてしまうケースは後を絶ちません。導入支援サービスには、マニュアル作成や社員向け研修、運用ルールの策定などが含まれるのが一般的です。
現場がスムーズに新システムへ移行できるよう、定着までのプロセスを手厚くサポートします。
複数のSaaSを連携させて効果を最大化したい
SaaSの真価は、他のシステムとデータを連携させることで発揮されます。
しかし、会計ソフト、勤怠管理、CRM(顧客管理)などがバラバラに稼働していると、データの二重入力や集計の手間が発生し、かえって業務効率が低下してしまいます。専門家による支援を受ければ、API連携や連携ツールの活用により、システム間のデータをシームレスにつなぐ設計が可能です。
業務全体が自動化され、リアルタイムな経営判断ができる環境を構築できます。
※1 出典:総務省|令和6年版 情報通信白書|SaaSの利用状況 (※一般的なSaaS定義の補足として参照)
SaaS導入に使える補助金とは

2025年も、中小企業のデジタル化や生産性向上を支援するための補助金制度が充実しています。
SaaS導入に特に活用しやすい主要な5つの補助金は以下の通りです。
- 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)
- 中小企業省力化投資補助金
- ものづくり補助金
- 新事業進出補助金
- IT導入補助金
それぞれ詳しく解説していきます。
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)
東京都内に本店または支店を持つ中小企業等を対象に、経営基盤の強化を目的とした取り組みを支援する制度です。
原材料価格の高騰や労働力不足など、厳しい事業環境に対応するためのシステム導入や設備投資が対象となります。インボイス制度対応や業務効率化に資するシステムなどが補助対象になり得ます。
助成率は最大で2/3、限度額も最大800万円と手厚く設定されており、都内の企業であればまずは検討したい有力な選択肢です。
中小企業省力化投資補助金
人手不足の解消を目的として、IoTやロボットなどの省力化効果がある製品の導入を支援する制度です。
カタログに登録された製品を選ぶ簡易な方式に加え、より自社に合わせたシステム構築が可能な「一般型」なども注目されています。SaaSなどのソフトウェアについては、単なる導入ではなく、自社の業務プロセスに合わせたカスタマイズやオーダーメイドの設定が伴う場合に対象となります。業務の自動化や省人化を実現するための個別設計が求められます。
人手不足に悩む企業が、デジタル技術を活用して生産性を大幅に向上させたい場合に適した制度です。補助額は最大1億円(従業員規模による)にも上ります。
ものづくり補助金
革新的なサービスの開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する、知名度の高い補助金です。
製造業だけでなく、サービス業や小売業など幅広い業種で利用でき、システム構築費も補助対象に含まれます。SaaSを活用した高度な連携システムの構築や、独自のビジネスモデルを実現するためのカスタマイズ開発などに最適です。
申請には「事業計画書」の策定が必須ですが、採択されれば最大数千万円規模の支援を受けられるため、大規模な改革にも対応できます。
新事業進出補助金
「事業再構築補助金」の後継として位置づけられ、既存事業とは異なる新分野への進出を支援する制度です。
市場環境の変化に対応するため、思い切った業態転換や新規事業の立ち上げを行う企業が対象となります。新規事業の基盤となるSaaS導入や、新たな顧客チャネルを開拓するためのマーケティングオートメーションツールの導入などが考えられます。
最大9,000万円(従業員規模による)の支援枠があり、リスクを伴う新規事業への挑戦において、初期投資の負担を大幅に軽減できます。
IT導入補助金
中小企業が自社の課題に合ったITツール(SaaS含む)を導入する経費の一部を補助する制度です。
ソフトウェアの購入費やクラウド利用料(最大2年分)、導入関連費などが対象となり、SaaS導入において最も利用しやすい補助金の一つです。
「通常枠」のほか、インボイス対応を重視した「インボイス枠」、セキュリティ対策を支援する「セキュリティ対策推進枠」などがあります。IT導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請するため、ツールの選定から導入サポートまでを一貫して相談できます。
※2 出典:サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局|IT導入補助金2025
SaaS導入支援サービスの主な内容

「SaaS導入支援」といっても、その内容は多岐にわたります。
単なるツールの販売だけでなく、企業の課題を根本から解決するためのコンサルティング要素が含まれるのが一般的です。専門家が具体的にどのようなサポートを行うのかを理解しておきましょう。
SaaS導入支援サービスで提供される主な内容は以下の通りです。
- 現状分析と課題の可視化(要件整理)
- 最適なSaaSの選定と導入計画の策定
- 導入設定・データ移行支援
- 運用定着と効果測定
それぞれ解説していきます。
1. 現状分析と課題の可視化(要件整理)
まずは、現在の業務フローを詳細にヒアリングし、どこにボトルネックがあるのかを洗い出します。
「なんとなく効率が悪い」という状態から、「受発注業務の手入力に月20時間かかっている」といった具体的な課題へと落とし込みます。課題を明確化することで、SaaS導入によって解決すべき優先順位が決まります。
現場の担当者へのインタビューなども行い、システムに求める要件(機能、予算、セキュリティ基準など)を整理・定義する重要なフェーズです。
2. 最適なSaaSの選定と導入計画の策定
整理した要件に基づき、数あるSaaS製品の中から自社にベストマッチするツールを選定します。
機能比較だけでなく、将来的な拡張性や他システムとの連携、サポート体制なども考慮して提案が行われます。選定後は、いつ、誰が、何をやるのかを明確にした導入スケジュール(ロードマップ)を策定します。
業務への影響を最小限に抑えながらスムーズに移行できるよう、段階的な導入計画を立てるなど、リスク管理も含めたプロの視点でのプランニングが提供されます。
3. 導入設定・データ移行支援
SaaSのアカウント発行や初期設定、権限管理など、システムが使える状態になるまでのセットアップを代行・支援します。
業務フローに合わせた詳細なパラメータ設定など、専門知識が必要な作業も任せられます。また、旧システムやExcelで管理していた既存データの移行も重要なタスクです。
データのクレンジング(整理)やフォーマット変換などを行い、新システムですぐに業務を開始できるようデータを整備します。ここで失敗すると業務が停止する恐れがあるため、プロの支援が特に役立つ工程です。
4. 運用定着と効果測定
導入直後は、操作方法に関する問い合わせやトラブルが発生しがちです。
マニュアルの作成や説明会の実施、ヘルプデスク対応などを通じて、現場社員がストレスなく使えるようサポートします。さらに、導入から一定期間経過後に効果測定を行います。
「業務時間がどれくらい削減されたか」「ミスが減ったか」などを定量的に評価し、必要であれば設定の見直しや追加研修を実施します。導入しっぱなしにせず、成果が出るまで伴走するのが導入支援の価値です。
※3 出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構|J-Net21
SaaS導入で補助金を活用する申請ステップ

補助金を活用してSaaSを導入するには、定められた手順に沿って申請を行う必要があります。
スケジュール管理や書類の準備など、やるべきことは多岐にわたります。ここでは、一般的な申請の流れを4つのステップで解説します。
申請ステップは以下の通りです。
- 申請に必要な書類と事前準備
- IT導入支援事業者との連携方法
- 公募スケジュールと申請の流れ
- 採択後に必要な実績報告の進め方
全体の流れを把握し、余裕を持って準備を進めましょう。
申請に必要な書類と事前準備
補助金申請には、法人の場合は履歴事項全部証明書や法人税の納税証明書、個人の場合は本人確認書類や確定申告書などが必要です。
これらの公的書類は取得に時間がかかる場合があるため、早めの手配が鉄則です。また、多くの補助金申請で必要となる「gBizIDプライム」アカウントの取得も済ませておく必要があります。
行政サービスにログインするための認証システムで、発行までに数週間かかることもあります。申請直前になって慌てないよう、真っ先に準備すべき項目です。
IT導入支援事業者との連携方法
IT導入補助金などの場合、単独で申請するのではなく、「IT導入支援事業者」として登録されているベンダーやコンサルタントと共同で申請手続きを行います。
導入したいSaaSを取り扱っている支援事業者を探し、相談することから始まります。支援事業者は、導入ツールの提案だけでなく、補助金申請のアドバイスや「事業計画」の策定サポートも行ってくれます。
パートナーとなる支援事業者の選び方が、採択率や導入の成否を大きく左右するため、実績豊富で信頼できる事業者を選ぶことが重要です。
公募スケジュールと申請の流れ
補助金には公募期間(申請受付期間)が決まっており、年間で複数回に分けて締め切りが設定されるのが一般的です。
公式サイトで最新のスケジュールを確認し、希望する導入時期から逆算して申請回を決めます。申請は基本的に電子申請システム(jGrantsや申請マイページ)を通じて行います。
自社の基本情報や財務情報、導入するITツールの情報、事業計画などを入力し、支援事業者側の確認を経て提出完了となります。締め切り直前はシステムが混み合うこともあるため、余裕を持った提出を心がけましょう。
採択後に必要な実績報告の進め方
「採択」の通知が来ても、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。
まずは「交付申請」を行い、正式な決定を受けてからSaaSの契約・導入・支払いを行います。その後、支払いの証拠書類(請求書や振込控など)を添えて「実績報告」を行う必要があります。
実績報告が承認されて初めて補助金が交付されます。さらに、導入後数年間にわたり、生産性向上などの効果を報告する「事業実施効果報告」が義務付けられる場合もあります。報告を怠ると補助金の返還を求められることもあるため、最後まで確実に対応しましょう。
※4 出典:サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局|申請・手続きフロー
補助金申請で注意すべきポイント

補助金は返済不要の資金調達手段として魅力的ですが、ルールを守らなければ受給できないばかりか、ペナルティを受けるリスクもあります。
また、すべてのSaaS導入経費が対象になるわけではありません。ここでは、補助金申請において特に注意すべき4つのポイントを解説します。
注意すべきポイントは以下の通りです。
- 不正受給と見なされるケース
- 補助対象外となるSaaSやサービスの例
- 専門家に相談する重要性
- 予算上限に達するリスクと対策
トラブルを未然に防ぎ、確実に支援を受けるための知識を身につけましょう。
1. 不正受給と見なされるケース
事実と異なる申請や、補助金の目的外利用は不正受給とみなされます。
例えば、実際には導入していないツールの費用を請求したり、支払いを偽装したりする行為は厳禁です。また、交付決定前にSaaSの契約や支払いを行ってしまうと、補助対象外となるケースがほとんどです(事前着手の承認を得ている場合を除く)。
「発注や契約は交付決定通知が来てから」という原則を徹底し、ルールを逸脱しないよう細心の注意を払う必要があります。
2. 補助対象外となるSaaSやサービスの例
SaaS導入支援と言っても、PCやタブレットなどのハードウェア購入費は、補助金の枠組みによっては対象外や補助率が低い場合があります。
IT導入補助金などでは、ハードウェアのみの申請は認められないことが一般的です。また、単なる広告宣伝費や、業務効率化に直結しない汎用的なソフトウェア(OSなど)も対象外となることが多いです。
導入しようとしているSaaSや役務(サポート費用)が、申請する補助金の対象経費に合致しているか、公募要領を熟読して確認しましょう。
3. 専門家に相談する重要性
補助金の申請要件や公募要領は非常に複雑で、年度ごとに内容が変更されることも珍しくありません。
自社だけで全てを理解し、完璧な申請書類を作成するのは多大な労力を要します。補助金に精通した専門家(中小企業診断士や認定経営革新等支援機関など)に相談することで、要件の見落としを防ぎ、採択されやすい事業計画書を作成できます。
加点項目のアドバイスなども受けられるため、採択率を高めるためにはプロの知見を借りるのが最も確実な近道です。
4. 予算上限に達するリスクと対策
人気の高い補助金は応募が殺到し、早期に予算上限に達して公募が終了してしまうことがあります。
また、申請件数が多い回は競争率が上がり、採択基準が厳しくなる傾向もあります。対策としては、公募が開始されたらできるだけ早い回に申請することが推奨されます。
「次の回でいいや」と先延ばしにせず、早めに情報収集と準備を開始し、余裕を持って申請手続きを完了させることが、採択への可能性を高めるカギとなります。
※5 出典:中小企業庁|補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
補助金を活用したSaaS導入の成功事例

実際に補助金を活用してSaaSを導入し、大きな成果を上げた企業の事例を紹介します。
具体的なイメージを持つことで、自社での活用検討にお役立てください。
ある林業の企業では、IT導入補助金を活用してドローン連携の3D解析ツール(SaaS)を導入しました。
従来は広大な森林を歩いて一本一本調査していましたが、解析ツールを活用することで、調査人員を約8割削減することに成功しました。人手不足の解消とコスト削減を同時に実現した好事例です。
また、小売業の企業では、販売管理システムをクラウドSaaSへ移行しました。
補助金を活用してコストを抑えつつ、インボイス対応と在庫管理の自動化を実現。手作業による入力ミスがなくなり、伝票発行業務の時間が6分の1に短縮されました。これにより、空いた時間を営業活動に充て、顧客数の増加につなげています。
※6 出典:IT導入補助金2025|ITツール活用事例
SaaS導入支援会社の選び方と比較ポイント

SaaS導入を成功させるには、パートナーとなる支援会社(ベンダーやコンサルタント)選びが極めて重要です。
会社によって得意分野やサポート範囲が異なるため、自社に合ったパートナーを見極める必要があります。ここでは、支援会社を選定する際に比較すべき4つのポイントを紹介します。
比較ポイントは以下の通りです。
- 自社の業界・課題に強みを持つか
- 補助金申請のサポート実績は豊富か
- 料金体系とサポート範囲
- 担当者との相性
これらを基準に、信頼できるパートナーを探しましょう。
1. 自社の業界・課題に強みを持つか
一口にSaaS導入支援といっても、製造業に強い会社、小売業の実績が豊富な会社など、得意な領域は異なります。
自社の業界特有の商習慣や課題を理解している会社であれば、より実践的で効果的な提案が期待できます。
Webサイトの導入事例などを確認し、同業他社への支援実績があるかをチェックしましょう。業界知識が豊富な担当者であれば、単なるツール導入にとどまらず、業務フローの改善提案まで踏み込んでくれる可能性が高まります。
2. 補助金申請のサポート実績は豊富か
補助金を活用する場合、支援会社が申請手続きに慣れているかどうかは死活問題です。
申請実績が豊富な会社は、採択されやすい事業計画書の書き方や、加点ポイントの押さえ方を熟知しています。「IT導入支援事業者」としての採択率や、過去の申請サポート件数を確認することをおすすめします。
補助金申請の手続きをリードし、安心してお任せできる実績を持つ会社を選ぶことで、事務作業の負担を大幅に減らせます。
弊社、株式会社イチドキリはエンジニア出身の代表のもと、完全成果報酬制で9割近くの採択実績を誇っている経営革新等支援機関です。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
3. 料金体系とサポート範囲
導入支援にかかる費用は、会社によって大きく異なります。
「初期費用+月額サポート費」なのか、「導入時の一括払い」なのか、料金体系を確認しましょう。また、見積もりに何が含まれているか(データ移行、マニュアル作成、研修など)を細かくチェックする必要があります。
安さだけで選ぶと、必要なサポートがオプション扱いで追加費用がかかったり、対応が不十分だったりすることもあります。自社が必要とするサポート内容と費用のバランスを見て、コストパフォーマンスを判断しましょう。
4. 担当者との相性
システム導入は数ヶ月にわたるプロジェクトになることも多いため、担当者とのコミュニケーションのしやすさは意外と重要です。
こちらの要望を汲み取ってくれるか、レスポンスは早いか、専門用語を使わずにわかりやすく説明してくれるかなどを確認しましょう。事前の相談会や面談を通じて、信頼関係を築けそうか、熱意を持って対応してくれるかを見極めることが大切です。
どんなに良い会社でも、担当者との相性が悪ければプロジェクトの進行に支障をきたす恐れがあります。
※7 出典:経済産業省|選定のポイント(IT導入支援事業者)
自社に合うSaaSを選ぶためのポイント

補助金が出るからといって、安易にツールを選んでしまうと失敗のもとです。
長く使い続け、成果を出すためには、自社の身の丈に合った適切なSaaSを選ぶ必要があります。ここでは、数あるSaaSの中から自社に最適な一つを選ぶための5つの視点を解説します。
選定のポイントは以下の通りです。
- 補助金対象のサービスから候補を絞る
- 導入目的を明確にして機能を見極める
- コストと補助率のバランスを考える
- 将来の拡張性やサポート体制を確認する
- 無料トライアルや事例で適性を確認する
後悔のない選択をするための指針としてください。
1. 補助金対象のサービスから候補を絞る
コストを抑えることを優先するなら、まずは利用したい補助金の対象となっているツールリストから候補を探すのが効率的です。
IT導入補助金であれば、公式サイトで「ITツール検索」ができ、登録されているSaaSを確認できます。ただし、対象ツールありきで選ぶのではなく、あくまで「自社の課題解決」が最優先です。
リストの中から要件を満たすものをピックアップし、その上で比較検討するという順序を忘れないようにしましょう。
2. 導入目的を明確にして機能を見極める
「何のためにSaaSを導入するのか」という目的を明確にしましょう。
「残業時間を減らしたい」「インボイス対応をしたい」「顧客情報を共有したい」など、具体的な目的があれば、必要な機能もおのずと決まってきます。多機能なツールは魅力的ですが、使わない機能が多いと操作が複雑になり、現場の混乱を招きます。
「必須機能(Must)」と「あれば良い機能(Want)」を整理し、過不足のない機能を持ったツールを選ぶことが定着への近道です。
3. コストと補助率のバランスを考える
導入時の初期費用だけでなく、月額利用料や保守費用などのランニングコストも含めた総額で検討します。
補助金は初期導入費や1〜2年分の利用料をカバーしてくれることが多いですが、それ以降は自費負担となります。補助金終了後も無理なく支払い続けられる金額かどうかもシミュレーションしておきましょう。
高額なツールを補助金頼みで導入してしまい、数年後に維持できなくなるという事態は避けなければなりません。
4. 将来の拡張性やサポート体制を確認する
企業が成長すれば、必要な機能や利用者数も変化します。
ユーザー数の追加が容易か、上位プランへのアップグレードが可能か、他システムとのAPI連携ができるかなど、将来の拡張性を確認しておくことが重要です。また、トラブル時のサポート体制もチェックポイントです。
電話サポートがあるか、チャットのレスポンスは早いか、日本語でのサポートが充実しているかなど、自社のITリテラシーに合わせて安心して相談できる窓口があるツールを選びましょう。
5. 無料トライアルや事例で適性を確認する
多くのSaaSは無料トライアル期間を設けています。
実際に現場の担当者に触ってもらい、操作感や画面の見やすさを確認することは非常に有効です。「直感的に使えるか」「動作は重くないか」など、カタログではわからない相性をチェックできます。
また、同業他社の導入事例を見ることで、具体的な活用イメージが湧きやすくなります。「自社と似た規模・課題を持つ企業がどう成功したか」を知ることは、ツール選びの大きな判断材料になります。
SaaS導入支援と補助金についてよくある質問
SaaS導入支援や補助金に関して、中小企業の皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
疑問を解消し、安心して導入検討を進めてください。
Q1. 補助金を使わずにSaaS導入支援を依頼できますか?
はい、もちろん可能です。
補助金はコスト削減に役立ちますが、申請手続きに時間がかかったり、公募時期が合わなかったりする場合もあります。スピードを優先したい場合や、補助対象外のツールを導入したい場合は、補助金を使わずに支援を依頼することも選択肢の一つです。
予算やスケジュールに合わせて柔軟に検討しましょう。
Q2. 導入支援の費用はどのくらいかかりますか?
導入支援の費用は、導入するSaaSの規模や支援内容、企業規模によって大きく変動します。
数万円程度の簡易的な設定代行から、数百万円規模の業務コンサルティングを含むものまで様々です。補助金を活用する場合は、支援費用の1/2〜2/3程度が補助されることも多いため、実質負担額を抑えることができます。
まずは見積もりを取り、内訳を確認することをおすすめします。
Q3. 地方の中小企業でも支援を受けられますか?
はい、受けられます。
最近はZoomなどのWeb会議ツールを活用して、全国どこからでもオンラインで導入支援を提供する会社が増えています。また、IT導入補助金などの制度も全国の中小企業が対象です。
地域に関係なく、自社に合った専門家のサポートを受けることが可能です。
Q4. 補助金の申請だけを代行してもらうことはできますか?
原則として、補助金の申請は「事業者自身」が行う必要があります。
ただし、認定支援機関やIT導入支援事業者が、申請書の作成支援や入力サポート(伴走支援)を行うことは一般的です。「丸投げ」はできませんが、専門家の強力なサポートを受けながら一緒に申請を進めることは可能です。
Q5. イチドキリに相談するメリットは何ですか?
株式会社イチドキリは、エンジニア出身の知見と補助金のプロとしての実績を兼ね備えています。
単なる申請サポートだけでなく、「システム的な観点」と「経営的な観点」の両面から、貴社に最適なSaaS選定と補助金活用プランを提案できる点が強みです。着手金0円・完全成功報酬型でリスクを抑えて相談できるため、初めての方でも安心です。
まとめ
SaaSの導入は、中小企業の業務効率化と成長に欠かせない投資です。
補助金制度を賢く活用し、導入支援のプロを味方につけることで、コストや運用のリスクを最小限に抑えながら、成果を最大化することができます。
省力化やDXを後押しする補助金は豊富に用意されています。このチャンスを逃さず、自社の課題解決に向けた第一歩を踏み出してください。
SaaS導入や補助金活用に関するご不安があれば、ぜひ株式会社イチドキリにご相談ください。専門家が貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案します。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。