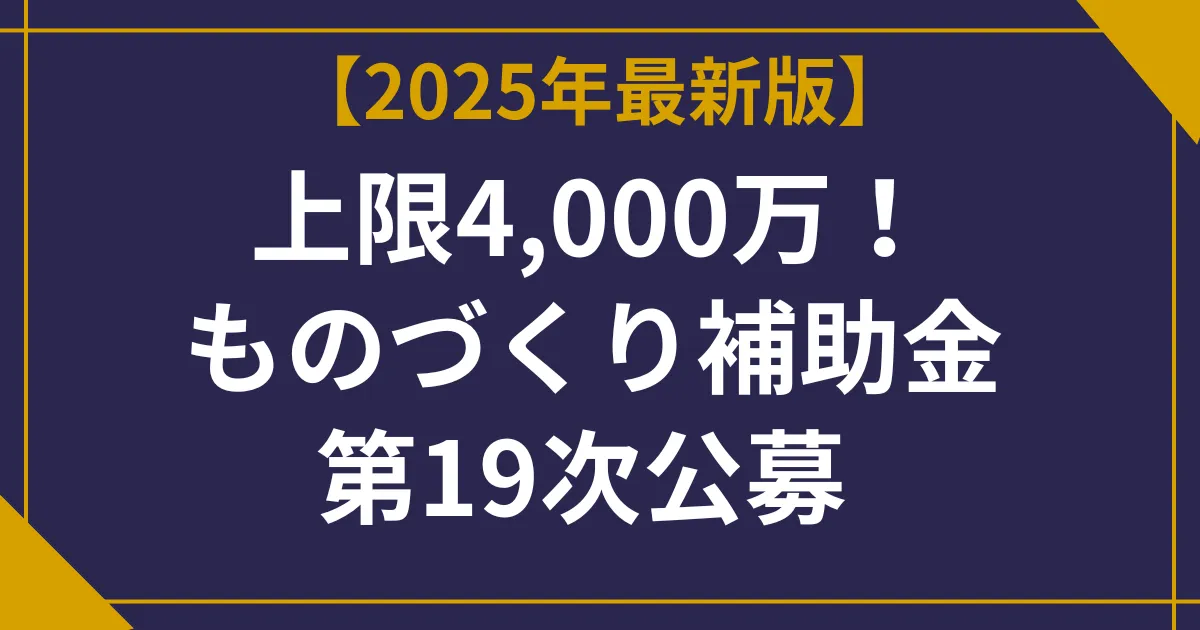ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者を対象に、生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発のための設備投資等を国が支援する補助金制度です。
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」で、中小企業が革新的な製品開発や生産プロセス改善、海外展開などに取り組む際の設備導入費用を補助します。
毎年多くの企業が応募する人気の補助金で、採択率は30~40%程度と競争も厳しく、採択されないケースも珍しくありません。
それだけ中小企業にとって魅力的な制度であり、設備投資による事業強化や新分野進出を強力に後押しするとして注目されています。
第19次公募の概要
第19次公募は、ものづくり補助金の2025年実施分にあたり、令和6年度補正予算によって継続が確定した最新の公募です。
ここでは第19次公募の補助内容や応募対象、スケジュールについて概要を説明します。
ものづくり補助金(第19次公募)の補助額・補助率
第19次公募では、企業規模や事業類型に応じて補助金の上限額と補助率が設定されています。補助額の上限は、通常枠(後述の「製品・サービス高付加価値化枠」)で最大3,500万円、海外展開を目的とするグローバル枠では最大4,000万円と大幅に拡充されました。
たとえば従業員5人以下の小規模事業者では上限750万円(大幅賃上げ時850万円)、51人以上の中小企業では上限2,500万円(大幅賃上げ時3,500万円)といった具合に段階的に設定されています。
補助率は通常、中小企業で1/2(小規模事業者等や再生事業者は2/3)ですが、一定の要件を満たす場合は中小企業でも2/3に引き上げられます。
具体的には「最低賃金引上げ特例」に該当する事業者(後述)であれば、中小企業でも補助率2/3が適用される仕組みです
対象企業(応募資格)
応募できる企業は、日本国内に本社や事業所を有する中小企業者等です。製造業に限らず卸売業、小売業、サービス業など幅広い業種の中小企業・小規模事業者が対象となります。
名前に「ものづくり」と付いていますが、システム開発やサービス開発など非製造業でも申請可能です。
中小企業基本法で定める中小企業の範囲(例:製造業で従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業で100人以下または1億円以下等)に該当し、かつ日本国内で補助事業を実施することが必要です。また、NPO法人や商工組合など法人格を持つ団体、一部の個人事業主等も含まれます。
要件を満たせば小規模な企業から中堅規模の企業まで幅広く応募可能ですが、大企業(中小企業の範囲を超える企業)は対象外です。
公募期間とスケジュール
第19次公募の公募期間は以下の通りです。
- 公募開始:2025年2月14日(金)
- 申請受付開始:2025年4月11日(金)17:00~
- 申請締切:2025年4月25日(金)17:00 必着
- 採択結果発表:2025年7月下旬(予定)
今回は約2ヶ月半の公募期間が設けられており、4月25日が締切日となっています。
電子申請の受付は4月11日から開始され、締切日17時までに申請を完了する必要があります。結果発表は7月末ごろが予定されており、採択された企業はその後事業を開始できます。締切直前は申請が非常に混み合うことが予想されるため、余裕を持った申請手続きが推奨されています。
実際、申請期限間際にはオンラインシステムがつながりにくくなる恐れもありますので、できるだけ早めに準備・提出を行いましょう。
申請要件と対象事業
第19次公募に応募するにあたって満たすべき申請要件と、補助の対象となる事業内容について解説します。従来より要件が強化・変更されている部分もあるため、最新の公募要領を確認し、以下のポイントを押さえておきましょう。
主な申請要件
- GビズIDプライムの取得:
ものづくり補助金の申請は電子申請(jGrants)で行うため、GビズIDプライムアカウントが必須です。ID取得には2週間程度かかるため、未取得の場合は早めに手続きを行ってください。 - 賃上げ要件の遵守:
第19次公募では賃上げに関する要件が強化されています。応募企業は「従業員一人当たりの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上」にするか、または「地域別最低賃金の上昇率以上」の賃上げ計画を有する必要があります。
(※従来は年平均+1.5%以上でしたが引き上げられました)。この賃上げ要件を満たさない企業は申請できません。また、事業実施後には実際にその賃上げ目標を達成することが求められ、未達の場合は補助金の返還義務が生じる可能性があります。 - 中小企業であること:
前述の通り、中小企業基本法に定める中小企業者または小規模事業者であり、日本国内に本社および事業実施拠点があることが条件です。反社会的勢力でないことや、過去に補助金の不正受給など重大な違反を起こしていないことも当然ながら求められます。 - その他の要件:
従業員数が21人以上の事業者については、「次世代法(次世代育成支援対策推進法)」に基づく行動計画の公表が新たに義務付けられています。
これは従業員規模の大きい企業に対し、子育て支援や働き方改革に関する計画策定・公表を求めるものです。また、申請にあたって事前に認定支援機関の関与は必須ではありませんが、金融機関や商工会議所などのサポートを受けることも可能です。応募に際しては最新の公募要領を熟読し、自社が全ての要件を満たしていることを確認しましょう。
補助対象となる事業内容
ものづくり補助金第19次公募では、事業内容に応じて*「製品・サービス高付加価値化枠」(以下、製品・サービス枠)と「グローバル枠」*の2つの申請枠が用意されています。
自社の計画に合った枠を選択して申請します。それぞれの枠の概要は次のとおりです。
- 製品・サービス高付加価値化枠:
国内市場を念頭に、新製品・新サービスの開発や既存製品の高付加価値化による生産性向上を図る事業が対象です。革新的な試作品開発や設備の導入、新技術の実装などによって、自社の製品・サービスの競争力強化や付加価値向上を目指す取組みが該当します。新規性・革新性の高いプロジェクトであることが求められ、単なる老朽設備の更新や営業範囲の拡大のみでは採択は難しいでしょう。 - グローバル枠:
海外展開や輸出拡大など、海外市場の開拓を目的とする事業が対象です。具体的には海外の展示会への出展、国際的な認証の取得、外国語サイトの構築、海外向け製品の開発など、海外販路開拓やブランド確立に繋がる取組みが該当します。中小企業の輸出力強化やインバウンド需要の取り込みを支援する枠であり、海外展開にチャレンジする企業にとって有利な内容になっています。なお、グローバル枠では後述の通り補助上限額が最大4,000万円と高く設定されており、大規模な海外プロジェクトにも対応できます。
いずれの枠においても、補助対象となる経費は事業実施に直接必要な設備投資や関連経費に限られます。建物の建設費や汎用的な事務用品の購入など、補助事業と直接関係のない経費は認められません。自社の計画がどの枠に該当しうるか、公募要領の記載を参照しながら検討してください。
申請手順(準備から申請まで)
ものづくり補助金の申請は電子申請で行われ、事前準備から申請完了までいくつかのステップがあります。ここでは一般的な申請手順を順を追って説明します。
- 事前準備(ID取得・体制整備)
補助金申請にはまずGビズIDプライムの取得が必要です。まだ取得していない場合、公募開始前に余裕を持って申請し、IDを入手してください。あわせて、自社の決算書類や会社概要など基本情報を整理し、申請担当者の体制を整えましょう。公募要領や申請マニュアルに目を通し、応募枠や要件を再確認することも重要です。 - 申請書類の準備
補助金の申請書(事業計画書)を作成します。事業計画書には、補助金を使って実施するプロジェクトの内容や目的、具体的な取組み、スケジュール、予算計画、期待される効果などを盛り込みます。審査では技術的な新規性・優位性、事業化の見込み、政策目的との合致度などが評価されるため、それらを意識した記載が必要です。自社の強みや市場ニーズ、競合との差別化ポイントを明確にし、補助事業によってどのように生産性が向上するかやどれだけ付加価値が増大するかを定量的に示すと効果的です。加えて、賃上げ計画や波及効果(地域経済への寄与やカーボンニュートラルへの貢献など)があれば具体的に記載しましょう。必要書類としては事業計画書のほか、見積書(設備や外注費の根拠となるもの)、直近の決算書類(貸借対照表・損益計算書)、会社の定款や登記事項証明書(法人の場合)などが求められます。提出書類は電子データ化して準備します。 - 電子申請の実施
用意した書類を、中小企業庁が指定する電子申請システム(jGrants)から提出します。ものづくり補助金はオンライン申請のみ受付であり、紙申請やメール送付は認められません。GビズIDでjGrantsにログインし、必要事項を入力して事業計画書等のファイルをアップロードします。入力項目は多岐にわたるため、事前に入力項目一覧を確認しておくとスムーズです。締切日時までに送信を完了すると受付けられ、受付番号が発行されます。締切間際の駆け込み申請はシステム障害等のリスクがありますので、時間に余裕を持って申請を済ませてください。万が一システムトラブルに遭遇した場合は、ものづくり補助金事務局のサポートセンターに早めに問い合わせましょう。 - 採択結果の確認
応募締切後、書類審査・外部有識者による審査が行われ、約3ヶ月後を目安に採択企業が発表されます。第19次公募では2025年7月下旬に結果公表が予定されています。結果はものづくり補助金の公式サイト等に採択者一覧として掲載され、自社が採択されたかどうかを確認できます。また採択企業には事務局から通知も届きます。採択された場合、今度は速やかに交付申請(補助金を正式に受け取るための手続き)を行い、事業を開始する流れになります。一方、不採択の場合も通知はありますが、理由の詳細までは示されないことが多いです。不採択だった企業は内容をブラッシュアップして次回以降に再チャレンジすることも可能です。
※採択後の流れについて:採択=即支給決定ではない点に注意してください。採択後、原則2ヶ月以内に交付申請を提出し交付決定を受けたうえで事業実施となります。
交付決定後は計画どおりに事業を遂行し、完了後に実績報告書を提出して初めて補助金の支払い申請(精算)ができます。補助金は立替払い方式(後払い)のため、一旦企業が自己資金で費用を支出し、後日補助金が振り込まれる形となります。
資金繰り計画も踏まえて進めましょう。
採択されるためのポイント(審査基準・成功事例)
せっかく応募するからには採択を勝ち取ることが重要です。ここでは審査の観点と、採択された成功事例から見るポイントを解説します。
審査のポイント(評価基準)
ものづくり補助金では審査において事業計画の技術面・事業化面・政策面等が総合的に評価されます。
技術面とは提案する製品・技術の新規性や優位性、実現可能性などであり、事業化面とは市場ニーズや収益見込み、人材・資金計画の妥当性など、事業として成功するかの観点です。政策面とは国の施策目的(例えば地域経済への波及効果、デジタル化・脱炭素化への寄与、賃上げや雇用創出への貢献など)との合致度合いを指します。
このため申請書では、自社プロジェクトの革新性・実現性・収益計画・社会的意義をバランスよくアピールする必要があります。特に「なぜこの取組みが必要で、補助金が投入されることでどんな成果が得られるのか」を第三者にも分かるように具体的に示すことが重要です。数値目標(生産性○%向上、売上高○円増加など)や根拠データを示すと説得力が増します。また、事業のリスクと対策について触れておくことや、自社の技術力・実績を客観的に証明する資料(特許や表彰歴、取引実績など)があれば併せて提示すると良いでしょう。
加点要素も可能な範囲で満たすよう検討しましょう。例えば「計画期間内に従業員給与◯%増を達成」「事業終了後も関連投資を継続」など公募要領で示される加点項目があれば、計画に組み込むことで評価が高まります。一方、虚偽記載や体裁不備は減点・失格につながるため注意してください。事業計画書は簡潔かつ論理的にまとめ、熱意だけでなく根拠と計画性のある提案を心がけましょう。
採択企業の成功事例
実際にものづくり補助金を活用して事業成果を上げた採択企業の事例をいくつか紹介します。自社の計画作りのヒントとして参考にしてください。
- 事例① 一次産業向けクラウドサービスの開発ものづくり補助金を活用して、一次産業の生産現場における記録とデータ集計を自動化するクラウドサービスを開発しました。このシステムにより、農業や漁業などの現場での作業効率が大幅に向上し、データの一元管理が可能となりました。結果として、生産性の向上と業務の効率化に寄与しています。
- 事例② ホテル向け多言語タッチパネル式客室オーダーシステムの試作開発ものづくり補助金を活用して、ホテル向けの多言語対応タッチパネル式客室オーダーシステムを試作開発しました。このシステムは、外国人観光客が増加する中、言語の壁を越えてスムーズに客室サービスを利用できるよう設計されています。導入後、ホテルのサービス品質向上と顧客満足度の向上に大きく貢献しています。
- 事例③ ドローンによる農薬散布の自動化とデータ解析力の強化ものづくり補助金を活用して、ドローンを用いた農薬散布の自動化システムと、収量増大のためのデータ解析力を強化するプロジェクトを実施しました。このシステムにより、農薬散布作業の効率化と精度向上が実現し、農作物の収量増加と農業従事者の負担軽減に寄与しています。
これらの事例からも分かるように、明確な課題意識と具体的なソリューションを持ったプロジェクトが成果を上げています。単に設備を買うのではなく、「その設備投資で何を実現し、事業にどうインパクトを与えるか」を描けている点が重要です。補助金を使って生産能力向上や新商品開発を成し遂げ、その後の販路拡大や収益増加につなげている事例は数多くあります。公式サイトの「成果事例紹介」には他にも採択案件の概要が掲載されているので、自社の業種に近い成功例をチェックしてみるとよいでしょう。
よくある質問と注意点
最後に、ものづくり補助金(第19次公募)に関して中小企業の経営者から寄せられがちな質問と注意点をQ&A形式でまとめます。
- Q1. 補助金はどんな経費に使えますか?
A. 補助対象となる経費は幅広く、主なものとして機械装置の購入費やシステム構築費があります。例えば生産設備の購入・設置費用や、新システム導入にかかるソフトウェア開発費などです。それ以外にも、技術導入費(新技術習得のための支出)、専門家経費(専門コンサルタントへの委託費)や外注費(製品開発を他社に委託する費用)、原材料費(試作品の材料費)、運搬費(設備搬入の輸送費)、クラウドサービス利用料(クラウドソフトの利用費)、知的財産権関連費(特許出願や権利取得費用)なども対象となります。逆に対象外経費の例として、建物の建設費、不動産の購入費、汎用性の高い事務機器(パソコンやプリンタ等)、研修費や接待交際費など補助事業と直接関係しない経費は補助金では賄えません。なお、補助対象となる機械装置・システムは*単価50万円以上(税抜)*である必要があります。小規模な備品や低額なソフトウェアは対象外となるため、計画の際はご注意ください。 - Q2. 製造業以外でも申請できますか?
A. できます。 ものづくり補助金の対象業種は製造業に限らず幅広い業種が含まれます。名称から「モノづくり(製造業)の企業しかダメでは?」と誤解されがちですが、実際にはシステム開発企業やサービス業、農業者なども多数採択されています。要は、扱う商材が形ある製品かどうかではなく、生産性向上につながる革新的な取組みであるかが重要です。現状の業務プロセスをIT導入で効率化する計画や、新サービスメニューの開発による付加価値向上策なども立派な「ものづくり補助金」対象事業となります。 - Q3. 採択されたらすぐに補助金がもらえるのですか?
A. いいえ、後払いです。 採択=交付決定ではなく、採択後に事務局との間で交付申請・交付決定の手続きを行い、その後に事業実施となります。補助金は原則として事業完了後に精算払いで支給されます。つまり、企業がまず自己資金で設備を発注・支払いを行い、すべての事業が完了してから補助対象経費について国から補助金が支払われる流れです。資金が手元に入るタイミングは事業終了後(第19次では2025年末~2026年初め頃)となるため、それまでの資金繰りを考慮しておく必要があります。また、交付決定前に発注・契約した経費は補助対象にならない点にも注意してください(原則、交付決定通知を受けた後に発注したものだけが補助の対象となります)。採択後は2ヶ月以内に交付申請書を提出し、交付決定通知を受領してから事業を開始する段取りになります。不明点がある場合は事務局に確認し、手続きを確実に踏みましょう。 - Q4. 補助事業で得た収益を国に納める必要がありますか?
A. 不要になりました。 従来、補助事業によって取得した設備等から収益が生じた場合、その一部を国庫に納付する「収益納付」制度がありましたが、第19次公募より収益納付は撤廃されました。これにより、補助金で導入した設備を活用して得た利益は、全て企業のものとなります。国に返納する必要がない分、その収益をさらに次の投資や事業拡大に充てることが可能です。収益納付の廃止は中小企業の成長を後押しする措置として歓迎されています。ただし、補助事業期間中および終了後一定期間は取得設備の管理や処分に制限がある点は引き続き留意してください(勝手に売却することは禁止など)。いずれにせよ、収益納付がなくなったことで、補助事業で生み出した利益をフルに活用できるようになっています。 - Q5. 他に注意すべきポイントはありますか?
A. いくつか重要な注意点を挙げます。事業実施期間の制約として、交付決定を受けてから原則10ヶ月以内(グローバル枠は12ヶ月以内)に事業を完了しなければなりません。例えば第19次公募では、交付決定時期にもよりますが、概ね2025年内~2026年初め頃までに事業を終え、支払いも完了する必要があります。この期限に間に合わないと補助金を受け取れないため、設備の納期遅延等が起きないようスケジュール管理が重要です。また、事業完了後5年間は毎年事業化状況(売上や付加価値の伸び、賃上げ達成状況)の報告義務があり、賃上げ目標など達成できなかった場合は補助金の一部返還を求められる可能性もあります。さらに、補助事業で取得した設備や成果物について処分制限期間が設けられ(50万円以上の資産は原則5年間勝手に売却等不可)、帳簿の整備・保存など守るべきルールがあります。
まとめ:ものづくり補助金について
ものづくり補助金は、自社の技術開発やサービス創出を加速させる絶好の資金支援策です。補助金獲得には周到な準備が求められますが、採択されれば開発費用の半分程度が国から支給されるため、事業成長の大きな追い風となるでしょう。ぜひ本記事で紹介したポイントを踏まえて計画を練り、チャレンジしてみてください。
また、『マイセレクト』は、中小企業や個人事業主の資金調達に役立つ情報を提供するサイトです。専門家の視点で厳選した消費者金融やファクタリング等のサービスを分かりやすく紹介しており、資金ニーズに応じた最適な選択肢を検討する際に参考になります。
お問い合わせ・無料相談: ものづくり補助金の申請をご検討中の事業者様は、ぜひ当社の専門コンサルタントによる無料相談をご活用ください。
補助金活用のご提案から申請書作成支援までサポートいたします。
引用元:ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト
関連記事
【最大1億円】人手不足解消!省力化投資補助金で最新設備を導入!申請の流れ&成功の秘訣を解説
2025年度はどうなる?東京都助成金「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」について
【2024年11月最新版】都内限定・新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(助成事業)とは?
参考:圧縮記帳とは?圧縮記帳の仕組みから記帳方法、注意点まで解説【江東区の税理士 保田会計事務所】
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。