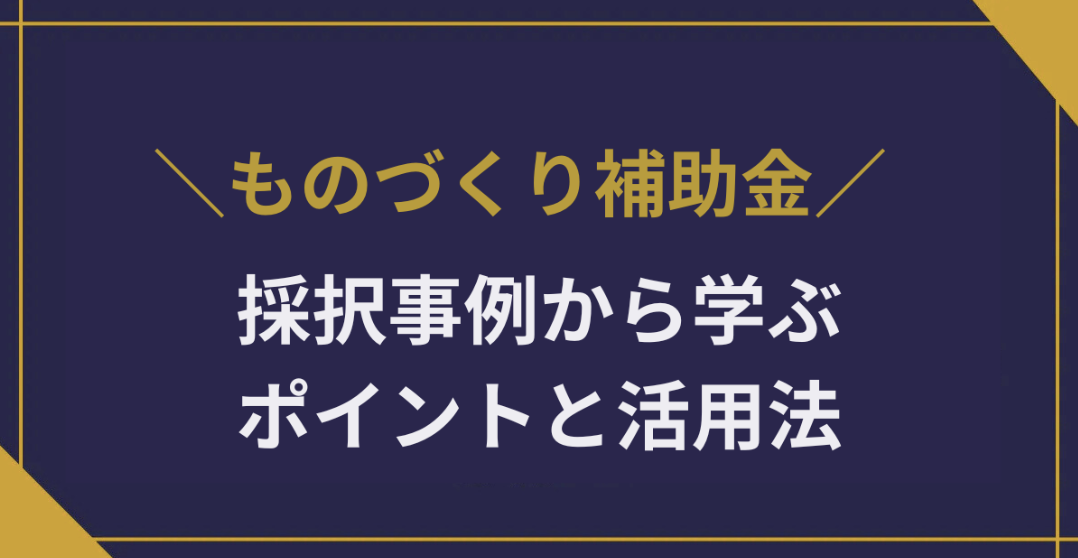中小企業やサービス業において、新しい設備投資や生産性向上に向けた取り組みは不可欠です。補助金制度の中でも人気の高いものづくり補助金では、採択事例を知ることで計画作成の参考になります。採択された企業の背景や成功の秘訣を学ぶことにより、申請前に準備すべき視点が明確になり、事業の成長戦略にもつながるでしょう。
本記事では、ものづくり補助金の実際の採択事例を紹介します。成功企業に共通するポイントや活用方法などをとおして具体的なヒントを得たい方は、ぜひ読み進めてみてください。
ものづくり補助金の採択事例から学ぶ意義
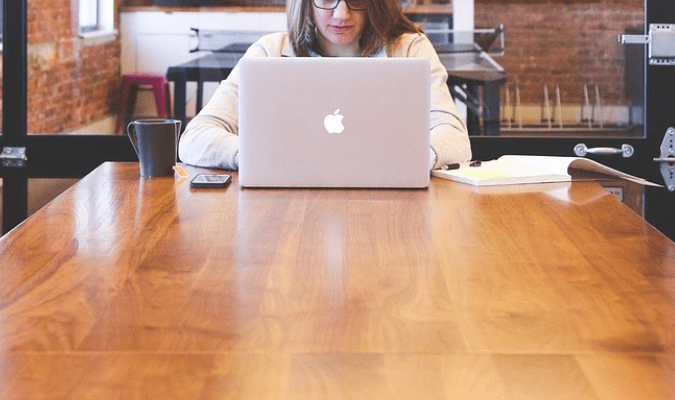
採択事例を学ぶことは、単に他社の成功を知るだけでなく、自社の計画を磨くきっかけになります。審査で求められる視点や事業化の方向性を知ることで、補助金の有効活用に向けた着眼点が定まるでしょう。ここでは、採択事例が持つ価値や共通点、事業化における重要性について順に解説します。
採択事例を見るべき理由
採択事例を確認することは、計画を立てる上での方向性を見つける手がかりになります。補助金審査では、具体性のある課題設定や実現可能性の高い解決策が求められます。
しかし、抽象的なアイデアのままでは説得力が弱く、審査を通過するのは難しいでしょう。したがって、過去に採択された事例を調べると、どのような視点が評価されたのかが明らかになり、自社の計画にも応用しやすくなります。
たとえば、省力化や高付加価値化、環境負荷の低減などが効果的に盛り込まれている計画は採択されやすい傾向にあります。採択事例を学ぶことで、実現性と説得力の高い計画に仕上げやすくなる点が大きなメリットです。
採択企業の共通する特徴
採択された企業には、いくつかの共通する要素があります。ひとつは、自社の現状を客観的に把握し、具体的な課題を特定している点です。曖昧な課題設定ではなく、業績や業務フロー、顧客動向などをデータで示し、なぜ改善が必要なのかを明確にしています。
さらに、解決策としての設備投資が、事業戦略と密接に結び付いていることも特徴です。単に新しい機械を導入したいのではなく、それが売上拡大や新規市場開拓にどう役立つのかを説明している計画が目立ちます。
共通点を理解した上で、計画の中に組み込むことが採択への近道となるでしょう。課題設定の具体性、投資の必然性、長期的な視野の三つを意識することが大切です。
採択事例が示す事業化への重要性
採択された計画は、補助金が交付された後にいかに事業化を実現できるかが重要です。実際の採択事例の多くは、設備導入だけで終わらず、導入後すぐに事業として成果を上げられる体制を整えています。
たとえば、自動化設備を導入する際には、現場スタッフへの教育や業務フローの再構築を同時に進めておくことで、稼働率を高め、短期間で効果を出しています。新商品開発に取り組む事例でも、発売時期や販売チャネル、プロモーション戦略まで計画しておくことで、成果が確実に事業に結び付いているのです。
審査でも事業化の具体性は評価されるポイントのひとつです。採択事例からは、事業化を見据えた準備の重要性が強く伝わってきます。投資の意義と成果を明確にする視点を持つことが、成功への第一歩になるでしょう。
ものづくり補助金の採択事例一覧
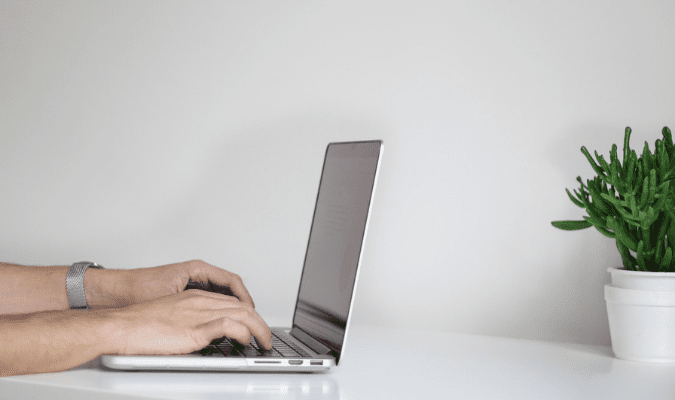
ものづくり補助金は製造業に限らず、幅広い業種で活用されています。多様な採択事例を知ることで、自社の課題解決や成長戦略に役立つヒントが得られるでしょう。
ここでは一例として、設備工事業、宿泊業、介護・医療、飲食料品小売業の事例を紹介します。
設備工事業の事例
愛知県のソノー電機工業株式会社は、電気モーターや制御盤の製造技術を活かし、観光ガイドサービス事業に挑戦するためものづくり補助金を活用しました。訪日外国人の増加に対して、現行の紙やウェブ媒体では対応が不十分であり、事業の多角化も狙いでした。
計画では、ロケーションベースのAR技術を用い、通信圏外でも利用可能な多言語対応の観光ガイドアプリ「パチリガイド」を開発しています。特許を活かした独自技術や、避難所誘導機能による防災貢献が強みです。補助金で安定した開発基盤を確立し、自治体や観光団体との連携が進んだ点も特徴です。
完成したアプリは日本語、英語、中国語などに対応し、地域活性化と防災支援を両立しました。技術力を応用し、新規事業に展開した好事例といえるでしょう。
介護・医療の事例
三重県の有限会社イトーファーマシーは、地域ケアの質向上と業務効率改善を目的に、ものづくり補助金を活用して「医療介護多職種連携PHRシステム」を開発しました。介護と医療の現場で情報共有が不足し、連携の質が低下していた課題に対し、クラウド型の情報共有基盤を整備しています。
ケアマネジャーや訪問介護員がタブレットで記録したデータを即時に共有できる仕組みとし、現場負担を減らしつつサービスの質を安定させました。計画書では、多職種ヒアリングを踏まえた仕様やテスト検証を明示し、実現性を高めています。
導入後は属人的な対応が減り、介護サービスが標準化されました。家族も遠隔で状況確認できる仕組みが利用者の安心感につながり、地域全体の介護水準向上に貢献する好事例です。
飲食料品小売業の事例
大阪市の食品開発株式会社は、食品ギフト業界での業務効率化と競争力強化を目指し、ものづくり補助金を活用して業務支援システムを開発しました。課題は、取引先ごとに異なるフォーマットで商品提案書を作成するため、多くの時間がかかり生産性が低い点でした。
従来1日50アイテムが限界だった作業を、商品情報や写真を自動変換する仕組みにより、約30分で500アイテム出力可能にしています。開発したシステムは汎用化とクラウド対応を施し商品化も実現しました。
社員が簡単に扱える設計で、ミス削減や短納期対応が可能となり、顧客満足度向上につながっています。計画書にはデータ管理や海外展開のビジョンまで盛り込み、高く評価されました。基盤強化と新規収益源確立を両立した好事例です。
採択事例に共通する成功のポイント

採択された企業は、業種を問わず共通した視点を持って事業計画を立案しています。課題設定の精度、計画の実現性、そして将来に向けた成長ストーリーが重視されている点が特徴です。
ここでは採択事例に共通する成功要素を4つに分けて解説します。これらを理解することで、より完成度の高い計画が作りやすくなるでしょう。
具体的な課題を明確化している
採択された事例の大半は、現状の課題が具体的に特定され、定量的なデータや状況説明がなされています。たとえば「人材不足による生産性低下」や「エネルギーコストの増加」といった課題が明確であり、それが事業継続にどのような悪影響を及ぼしているのかまで丁寧に記載されているのが特徴です。
審査側が必要性を理解できる形で、課題と改善の優先度を示している計画は説得力が増します。また、課題の背景にある市場動向や顧客ニーズを分析することで、より現実的な問題意識が伝わりやすくなるでしょう。
課題設定が不十分だと、計画の意義が薄れ採択は難しくなります。現場のデータや声を収集して課題を可視化する姿勢が、採択につながる重要な第一歩です。
設備投資が事業戦略と合致している
採択事例では、設備投資の目的が経営戦略に沿っている点も共通しています。ただ新しい設備を導入するだけでなく、それが経営課題の解決策として機能し、売上拡大や競争力強化にどうつながるのかまで計画に落とし込まれています。
たとえば、航空機部品市場への進出を目指して高精度加工設備を整備した事例や、人材不足を補うために自動化ラインを導入した事例など、経営戦略の一環として設備投資が位置づけられています。導入する設備の選定理由や、導入後の運用体制まで具体的に説明することで、審査側の理解も深まります。事業全体の中で投資の意義が明確であることが、計画の信頼性を高めるでしょう。
将来の成長ストーリーが描けている
採択されている計画では、短期的な成果だけでなく、中長期的な成長のビジョンが必ず描かれています。設備導入や新規事業開始によって、どのように売上を伸ばし、どのような市場でシェアを獲得するのかまで計画書に示されています。
さらに、3年後、5年後に達成したい数値目標や、経営基盤の強化に至る道筋も明確です。成長ストーリーは、補助金が単なる一時的な支援にとどまらず、持続的な成果につながる投資であることを証明します。
計画の先にある未来像を描き、そのために必要な施策を順序立てて説明することが、採択のポイントになります。成長の過程を段階的に示す意識を持ちましょう。
外部支援機関の活用方法
採択事例の多くでは、商工会議所や中小企業診断士、認定支援機関といった専門家のサポートを活用しています。第三者視点を取り入れることで、計画の客観性が高まり、改善点も見えやすくなることがメリットです。支援機関は、補助金申請のポイントや事例の蓄積が豊富であり、計画書の作成段階から有益なアドバイスを提供してくれます。
さらに、経営全体の戦略立案や市場調査についても専門的な知見が得られるため、計画の完成度が向上します。支援を受ける際には、目的や戦略を明確にし、主体的に進めることが大切です。無料相談などを積極的に活用し、専門家の知見を取り入れることで、より実現性の高い計画が仕上がるでしょう。
採択事例を参考に事業を前進させよう

採択事例から学ぶべき視点や成功のポイントを理解した後は、それを自社に活かし、実際に事業を進める準備を整えることが重要です。事例を単なる模倣にせず、自社の現状や目標に合う形で取り入れることで、より現実的で持続可能な成長戦略が描けるでしょう。
ここでは、採択事例を参考にしながら事業を前進させるための具体的なアプローチを4つの視点で解説します。
自社の強みと課題を見つめ直す
採択事例に共通しているのは、まず自社の現状を丁寧に分析している点です。強みがどこにあり、逆にどの部分に課題が潜んでいるのかを把握することで、計画の方向性が定まります。たとえば、製品の品質や技術力が強みであれば、その価値をさらに高める設備投資が適切です。
一方で、生産性の低さや人材不足といった課題が大きい場合は、工程改善や省力化が必要になるでしょう。採択事例を見る際には、自社と同じ業種や規模の企業がどのような課題をどう解決したのかに注目すると参考になります。現状の数値データや現場の声をもとに、自社の立ち位置を明確にしてから計画を立てる姿勢が求められます。自社ならではの特性を反映させる意識が、成功に近づく第一歩でしょう。
成功事例をヒントに事業計画をブラッシュアップ
採択事例は、計画を立案する上で貴重なヒントになりますが、そのまま真似るだけでは十分ではありません。業種や地域、顧客層によって条件は異なるため、自社に合わせてアレンジする必要があります。計画をブラッシュアップする際は、課題の設定、目標の明確化、設備投資の意義を中心に見直すとよいでしょう。
とくに、投資の根拠や期待される効果を具体的にすることが重要です。数値目標やスケジュールを盛り込み、実現性を高める工夫を加えましょう。
また、事例の中で参考になる表現や構成があれば取り入れ、独自性と客観性を両立させることも大切です。計画の精度が上がることで、採択の可能性は確実に高まります。完成度の高い提案を目指して何度も見直しを行いましょう。
事例の裏にある工夫や意識を取り入れる
採択事例には、設備導入や売上増加といった目に見える成果だけでなく、そこに至るまでの工夫や意識も含まれています。現場の業務フローを改善する努力や、スタッフ教育、マニュアル整備といった細かな取り組みが成果につながっているのです。
計画を立てる際も、導入した設備をどう活用し、どのように運用していくのかまで考えることが必要でしょう。裏側の準備が不足していると、せっかくの設備投資も十分に活かせません。事例からは、単なる購入計画ではなく、事業全体の運用まで視野に入れる重要性が学べます。
審査においても、運用体制や社内教育が整っている計画は評価されやすいものです。見えない部分にまで目を配り、計画に反映させる工夫が求められます。
無料相談で専門家の視点を取り入れる
計画づくりの最終段階では、専門家の意見を積極的に取り入れるのも有効です。採択事例においても、商工会議所や認定支援機関、中小企業診断士のサポートを受けながら進めたケースが多くみられます。第三者の視点が入ることで、自社では気づきにくい弱点や改善点が明らかになります。
さらに、補助金申請に精通した専門家は、審査で評価されるポイントを熟知しており、計画をより効果的にブラッシュアップしてくれます。相談する際は、自社の目的や課題をしっかりと整理しておくと、より的確な助言が得られやすいでしょう。
無料相談の仕組みも各地で整っているため、気軽に利用できます。専門家の知見を活用して、完成度の高い計画を仕上げましょう。
まとめ
ものづくり補助金は、革新的な取り組みや生産性向上を目指す企業にとって心強い制度です。採択事例を振り返ると、業種を問わず、課題を明確にし、戦略に沿った設備投資を計画した企業が成果を上げていることがわかります。採択された事業者の共通点や事業化への視点を学ぶことで、自社の計画にも具体性や説得力を加えることができるでしょう。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として、書類作成から面接対策まで一貫して支援し、採択率の高い申請をサポートしています。着手金0円・完全成功報酬型のため、安心してご依頼いただけます。
事業成長に向けた最初の一歩として、専門家と共に計画を作り上げてみませんか。まずは、無料相談をご活用ください。
【株式会社イチドキリ|無料相談はこちら】
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。