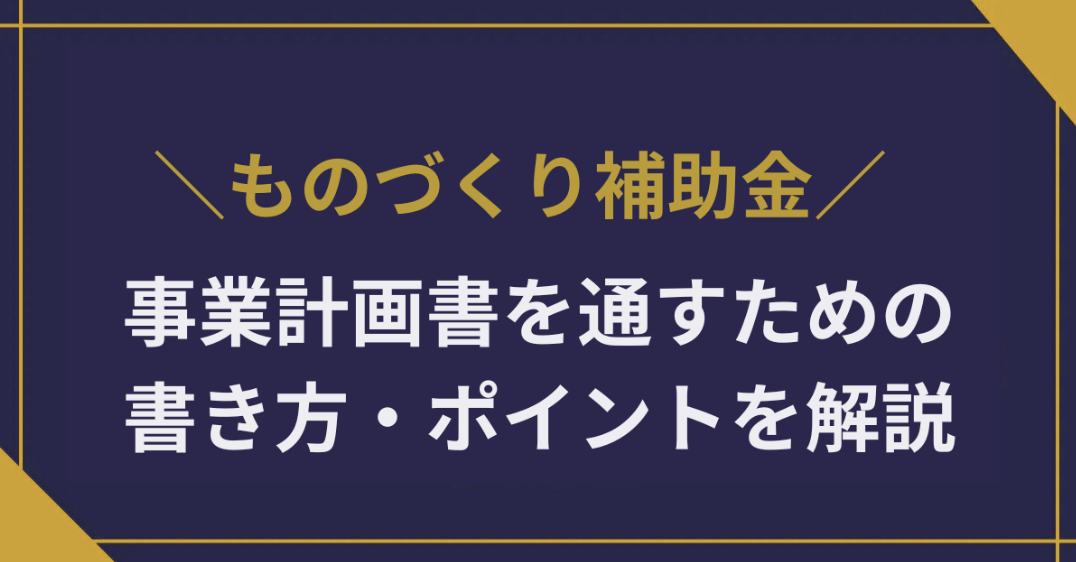ものづくり補助金を申請する際に求められる事業計画書は、採択の成否を決める最重要書類といえます。実現性や革新性、将来性をどれだけ審査員に伝えられるかによって評価は変わりますが、文章構成や情報の見せ方が不十分だと、せっかくの事業案も低い評価で終わってしまうことがあります。
適切な事業計画書を書くためには、審査基準を踏まえ、数字や根拠を添えて論理的に説明する力が必要です。本記事では、採択率を高めるための書き方のコツやNG例を、段階ごとに解説していきます。
- ものづくり補助金の事業計画書の書き方が重要な理由
- 採択されやすい事業計画書の基本構成と書き方
- 事業計画書の書き方で気をつけたいポイント
- 不採択になりやすいNGな事業計画書の書き方
- 事業計画書の書き方に不安がある場合の対処法
- まとめ
ものづくり補助金の事業計画書の書き方が重要な理由

採択されるかどうかは、事業計画書の出来栄えで決まるといっても過言ではありません。なぜ書き方がそれほどまでに大切なのか、どのように評価が左右されるのか、また誤った書き方が及ぼす影響について具体的に見ていきましょう。
審査員に伝わる計画書が採択を左右する
事業計画書は、事業のビジョンを第三者に正しく理解してもらうための重要なツールです。審査員は申請者と直接会話することなく、提出された書類のみで判断を行います。したがって、申請者の考えや事業の背景が読み取れない場合、評価は低くなる傾向があります。
必要なのは、事業の目的や課題解決策、そして将来的な利益や社会的意義を順序立てて明記することです。読み手の立場に立ち、過不足のない記載を意識すると伝わりやすい計画書になります。
さらに、文章は簡潔かつ具体的にし、曖昧な表現を避けると説得力が増します。こうした工夫により、審査員に理解されやすい計画書が完成し、結果として採択される可能性が高まるのです。
書き方の違いで評価が変わるポイントとは
同じ事業案でも、書き方次第で審査員の印象は大きく変わります。根拠があいまいな記載は、事業の実現性や収益性に疑問を持たれる原因となりやすいものです。
一方で、現状の課題や市場環境を分析したうえで、事業の有効性を数値やデータで裏付けると評価が高まります。加えて、事業の革新性や社会的な意義についても、単なるスローガンではなく具体的な事例や数値目標を提示するとより説得力が増します。
審査員は短時間で複数の計画書を確認するため、内容を一目で理解できるように整理されているかも大切です。記載の仕方ひとつで事業の価値が伝わるかどうかが決まるため、記載の精度向上を意識しましょう。
書き方を間違えると不採択につながるリスク
不適切な書き方は、良い事業案を持ちながらも採択を逃す原因になります。現状分析が浅く課題があいまいな場合や、計画の実現性を示す数値根拠が不足している場合、審査員から信頼性が低いと判断される恐れがあります。
また、構成が乱雑で読みづらい書類も、事業全体の計画性が疑われる要因となります。さらに、必須項目の記載漏れやルールを逸脱した書き方をしていると、形式面でも減点されてしまうのが実情です。
リスクを避けるためには、計画書を一度書き上げたあとに公募要領を見直し、抜けや齟齬がないかを確認する作業が欠かせません。採択率を高めるためには、ルールを守りつつ論理性の高い文章に仕上げる工夫が必要でしょう。
採択されやすい事業計画書の基本構成と書き方

事業計画書には、審査員が理解しやすい基本構成があります。それぞれのパートで何をどのように書くべきかを知ることで、説得力が高まり評価されやすくなります。ここでは、事業計画書を構成する代表的な3つの要素と電子申請における工夫について順に見ていきましょう。
補助事業の具体的取組内容の書き方
補助事業の具体的取組内容では、まず現状の事業環境やこれまでの取り組みの経緯から説明を始めると効果的です。そのうえで、自社が直面している課題とその重要性を明確に示すことで、補助事業の必要性が伝わります。
次に、課題を解決するために導入する設備や新たな仕組み、それによって達成したい目標を具体的に記載しましょう。ここでは、単なる宣言ではなく、工程ごとの改善計画や新規技術の活用方法など、実現可能性を感じさせる内容にすることが求められます。
さらに、達成時期や進め方についても言及することで、計画性の高さが伝わりやすくなります。こうした流れを意識することで、審査員の共感を得られる書き方が実現できるでしょう。
将来の展望の書き方
将来の展望を記載する際には、取り組みが市場や顧客にどのような価値をもたらすかを中心に据えます。自社の立ち位置とターゲット市場の状況、競合分析などを踏まえたうえで、差別化のポイントや将来の事業規模を示すと説得力が高まります。
また、目標市場の成長予測や顧客のニーズ変化にも触れ、そこに自社の戦略がどう対応するかを説明しましょう。売上や利益といった数値目標も具体的に記載することで、実現可能性が評価されやすくなります。
さらに、地域社会や業界全体への波及効果にまで言及すれば、政策的な意義も強調できます。将来的な計画を具体的かつ現実的に示す姿勢が、審査員に好印象を与えるでしょう。
会社全体の事業計画の書き方
会社全体の事業計画では、補助事業が自社全体の成長戦略の中でどのような位置付けにあるかを説明します。基準年度を起点に、3年後、5年後の売上や営業利益の推移を計画し、補助事業によってどのように業績が改善するかを明示しましょう。
重要なのは、補助事業単体の成否だけではなく、それが全社的な目標に寄与することを具体的に伝える点です。たとえば、新規顧客の獲得数や、従業員一人当たりの生産性向上率など、測定可能な指標を記載すると、計画性と現実性が高く評価されます。スケジュールや数値目標を体系的に記載することが、全体計画の完成度を高めるコツでしょう。
電子申請に合わせた書き方の工夫
近年では、事業計画書の提出方法が電子申請に切り替わっています。電子申請に対応するためには、システムに入力する際の仕様に沿った文量や表現を意識することが欠かせません。長文になりすぎず、項目ごとに端的かつ具体的な記載を心がけるとスムーズです。
また、入力欄に応じてキーワードや数字を効果的に盛り込むことで、評価ポイントを押さえやすくなります。さらに、加点対象となる項目が入力画面に設定されているケースもあるため、それらを漏れなく記入するよう準備しておくと安心です。電子申請の特性を理解し、適切に対応する姿勢が審査結果を左右することもあるため、準備段階から意識して進めるとよいでしょう。
事業計画書の書き方で気をつけたいポイント
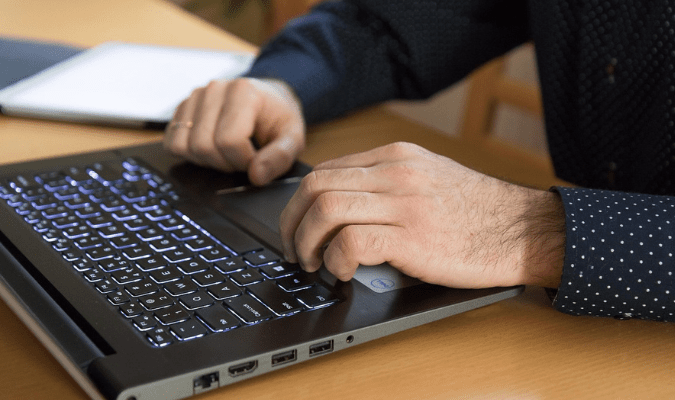
事業計画書の完成度を高めるためには、ただ情報を並べるだけでは不十分です。公募要領に沿って正確かつ論理的に記載し、審査員が理解しやすい文章を心がける必要があります。ここでは、記載時にとくに注意すべき具体的なポイントを4つに分けて解説します。
公募要領のルールに沿った表現を使う
事業計画書を作成する際は、必ず公募要領に記載されたルールを確認し、その内容に準拠した記載を意識することが重要です。審査基準や必要な記載項目が明示されているため、それらを無視した構成で提出すると、減点や不採択の原因となる恐れがあります。
まずは公募要領を熟読し、どの項目にどの情報が求められているのかを把握しましょう。たとえば、補助事業の具体的な内容、課題とその解決策、数値目標、社会的な意義などが必須項目として定められていることが多いです。
さらに、過去の採択事例や公式サイトで公開されている記載例も参考にすることで、正しい流れを把握しやすくなります。書き上げた後は、公募要領に沿っているかどうかをチェックリスト形式で確認すると確実です。
専門用語や略語を多用しすぎない
読みやすい計画書を作成するには、専門用語や略語を多用しすぎないことも大切です。審査員の中には業界の専門知識を持たない方もいるため、専門的な用語や独自の略称が頻繁に登場すると理解が追いつかず、評価が下がる可能性があります。
業界で一般的に使われる表現であっても、読み手にとって分かりにくい可能性がある場合は、初出しの際に簡単な説明や補足を付け加えると親切です。難解な表現を避け、平易な言い回しに言い換える工夫をすることで、読みやすさが格段に向上します。
審査員がストレスなく内容を把握できる計画書こそ、高く評価される傾向があります。全体を読み直して、不要な専門用語がないか確認しておきましょう。
図表や数値を活用してわかりやすくする
文章のみで構成された事業計画書は、情報が多いほど読み手に負担をかけてしまいます。したがって、必要に応じて図表や数値を活用して視覚的に伝わりやすくする工夫が効果的です。たとえば、売上推移や投資回収の見通し、工程スケジュールなどはグラフや表にまとめると一目で理解できます。
加えて、文字だけでは伝わりにくい現場の状況やフロー図も、イメージしやすい形に整理することで評価が高まります。図表に使うデータは正確で、かつ根拠が示せるものに限定することが信頼性を高めるポイントです。文章と図表のバランスを意識し、視覚的に伝わる計画書を目指すと審査員の印象が良くなるでしょう。
加点項目や数値目標を明記する
事業計画書では、評価の基準となる必須項目だけでなく、加点項目を積極的に記載する姿勢も重要です。たとえば、経営革新計画や事業継続力強化計画の認定を受けている場合は、それを明記することで加点対象となる場合があります。事前に公募要領で加点の条件を確認し、自社が該当するものはすべて計画書に反映させるとよいでしょう。
さらに、事業の目標数値も具体的に設定することで、計画の現実性が伝わりやすくなります。売上成長率や利益率、従業員数の変化など、測定可能な数値を示すと説得力が増します。単なる理想論ではなく、具体的な根拠や計算に基づいた目標設定が、審査員の納得感につながります。
不採択になりやすいNGな事業計画書の書き方
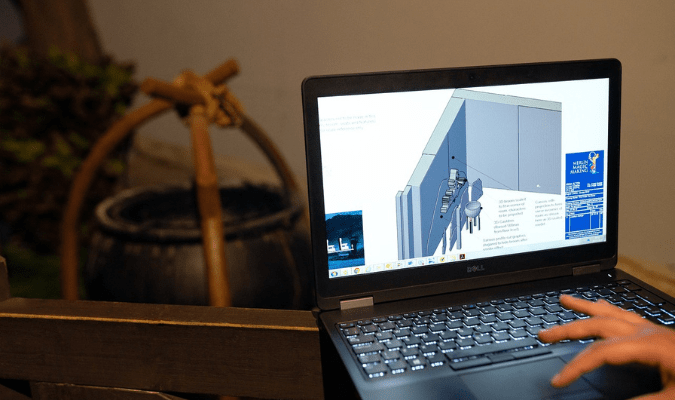
事業計画書の中には、見栄えや分量だけは整っていても、評価されにくい内容になってしまう例が少なくありません。審査員の視点を意識せずに書かれた計画書は、せっかくの事業案を伝えきれずに終わる可能性があります。ここでは、よく見られるNGな書き方を4つ挙げ、それぞれの問題点と改善の方向性について説明します。
根拠のない売上や利益の予測を書いてしまう
事業計画書でとくに目立つNG例が、根拠のない数字を並べてしまうケースです。市場の規模や競合状況、現状の経営指標といった裏付けなしに「売上3倍」や「利益率20%向上」といった目標だけを書いてしまうと、計画性のない夢物語と受け取られやすくなります。
数字そのものは必要ですが、それに至るまでの過程や論理的な説明が不可欠です。たとえば、業界データや自社の過去実績を引用して、その数字がどのようにして実現されるのかを段階的に示すと納得感が増します。数字を使う際は、あくまで現実的な根拠を示す意識を持つようにしましょう。
現状の課題が不明瞭なまま計画を書く
採択されない事業計画書の多くは、現状の問題が十分に説明されていない傾向があります。自社の業務や市場環境にどのような課題があり、それをなぜ解決しなければならないのかが書かれていないと、事業の必要性が伝わりません。
設備投資や新サービスの導入理由が不明確なままでは、単なる設備更新や利益追求に見られ、審査員に響きません。まずは現状を定量的・定性的に分析し、課題を明確にしてから、その解決策として計画を説明する順序が重要です。課題の設定が的確であるほど、計画全体の説得力が高まります。
必要性や効果が伝わらない抽象的な記載
文章に具体性がなく抽象的すぎると、事業の方向性や効果が理解されません。たとえば「地域経済に貢献する予定」や「効率化を進める予定」といった表現だけでは、具体的にどのような変化をもたらすのかが見えてこないため、評価が低くなりがちです。
どの指標でどれほどの改善が見込めるのか、具体的な行動や成果を数字で示すことが望ましいでしょう。抽象的な目標を並べるのではなく、工程や目標値、スケジュールを示しながら書くことで、計画全体が現実的で実現性が高いと判断されやすくなります。
ボリュームが過剰・不足で読みづらい
計画書の内容が過剰に膨らみすぎたり、逆に極端に情報が不足していたりすることも、評価を落とす要因になります。ボリュームが多すぎると要点がわかりにくく、審査員に負担をかける結果になりやすいでしょう。
反対に、情報が簡略化されすぎて必要な項目が抜け落ちていると、計画の全体像が伝わりません。公募要領で示された分量やページ数の目安を守りつつ、適度な情報量で整理する姿勢が大切です。簡潔ながらも網羅的で、読みやすさを意識した文章構成にすることで、審査員の理解を助ける計画書が完成します。
事業計画書の書き方に不安がある場合の対処法
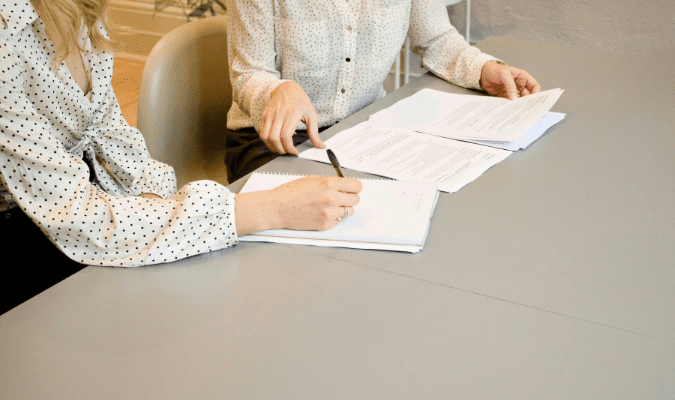
事業計画書の作成には、専門知識や豊富な経験が求められます。初めて挑戦する場合や過去に不採択の経験がある場合は、正しい書き方がわからず不安を感じることも多いでしょう。そんなときは、社内の見直しや外部リソースの活用など、適切な対処法を選ぶことが成功への近道となります。ここでは、書き方に不安があるときに役立つ具体的な3つの方法を紹介します。
自社内でレビューを繰り返してみる
まず取り組みやすいのが、自社内で計画書の内容を複数人でレビューする方法です。経営層や現場担当者、営業スタッフなど、異なる立場のメンバーに確認してもらうことで、さまざまな視点からの意見を取り入れられます。
とくに現場担当者からは実務面での具体的な課題や改善案、営業スタッフからは市場の反応に基づいた意見が得られるでしょう。レビューを繰り返すことで、主観的な文章表現や不自然な流れに気づき、修正することができます。
さらに、公募要領を横に置いて一項目ずつ見比べながら進めると、抜けや漏れを防げます。自社内での意見を積極的に取り入れる姿勢が、計画書の完成度を高める第一歩です。
専門家に添削を依頼する方法
より確実に精度を高めたい場合は、専門家に添削を依頼するのも有効です。中小企業診断士や経営革新等支援機関の担当者は、審査基準や採択傾向に精通しているため、的確なアドバイスが期待できます。
第三者の視点で客観的に計画書を読み込み、弱点や改善点を指摘してもらうことで、自己流では気づけなかった課題に気づくことができます。とくに、事業の強みや政策的な意義をより強調する書き方や、加点項目を見逃さない記載方法についてアドバイスをもらえるのが強みです。添削を受けた後に修正を重ねることで、審査員に伝わりやすく完成度の高い計画書が仕上がります。
書類作成支援サービスの活用も視野に
社内での作業時間を確保しにくい場合や、申請に慣れていない場合は、書類作成支援サービスの利用も検討する価値があります。実績のあるサービスでは、過去の採択事例や最新の公募要領に基づいたノウハウを活用し、申請に最適化された計画書を作成してくれます。
さらに、着手金不要や成果報酬型で対応しているところもあり、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。とくに、申請の期日が迫っている場合や人手が不足している場合は、効率的に準備を進める手段となります。外部サービスを上手に活用することで、時間の節約と採択率向上を両立させることが可能です。
まとめ
ものづくり補助金の事業計画書は、単なる申請書類ではなく、審査員に事業の価値を伝える最も重要なプレゼン資料です。課題や解決策を具体的に示し、数値で裏付けることにより、採択の可能性を大幅に高めることができます。
一方で、抽象的な表現や根拠のない予測、構成の乱れは不採択のリスクを高めるため、書き方には十分な注意が必要です。専門家の視点や支援サービスを活用することで、計画書の完成度は格段に向上します。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として、ものづくり補助金の申請支援を着手金0円・完全成功報酬型で提供しています。書類作成から電子申請、採択後のフォローまで、経験豊富なスタッフが徹底サポートし、申請にかかる作業時間を大幅に削減します。
採択後の事業運営まで見据えた継続的な支援も可能です。採択率を高めたい方や書き方に不安がある方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。