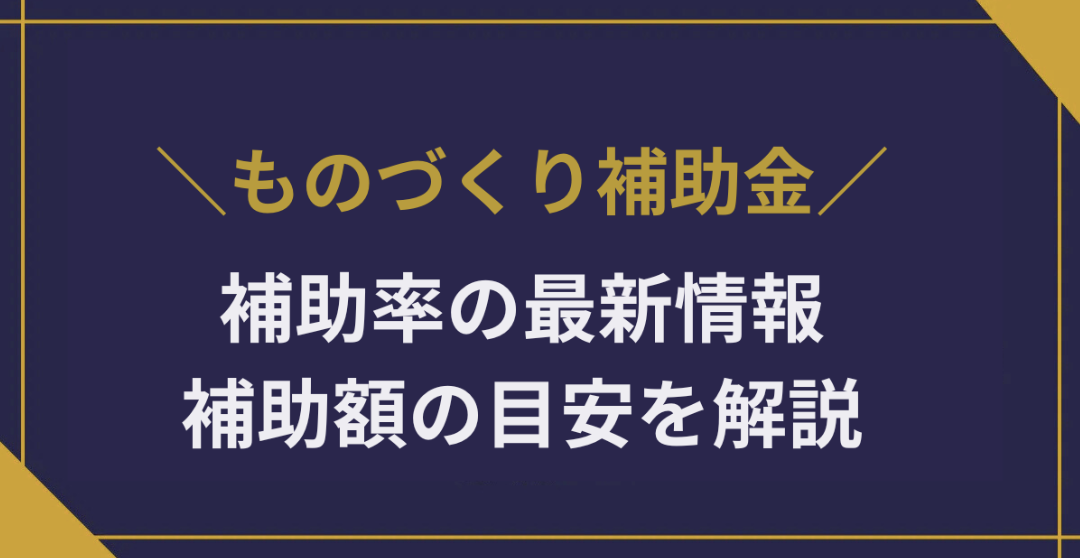設備投資や新製品開発を支援する制度として人気が高いものづくり補助金は、補助率の違いを理解することで採択後の負担軽減に役立ちます。補助率は一律ではなく、企業規模や選ぶ申請枠、さらには賃上げなどの取り組みに応じて変動します。そのため、自社がどの補助率に該当するのかを正確に知ることが重要です。
本記事では、最新情報をもとに補助率の基本から高い補助率を適用するための条件までわかりやすく解説します。
ものづくり補助金の補助率とは

補助金制度を活用する際、補助率の正しい理解が不可欠です。補助率は申請した経費のうちどれくらいが補助されるかを示す割合で、申請枠や事業規模によって異なります。補助率の高低は採択後の自己負担額に直結するため、制度の仕組みを知ることが重要です。
ここでは、補助率の基本的な考え方や補助上限額との違い、計画に及ぼす影響について解説していきましょう。
補助率の基本的な考え方
ものづくり補助金では、補助対象経費に対して支援される金額の割合を「補助率」と呼びます。たとえば経費が2,000万円の場合、補助率が2分の1ならば補助金は1,000万円となり、残りは事業者が負担します。
制度では、事業規模が小さいほど補助率が高くなる傾向があり、小規模事業者や特定の枠では3分の2まで上がる場合もあるのです。補助率の数値は申請時に決まるため、あらかじめ自社に適用される補助率を調べておくことが必要でしょう。
さらに、補助率が高い枠を選ぶには追加の条件が課されることも多く、事業内容との整合性も見極めたいところです。補助率を正しく理解することで、事業資金計画の策定がしやすくなり、無理のない投資が可能になります。申請する際には、この考え方を踏まえて計画を組み立てましょう。
補助率と補助上限額の違い
補助率と混同しやすい概念に「補助上限額」があります。補助率が高くても、補助上限額を超えた金額は補助されません。たとえば補助率が3分の2であっても、上限額が750万円の場合、それ以上の補助金は支給されず、残りは自己負担になります。
この仕組みは限られた予算を公平に分配するためのものであり、どの枠を選ぶかによって上限額の設定も異なります。
計画段階では、以下の3つを組み合わせて試算して、最終的な負担額を見積もると良いでしょう。
- 経費総額
- 補助率
- 上限額
申請枠によっては上限が高めに設定されるものもあり、大規模な投資が必要な事業者に適した選択肢になります。制度を理解する際は、補助率だけでなく上限額の確認も忘れずに行いたいところです。
補助率が申請額に与える影響
補助率の違いは、最終的な自己負担額に大きな影響を与えます。たとえば、経費が3,000万円のプロジェクトで補助率が2分の1の場合、自己負担は1,500万円です。しかし補助率が3分の2に上がれば、負担は1,000万円となり、資金繰りの余裕が生まれます。
補助率の差は事業の実行可能性に直結するため、補助率の高い枠が選べるなら積極的に検討したいところです。ただし、補助率が高い枠は要件が厳しくなる傾向もあります。申請に必要な計画内容や達成すべき指標が増えることもあり、採択されるためのハードルは上がります。
無理に高い補助率を狙うのではなく、現実的に達成可能な条件で申請する方が賢明でしょう。補助率の影響を十分に理解し、自社にとって最適な申請戦略を立てることが重要です。
補助率は事業規模でどう違う?
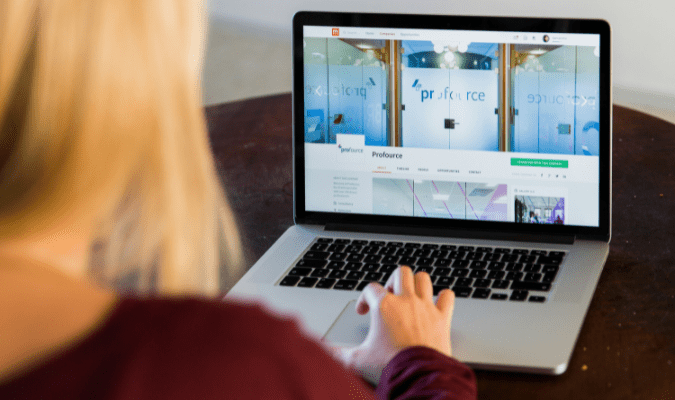
ものづくり補助金では、企業や事業者の規模によって適用される補助率が異なります。小規模な事業者には高い補助率が適用される一方で、中堅規模以上の事業者は標準的な補助率になります。
ここでは、それぞれの事業規模に応じた補助率の特徴を詳しく解説していきます。
中小企業の場合の補助率
中小企業に分類される事業者の補助率は、通常枠で原則として2分の1です。すなわち、経営基盤が比較的整っている事業者が対象となるため、自己負担の割合も一定以上を求められる仕組みです。
従業員数が6人から20人程度の企業が該当するケースが多く、上限額は1,000万円前後に設定される傾向があります。補助率は標準的ではありますが、事業計画の内容や取り組むテーマによって、加点や特例が適用される場合もあります。
事業の成長性や実現性を十分に示すことで、採択の可能性が高まるでしょう。中小企業の経営者は、自社の状況に応じて無理のない範囲で計画を練ることが肝心です。安定した資金計画と事業の将来性を示せるよう準備を進めると安心です。
小規模事業者や個人事業主の補助率
小規模事業者は、補助率が最大で3分の2まで引き上げられます。小規模事業者が新規事業に挑戦しやすい環境を整えるための措置です。
たとえば、飲食店や小売業など地域に根ざした事業者が設備投資や新サービスの導入を検討する場合、この高い補助率が大きな後押しとなります。小規模な事業者にとっては、資金調達のハードルが高いため、この制度を活用する価値が高いといえるでしょう。
ただし、補助率が高いからといって、安易な計画にしてしまうと採択されにくくなる点には注意が必要です。しっかりとした計画書を用意し、実現性のある目標を掲げることが重要です。採択されやすい内容にするためには、事業の独自性や社会的な意義も盛り込むと良いでしょう。
従業員数が多い場合の注意点
従業員数が50人以上の事業者の場合、補助率は原則2分の1で据え置かれ、補助上限額は規模に応じて高めに設定されます。しかし、補助率を高くするための特例は適用されにくく、賃上げや環境対応など追加の取り組みが必要です。
従業員数が多い企業は、事業規模が大きくなる分、計画の緻密さや実現性の高さが問われます。申請にあたっては、投資の規模と補助率、そして自己負担の割合をしっかり把握し、採択後の負担に耐えられる計画を立てることが大切です。
大規模な投資を計画する場合は、上限額を有効に活用しながら、自社の強みを活かせる事業内容にすることが求められます。事業計画の精度を高め、審査での評価が上がるよう準備を重ねると良いでしょう。
補助率は申請枠によっても変わる

ものづくり補助金では、申請する枠ごとに補助率や上限額が異なります。2025年の最新制度では「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」が選択肢として設けられています。自社の事業方針やターゲット市場に合わせて適切な枠を選ぶことで、最大限の支援を受けられる可能性が高まります。
それぞれの特徴や条件を理解し、効果的に制度を活用しましょう。
製品・サービス高付加価値化枠の補助率
製品・サービス高付加価値化枠は、中小企業が国内市場で新製品や新サービスの開発に取り組む際に利用しやすい制度です。2025年公募では、従業員数に応じて補助上限額が段階的に設定され、補助率は原則として中小企業が2分の1、小規模事業者および再生事業者が3分の2まで適用されます。
さらに、最低賃金の引き上げに積極的に取り組む企業には、特例として補助率を3分の2に引き上げる措置が用意されています。従業員数が5人以下の場合の上限は750万円からスタートし、規模に応じて最大2,500万円まで設定されているのです。
経営資源が限られた事業者にとって、自己負担を抑えて新しい価値を市場に提供できる点が大きな魅力です。この枠を活用する場合は、革新性の高い内容であることや、生産性向上につながることを明確に示す計画作りが求められます。
グローバル枠の補助率
グローバル枠は、海外市場の開拓を目指す事業者に適した制度です。2025年の公募においては、補助上限額が一律で3,000万円に設定されており、補助率は中小企業が2分の1、小規模事業者および再生事業者が3分の2となります。
対象となる事業は、輸出向け製品開発や海外市場向けマーケティング、インバウンド需要対応、さらには海外企業との共同プロジェクトなど幅広い取り組みが含まれます。グローバル枠を選択する際は、海外市場での実現可能性や持続性を十分に示すことが重要です。
また、国内市場と比較してリスクが高い分、計画内容の精度や戦略性も求められます。高い補助率を活用しつつ、新たな市場開拓による事業成長を狙いたい事業者にとって有力な選択肢といえるでしょう。採択されるためには、現地の市場調査や協業先の確保など、具体的な準備を進めたうえで申請することが推奨されます。
補助率を2/3にするための条件

ものづくり補助金では、一定の条件を満たすと補助率を最大3分の2まで引き上げることが可能です。通常枠のままでは負担が大きいと感じる場合や、小規模な経営規模で挑戦する場合には、この仕組みを理解して申請に活かすと良いでしょう。
ここでは、補助率を高めるために求められる代表的な条件について紹介します。
小規模事業者が対象となるケース
補助率を3分の2に引き上げる最も一般的なケースが、小規模事業者に該当する場合です。従業員数が5人以下の法人や個人事業主であれば、原則として3分の2の補助率が適用されます。経営基盤が脆弱で資金調達が難しい事業者を支援するための措置です。
たとえば、地域の飲食店や小売業、クリニックなど、少人数で運営している事業者が対象となります。こうした事業者が設備更新や新サービスの開発を進めやすいよう制度が設計されています。
ただし、申請書類や計画の質が低いと不採択となる可能性もありますので、補助率が高いからといって油断せず、事業の意義や実現性を明確に示すことが重要です。小規模であっても計画の完成度が高いほど審査で有利になるでしょう。
再生事業者として申請するケース
事業再生に取り組む企業もまた、補助率3分の2が適用される場合があります。具体的には、経営改善計画を策定し、認定された「再生事業者」であることが条件です。過去に業績悪化を経験し、改善に向けて取り組む企業に対し、支援を手厚くする目的で設定された制度です。再生事業者の場合は、再建の進捗状況や将来の収益計画を明示する必要があり、通常の事業者以上に審査基準が厳しくなることもあります。
再建の一環として設備投資や新製品開発を行い、付加価値の向上や雇用の維持につながることを示すことが求められます。計画の説得力を高めるためには、専門家や支援機関の協力を得ながら準備を進めると良いでしょう。再生事業者に適用される高い補助率は、経営の立て直しに大きな力となります。
賃上げ要件を満たした場合の特例
賃上げの取り組みを計画に組み込むことで、補助率が引き上げられる特例も用意されています。地域別最低賃金を一定額以上上回る水準まで従業員給与を引き上げることを約束する事業者が対象です。
具体的には、計画期間内に給与支給総額や最低賃金の増加を達成することが条件となります。地域社会への還元や雇用の安定を目的とした制度であり、社会的意義の強い事業計画として評価される傾向があります。
ただし、賃上げ目標を達成できなかった場合には返還リスクが生じることもあり、無理のない範囲で目標設定を行うことが大切です。賃上げ特例を活用する際には、従業員の働き方改革や生産性向上施策とあわせて計画を策定し、説得力のある事業として審査を通過できるよう工夫しましょう。
補助率を正しく理解し有効に活用するために

補助率の仕組みをきちんと把握しておくと、無理のない計画を立てやすくなり、採択後の負担軽減にもつながります。制度の詳細を調べ、自社に適した補助率を選ぶことで、事業成功の可能性が高まるでしょう。
ここでは、補助率の確認方法や事業計画への影響、計画時の注意点について紹介します。
補助率の確認方法と最新情報の把握
補助率は、申請時期や制度改定によって見直される場合があります。申請する前に、必ず公募要領や公式サイトで最新情報を確認しましょう。とくに、公募のタイミングによって申請枠や補助上限額が変動することも少なくありません。
公募要領には、申請枠ごとの補助率が明示されているため、自社の規模や計画内容に合った枠の条件を確認してから準備を始めると良いでしょう。さらに、支援機関や専門家のアドバイスを受けることで、見落としがちな注意点にも気づきやすくなります。補助率の確認作業は申請の基本中の基本であり、事業の成否を左右する重要なステップといえます。
補助率の違いが事業計画に与える影響
補助率の高低は、事業計画の規模や実現性に直接関わってきます。高い補助率が適用されれば自己負担が軽減されるため、より大規模な設備投資や先進的な取り組みも検討しやすくなるでしょう。
一方で、補助率が低い場合は自己資金の割合が増えるため、無理のない範囲で計画を見直す必要があります。事業計画を作成する際は、まず現時点で適用可能な補助率を想定し、その範囲で最大限の効果が出る内容を検討することが重要です。
採択された後に資金が不足するリスクを避けるためにも、過剰な見積もりはせず、補助率を考慮した現実的な計画を心がけましょう。
補助率に応じた予算の立て方
補助率に応じて予算を適切に配分することは、事業計画の信頼性を高めるうえで欠かせません。補助金で賄える範囲と自己資金で負担する部分を明確にしておくと、事業全体の収支管理がしやすくなります。予算を立てる際は、補助率が最大限適用される前提だけでなく、万が一想定より低い補助率となった場合のシミュレーションも行っておくと安心です。
また、設備投資や人件費、外注費など補助対象となる経費と対象外の経費を分けて記載することで、審査の際にも評価されやすくなります。しっかりした予算管理ができていれば、採択後の実績報告や検査の際にも問題が生じにくくなるでしょう。補助率に合わせた予算設計が、長期的な経営の安定につながります。
まとめ
ものづくり補助金の補助率は、申請する事業規模や選択する枠、さらに特定条件の有無によって1/2から2/3の範囲で決まります。制度の詳細を把握し、無理のない範囲で計画を立てることで、採択後の負担を軽減しながら設備投資や新規開発に取り組めるでしょう。
申請前に正確な補助率を確認し、事業計画に反映させることが重要です。補助率の違いがもたらす影響や活用の仕方を理解し、採択につながる具体的な準備を進めることが成功への近道です。
株式会社イチドキリは、経営革新等支援機関として、中小企業や小規模事業者のものづくり補助金申請を全面的に支援しています。申請書類の作成や電子申請サポートはもちろん、採択後の継続的な伴走支援まで、経験豊富なスタッフが対応します。
書類作成に時間を割けない方や、補助率を最大限に活用したい方に最適なサービスです。無料相談にて現状診断も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
参考:ホームページ制作補助金を個人事業主が活用!最新情報と成功例36選|マーケティング情報局
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。