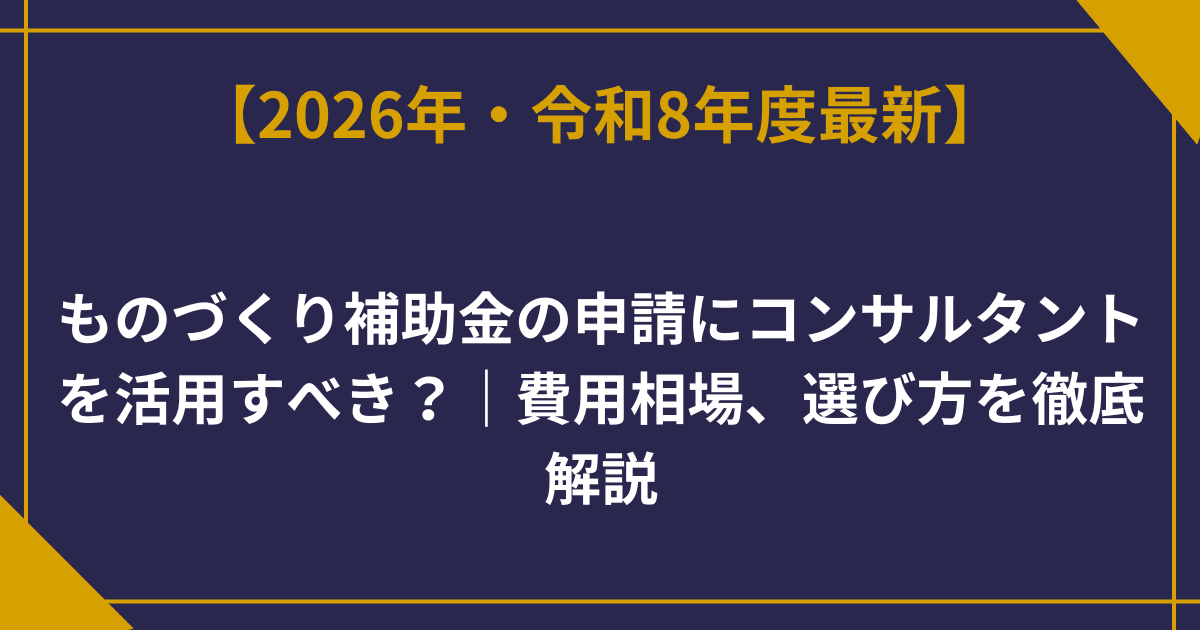- ものづくり補助金にコンサルは必要?
- ものづくり補助金コンサルを利用する3つのメリット
- ものづくり補助金コンサルを利用する際の注意点・デメリット
- ものづくり補助金コンサルの費用
- ものづくり補助金の申請から受給までの流れ
- 【業種別】採択事例紹介
- ものづくり補助金についてよくある質問
- イチドキリの特徴
- まとめ
ものづくり補助金にコンサルは必要?
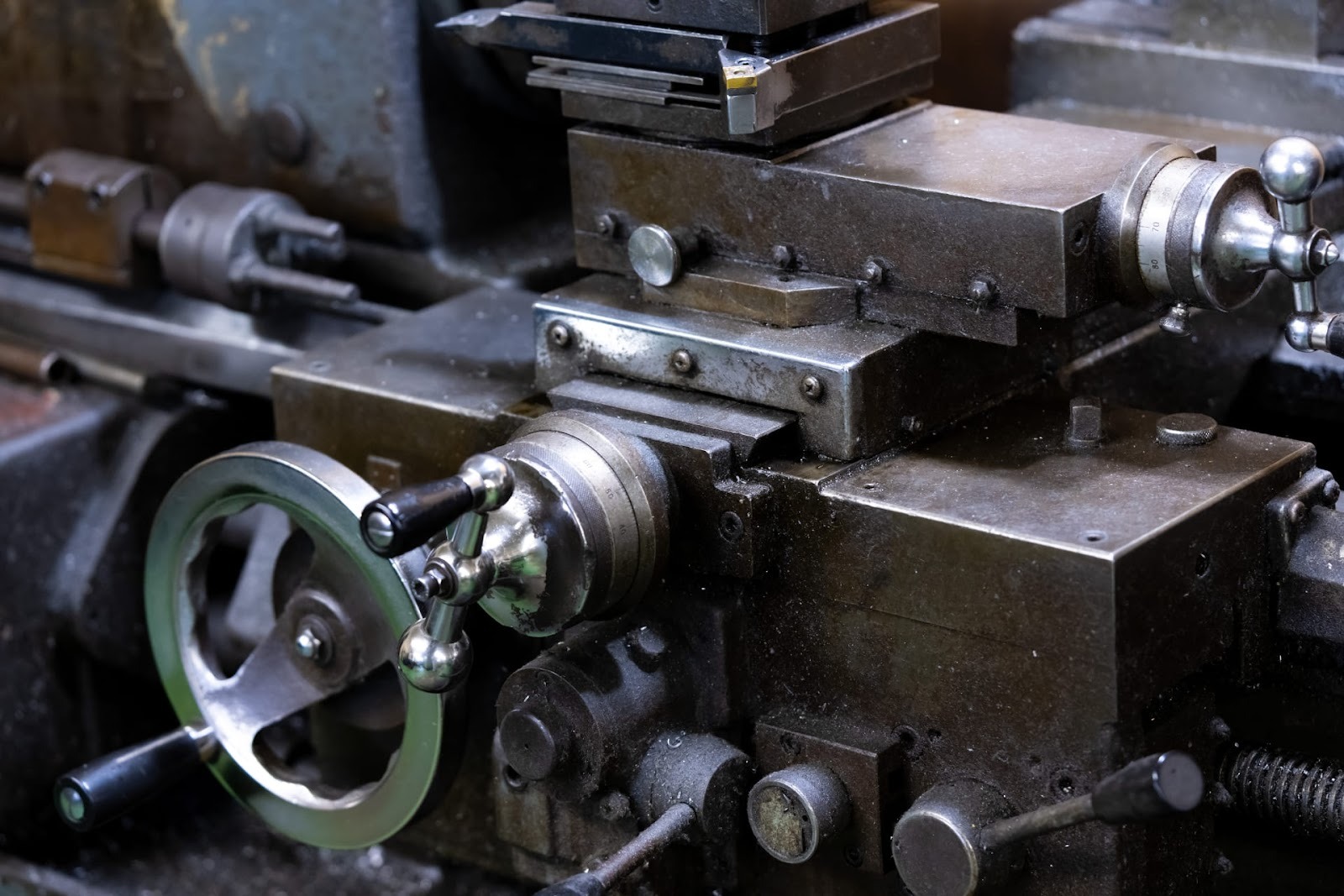
結論から言えば、申請にコンサルタントは必須ではありません。しかし、採択を勝ち取るためには、専門家であるコンサルの活用が事実上の最短ルートと言えます。
ものづくり補助金は、中小企業の革新的な挑戦を支援する制度ですが、その申請プロセスは非常に複雑です。第20次公募では採択率が約33.6%と、申請した3社のうち2社は不採択となる厳しい現実があります。質の高い事業計画書の作成には専門的な知識と多くの時間が必要となるため、多くの企業がプロの力を借りています。
ものづくり補助金コンサルを利用する3つのメリット

コンサルを利用するメリットは、単に申請作業が楽になるだけではありません。主なメリットは以下の3つです。
- 採択率が飛躍的に向上する
- 申請にかかる膨大な手間と時間を削減できる
- 補助金採択後の手続きもスムーズに進む
それぞれ具体的に解説していきます。
1. 採択率が飛躍的に向上する
最大のメリットは、やはり採択率の向上です。専門家は最新の審査傾向や加点項目を熟知しており、採択される事業計画書のポイントを的確に押さえています。
自社だけでは気づきにくい事業の強みを引き出し、審査員に響くストーリーを構築してくれます。「新しい機械を導入したい」という要望を、「この機械でこんな未来が実現できる」という評価されるビジョンへと昇華させるのです。実績豊富なコンサルの中には、採択率80%以上を誇るケースも少なくありません。
2. 申請にかかる膨大な手間と時間を削減できる
申請にかかる膨大な手間と時間を削減できる点も、経営者にとって大きな利点です。ものづくり補助金の申請には、事業計画書の作成だけで数十時間、慣れていないと100時間以上かかることもあります。
公募要領の読み込みから、数値計画の作成、必要書類の準備まで、やるべきことは山積みです。これらの煩雑な作業をプロに任せることで、経営者は本来注力すべき本業に集中できます。これは、目に見える費用以上の価値があると言えるでしょう。
3. 補助金採択後の手続きもスムーズに進む
意外と見落とされがちですが、採択後の手続きサポートも重要です。ものづくり補助金は採択されたら終わりではなく、その後の手続きを正確に行わなければ、実際の入金まで辿り着けません。
採択後の「交付申請」、事業期間中の「中間監査」、終了後の「実績報告」など、手続きは長期にわたります。書類に不備があれば交付が遅れたり、最悪の場合は受給できなくなるリスクも。一貫してサポートしてくれるコンサルがいれば、最後まで安心して事業を進められます。
ものづくり補助金コンサルを利用する際の注意点・デメリット

多くのメリットがある一方で、コンサル利用には注意すべき点も存在します。後悔しないために、以下の3つのポイントを理解しておきましょう。
- コンサルティング費用が発生する
- コンサルタントの質にばらつきがある
- 事業計画策定に主体的な関与が求められる
これらを事前に把握し、納得した上で依頼することが重要です。
1. コンサルティング費用が発生する
当然ながら、依頼には費用が発生します。着手金と成功報酬を合わせると、数十万円から数百万円のコストがかかることもあります。
しかし、これを単なるコストと見るか、投資と見るかが分かれ目です。例えば1,000万円の補助金が採択されれば、費用を差し引いても手元に残る資金は大きなプラスになります。自社で対応した場合の人件費や時間を考慮し、事業成長に必要な投資として費用対効果を見極めましょう。
2. コンサルタントの質にばらつきがある
残念ながら、コンサルタントの質には大きな差があるのが現状です。実績が乏しいにもかかわらず、高額な費用を請求する業者も存在するため、慎重な選定が不可欠です。
特に「採択率100%」といった根拠のない甘い言葉には注意してください。厳格な審査がある以上、確実な保証は誰にもできません。安易に1社に決めず、実績やサポート内容を比較検討し、信頼できるパートナーを見極める目を持つことが大切です。
3. 事業計画策定に主体的な関与が求められる
コンサルはあくまでサポート役であり、申請を「丸投げ」することはできません。採択される計画を作るには、事業者自身が主役として主体的に関与することが求められます。
事業の強みやビジョンを最も理解しているのは経営者自身です。コンサルはその想いを、審査員に伝わる形に翻訳するパートナーだと考えてください。この共同作業を通じて自社の事業を見つめ直す経験は、結果に関わらず、将来の経営にとって貴重な財産になるはずです。
ものづくり補助金コンサルの費用

コンサルティング費用は、主に「着手金」と「成功報酬」の2つで構成されています。一般的な相場を理解しておくことで、提示された見積もりが適正か判断できるようになります。
- 着手金の相場
- 成功報酬の相場
- 株式会社イチドキリの料金体系
それぞれ見ていきましょう。
1. 着手金の相場
着手金は、契約時に支払う初期費用です。一般的な相場は10万円~30万円程度ですが、中には無料の会社もあります。
この費用は、採択の結果に関わらず、事業計画策定などの作業対価として支払うものです。そのため、基本的には返金されないと考えておきましょう。着手金が無料の場合、そのぶん成功報酬が高めに設定されている傾向があるため、トータルの費用で比較検討することが重要です。
2. 成功報酬の相場
成功報酬は、補助金が採択された場合にのみ支払う費用です。補助金交付決定額の10%~15%程度が一般的な相場とされています。
例えば、1,000万円の補助金なら100万円~150万円程度です。注意点として、補助金が入金されるのは事業終了後のため、成功報酬は一時的に自己資金から支払う必要があります。報酬が20%を超えるような場合は割高な印象があるため、契約前にしっかり確認しましょう。
3. 株式会社イチドキリの料金体系
株式会社イチドキリでは、事業者様の状況に合わせた最適なプランをご提案しています。透明性の高い料金体系で、安心してご依頼いただける環境を整えています。
具体的な金額は事業内容や規模によって異なりますが、無理な提案は一切いたしません。「まずは対象になるか知りたい」 「見積もりが欲しい」といったご相談も大歓迎です。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ものづくり補助金コンサルの選び方

コンサル選びの成否が、結果を大きく左右すると言っても過言ではありません。最適なパートナーを見つけるために、以下の4つのポイントをチェックしましょう。
- 採択実績と専門性で選ぶ
- 認定経営革新等支援機関かどうかで選ぶ
- サポート範囲と料金体系の透明性で選ぶ
- 自社の業界への理解度と相性で選ぶ
これらを基準に、慎重に比較してください。
1. 採択実績と専門性で選ぶ
まずは具体的な採択実績を確認してください。単なる採択率だけでなく、どのような業種や規模での実績が豊富なのかを見ることが大切です。
公式サイトで具体的な事例を公開している会社は信頼性が高いと言えます。特に、自社と同じ業種や似た課題を持つ企業の支援実績があれば、的確なサポートが期待できるでしょう。制度は頻繁に変わるため、直近の公募回でも結果を出しているかどうかも重要な判断材料です。
2. 認定経営革新等支援機関かどうかで選ぶ
信頼できるかどうかの指標として、「認定経営革新等支援機関」であるかを確認しましょう。これは、中小企業支援の専門知識や実務経験が一定レベル以上あると国が認定した公的な支援機関のことです。
税理士や中小企業診断士などが認定を受けており、制度への深い理解に基づいた質の高い支援が期待できます。必須ではありませんが、迷った際の安心材料になります。もちろん、株式会社イチドキリもこの認定支援機関です。
3. サポート範囲と料金体系の透明性で選ぶ
契約前に、どこまでやってくれるのかを明確にしましょう。「申請書の作成だけ」なのか、「採択後の実績報告」まで含むのかで、負担は大きく変わります。
口頭審査の対策や、不採択時の再申請サポートの有無なども確認しておきたいポイントです。料金についても、着手金と成功報酬の内訳、支払いのタイミングなどを事前に詳しく説明し、契約書に明記してくれる透明性の高い会社を選ぶことがトラブル防止につながります。
4. 自社の業界への理解度と相性で選ぶ
最後に見落としがちなのが、担当者との相性です。事業計画の策定は、自社の未来を共有する共同作業であり、円滑なコミュニケーションが不可欠です。
無料相談などを活用して、話しやすさや人柄を確認しましょう。こちらの話を親身に聞いてくれない、専門用語ばかりで分かりにくいといった場合は注意が必要です。自社の業界特有の課題を理解し、二人三脚で歩んでいけるパートナーを見つけてください。
ものづくり補助金の申請から受給までの流れ

採択を勝ち取り、補助金を受け取るためには、計画的な準備が必要です。申請準備から受給後までの流れを5つのステップで解説します。
- STEP1: 事業計画の策定と申請準備
- STEP2: GビズIDプライムアカウントでの電子申請
- STEP3: 採択発表・交付申請
- STEP4: 事業実施と実績報告
- STEP5: 補助金の受給と事業化状況報告
全体のスケジュール感を掴んでおきましょう。
STEP1: 事業計画の策定と申請準備
すべては質の高い事業計画作りから始まります。補助金の採択を左右する最も重要なステップです。
自社の事業内容を踏まえ、革新性や実現可能性を具体的に示し、「この設備でどんな価値を生み出すか」というストーリーを描きます。並行して、申請に必須となる「GビズIDプライムアカウント」の取得も進めましょう。発行に2~3週間かかる場合があるため、早めの手続きが肝心です。
STEP2: GビズIDプライムアカウントでの電子申請
計画が固まったら、電子申請システム「Jグランツ」から申請を行います。ものづくり補助金は電子申請のみで、郵送などは受け付けていません。
ログインにはSTEP1で取得した「GビズIDプライムアカウント」を使用します。これは1つのIDで様々な行政サービスを利用できる共通認証システムです。締切直前はシステムが混み合うこともあるため、余裕を持って申請を済ませることを強くおすすめします。
STEP3: 採択発表・交付申請
締切から約2ヶ月後に結果が発表されます。採択されてもまだ「権利を得た」だけで、次の「交付申請」を経て初めて事業をスタートできます。
詳細な経費内訳などを提出し、正式な交付決定を受ける手続きです。この「交付決定通知」を受け取る前に契約や発注をしてしまうと、補助金の対象外となる「フライング」扱いになるため、絶対に注意してください。
STEP4: 事業実施と実績報告
交付決定を受けたら、いよいよ計画の実行です。設備の導入などを行い、事業完了後は期間内に「実績報告書」を提出します。
発注書や請求書、振込控えなど、計画通りに経費を使ったことを証明する書類を整理して提出します。これに基づき事務局の「確定検査」が行われ、最終的な補助金額が決定されます。中間監査が入ることもあるため、書類は常に整理しておきましょう。
STEP5: 補助金の受給と事業化状況報告
検査完了後、請求手続きを経てようやく補助金が振り込まれます。原則として後払いのため、設備投資資金は一時的に自社で立て替える必要がある点を覚えておきましょう。
また、補助金受給後も5年間は「事業化状況報告」の提出義務があります。事業がどれだけ成長したかを報告するもので、これを怠ると補助金の返還を求められる可能性もあるため、忘れずに対応してください。
【業種別】採択事例紹介
ここでは、業種別に3つの事例をご紹介します。
- 【製造業】最新機械導入による生産性向上
- 【サービス業】AI・DX導入による新サービス
- 【建設業】DX化による現場管理の効率化
貴社の事業に近い事例を参考にしてみてください。
【製造業】最新機械導入による生産性向上と新製品開発
金属加工業の企業様で、旧式機械による生産性の低さと技術継承が課題でした。最新の5軸マシニングセンタ導入の計画を策定し、見事採択されました。
複雑な部品加工が可能になり、生産性が30%向上。外注していた高精度部品の内製化にも成功し、新たな受注につながりました。単なる設備更新ではなく、技術継承問題の解決や地域経済への貢献といった視点を盛り込んだ点が評価されました。
【サービス業】AI・DX導入による新サービス提供
Web制作会社様では、顧客ニーズへの対応力が課題でした。AIを活用した顧客データ分析システムとMAツールの導入計画で採択を勝ち取りました。
行動履歴に基づいた最適な提案が可能になり、サービスの付加価値が向上。高単価な契約が増加しました。DXによって労働生産性を高め、いかに新たな顧客価値を創造するかを具体的に示した点が採択の鍵となりました。
【建設業】DX化による現場管理の効率化
建設会社様では、人手不足と紙ベースの非効率な情報共有に悩んでいました。ドローン測量システムと現場管理アプリを連携させる計画で採択に至りました。
数日かかっていた測量が半日で完了し、アプリでのリアルタイム情報共有によりコミュニケーションロスが激減。建設業界の深刻な「人手不足」という社会課題を、デジタル技術で解決する明確なビジョンが高く評価された事例です。
ものづくり補助金についてよくある質問
最後に、事業者様からよく寄せられる質問にお答えします。申請検討時の疑問解消にお役立てください。
ものづくり補助金の採択率はどのくらいですか?
公募回によりますが、近年はおおむね30%~50%前後で推移しています。
第20次公募では約33.6%で、3社に1社しか通らない狭き門でした。だからこそ、審査ポイントを知り尽くした専門家のサポートが有効なのです。万が一不採択でも、計画をブラッシュアップして再チャレンジすることは可能です。
補助金はいつ受け取れますか?
採択後すぐではなく、事業終了後の検査を経てからの支払いです。原則として「後払い(精算払い)」となります。
実績報告と確定検査が完了した後に請求し、振り込まれる流れです。そのため、設備投資に必要な資金は、一旦全額を自社で用意する必要があります。事前に金融機関からの融資などで資金繰りの計画を立てておくことが非常に重要です。
補助金の申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書の他に、法人の場合は直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書など)が必須です。
その他、従業員数確認のための労働者名簿や、賃上げ計画の証明書類なども必要に応じ提出します。個人事業主なら確定申告書が必要です。公募回によって変更されることもあるため、必ず最新の公募要領を確認しましょう。書類不備は審査で不利になるため注意が必要です。
補助金コンサルタントは違法ではないのですか?
コンサルティング自体は違法ではありません。ただし、行政書士でない者が報酬を得て公的な申請書類を作成することは法律で禁じられています。
信頼できるコンサル会社は、行政書士と提携したり、社内に行政書士を配置したりして法令遵守の体制を整えています。契約前に、誰が書類作成を担当するのか、コンプライアンス体制がどうなっているかを確認すると安心です。
申請代行に特定の資格は必要ですか?
コンサルティングに必須の資格はありません。しかし、中小企業診断士や行政書士などは専門知識があり、質の高いサポートが期待できます。
特に、国の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のコンサルタントは信頼の目安になります。資格の有無だけでなく、ものづくり補助金の支援実績が豊富かどうかも併せて確認することが、良いパートナー選びの鍵です。
着手金なしの完全成功報酬で依頼することは可能ですか?
完全成功報酬制の会社もあります。初期費用を抑えられますが、そのぶん成功報酬が割高に設定されているケースが一般的です。
着手金は計画策定の対価でもあるため、それがないとサポートの質が下がる懸念もゼロではありません。目先の安さだけでなく、トータルコストとサポート内容のバランスを見て判断しましょう。複数の会社の話を聞いてみることをおすすめします。
採択されなかった場合、費用はどうなりますか?
不採択なら成功報酬は発生しませんが、契約時の着手金は原則として返金されません。
着手金は、コンサルタントが行った作業やノウハウ提供への対価だからです。ただし、会社によっては次回申請を無料でサポートするなどの保証をつけているところもあります。契約前に、万が一の時の対応についても確認しておくと安心です。
相談する前に何を準備すればよいですか?
初回相談では詳細な資料は不要です。「どんな事業で、どんな設備を入れたいか」というアイデア段階でも構いません。
対話を通じて、そのアイデアをどう事業計画に落とし込むかを具体化するのがコンサルの役目です。もしあれば、会社パンフレットや直近2期分の決算書があると話がスムーズに進みます。イチドキリでは無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
イチドキリの特徴

株式会社イチドキリは、中小企業庁認定の経営革新等支援機関として、補助金申請支援を得意とする会社です。とくにITやAIを活用した新規事業に強みを持ち、経営者の想いに寄り添ったコンサルティングを行っています。
ここでは、イチドキリが選ばれる理由を2つの側面から紹介します。
着手金ゼロ・完全成功報酬
一般的な補助金コンサルは着手金として10~30万円程度を求めることが多いですが、株式会社イチドキリは着手金や顧問料を一切不要とし、完全成功報酬制を導入しています。これにより、初期コストを抑えて安心して申請に挑戦できる点が大きな魅力です。
採択されなければ費用は発生しないため、資金に不安を抱える中小企業でもリスクを最小限に抑えられます。さらに、採択後のフォローアップも費用に含まれ、実績報告や進捗管理など煩雑な事務作業も任せられます。
費用体系が明確で追加料金の心配も少なく、長期的な経営計画を立てやすいことも特徴です。イチドキリの仕組みは、補助金申請に不慣れな企業にとって強力な後押しになるでしょう。
エンジニア出身の補助金のプロが担当
イチドキリの強みは、補助金支援を担当するスタッフがエンジニア出身である点です。技術分野に精通しているため、AIやシステム開発を伴うプロジェクトでも説得力のある事業計画を作成できます。
補助金申請では革新性や市場効果を論理的に示す必要がありますが、専門知識が不足していると記載に曖昧さが残りやすくなります。エンジニアとしての実務経験を持つ担当者が関与することで、技術的な根拠を明確にし、審査で評価されやすい計画に仕上げられるのです。
過去には教育分野やシステム開発に関する採択事例もあり、幅広い業種に柔軟に対応できる点も安心材料です。事業成長を目指す企業にとって、専門的な知見を持つコンサルタントの存在は大きな支えとなるでしょう。
ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上や新規事業の推進に役立つ制度ですが、採択率は決して高くなく、制度要件も年々厳格化しています。採択を目指すためには、事業計画の完成度を高め、書類不備を防ぎながら審査員に伝わる内容を準備することが欠かせません。
そこで役立つのがコンサルタントの存在です。申請準備にかかる膨大な時間を削減し、計画を客観的にブラッシュアップすることで、採択可能性を大きく高められます。ただし、依頼には費用が発生し、悪質な業者を避けるための注意も必要です。
実績や採択率、認定支援機関の有無、担当者との相性を慎重に確認することで、信頼できる依頼先を見つけられるでしょう。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。