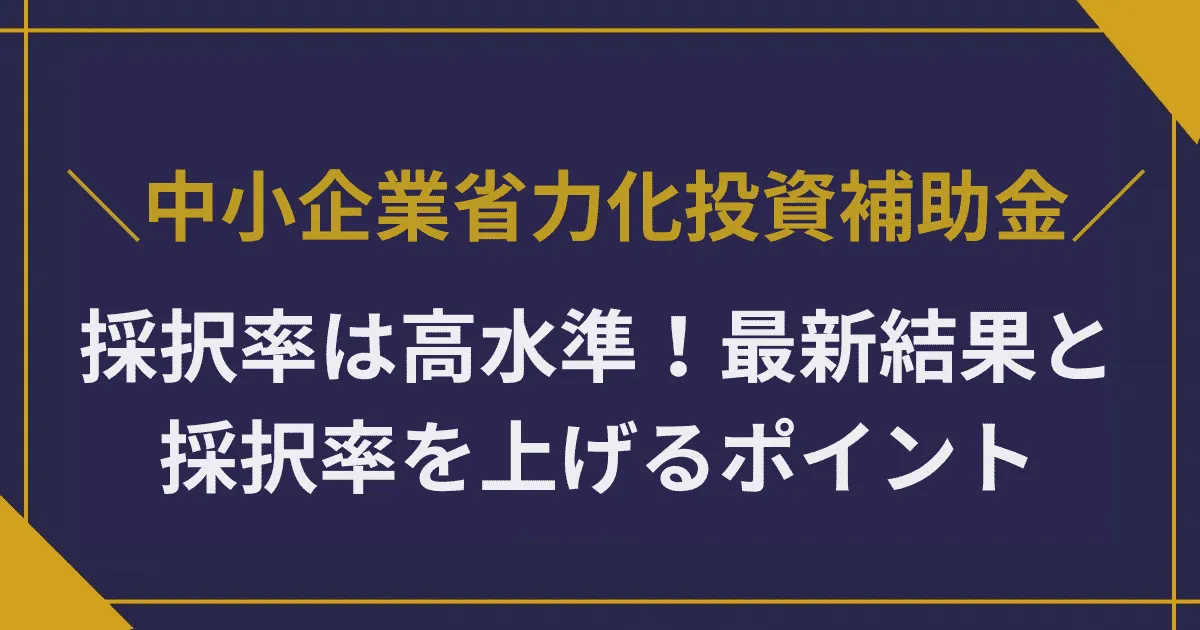中小企業が人手不足解消や生産性向上を目指す際に注目されているのが、中小企業省力化投資補助金です。初回公募の結果が公表され、高い採択率が確認されました。製造業だけでなく、多様な業種に活用の可能性が広がっています。
採択されやすい事業計画の特徴や、準備を進めるうえで押さえるべきポイントを理解することが、効率的な申請と事業成長への近道です。本記事では最新結果の分析から次回公募対策まで、重要な情報を整理して解説します。
- 中小企業省力化投資補助金の採択率の最新動向
- 採択率から読み解く補助金の特徴
- 採択率を上げるための申請ポイント
- 中小企業省力化投資補助金を申請する際の注意点
- 次回公募スケジュールと準備ステップ
- 採択率を最大化するための活用方法
- まとめ
中小企業省力化投資補助金の採択率の最新動向
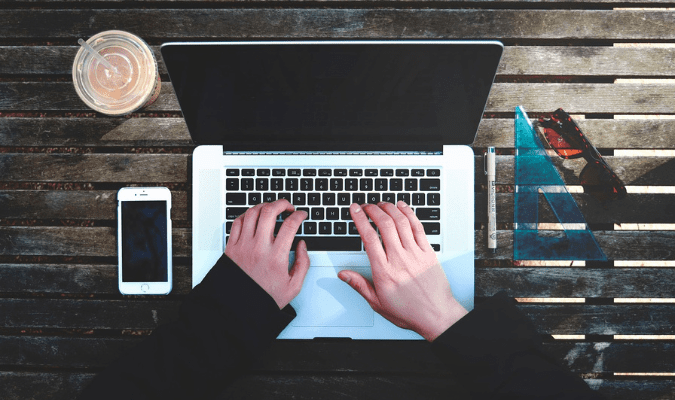
中小企業省力化投資補助金の最新採択率を把握すると、申請戦略の立て方が見えてきます。申請件数や採択件数の傾向、業種別・地域別の結果、申請金額の分布を理解することで、どの企業が採択されやすいかが明確になるでしょう。ここでは、最新動向を詳細に解説します。
第1回公募の採択率は68.5%と高水準
令和7年6月16日に公表された第1回公募の採択結果では、申請件数1,809件に対して採択件数は1,240件でした。採択率は68.5%に達し、近年の中小企業向け補助金の中でも高水準となっています。
参考として、ものづくり補助金のオーダーメイド型では直近の採択率が25~35%前後に留まっています。数値だけを見ても、省力化投資補助金が比較的チャレンジしやすい制度であることがうかがえるでしょう。
採択率の高さは、政府が人手不足対策や生産性向上に直結する取り組みを重視している姿勢の表れと考えられます。申請を検討する中小企業にとっては、戦略的に事業計画を練れば十分なチャンスがあるといえるでしょう。
製造業・建設業が中心だが非製造業も約3割採択
採択結果を業種別に見ると、製造業が全体の61.7%を占め、建設業が11.3%となりました。さらに、卸売業や小売業、宿泊業や飲食サービス業などの非製造業も合計で3割近く採択されています。これは、省力化効果が期待できる投資であれば業種を問わずチャンスがあるといえるでしょう。
製造業では溶接ロボットや自動化ラインの導入が目立ち、建設業ではCAD図面のQR管理や鉄筋加工装置の導入が採択されています。一方で、小売業ではオートカッターや自動ラベリング機器、宿泊業では予約一元管理システムの導入事例が確認されました。
多様な業種で採択が広がっている事実は、申請対象の幅が広いことを示しています。業務効率化や人手削減につながる取り組みであれば、業種にかかわらず挑戦する価値があります。
都道府県別では大阪・愛知・東京が上位
地域別の採択件数では、大阪府が124件で全体の10.0%を占め、続いて愛知県が108件(8.7%)、東京都が93件(7.5%)となりました。いずれも製造業の事業所数が多く、設備投資が活発な地域であることが特徴です。
ただし、採択は全国47都道府県に広がっており、地方圏でも多くの企業が認められています。これは、採択可否が地域よりも事業内容や省力化効果に大きく左右されることを示唆しているのです。自社の所在地が都市部でなくても、内容が明確で実現性の高い計画であれば十分に採択の可能性があります。
今後の公募でも、地域差よりも事業の完成度や設備の選定理由が重視される傾向が続くと考えられます。申請予定の企業は、地域要因を過度に気にせず、計画精度に注力しましょう。
申請額は1,500万〜3,000万円未満がボリュームゾーン
採択企業の補助金申請額を分析すると、1,500万円以上1,750万円未満が最も多く17.6%を占めています。さらに、全体の約84%が3,000万円未満に集中しており、比較的中規模の投資が主流であることが分かるでしょう。
一方で、上限に近い1億円規模の申請も存在しており、事業計画の内容によって幅広い投資額が認められています。中小企業にとっては、現実的な投資額であっても十分に採択される可能性がある点が魅力です。
予算に余裕がない企業は、複数工程の効率化や人手削減につながる中核的設備に絞って申請する戦略も有効でしょう。計画段階で投資額と補助対象経費のバランスを整理し、無理のない規模感で申請すると採択後の実行もスムーズになります。
採択率から読み解く補助金の特徴
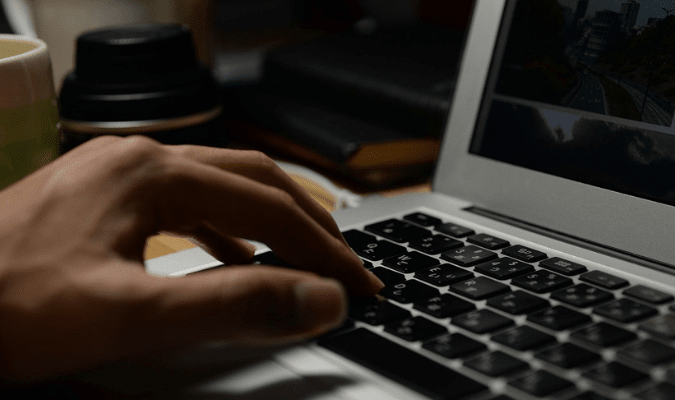
中小企業省力化投資補助金は、他の中小企業向け補助金に比べて採択率が高めです。その背景には制度の目的や審査傾向が関係しています。採択のしやすさの理由や、採択される事業計画の特徴を把握することで、今後の申請戦略に活かせるでしょう。ここでは採択率の裏側を詳しく分析します。
他補助金と比べても採択されやすい理由
中小企業省力化投資補助金の採択率は68.5%となり、他の代表的な補助金制度と比べても高い水準です。たとえば、事業再構築補助金は25%〜50%前後、ものづくり補助金のオーダーメイド型は25~35%にとどまっています。
採択率の高さには理由があります。第一に、国が人手不足対策と生産性向上を重点施策として位置づけていることが挙げられるでしょう。業務効率化や自動化に直結する投資は政策的にも優先度が高く、審査で評価されやすいのです。
第二に、申請件数に対して予算規模が大きく確保されている点も影響しています。十分な採択枠があるため、内容さえ整っていれば比較的採択されやすい傾向があります。補助金申請に不安を抱く企業も、計画精度を高めれば十分な可能性があるでしょう。
採択されやすい事業計画の傾向
採択されやすい計画には共通点があります。まず、省力化や効率化の効果が明確に示されている点が重要です。ただの設備購入ではなく、複数工程の自動化や人手削減に直結する計画が評価されます。
具体例としては、製造現場における溶接ロボット導入や、建設現場での図面管理の自動化システムが挙げられます。また、複数の汎用設備を組み合わせて工程全体の効率化を図る計画も高く評価されるでしょう。
さらに、数値での効果予測が添えられている計画は審査での説得力が増します。たとえば、作業時間削減率や人員削減効果を数値化すると、審査担当者に意図が伝わりやすくなります。自社の課題と解決策を結びつけるストーリーが整理されているかどうかも採択率に直結する要素です。
採択率の高さを支える政府の省力化推進方針
採択率の高さの背景には、政府が進める省力化推進の政策があります。中小企業における人手不足や高齢化は深刻であり、業務自動化による生産性向上が急務です。
したがって、ロボットやIoT機器の導入、業務プロセスの自動化に対する支援は重点的に実施されているのです。予算規模も大きく、関連事業全体で3,000億円規模での支援が計画されています。このような政策環境では、審査側も省力化効果の高い事業を積極的に後押しする姿勢が強まります。
企業にとっては、国の方針と一致した取り組みを計画することが有利にはたらくでしょう。業務のどこに自動化や効率化の余地があるかを洗い出し、補助金の目的に沿った申請を行うことで、採択率をさらに高めることが可能です。
採択率を上げるための申請ポイント
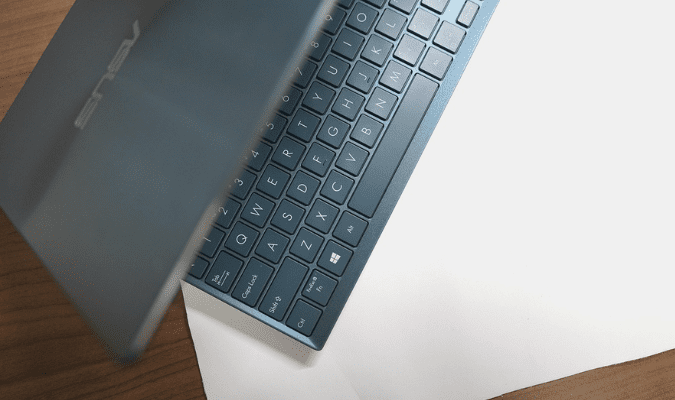
採択率を高めるには、単に補助対象となる設備を購入するだけでは不十分です。審査側が重視するのは、省力化効果や生産性向上の具体性、そして事業計画全体の完成度です。採択を狙う企業は、事前準備と計画作成の工夫が欠かせません。ここでは、実践的なポイントを整理して解説します。
省力化効果を数値で示す計画書を作る
採択率を引き上げる第一歩は、事業計画書で省力化効果を明確に伝えることです。ただ率化できると書くだけでは説得力が弱く、審査担当者に具体的なイメージが伝わりません。
作業時間削減率、必要人員の減少見込み、生産量の増加など、数値で示すことが効果的です。たとえば、溶接作業を自動化するロボットを導入した場合、作業時間が40%短縮し、1人分の作業が削減されるといった定量的な説明が望ましいです。
さらに、導入前後の工程フローやシミュレーション結果を添えると、計画の実現性が伝わりやすくなります。数値化された根拠を盛り込んだ計画書は、審査側に「投資効果が明確」と判断されやすくなり、採択の可能性を高められます。
複数工程の自動化・効率化を組み込む
単一作業の効率化だけでなく、複数工程にまたがる改善を計画に盛り込むことが有効です。審査では、事業全体としての省力化効果がどれだけ大きいかが重視されます。
たとえば、製造業であれば原材料投入から検品・出荷までを一連で自動化する計画が評価されやすくなります。建設業でも、設計データのデジタル管理と現場加工の自動化を組み合わせることで、全体最適につながると判断されるでしょう。
複数の汎用設備を組み合わせるだけでも、工程全体の効率化につながる場合は評価対象になります。重要なのは、個別の設備導入が点で終わらず、線として業務プロセスに連動していることです。全体像を意識した計画は、補助金の目的と一致し、採択率の向上に直結します。
審査基準に沿った事業計画のストーリーを整理する
採択される事業計画は、単なる設備投資計画ではありません。審査基準に沿ったストーリーが整理されていることが大切です。
最初に、現状の課題や人手不足の状況を明確にし、次に導入する設備やシステムでどのように改善するかを順序立てて説明します。その上で、投資後に期待される効果や売上・生産性の向上見込みを数値で示すと説得力が増します。
また、補助金の趣旨である生産性向上や雇用への波及効果とリンクさせることで、評価が高まりやすくなるでしょう。審査側は論理的に整理された計画を好みます。章立てや図表を活用して視覚的にわかりやすく整理すれば、読み手に伝わりやすくなり、採択率向上に直結する計画に仕上げられます。
補助金サポート専門家への相談で精度を高める
採択率を確実に高めたい場合、補助金申請に精通した専門家への相談が有効です。事業計画書の書き方や、審査で評価されるポイントは、経験者でなければ気づきにくい部分が多く存在します。
専門家に相談すると、計画の弱点を客観的に指摘してもらえたり、過去の採択事例に基づいた改善提案を受けられたりします。さらに、補助対象経費の整理や必要書類の準備もスムーズになり、申請作業全体の負担が軽減されるでしょう。
とくに初めて申請する企業にとっては、サポートを受けることで不備や誤りを防ぎやすくなります。結果として、計画の完成度が上がり、採択される確率が向上します。限られた時間で確実な成果を目指す場合は、専門機関やコンサルタントの力を借りることを検討しましょう。
中小企業省力化投資補助金を申請する際の注意点

省力化投資補助金の申請では、計画の工夫だけでなく、基本的な注意点を押さえることも採択率に直結します。審査で不利になる要因は、意外にも初歩的なミスや準備不足によるものが多くみられます。
申請段階でのリスクを把握し、必要な確認を行うことで、不採択の可能性を大幅に下げられるでしょう。ここでは、中小企業省力化投資補助金を申請する際の注意点について解説します。
カタログ未掲載設備の申請は補助対象外なる
省力化投資補助金のカタログ注文型の申請にあたっては、導入予定の設備が事務局公開の製品カタログに掲載されているかを必ず確認する必要があります。カタログに掲載されていない設備は、補助対象として認められません。
初めて申請する企業は、設備選定の段階で販売事業者やメーカーと連携し、補助対象の可否を明確にしておくことが重要です。
効果を定量化しない計画は審査で不利
補助金の目的は、省力化や効率化による生産性向上です。したがって、計画書に効果を定量的に示していない場合、審査で評価が低くなりがちです。
「効率化できる見込み」といった抽象的な表現だけでは、実際の効果が伝わらず説得力を欠きます。作業時間の削減率、必要人員の減少見込み、生産能力の向上幅など、数値を用いて明確に記載することが重要です。
たとえば、導入後に作業時間が30%短縮され、2名分の作業が削減されるといった形で数値化すると、審査担当者にイメージが伝わりやすくなります。定量的な説明は、計画の実現性や投資効果を裏付ける要素となり、採択率の向上に直結します。
書類不備や提出遅延は即失格の可能性
補助金申請では、書類不備や提出遅延が即時失格につながる可能性があります。法人登記簿謄本や納税証明書、決算書、見積書などの基本書類が不足すると、審査対象外とされるケースがあります。
提出期限を過ぎた申請は受理されないため、スケジュール管理も重要です。とくに、補助対象経費の証拠書類や製品仕様書は事前準備に時間を要する場合があります。早い段階で必要書類をリスト化し、担当者間で共有すると、漏れを防ぎやすくなります。
さらに、社内で複数人によるダブルチェック体制を構築すれば、誤記や記載漏れのリスクを減らせるでしょう。書類管理と提出スケジュールを徹底することが、採択への基本条件となります。
申請内容と社内体制に矛盾がないか確認する
申請計画の内容と社内体制に矛盾がある場合、審査で実現性を疑われる可能性があります。たとえば、導入予定の設備を運用する担当者が不在であったり、実際の業務フローと計画書がかみ合っていなかったりすると、計画の信頼性が低下しかねません。
審査では、現場の運用体制や導入後の管理方法まで確認されることがあります。社内の現場責任者や経営層と計画を共有し、内容に齟齬がないか事前に確認しておくことが重要です。
業務フロー図や人員配置表を添付すると、体制の整合性が伝わりやすくなります。社内での意思統一と整合性確認は、採択率を安定させるうえで不可欠な工程です。
次回公募スケジュールと準備ステップ
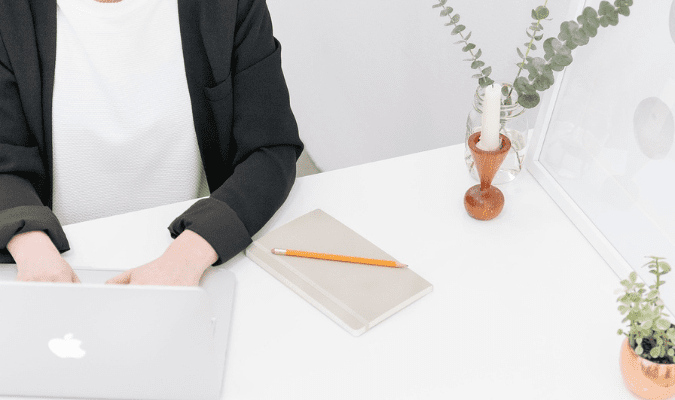
補助金申請の成功には、スケジュール管理と事前準備が欠かせません。公募の締切や必要書類を正しく把握することで、余裕を持った申請が可能になります。準備不足は不備や審査落ちにつながるため、早めの行動が採択率向上のポイントです。ここでは、次回公募の時期と準備の手順を整理します。
第3回公募は8月下旬締切、早めの準備が必須
省力化投資補助金の第3回公募は、8月下旬の締切が予定されています。スケジュールに余裕があるように見えても、計画書作成や社内調整には時間がかかります。とくに、補助対象となる設備の選定や、導入効果を示す資料の準備は早期着手が必要です。
直前に申請準備を始めると、内容が不十分になりやすく、審査で不利になる可能性があります。スケジュールを逆算して、1か月前には計画書の素案が完成している状態が理想です。
さらに、事務局の公表するスケジュールや公募要領の更新情報も定期的に確認しましょう。早めに動くことで、余裕を持った申請が可能となり、採択率向上にもつながります。
必要書類と社内確認体制を整える
採択を目指すうえで、申請書だけでなく付随する証明書類や社内体制の整備も欠かせません。法人登記簿謄本、納税証明書、決算書などの基本書類に加え、設備の見積書や図面、効果を示す資料なども必要となります。
書類の不備はそのまま審査の減点につながるため、早めにリスト化して準備することが重要です。また、社内での確認体制を整えることも大切です。経営層、現場責任者、経理担当が連携して計画を共有し、申請内容の整合性を確保しましょう。
複数人で確認する体制を作ると、誤記や漏れを防ぎやすくなります。書類と社内の準備を同時並行で進めることで、締切前の慌ただしさを避け、スムーズな申請が実現できます。
申請前にカタログ製品の適合可否をチェックする
一般型の申請では、導入を検討している設備が補助対象かどうかの確認が不可欠です。事務局が公開する製品カタログには、省力化効果が認められた設備が掲載されています。対象外の設備を申請しても、審査で認められない可能性が高くなります。
したがって、申請前に必ずカタログを確認し、導入予定設備の適合可否を把握しましょう。さらに、カタログ外の設備を導入する場合は、効果や必要性を証明する書類の準備が求められます。
早い段階で販売事業者やメーカーと連携し、証明書や仕様書を入手すると安心です。設備選定の段階で適合性を確認しておけば、申請後の修正や差し戻しを避けやすくなり、スケジュール通りの進行が可能になります。
採択率を最大化するための活用方法

補助金の採択だけでなく、その後の事業成長に結びつける活用が重要です。導入した設備やシステムを最大限に生かし、事業全体の生産性向上や売上拡大につなげることが、補助金活用の真価です。
さらに、計画段階での工夫や専門家の支援を取り入れることで、採択率を高めつつ、活用効果も最大化できます。ここでは、採択率を最大化するための活用方法について解説します。
社内の人手不足対策と生産性向上に直結させる
補助金で導入した設備やシステムは、単なる投資に留めず、社内の課題解決に直結させることが重要です。たとえば、製造業であればロボット導入による溶接工程の自動化、建設業であればCADデータのQR管理と連動した加工装置の導入などが挙げられます。
したがって、人手不足の解消だけでなく、作業時間短縮や品質向上が実現します。さらに、効果を数値で把握し、定期的に社内で共有すると改善サイクルが回りやすくなるでしょう。
ただの省力化にとどまらず、事業全体の生産性向上に結びつけることで、補助金活用の意義が明確になり、次回以降の申請時にも有利にはたらく可能性があります。補助金は投資の後押しであると同時に、経営課題解決の手段として戦略的に活用しましょう。
補助金で導入した設備を事業成長戦略に組み込む
導入設備を日常業務の一部として活用するだけでは、補助金の効果を十分に発揮できません。中長期の事業成長戦略に組み込むことで、投資効果を最大化できます。たとえば、業務の省力化で生まれた余力を、新規製品開発や新市場開拓に振り向ける戦略が考えられます。
販売データや生産データを一元管理する仕組みを導入すれば、次の経営判断にも役立つでしょう。また、投資効果を社外にアピールすることで、取引先や金融機関からの評価向上も期待できます。
補助金で整備した仕組みを単なる社内効率化にとどめず、売上増加や利益改善に結びつけることが、事業の持続的成長につながります。設備導入後は、活用計画と成果指標を明確にし、経営戦略の中核に位置づけましょう。
成功事例を参考に自社向けプランを設計する
採択率を高めるうえで、成功事例の分析は有効な手段です。過去に採択された企業の取り組みを調べると、審査で評価されやすいポイントや工夫が見えてきます。製造業であれば、複数の汎用設備を組み合わせて工程全体を効率化した事例、飲食業であれば自動フライヤーと注文管理システムを連携させた事例などが参考になります。
事例をそのまま模倣するのではなく、自社の課題や強みに合わせて計画を設計することが大切です。また、成功事例に基づく改善提案を計画に盛り込むことで、説得力が増し、審査での評価向上につながります。
事例の活用は、申請準備だけでなく、導入後の運用にも役立ちます。過去の成功パターンをヒントに、自社独自の省力化プランを完成させましょう。
まとめ
中小企業省力化投資補助金は、初回公募で採択率68.5%と高い結果が示されました。製造業を中心に幅広い業種で活用が進み、設備導入による人手不足解消や業務効率化が期待できます。
採択率を高めるには、数値で示す省力化効果や複数工程の効率化を盛り込んだ計画作成が重要です。専門機関のサポートを活用すれば、計画精度と採択可能性はさらに向上します。
株式会社イチドキリでは、経営革新等支援機関として着手金0円・完全成功報酬型で補助金申請をサポートしています。採択率を高め、事業成長につなげたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。