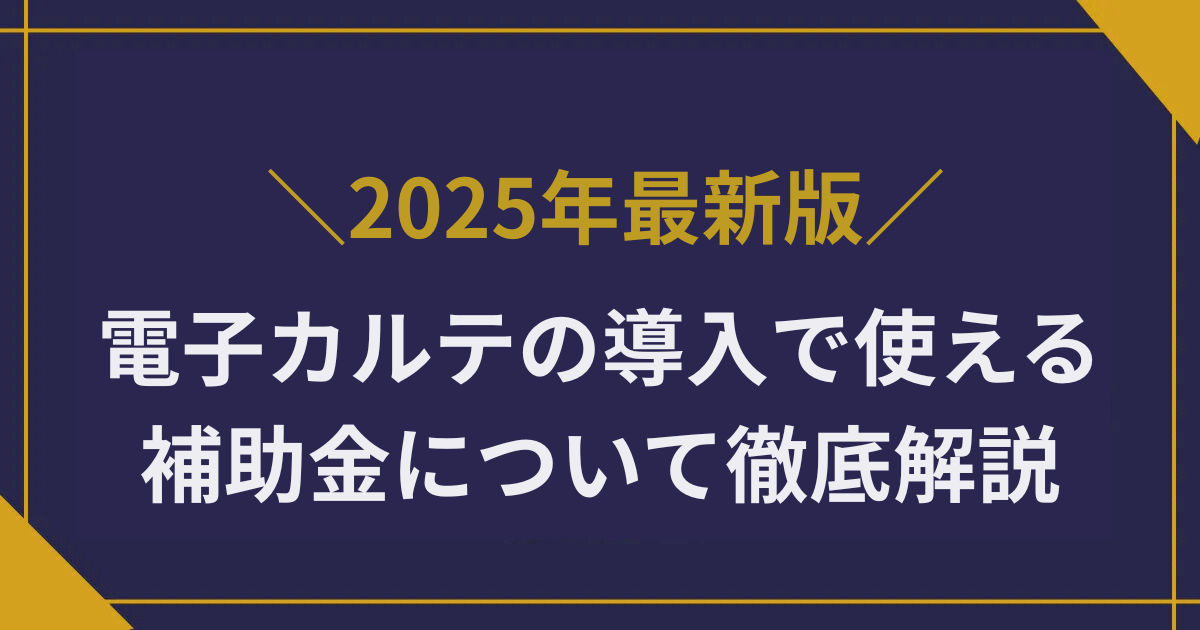電子カルテ導入における補助金申請は、多くの医療機関にとって大きな支援となりますが、申請内容によっては「対象外」と判断されるケースもあります。特に、契約や支払いのタイミング、導入するシステムの仕様、申請手順の誤りは不採択の原因になりやすい項目です。本記事では、補助金を無駄にしないために知っておくべき注意点を整理します。
電子カルテは義務化される?

現時点で全国一律の法的義務化は明記されていませんが、政府は遅くとも2030年までに概ね全ての医療機関で患者の医療情報を共有できる電子カルテの導入を目標としています。達成に向けて標準型電子カルテの本格運用内容を2025年度中に示し、2026年度中の完成を目指す方針が示されています。
加えて電子カルテ情報共有サービスの法制化や、地域医療支援病院等への体制整備の努力義務化が進み、オンプレ中心の高コスト構造からクラウドネイティブ移行を促す施策が打ち出されています。歯科は機能要件を検討し2026年度中に方針決定とされました。
医療DX令和ビジョン2030
医療DX令和ビジョン2030では全国医療情報プラットフォームの構築を掲げ、電子カルテ情報共有サービスの普及、標準型電子カルテの実装、PHR利活用を一体で推進します。2025年度中に標準型電子カルテの本格運用内容を提示し、2026年度以降に本格実施を目指す計画です。
病院の情報システムはサイバー対策と運用負担の観点からクラウド型へ刷新を促進し、関係システムと連携可能な標準APIやデータ引継ぎ互換性を要件化します。さらに医薬品コードの一元管理や臨床検査コードのJLAC11標準化を進め、相互運用性と医療安全の向上を図る構えといえます。
電子カルテの普及率
電子カルテの普及率は2023年医療施設調査で医科診療所約55%、一般病院約65%となりました。未導入の医科無床診療所に対し国はSaaS型で廉価な標準型電子カルテを開発し、2025年に本格運用内容を示したうえで2026年度中の完成を目標に普及を加速します。
共有サービスは2025年にモデル事業を開始し、導入済機関には次回更改時の改修、未導入機関には標準仕様準拠の導入を促進します。政府は2026年夏までに具体的な普及計画を取りまとめ、2030年の全国的な導入目標に向け制度整備と財政支援の検討を進める見通しです。
電子カルテに使える代表的な補助金の種類

電子カルテの導入や更改は設備費とシステム費が重くなりがちです。そこで活用候補となるのが省力化投資補助金(一般型)、事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)、IT導入補助金の3本柱です。対象要件や補助率、上限額が異なるため、医療機関の規模や導入形態に合わせて最適な制度を選ぶことが重要となります。
助成限度額は800万円、助成率は原則2/3、賃上げ計画を策定し実施した事業者は3/4、小規模事業者は4/5まで拡充されます。申請はJグランツの電子申請で、gBizIDプライム取得が必須です。単なる老朽更新や義務対応のみの投資は対象外となるため、効果や戦略性の記載が鍵となります。
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者の生産性向上を目的に、事前登録済みのITツール導入を支援します。申請は登録「IT導入支援事業者」とのパートナー申請が前提で、ソフトウェアやクラウド利用料、サポート費も補助対象に含まれます。
枠は通常枠のほか、インボイス枠(会計・受発注・決済・PC等)、電子取引類型、セキュリティ対策推進枠、複数社連携枠を用意します。電子カルテをクラウド型で導入し、院内業務の標準化やセキュリティ強化を図る計画とも相性が良好です。医療法人も要件内で対象となり、交付決定から実績報告までの期日管理と、登録ツール選定が実務の成否を左右します。
電子カルテ情報共有サービス関連の支援制度
電子カルテ情報共有サービス接続を前提に、標準仕様対応や健診部門システムとの連携整備費を補助する制度があります。対象は20床以上の病院で、申請は医療機関等向け総合ポータルから行ってください。申請期限は2031年9月30日、導入完了は2031年3月31日までが要件となります。
IT導入補助金申請の流れ
電子カルテの導入補助金を確実に受けるには、制度理解から交付決定までの手順を正確に進めることが重要です。各段階で必要書類や登録が異なり、特にGビズIDやSECURITY ACTIONの申請には時間がかかるため、早めの準備が求められます。以下で主要4ステップを順に解説します。
①補助事業について理解する
まず最初に行うのは、補助金制度の仕組みを正しく理解することです。公募要領や公式サイトを確認し、自院が対象となる補助金の要件、補助率、対象経費を把握します。電子カルテ導入における補助事業では、機器やソフトウェア、クラウド利用料、外注費などが含まれますが、事前契約や対象外経費を申請してしまうと不採択の原因となります。
また、補助対象は中小企業や医療法人等に限定されるため、法人区分と従業員規模を確認することも大切です。特に複数社連携枠を検討する場合は、申請要件や申請フローが通常枠と異なるため、公募要領内の「交付申請方法」を事前に確認しておくとスムーズです。
②GビズIDの取得
交付申請には、政府共通認証アカウント「GビズIDプライム」の取得が必須です。発行には書類確認を含め約2週間かかるため、余裕を持って申請を行いましょう。GビズIDは電子申請システム「Jグランツ」でも共通利用されており、補助金申請の基本アカウントとなります。
さらに、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の★一つ星または★★二つ星の自己宣言も必要です。この宣言により情報セキュリティ対策への取り組み姿勢を示し、交付要件の一部を満たすことになります。宣言済アカウントIDの発行には2〜3日を要するため、GビズIDと並行して準備を進めるのが効果的です。
③事業・ツールの選定
補助事業の申請準備が整ったら、自院の業務課題と導入目的を明確にし、最適なITツールと支援事業者を選定します。IT導入補助金の場合は、事務局が登録した「IT導入支援事業者」と連携して申請を行う必要があり、単独申請はできません。
ツール選定は公式サイトの「ITツール検索」から行い、電子カルテ、会計連携、オンライン資格確認など必要機能を比較します。特に電子カルテ導入では、標準規格準拠の仕様か、情報共有サービス対応かを確認することが重要です。
また、導入後の運用支援やクラウド利用料が補助対象に含まれるかもチェックし、導入計画を支援事業者と共に策定します。申請時には見積書や仕様書などの根拠資料を整備しておくと審査が円滑です。
④交付申請
最後に、選定したIT導入支援事業者と共同で交付申請を行います。支援事業者から「申請マイページ」への招待を受け、代表者情報や事業計画値、導入ツール内容などを入力します。必要書類を添付し、入力内容を確認後、電子宣誓を行って提出します。交付申請後は事務局による審査を経て、採択結果が通知されます。
交付決定を受けた時点で正式に補助事業者となり、導入事業を開始できます。申請締切は各回ごとに定められており、直前はアクセス集中で提出が遅れることもあるため、余裕を持った申請が推奨されます。交付後は実績報告書の提出や検収完了報告が必要となるため、導入スケジュールを事業計画書と照らし合わせて進行管理することが大切です。
補助金の対象外になりやすいケース

電子カルテ導入の補助金は要件が細かく定められており、形式的なミスや対象外経費の申請で不採択となる事例も少なくありません。補助金を確実に活用するには、申請前に「対象外」となりやすいパターンを把握し、回避策を講じることが重要です。以下の3項目は特に注意が必要なポイントです。
導入済み更新や事前契約・支払い済みの扱い
補助金は「これから実施する投資」に対して支援されるため、既に導入済みの電子カルテ更新や支払い完了分は補助対象外です。契約日や支払日のタイミングは審査で厳密に確認され、交付決定前に発注・契約・支払いが行われている場合は全額自己負担になります。
また、見積書や契約書の日付が交付決定日より前の場合も対象外として扱われるため、事前準備段階では見積取得や比較検討に留めておくことが安全です。補助金事務局では「交付決定前の着手禁止」を原則としており、リース契約・サブスク契約も同様の扱いを受けるため注意が必要です。導入スケジュールは必ず交付決定日を基準に計画を立てましょう。
カスタム開発中心や汎用ツールの適合性不足
補助金制度では、導入するシステムが「標準仕様」や「登録済みITツール」に該当しているかが重視されます。特注開発や独自仕様の電子カルテは、補助金の目的である「標準化・汎用化・生産性向上」に合致しないと判断されるケースが多く見られます。
特にカスタマイズによる改修費用や既存システムとの連携開発費は、上限額を超えた部分が自己負担となりやすく、審査でも「費用対効果が不明確」とされることがあります。
これを防ぐためには、登録済みのIT導入支援事業者が提供する公認ツールを選び、仕様書や導入目的に「業務効率化」「標準規格準拠」「共有サービス対応」などを明記することが有効です。特注開発を検討する場合は、補助対象外となる範囲を明確に分けて見積もりを作成しましょう。
支援事業者非経由や要件未達による失格
補助金申請は、原則として「登録されたIT導入支援事業者」を経由して行う必要があります。支援事業者を通さずに独自に申請した場合や、登録外のベンダーから導入した場合は不受理となります。また、GビズIDプライムの未取得やSECURITY ACTION未宣言などの形式要件を満たしていない場合も失格の対象です。
さらに、賃上げ計画を表明していない事業者や、事業計画書に定量的な生産性向上目標が示されていない場合も減点・不採択のリスクが高まります。申請直前になって要件不足に気づくケースも多いため、支援事業者と早期に連携し、必要書類や制度条件を一つずつ確認することが重要です。交付決定後の変更手続きにも制約があるため、初期段階から正確な要件管理を徹底することで採択率を高められます。
自社独自の電子カルテを開発する際に使える補助金
医療機関や介護施設の業務特性に合わせた独自の電子カルテを開発する場合も、補助金を活用できます。既存システムでは対応しにくい診療内容や業務連携に最適化した機能開発を支援する制度として、中小企業省力化投資補助金や経営基盤強化事業(一般コース)が利用可能です。
中小企業省力化投資補助金(一般型)
人手不足解消と生産性向上に資する設備導入・システム構築を幅広く支援します。機械装置費やシステム構築費は必須で、クラウドサービス利用料や外注費、知的財産権関連経費も計上可能です。
上限は従業員規模に応じて最大1億円、補助率は中小企業で1500万円まで1/2(要件充足で2/3)、超過分1/3、小規模事業者等は1500万円まで2/3、超過分1/3となります。ハードとソフトを一体で計画できるため、電子カルテ本体と周辺連携の同時導入に向きます。公募回制で採択審査は省力化指数や投資効率などを重視します。

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)
ポストコロナ等の環境変化に対応し、既存事業の深化や発展につながる投資を支援します。助成対象はシステム等導入費や設備導入費、規格認証費、委託費、専門家指導費など幅広く、電子カルテ導入による品質向上や生産性向上の取組として位置付けやすい点が特長です。

まとめ
電子カルテ導入時の補助金活用は、コスト負担を軽減しDX化を推進する重要な手段です。しかし、交付決定前の契約・支払い、標準規格に準拠しないカスタマイズ開発、登録外事業者による申請などは不採択の代表例です。制度の目的は「業務効率化」「標準化」「情報共有の促進」にあるため、要件を満たす形で正しく申請を進めることが成功の鍵となります。
特にGビズIDやSECURITY ACTIONの登録、支援事業者との連携などの準備を怠らず、計画的に進めることで採択率を高められます。導入効果を最大化するためにも、最新の公募要領や申請マニュアルを随時確認し、制度の変更点を把握しておくことが重要です。
株式会社イチドキリは中小企業庁認定の経営革新等支援機関。エンジニア出身の補助金のプロが着手金0円・完全成功報酬で制度選定から申請書類・実績報告まで伴走します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。