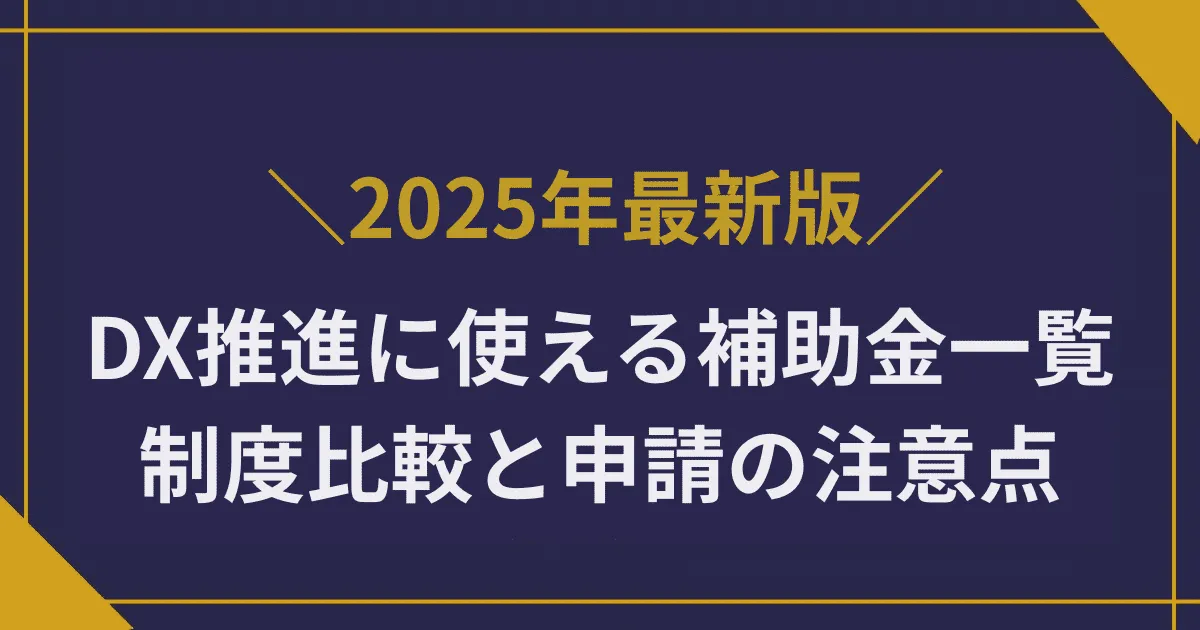企業がデジタル化を進めるうえで、資金面の負担は大きな障害になります。システム導入や人材育成には多額の費用がかかり、経営者にとっては慎重な判断が求められます。補助金を活用すれば、返済不要の資金で投資リスクを軽減でき、DX推進を加速させることが可能です。
本記事では、DXに使える主要な補助金の特徴や補助率・上限額、申請から受給までの流れを解説します。さらに、活用のメリットと注意点を整理し、成功に結び付けるポイントも紹介します。補助金制度を正しく理解し、自社の成長に役立てていきましょう。
- DX推進に使える補助金の基本を理解する
- DX推進をサポートする補助金の種類と特徴
- DXを進める補助金の補助率・上限額を比較
- DX推進における補助金の申請から受給までの流れ
- DX推進に補助金を活用するメリット
- DX推進に補助金を活用する際の注意点
- 補助金を活用してDXを成功させるポイント
- まとめ
DX推進に使える補助金の基本を理解する

デジタル技術を用いた業務改革を進める際、多くの企業が課題とするのが投資資金の確保です。そこで活用できるのが補助金制度です。補助金は返済不要の資金を得られる仕組みであり、企業にとって新しい取り組みを進める際の大きな支えになります。
ここでは補助金の基本的な役割や対象となる費用、国が導入を進める背景を理解していきましょう。
DX推進における補助金の役割
デジタル化を進めるためにはシステム導入費やクラウド利用料、設備投資、人材育成といった幅広い経費が必要になります。資金面で不安を抱える中小企業にとって補助金は大変役立つ存在です。
補助金を利用すれば新しい技術導入や組織改革に伴うコストを軽減でき、実行に踏み切りやすくなります。また、採択を受けた事業計画は行政からの認定を得た形になり、取引先や金融機関からの信用も高まります。
資金支援だけでなく社会的な信頼性向上にも役立つ点が特徴です。こうした仕組みは企業の挑戦を後押しする力となり、継続的な成長を実現するための土台になります。補助金は単なる資金援助にとどまらず、DXを戦略的に進めるうえで不可欠な仕組みとして機能します。
DXに必要な投資と主なコスト項目
デジタル変革に取り組む際には、多様なコストが発生します。まず欠かせないのが基幹システムやクラウドサービス、ハードウェアなどの技術インフラです。さらに、外部専門家やコンサルタントに支払う報酬、データセキュリティの強化費用も重要な支出となります。
加えて、社員に新しいスキルを習得させるための研修や教育費も大きな負担になります。新規サービスを市場に浸透させるには広告宣伝費も避けられません。さらに、DXプロジェクトを担う専任チームの立ち上げに伴う人件費や組織体制の再編費用も必要になります。
費用は個別に見ると小さくても、全体を合算すると相当な額になります。補助金はこれらの負担を軽減し、企業が戦略的に投資を進めやすくするための重要な施策です。
国が補助金制度でDXを支援する背景
日本では先進国に比べてデジタル化が遅れているといわれています。古いシステムを使い続ける組織文化やIT人材不足などが原因で、生産性向上や新しいサービス創出に課題を抱える企業が多く存在するのです。
こうした状況を改善するため、政府は補助金制度を整備し、企業のDX投資を積極的に支援しています。制度の導入により、事業者はリスクを抑えながら新しい取り組みに挑戦できるようになりました。
さらに、補助金は地域経済の活性化や雇用創出にもつながるため、国全体の競争力強化にもつながります。補助金政策は、企業単体の利益だけでなく経済成長全体を支える戦略的な取り組みとして位置づけられています。
DX推進をサポートする補助金の種類と特徴
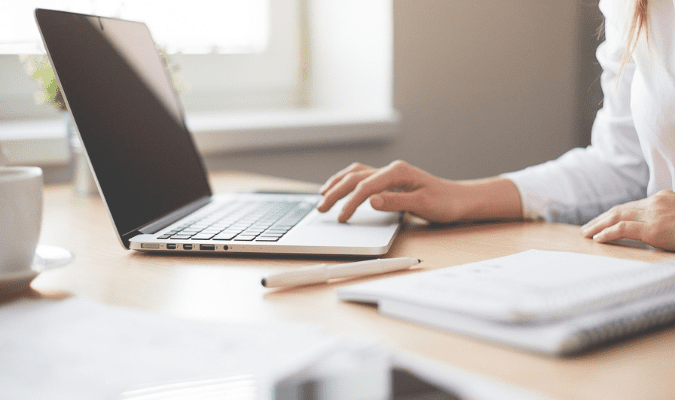
補助金と一口に言っても対象や目的は多岐にわたります。業務効率化、新規事業展開、人手不足解消、小規模事業者支援など、それぞれの課題に応じて制度が設計されています。制度の違いを理解することは、自社に適した申請を行ううえで非常に重要です。
ここでは代表的な五つの補助金を取り上げ、どのような取り組みに利用できるかを解説していきます。
IT導入補助金の内容と活用シーン
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者のデジタル化を支援する代表的な制度です。対象となるのは、ソフトウェアやクラウドサービスの導入に加え、パソコンやタブレットといったハードウェアの購入費まで幅広く含まれます。
さらに、導入支援事業者と提携することが申請の必須条件となり、セキュリティ宣言の実施も求められます。補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3が基本で、上限額は最大450万円です。
特別枠を利用すれば条件に応じて3,000万円まで拡大される可能性もあります。小規模からデジタル投資を始めたい企業に適した選択肢であり、比較的導入ハードルが低い点が強みになります。
事業再構築補助金で新分野展開を後押し
事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換を目指す企業の挑戦を支援する制度です。既存事業の延長ではなく、抜本的な変革を伴う取り組みに焦点を当てているのが特徴です。
対象経費は建物費やシステム構築費、広告費、研修費など幅広く、投資規模に応じて数千万円から最大5億円規模まで支援される枠があります。補助率は原則として1/2から2/3で、条件を満たす場合には3/4が適用されるケースも存在します。
採択の難易度は高いものの、採択されれば大規模な資金を確保できる強力な制度といえるでしょう。大きな変革を計画している企業にとって、有効な成長加速の手段となります。
ものづくり補助金で生産性向上を支援
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的な製品やサービスの開発に取り組む際に活用できる制度です。対象経費は機械装置やシステム構築費に加え、クラウドサービス利用費、知財関連費用、外注費など多岐にわたります。
補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3が基本で、上限額は通常750万円から2,500万円です。さらに、グローバル展開を視野に入れた枠では3,000万円までの支援を受けられる場合があります。
新技術導入や設備更新を通じて生産性を高めたい企業に最適であり、競争力強化に直結する支援を得られます。中長期的な成長基盤づくりを目指す経営者にとって重要な選択肢になるでしょう。
省力化投資補助金で人手不足を解決
省力化投資補助金は、人手不足の解消を目的として設計された制度で、AIやロボットを活用した省人化設備の導入を支援します。カタログ掲載設備を導入するカタログ型と、自由度の高い一般型が用意され、用途や規模に応じて選べる仕組みです。
上限額は200万円から最大1億円までと幅広く、補助率は1,500万円までが2/3、それを超える部分は1/3が基本です。生産性向上や人件費削減につながる取り組みを後押しし、労働力不足を抱える企業に実効性のある制度となります。
業務効率の改善だけでなく、長期的な利益構造の強化にもつながる可能性があります。将来を見据えた投資を計画する際に有効な支援策になるでしょう。
小規模事業者持続化補助金の活用方法
小規模事業者持続化補助金は、少額投資で経営改善や販路拡大を目指す事業者に適しています。対象経費は広告費やウェブ制作費、ECサイト構築費、機械設備の購入費など、現場に直結する支出が多い点が特徴です。
上限額は通常枠で50万円ですが、後継者支援枠や賃金引上げ枠では200万円が設定され、インボイス対応ではさらに50万円が上乗せされます。補助率は原則2/3で、赤字事業者には3/4が適用される場合もあります。
小規模ながらも経営改善の可能性を広げられる実用的な制度であり、販路拡大を重視する企業にとって有効です。大規模な投資が難しい中小企業にとって、成長を支える現実的な手段になるでしょう。
DXを進める補助金の補助率・上限額を比較

補助金を効果的に使うためには、対象となる経費や申請条件だけでなく、補助率と上限額の両方を正確に把握することが欠かせません。支援規模が投資計画に合致しているかどうかを判断できれば、無駄のない申請が可能です。
さらに、対象経費の範囲を比較することで、実際に自社が取り組みたい施策が適用範囲に含まれるかを確認できます。主要な制度を一覧表にまとめたうえで、それぞれの特徴を整理していきます。
主要補助金の条件を一覧で確認
下表では、代表的な五つの補助金について補助率、上限額、対象経費を整理しました。投資規模や活用目的に応じて選びやすくなるはずです。
| 補助金名 | 補助率 | 上限額 | 主な対象経費 |
|---|---|---|---|
| IT導入補助金 | 中小企業 1/2、小規模 2/3(枠により最大2/3) | 最大450万円(特別枠で3,000万円) | ソフトウェア、クラウド利用料、研修、ハードウェア |
| 事業再構築補助金 | 1/2~2/3(類型により最大3/4) | 3,000万円~1億円超(最大5億円枠あり) | 建物費、システム構築費、広告宣伝費、研修費 |
| ものづくり補助金 | 中小企業 1/2、小規模 2/3 | 750万円~2,500万円(特例で3,000万円超) | 機械装置費、クラウド利用料、外注費、知財関連 |
| 省力化投資補助金 | ~1,500万円:2/3、超過分:1/3 | 750万円~8,000万円(賃上げ要件で1億円) | AI・IoT設備、ロボット導入費、技術導入費、専門家経費 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 基本2/3(赤字事業者は3/4) | 50万円~200万円 | ウェブ制作、広告費、ECサイト構築、機械設備 |
一覧を見比べると、事業再構築補助金や省力化投資補助金は大規模投資を支援する性格が強く、反対に持続化補助金は小口投資向けであることが一目で分かります。制度ごとの特性を把握することで、資金計画と申請内容をより精緻に組み立てられるでしょう。
上限額と補助率から見える適用範囲
比較表に示したとおり、上限額は制度ごとに数十万円から数億円まで幅があります。大規模な投資を伴う事業再構築補助金や省力化投資補助金は、経営戦略の転換や大規模なシステム導入に適しています。
一方で、販路拡大や小規模なシステム投資を目指す場合には持続化補助金が効果的です。補助率も制度により差があり、採択された場合にどれほど負担を軽減できるかが異なります。
自社が想定する投資規模や目的と合致しない制度を選ぶと、採択の可能性も下がります。制度を理解したうえで、どの補助金が最も効果的に資金をカバーできるかを検討する姿勢が欠かせません。
対象経費を精査して最適な制度を見極める
補助金を利用するにあたって、対象経費の範囲を見落とすと不採択のリスクが高まります。IT導入補助金はソフトウェアやクラウド利用料など小回りの利く支出に向いています。事業再構築補助金は広告宣伝費や建物費まで広く認められ、事業転換を包括的に支援する内容です。
ものづくり補助金は設備投資や研究開発寄りの経費を補助し、省力化投資補助金はAIやロボット導入など省人化に直結する費用が中心です。小規模事業者持続化補助金は販路拡大に関連する経費が主対象となります。
投資目的に合致する経費が補助対象に含まれているかを確かめることは必須といえるでしょう。目的に適合した制度を選び、計画的に申請を進めれば、採択の可能性は大きく高まります。
DX推進における補助金の申請から受給までの流れ

補助金を申請する際は、制度の概要を理解するだけでなく、手続きの流れを把握することが不可欠です。準備から受給までの一連のプロセスを把握しておくことで、申請の精度を高められます。
さらに、流れを理解しておけばスケジュールの見通しを立てやすくなり、資金繰りに関する不安も和らげられます。ここでは、申請前の準備から支給決定までを段階的に見ていきましょう。
申請前に準備しておくこと
補助金申請を円滑に進めるためには、事前の準備が欠かせません。まず、自社のDX推進計画を明確化し、経営課題と解決策を整理して計画書の骨子を固める必要があります。
次に、GビズIDプライムの取得やセキュリティ対策に関する宣言登録など、申請の前提となる要件を早めに整えることが求められます。さらに、導入予定のITツールや協力事業者を選定し、対象経費に該当するかを確認しておくことも重要です。
準備を怠ると不備の多い申請となり、審査通過の可能性を下げてしまいます。反対に、十分な準備を整えればスムーズな申請が可能となり、交付決定を得やすくなります。計画性を持った事前対応が結果を左右する大きな要素といえるでしょう。
申請から交付決定までのステップ
準備を終えたら、次は申請作業に移ります。専用のオンラインシステムにアクセスし、事業計画書や見積書、必要資料を添付して提出する流れです。
審査では革新性や実現可能性、経営改善への効果などが評価されます。提出書類に不備があれば受理されないため、正確で説得力のある記載が必要です。審査を通過すれば採択通知が届き、正式な交付決定が下されます。
交付決定の前に発注や契約を行った経費は対象外となるため、スケジュール管理には細心の注意を払う必要があります。採択を受けるためには、事業の独自性や社会的意義を明確に示すことが大切です。綿密な計画と丁寧な準備が交付決定を勝ち取るための条件となります。
DXプロジェクトの実施と報告義務
交付決定を受けた段階で初めて事業を開始できます。実施時には、計画に沿ってシステム導入や設備投資を進めると同時に、経費の記録や領収書の管理を徹底することが必要です。補助金事業では中間検査や進捗報告が課される場合があり、その際に資料が不十分だと支給額が減額される恐れがあります。
さらに、進行中に計画変更が生じた場合には事前の承認が必須であり、独断での変更は認められません。報告書や実績資料は採択後の支給判断に直結するため、正確な記録が不可欠です。透明性の高い運用を意識すれば、支給プロセスが円滑に進みます。計画的な事業遂行と適切な報告対応が、最終的な補助金受給に欠かせない要素となります。
補助金の支給確定と受領
事業が完了したら、実績報告書を作成して提出します。報告書には支出明細や成果物を詳細に記載し、確定検査を受ける必要があります。検査で承認されれば補助金額が確定し、指定口座に入金される仕組みです。
ただし補助金は後払い方式であり、企業が事前に自己資金や借入金で立て替える必要があります。したがって、銀行融資や内部資金を活用して資金繰りを確保しておくことが求められます。入金までには数か月を要するケースも多く、長期的な資金計画が不可欠です。
さらに、受領後も領収書や契約書の保管義務が課され、一定期間は調査対象となる可能性があります。ルールを守らなければ返還を求められるリスクもあるため、最後まで責任を持った対応が必要です。
DX推進に補助金を活用するメリット
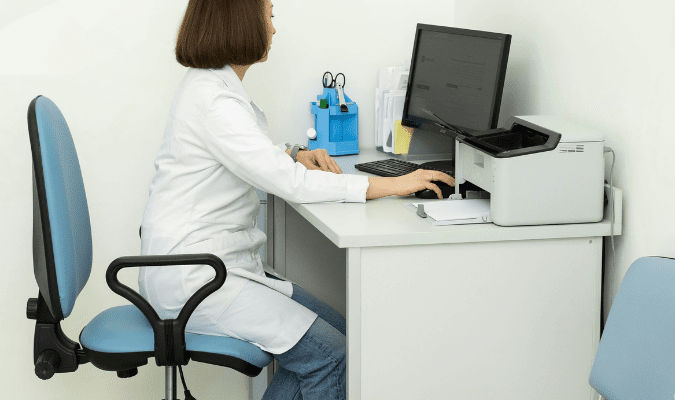
補助金は単なる資金援助にとどまらず、企業の成長戦略に幅広い効果をもたらします。資金調達を容易にするだけでなく、信頼性の向上や大規模な投資実現にも役立ちます。
さらに、補助対象の広さが柔軟性を生み、経営の選択肢を広げる点も見逃せません。ここでは、補助金を活用することで得られる代表的なメリットを詳しく解説していきます。
返済不要の資金で投資負担を軽減できる
補助金の最大の特長は返済義務がない点です。金融機関から融資を受ける場合とは異なり、利息や返済スケジュールに縛られることがなく、資金繰りの圧迫を防ぐことができます。
ITシステムや設備投資にかかる費用を補助金でまかなえば、余剰資金を研究開発や人材育成など成長領域に投じられます。中小企業は内部留保が少なく資金調達の選択肢が限られるため、返済不要の仕組みは有効です。
初期投資のリスクを抑える効果もあり、経営者が新しい挑戦に踏み出しやすくなるでしょう。資金の自由度が増すことで、長期的な経営基盤を築く一助にもなります。補助金は安心感をもたらす資金源として、積極的な活用が推奨されます。
数百万円規模の大規模投資を後押しできる
補助金は、多額の投資を実現するための有力な手段です。システム刷新や設備導入は高額な費用を伴い、中小企業には大きな負担になります。補助金を利用すれば、数百万円から場合によっては数千万円規模の支援を受けられる可能性があります。
たとえば、生産ラインの新設や先端技術を活用したサービス開発は、補助金を通じて実現可能性が高まるでしょう。こうした投資は効率化にとどまらず、売上拡大や競争力向上にもつながります。
自社の資金だけでは難しい取り組みを補助金で実現できれば、短期間で飛躍的な成長を狙える点が魅力です。資金調達の課題を乗り越え、長期的な成長戦略を支える制度として補助金の活用価値は大きいといえます。
幅広い経費に活用できる柔軟性
補助金の対象経費は幅広く、制度ごとに多様な用途に対応している点も特徴です。IT導入補助金ならソフトウェアやクラウド利用料、ものづくり補助金なら設備や知財関連費用、省力化投資補助金ならAIやロボット導入などが含まれます。
広告宣伝費や研修費も認められるケースがあり、経営戦略全体を後押しする効果を持ちます。経費の自由度が高ければ、自社が優先したい分野に応じて柔軟に資金を振り向けられます。資金不足を理由に計画を断念するリスクを軽減できる点は大きな魅力です。
制度を上手に組み合わせれば部分的なニーズにも対応可能です。柔軟性の高さは業種や規模を問わず多くの企業にとって利用価値があり、実践的な支援策となります。
採択によって事業計画の信頼性が高まる
補助金の採択は、事業計画が公的に認められた証明となります。国や自治体からの承認を受けた事実は、取引先や顧客に対して強い信頼を与えます。新規事業や未知の市場に参入する際、外部からの評価が事業の成否に影響する場合があるでしょう。
採択実績は計画の妥当性や実現可能性を裏付けるものであり、協力者やパートナーを得やすくなります。さらに、採択企業は自社のブランド価値の向上につなげられます。公表されるケースも多く、広報やPRに利用できる点も利点です。
信頼性の向上はイメージ戦略にとどまらず、優秀な人材や新しい顧客を引き付ける効果も期待できます。企業成長を加速させる重要な要素になります。
金融機関からの信用力向上につながる
補助金を獲得した企業は、公的機関に事業内容を評価されたとみなされます。そのため、金融機関からの信用が高まり、融資の審査で有利に働くことがあります。
資金繰りを安定させたい企業にとっては大きな利点です。補助金を通じて実績を積み重ねれば、将来の資金調達においても有利な立場を築けます。金融機関は事業計画の実現可能性を重視するため、補助金採択は信頼性を示す材料となります。
信用力が高まれば、新しい投資機会にも積極的に取り組みやすくなり、長期的な成長を描けるでしょう。外部からの信用は経営資産の一部として価値を持ち、補助金はその価値を引き上げる手段となります。結果的に、安定と成長を両立させる力を持つことになるでしょう。
DX推進に補助金を活用する際の注意点
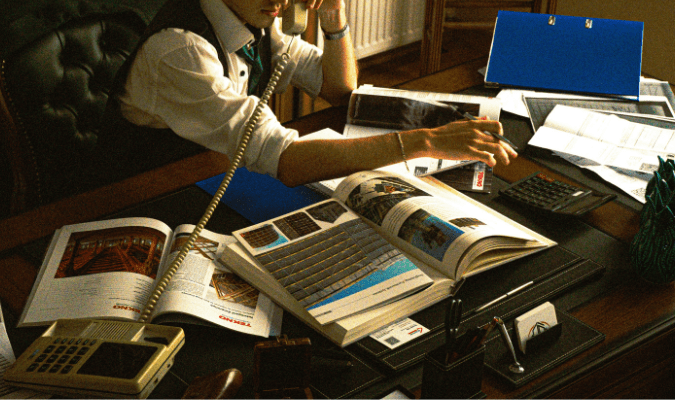
補助金は魅力的な支援制度ですが、注意点を理解しないまま申請すると失敗につながります。採択率が低い制度も多く、準備不足や誤解が原因で不採択になるケースも少なくありません。
さらに、受給のタイミングや対象経費の扱いを誤ると資金計画が崩れる恐れもあります。ここでは、申請時や事業実施時に気を付けるべき代表的なポイントを整理し、成功の確率を高めるための注意点を解説します。
申請書類の作成は時間と労力がかかる
補助金の申請書類は複雑で、事業計画の根拠や収益性の説明を詳細に記載しなければなりません。計画内容が抽象的であれば審査通過は困難になり、審査員を納得させるための資料作成には多大な時間を割く必要があります。
さらに、形式的な不備があれば受理すらされないため、細心の注意を払う必要があります。小規模な企業にとっては日常業務と並行して準備を進める負担が大きく、経営資源を圧迫することもあるでしょう。
課題に対応するには、専門家や認定支援機関との連携が有効です。外部の知見を活かせば、必要な要素を盛り込みながら効率的に申請書を仕上げられます。事務作業ではなく戦略策定の一部と捉える姿勢が求められるでしょう。
補助金は後払い方式で資金繰りに影響する
補助金は交付決定後に事業を開始し、完了後の実績報告を経て振り込まれる仕組みです。そのため、企業はまず自己資金や借入金で立て替える必要があります。十分な運転資金を確保していなければ、事業を途中で断念する事態も起こり得ます。
さらに、入金まで数か月を要することも多く、短期的な資金計画では対応が難しい場合もあるでしょう。金融機関との連携を早めに進め、つなぎ融資や追加融資を確保しておくことが現実的な対応策といえます。
資金調達の準備を怠れば、採択を受けても事業遂行が滞る可能性が高まります。補助金を活用する際には、長期的かつ柔軟な資金計画を立てることが不可欠です。制度の仕組みを理解した資金繰り対策が成功の前提になります。
制度の目的と経費内容を一致させる重要性
補助金ごとに設定された目的と申請内容が合致していなければ、採択はほぼ不可能です。省力化投資補助金では労働力不足の解消、事業再構築補助金では業態転換や新分野進出といった明確な方向性があり、計画内容がずれていれば対象外となります。
また、対象経費に含まれない支出を計上すれば、審査で減額や却下の対象となります。必要な経費を整理し、見積書や根拠資料を添えて説明することで審査担当者の理解を得やすくなるでしょう。
さらに、制度の目的を深く理解することで、事業計画を制度趣旨に沿った形に設計でき、評価を高めることが可能です。制度理解の浅さは致命的な失敗につながるため、目的と経費の一致を常に意識する必要があります。
補助金を活用してDXを成功させるポイント

補助金は資金面での後押しを受けられる一方、成功させるには単なる申請にとどまらない戦略が必要です。DXは経営全体に関わる変革であるため、短期的な導入効果だけでなく、長期的なビジョンや組織体制の整備も欠かせません。
ここでは、補助金を有効活用しながらDXを推進するために意識すべき重要なポイントを解説していきます。
経営陣が明確なビジョンを打ち出す
DXを推進するには、経営陣が主体的に方針を示すことが不可欠です。補助金を活用して導入した技術も、目的が不明確であれば現場で活かされません。
経営者が組織全体に向けて「何を目指すのか」「どの分野を強化するのか」を明文化し、数値指標を設定すれば従業員は目標を共有できます。さらに、進捗を定期的に発信し、成果を社内で可視化する取り組みも効果的です。トップダウンで方向性を定めつつ、現場の意見を取り入れることで実行可能な計画になります。
組織全体を巻き込む姿勢が、補助金を使った投資を単なる一過性の取り組みで終わらせないうえで重要です。明確なビジョンの提示は、社内のモチベーション向上にも直結する要素といえるでしょう。
自社に適した戦略を設計する
補助金を最大限に活かすには、自社の状況に合った戦略設計が欠かせません。業種や規模によって優先すべき課題は異なり、製造業では生産効率の改善、サービス業では顧客体験の向上といった違いが生じます。
制度の対象経費を正確に把握し、自社の課題解決につながる投資を選ぶ必要があります。短期的な成果だけでなく、中長期の成長戦略を盛り込むことで、採択の可能性も高まるでしょう。
さらに、補助金を全体戦略の一部として組み込み、既存施策との整合性を意識することが大切です。独自の強みを反映させた計画を作成すれば、単なる資金確保にとどまらず企業価値を高める投資になります。戦略的な設計こそが補助金を活用したDX推進の成否を左右するポイントです。
必要な人材を確保し育成する
補助金による投資を成功に導くには、人材の存在が欠かせません。どれほど優れたツールや設備を導入しても、運用できる人材がいなければ成果は限定的になります。まず、自社に不足しているスキルを洗い出し、外部専門家の活用や新規採用で補完することが重要です。
並行して既存社員に対して研修を行い、DXに必要なスキルを育成する取り組みも必要です。制度によっては研修費用が対象になるため、人材育成を計画に組み込むと費用面の負担を減らせます。
さらに、長期的には自社内にDXをリードする人材を育て、ノウハウを蓄積していく仕組みを作ることが望ましいです。人材戦略を重視すれば、補助金を活かした投資が持続的な成果に結びつきます。
小規模から始めて成果を積み重ねる
DX推進を補助金で成功させるには、一度に大規模な投資を行うよりも、小規模なプロジェクトから始める方が現実的です。まずは短期間で成果が見えやすい領域に取り組むことで、社内に成功体験を蓄積できます。
たとえば、在庫管理のシステム化や顧客対応の自動化は効果がわかりやすく、従業員の理解を得やすい施策です。成果を積み重ねれば、次のステップに進むための説得力が生まれ、追加投資も正当化できます。
さらに、社外への発信によって取引先や顧客からの信頼も高まり、ブランド価値の向上にもつながります。小さな成功を積み重ねていく姿勢が、大規模プロジェクトを実現する原動力となるでしょう。補助金を活かすには、段階的に取り組む戦略が効果的です。
関連記事:マーケティングフレームワーク完全ガイド【基礎から実践まで徹底解説】|InnoMark
まとめ
DXを推進する際には、ITツール導入や人材育成、設備投資など幅広い費用が発生します。補助金は返済不要の資金を確保できるため、資金負担を抑えながら挑戦を後押しする有効な手段です。さらに、採択を受けた事業は社会的な信頼を得やすくなり、金融機関からの信用力向上にもつながります。
一方で、申請書類の作成には専門的な知識が必要であり、資金は後払い方式で支給されるため計画的な対応が求められます。制度の目的や対象経費を正しく理解し、自社に適した戦略を描くことが重要です。
株式会社イチドキリは、中小企業向けに補助金申請支援サービスを行っています。経営基盤強化や新規事業への挑戦を支援し、高い採択率と迅速な対応で多くの企業をサポートしてきました。
着手金0円・完全成功報酬型で、書類作成から面接対策までトータルで支援いたします。DXを本格的に進めたい経営者の方は、ぜひご相談ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。