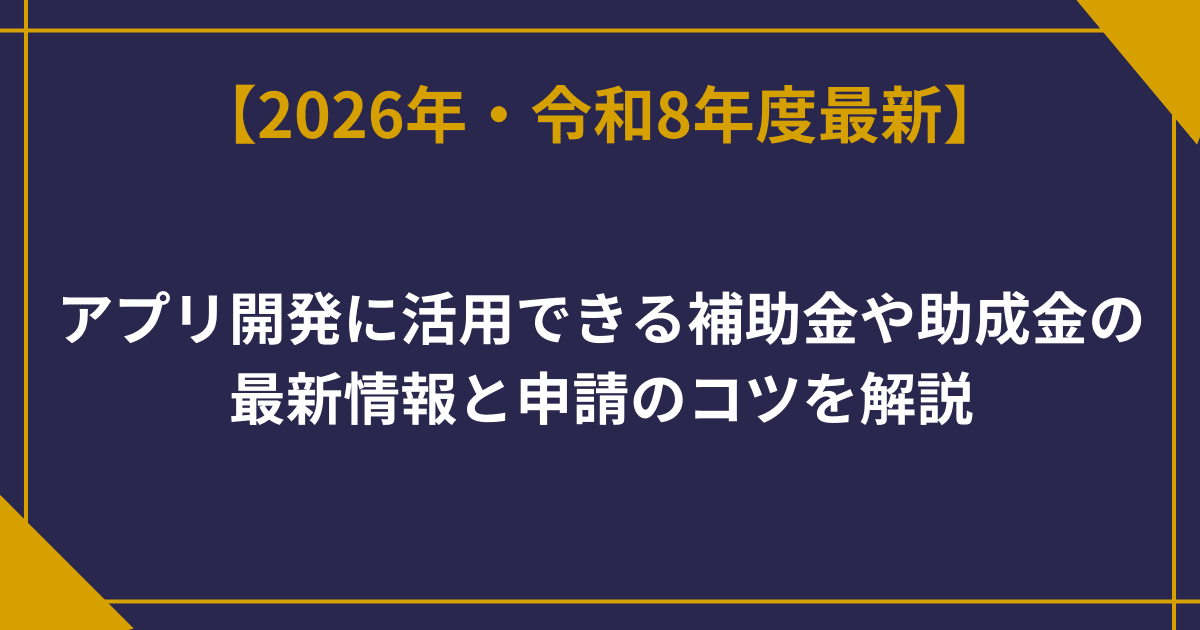アプリ開発には、企画・設計・開発・テストまで多額の費用がかかります。しかし、国や自治体が提供する助成金・補助金を活用すれば、初期投資を大幅に抑えながら、高品質なアプリを開発できます。2026年も、中小企業のデジタル化を支援する制度が数多く実施されており、今こそ積極的に活用すべきタイミングです。
本記事では、アプリ開発に使える最新の助成金・補助金9選を徹底比較し、採択率を高めるための申請のコツまで詳しく解説します。返済不要の資金を手に入れ、企業の成長を加速させましょう。
- アプリ開発で助成金・補助金を活用すべき3つの理由
- 【2025年度版】アプリ開発に使える助成金・補助金9選 比較一覧表
- アプリ開発で助成金・補助金を活用する際の全知識【メリット・デメリット】
- 補助金と助成金の違いとは?アプリ開発で知っておくべき基礎知識
- 採択率を高める5つのコツ【補助金のプロが徹底解説】
- 【2025年度】アプリ開発の助成金・補助金申請の一般的な流れ 6ステップ
- アプリ開発の助成金・補助金申請なら株式会社イチドキリへ!
- アプリ開発の助成金・補助金に関するよくある5つの質問
- まとめ:2026年は助成金・補助金活用が経営の分かれ目。専門家と連携し、アプリ開発で事業を加速させよう
アプリ開発で助成金・補助金を活用すべき3つの理由

アプリ開発で助成金・補助金を活用すると、コスト削減だけでなく、財務基盤や信頼性の向上といった多様なメリットが得られます。
1. 初期投資コストを大幅に削減できる
補助金を活用すれば、開発費用の最大1/2〜2/3が補助されるため、自己負担を大幅に削減できます。 アプリ開発には数十万円から数千万円の初期投資が必要ですが、IT導入補助金やものづくり補助金では、外注・委託費用やソフトウェア導入費用が対象です。ノーコード開発と組み合わせることで、約80%の費用削減も見込めます。初期費用を抑えることで、広告費や追加機能開発など成長施策に予算を回せるようになります。
2. 返済不要の資金調達で財務リスクを最小化
補助金や助成金は、銀行融資とは異なり原則として返済が不要です。 融資を受けた場合、事業の利益から毎月返済していく必要がありますが、補助金にはその義務がありません。得られた資金をすべて事業投資に回せるため、自己資金を維持しながら、より積極的な事業展開が可能です。数千万円規模の支援を受けられるケースもあり、投資リスクが低減されることでキャッシュフローの安定化にもつながります。
3. 国の支援制度を活用することで企業の信頼性が向上
補助金の審査を通過することは、企業の事業計画が国や自治体によって客観的に評価されたことを意味します。 この実績は、取引先や金融機関からの信頼を得やすくする効果があります。特に中小企業にとって、補助金採択は経営の健全性や将来性を示す証明となり、新規取引の獲得や融資審査で有利に働きます。また、財務基盤の健全性が評価されることで、次の支援制度への申請でも優位性が生まれます。
【2025年度版】アプリ開発に使える助成金・補助金9選 比較一覧表

アプリ開発には様々な補助金・助成金が活用できます。各制度には補助上限額、補助率、対象経費などに違いがあるため、自社の事業規模や目的に応じて最適な制度を選ぶことが重要です。
アプリ開発に使える助成金・補助金 比較一覧表
| 制度名 | 補助上限額 | 補助率 | 対象事業者 | 主な対象経費 |
| ものづくり補助金 | 750万円~4,000万円 | 中小企業1/2、小規模2/3 | 中小企業・小規模事業者 | システム構築費、外注費 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 50万円~200万円 | 2/3 | 小規模事業者 | 広報費、システム開発費 |
| IT導入補助金 | 5万円~450万円 | 1/2~4/5 | 中小企業・小規模事業者 | ソフトウェア購入費 |
| キャリアアップ助成金 | 20万円~80万円/人 | 定額 | 非正規雇用労働者を雇用する事業主 | 人材育成経費 |
| 人材開発支援助成金 | 経費助成45%~75% | 45%~75% | 雇用保険適用事業所 | 研修費、賃金 |
| 事業承継・M&A補助金 | 150万円~2,000万円 | 1/2~2/3 | 事業承継・M&A実施企業 | 設備費、外注費 |
| 研究開発助成金 | 各団体により異なる | 各団体により異なる | 研究開発企業 | 研究開発費 |
| 創業助成金(東京都) | 100万円~400万円 | 2/3 | 都内創業5年未満の事業者 | 賃借料、広告費 |
| 地域独自のIT補助金 | 各自治体により異なる | 各自治体により異なる | 各自治体の中小企業 | IT導入費、デジタル化費用 |
出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金|全国中小企業団体中央会
出典:『IT導入補助金2025』の概要|中小企業庁
出典:事業承継・M&A補助金のご案内|中小機構
1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
ものづくり補助金は、中小企業が革新的なサービス開発や生産性向上に取り組む際に活用できる大型補助金です。 2025年度は、補助上限額が従業員規模によって750万円~4,000万円に設定されています。
補助率は、中小企業で1/2、小規模事業者や再生事業者は2/3です。対象経費には、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、外注費などが含まれ、アプリ開発の外注費用も補助対象です。
2. 小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する制度です。 補助上限額は、通常枠で50万円、創業型で200万円です。賃金引き上げ特例の要件を満たすと、通常枠に150万円が上乗せされます。
補助率は2/3で、たとえば150万円の経費をかけた場合、100万円が補助されます。対象経費には、ウェブサイト関連費、広報費、システム開発費、外注費などが含まれ、アプリ開発やECサイト構築にも利用可能です。
3. IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のITツール導入を支援する制度で、アプリ開発に最も直接的に活用できる補助金です。 2025年度の補助上限額は、通常枠で5万円~450万円です。補助率は枠により異なり、通常枠は1/2、インボイス枠は補助額50万円以下の部分が中小企業3/4・小規模事業者4/5です。
対象経費には、ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア関連費、導入関連費が含まれます。
4. キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を行った事業主に支給される助成金です。 2025年4月の改正により、中小企業が有期雇用から正社員に転換した場合、要件を満たさないケースで80万円、要件を満たすケースで40万円が支給されます。
また、賃金規定等改定コースでは、賃金を3%以上引き上げた場合、中小企業で1人あたり2万8,500円が支給されます。助成金は定額支給で、要件を満たせば確実に受給できる点が特徴です。
5. 人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、従業員に対して研修や職業訓練を実施する企業を支援する制度です。 2025年度の助成率は、人材育成支援コースで経費助成45%、賃金助成760円/時間です。人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練)では、経費助成75%、賃金助成960円/時間に引き上げられます。
たとえば、50,000円の研修を15時間実施した場合、経費助成35,000円と賃金助成12,000円で、合計47,000円が助成されます。
6. 事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・M&A補助金は、事業承継やM&Aを契機として新たな取り組みを行う中小企業を支援する制度です。 2025年度は4つの支援枠が設けられています。事業承継促進枠では、補助上限額800万円、補助率は中小企業1/2(小規模事業者2/3)です。
専門家活用枠では、買い手・売り手支援類型で600万円~800万円となっています。対象経費には、設備費、産業財産権等関連経費、外注費、委託費などが含まれます。
7. 研究開発助成金(各種団体・財団)
研究開発助成金は、民間の財団や団体が独自に実施する助成制度で、先進的な技術開発やイノベーションを伴うアプリ開発に活用できます。 各団体により助成上限額や助成率は異なりますが、東京都では知的財産活用製品化支援助成金として最大1,500万円が提供されています。
対象となる経費は、研究開発費、試作品製作費、外注費、人件費などで、AI技術やIoT、ブロックチェーンなど先端技術を活用したアプリ開発案件が採択されやすい傾向にあります。
8. 創業助成金(東京都)
創業助成金は、東京都が都内で創業を予定している方や創業から5年未満の中小企業・個人事業主を支援する制度です。 2025年度の助成上限額は、従来の300万円から400万円に増額されました。助成下限額は100万円で、助成率は対象経費の2/3以内です。
対象経費には、賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費などが含まれ、アプリ開発に関わる外注費や人件費も対象です。
9. 【都道府県・市区町村別】地域独自のIT・デジタル化補助金
全国の都道府県や市区町村では、地域経済の活性化を目的とした独自のIT・デジタル化補助金が数多く実施されています。 東京都では、革新的事業展開設備投資支援助成金(最大1,500万円、助成率1/2~2/3)、DX推進助成金(最大1,500万円、助成率2/3~3/4)などが提供されています。
地域独自の補助金は、各自治体の産業振興課や商工会議所が窓口です。自社の所在地や事業所がある自治体のホームページを定期的にチェックし、最新情報を収集することが重要です。
アプリ開発で助成金・補助金を活用する際の全知識【メリット・デメリット】
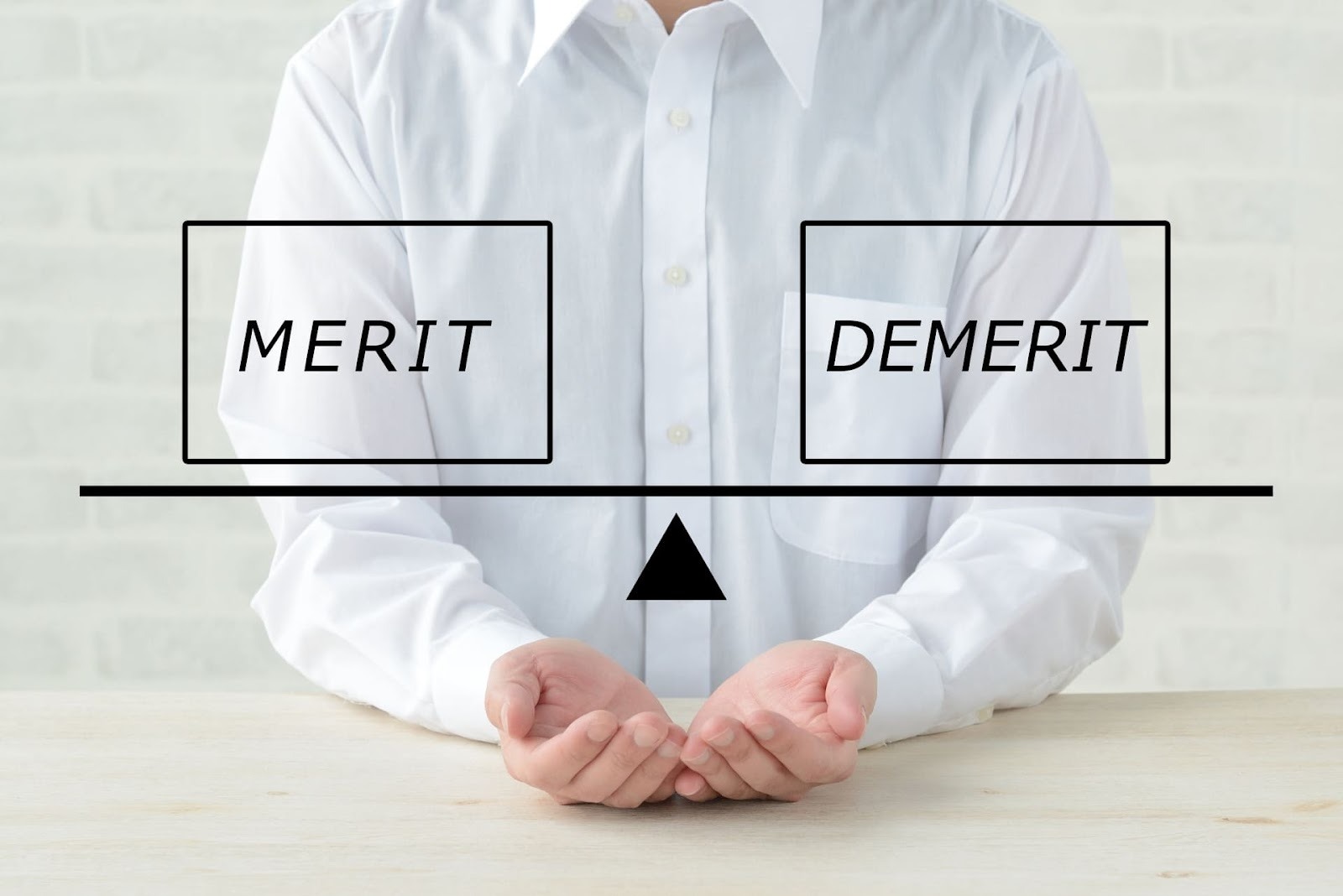
助成金・補助金は、アプリ開発にかかる費用を大幅に削減できる魅力的な制度ですが、メリットだけでなくデメリットも正しく理解しておくことが重要です。
1. 助成金・補助金を活用する5つのメリット
助成金・補助金には、返済不要という最大の魅力のほか、複数のメリットが存在します。
- 返済不要で財務負担がゼロ
- 初期投資リスクを大幅に軽減できる
- 売上換算で大きな利益効果を生む
- 中小企業に有利な制度設計
- 労務管理・経営体制の健全化につながる
それぞれ解説していきます。
①返済不要で財務負担がゼロ
助成金・補助金は融資とは異なり、原則として返済が不要です。 銀行融資を受けた場合、毎月の返済と利息負担が発生しますが、補助金にはそうした義務がありません。受給した資金はすべて事業投資に回すことができ、キャッシュフローを圧迫せずに事業を展開できます。
特に創業期や事業拡大期の企業にとって、返済義務のない資金は大きな安心材料です。ただし、補助金で購入した設備等を売却する場合は「財産処分」の手続きが必要となり、補助金を返還するケースもあります。
②初期投資リスクを大幅に軽減できる
補助金を活用することで、事業のリスクを大幅に軽減できます。 アプリ開発には数百万円から数千万円の初期投資が必要ですが、補助率1/2~2/3の支援を受けることで、自己負担を最小限に抑えられます。
たとえば、600万円のアプリ開発プロジェクトに補助率2/3の補助金を活用すれば、400万円が補助され、自己負担は200万円で済みます。資金基盤が十分ではない中小企業・小規模事業者にとって、投資リスクを抑えながら新たな挑戦ができる点は非常に魅力的です。
③売上換算で大きな利益効果を生む
受給した助成金・補助金は雑収入となり、使途に制限がありません。 つまり、受給した資金は純利益として計上され、自由に活用できます。助成金の金額が大きくなくても、売上換算すると大きな効果があります。
たとえば、利益率5%の企業が50万円の助成金を獲得した場合、売上換算では1,000万円に相当します。これは、1,000万円の売上を上げなければ得られない利益を、助成金によって直接得られることを意味します。
④中小企業に有利な制度設計
ほとんどの助成金・補助金は、大企業よりも中小企業・小規模事業者に優位な受給額が設定されています。 補助率も中小企業の方が高く設定されており、小規模事業者はさらに優遇されるケースが多くあります。
たとえば、ものづくり補助金では中小企業の補助率が1/2に対し、小規模事業者や再生事業者は2/3となります。IT導入補助金のインボイス枠でも、小規模事業者は補助率4/5と、より手厚い支援が受けられます。
⑤労務管理・経営体制の健全化につながる
助成金を獲得できる企業は、高いレベルの労務管理水準を満たしている証明となります。 適切な労務管理がなされていない場合、助成金が受給できなくなるため、審査は厳しくなります。その結果、助成金の申請プロセスを通じて、募集・採用・雇用契約・賃金計算・退職に至るまで適正な管理体制が整備されます。
これは企業の信頼性向上にもつながり、従業員の満足度向上や人材定着にも効果があります。また、補助金の審査を通過することで、事業計画の精度が高まります。
2. 知っておくべき4つのデメリットと注意点
助成金・補助金には多くのメリットがある一方で、活用にあたっては必ず理解しておくべきデメリットと注意点が存在します。
- 補助金は後払いで全額立替が必要
- 審査があり必ず受給できるわけではない
- 手続きが煩雑で事務負担が大きい
- 補助対象外経費が多く使途に制約がある
それぞれ解説していきます。
①補助金は後払いで全額立替が必要
補助金は原則として事業終了後の「後払い(精算払い)」です。 採択されたら事業を開始しますが、この段階ではまだ補助金を受け取れていません。そのため、事業者が一度は補助対象となる費用全額を立て替えなくてはなりません。
たとえば、600万円のアプリ開発案件で補助金400万円が採択されても、まずは600万円全額を用意する必要があります。事業が完了し検査を受け、そこで合格すると補助金が交付される仕組みです。資金繰りに不安がある場合は、取引先の金融機関に「つなぎ融資」を相談することをお勧めします。
②審査があり必ず受給できるわけではない
助成金は要件を満たして申請すれば原則受給できるものが多いのですが、補助金は要件を満たして申請しても必ずもらえるわけではありません。 事業計画書や決算書などの書類を審査し、補助金の交付に値する事業として「採択」される必要があります。
公募が締め切られてから「採択」まで通常2か月程度かかり、その後に「交付申請」の手続きがあるため、事業の開始時期は数か月後になる点に注意が必要です。そのため、補助金ありきで事業を計画するのではなく、補助金がなくても実施可能な範囲で計画を立てる姿勢が望ましいでしょう。
③手続きが煩雑で事務負担が大きい
助成金・補助金の申請には、事業計画書の作成、必要書類の収集、電子申請の操作など、手続きが面倒です。 さらに、採択後も事業実施中の進捗報告、経費の証拠書類の保管、実績報告書の作成など、継続的な事務作業が発生します。労務管理を適切に行うため、募集・採用・雇用契約・就業中・退職に至るまで注意が必要です。
複数の助成金を同時進行する場合には、管理がさらに困難になります。中小企業では専任担当者を置くことが難しい場合もあり、専門家のサポートを受けることも検討すべきでしょう。
④補助対象外経費が多く使途に制約がある
補助金には明確な対象経費が定められており、すべての経費が補助対象となるわけではありません。 たとえば、ものづくり補助金では、建設費、広告費・販売促進費、研修費、不動産全般の経費、汎用性が高い事務機器や家電、自社の人件費などは補助対象外です。
事業再構築補助金でも、パソコンやタブレットなど汎用性の高い物品、従業員給与、土地・株式の購入費用、事務所の家賃・光熱費などは対象外です。補助対象経費と対象外経費を正確に理解し、事前に確認しておくことが重要です。
補助金と助成金の違いとは?アプリ開発で知っておくべき基礎知識

補助金と助成金は、どちらも返済不要の公的支援制度ですが、管轄省庁や受給条件が大きく異なります。アプリ開発に活用する際は、それぞれの特徴を理解し、自社の状況に適した制度を選ぶことが成功への近道です。
1. 補助金と助成金の定義と主な違い
補助金と助成金の主な違いは、管轄省庁、受給条件、審査の有無です。 助成金は主に厚生労働省が管轄し、要件を満たせば原則受給できるのに対し、補助金は主に経済産業省や地方自治体が管轄し、審査を通過しなければ受給できません。
助成金は雇用促進や労働環境の改善を目的とし、事前審査がなく、通年で申請を受け付けていることが多いため、比較的取得しやすい制度です。一方、補助金は事業を通じた社会貢献や産業振興を目的としており、予算と採択件数があらかじめ決まっています。
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
| 主な管轄 | 経済産業省、地方自治体 | 厚生労働省 |
| 目的 | 新規事業や産業振興 | 雇用促進や労働環境の改善 |
| 受給条件 | 要件を満たしても審査に通過しないと受給できない | 要件を満たせば受給できる可能性が高い |
| 審査 | あり(厳しい事前審査) | なし(要件確認のみ) |
| 申請時期 | 公募期間が限定的 | 通年受付が多い |
| 支払時期 | 後払い | 後払い |
2. アプリ開発に適した制度の選び方
アプリ開発に適した制度を選ぶには、開発の目的や企業の状況を明確にすることが重要です。 事業拡大や新サービス開発を目指すなら補助金、人材育成や労務環境整備に重点を置くなら助成金が適しています。
補助金は、ものづくり補助金やIT導入補助金など、設備投資やシステム開発に直接活用できる制度が豊富です。一方、助成金はアプリ開発に直接使える制度は少ないものの、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など、開発人材の育成や確保に活用できます。
採択率を高める5つのコツ【補助金のプロが徹底解説】
補助金の採択率を高めるには、単に申請書を作成するだけでなく、戦略的なアプローチが必要です。ここでは、補助金のプロが実践する以下5つの重要なコツを解説します。
- 最新の公募要領を読み込み、加点項目を確実に押さえる
- 審査員に響く、ストーリー性のある事業計画書を作成する
- 認定経営革新等支援機関と連携し、計画の質を高める
- 補助対象経費と対象外経費を正確に理解する
- 公募スケジュールを把握し、余裕を持った準備を行う
1. 最新の公募要領を読み込み、加点項目を確実に押さえる
補助金の採択率を上げる最も確実な方法は、公募要領に記載された加点項目を満たすことです。 加点項目とは、特定の条件を満たす申請者に追加の得点を与える制度で、競争率が高い補助金ほど、加点の有無が採択を左右します。ものづくり補助金では、パートナーシップ構築宣言の登録、賃上げ計画の策定など、全15項目の加点要件があります。
特にパートナーシップ構築宣言は、中小企業庁のポータルサイトで登録すれば取得でき、すぐに加点対象となるため優先的に取り組むべきです。
2. 審査員に響く、ストーリー性のある事業計画書を作成する
補助金の事業計画書は、審査員が自然に理解できるストーリー構造を持たせることで説得力が大幅に高まります。 ここでいうストーリーとは、「現状分析→課題→解決策→投資内容→成果」という論理的な流れです。
まず、現状分析では企業概要とSWOT分析を明確にし、自社の強みと弱み、外部環境の機会と脅威を整理します。次に、現状分析から導き出される課題を明確にし、その解決策としてアプリ開発がなぜ最適なのかを論理的に説明します。審査員が「この投資は必然だ」と納得できるストーリーを描くことが、採択への近道です。
3. 認定経営革新等支援機関と連携し、計画の質を高める
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)と連携することで、事業計画の質が高まり、補助金の採択率が向上します。 認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあるとして、国の認定を受けた支援機関です。
事業計画の策定支援を受けることで、経営の現状を正しく把握でき、課題を発見できます。また、ものづくり補助金や事業再構築補助金など、多くの補助金では認定支援機関の確認書が申請要件です。認定支援機関は中小企業庁のサイトで検索できます。
4. 補助対象経費と対象外経費を正確に理解する
補助対象経費と対象外経費を正確に理解しておくことは、採択後のトラブルを防ぎ、確実に補助金を受給するために不可欠です。 申請する経費の大半が補助対象外の場合、審査で不採択となるか、採択後に取り消される可能性があります。
事業再構築補助金では、パソコンやタブレットなど汎用性の高い物品、従業員給与、土地・株式の購入費、事務所の家賃・光熱費などは対象外です。ものづくり補助金でも、建設費、広告費、研修費、汎用性の高い事務機器、自社の人件費などは補助対象外です。公募要領で経費項目を必ず確認しましょう。
5. 公募スケジュールを把握し、余裕を持った準備を行う
補助金の公募スケジュールを把握し、余裕を持って準備することが、採択率を高める重要なポイントです。 公募期間は限定的で、申請から採択まで通常2か月程度かかるため、計画的な準備が求められます。
2025年度の主要補助金スケジュールを見ると、ものづくり補助金は第22次公募が2025年12月26日~2026年1月30日、小規模事業者持続化補助金の第9次は2026年1月23日~3月31日に実施されています。公募開始前から事業計画書の骨子を作成し、必要書類を準備しておくことが重要です。
出典:R7年度 小規模事業者・中小企業向け補助金スケジュール|中小機構
【2025年度】アプリ開発の助成金・補助金申請の一般的な流れ 6ステップ

アプリ開発で助成金・補助金を活用するには、明確な手順を理解し、計画的に進めることが重要です。申請から受給までには通常数か月を要し、各段階で必要な手続きや書類提出があります。
この章では、アプリ開発の助成金・補助金申請の以下6つのステップについて解説します。
- 自社の課題と開発したいアプリの明確化
- 対象となる助成金・補助金の選定と情報収集
- 事業計画書の作成と申請準備
- 申請受付期間内に電子申請を行う
- 採択結果の通知と交付申請
- 事業実施、実績報告、補助金の受給
1. 自社の課題と開発したいアプリの明確化
補助金申請の第一歩は、自社が抱える課題を明確にし、その解決策としてどのようなアプリを開発すべきかを具体化することです。 現状把握のためには、SWOT分析や経営デザインシートといったツールを活用することが有効です。SWOT分析では、自社の強み、弱み、外部環境の機会、脅威を整理します。
たとえば、「顧客管理が属人化しており営業効率が悪い」という課題があれば、「顧客情報を一元管理し、営業活動を可視化するCRMアプリの開発」という解決策が導き出されます。このように、課題と解決策を明確にすることで、審査員を納得させる事業計画の土台が築かれます。
2. 対象となる助成金・補助金の選定と情報収集
課題と開発したいアプリが明確になったら、次は自社の事業にマッチする補助金を探します。 補助金は国の政策ごとに様々な分野で募集されており、それぞれに「目的」や「仕組み」が異なります。補助金を選ぶ際は、公募要領を必ず確認し、補助対象となる経費、補助率、上限額、申請期間などを把握しましょう。
アプリ開発には、ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金などが適しています。情報収集には、中小企業庁の公式サイトや「J-Net21 支援情報ヘッドライン」を活用します。
3. 事業計画書の作成と申請準備
補助金申請で最も重要なのが、事業計画書の作成です。 事業計画書には、現状把握、目標設定、具体的な取り組み内容を論理的に記載し、審査員が「実現性」を判断できる内容にする必要があります。事業計画書は経営者が主体的に責任を持って作成しなければなりません。
作成にあたっては、商工会議所・商工会、金融機関、認定経営革新等支援機関から第三者視点のアドバイスを受けることで、説得力のある計画書にブラッシュアップできます。売上や利益などの数値目標は、統計やアンケート調査などに基づいた「予測値」として根拠を示すことが重要です。
4. 申請受付期間内に電子申請を行う
申請書類が整ったら、公募期間内に申請を行います。 現在、多くの補助金はjGrants(Jグランツ)という電子申請システムを通じて、オンラインで申請できます。jGrantsにログインするには、GビズIDが必要です。
取得には2週間程度かかるため、早めに準備しましょう。jGrantsで申請したい補助金を検索し、対象の補助金ページで「申請する」ボタンをクリックします。事業者情報、業種、財務情報、事業計画内容を入力し、必要な添付書類をアップロードします。申請締切直前は申請が集中し、システムが混雑する可能性があるため、余裕を持って申請することが重要です。
5. 採択結果の通知と交付申請
公募期間が終了すると、事務局が提出された書類を審査し、採択事業者を決定します。 採択までには通常2か月程度かかります。採択されたからといって、すぐに補助金が受け取れるわけではありません。
採択後は、補助金を受け取るための「交付申請」という手続きが必要です。交付申請の内容が認められると「交付決定通知書」が発行され、ここで初めて補助事業を開始できます。交付決定前に事業を開始した経費は補助対象外となるため、必ず交付決定後に発注・契約を行ってください。
6. 事業実施、実績報告、補助金の受給
交付決定後、決定された内容に基づいて補助事業を実施します。 事業実施中は、領収書や証拠書類をすべて保管しておく必要があります。事業が完了したら、実績報告書を提出し、事業内容と経費を報告します。事務局が実績報告を審査し、正しく実施されたことが確認されると、補助金額が確定します。
その後、補助金額確定通知書が発行され、請求手続きを経て補助金が支払われます。補助金は原則として後払いであり、事業完了後に受け取る仕組みです。補助事業終了後も、領収書や証拠書類は5年間保管する義務があります。
アプリ開発の助成金・補助金申請なら株式会社イチドキリへ!
アプリ開発で助成金・補助金の活用を検討しているなら、経済産業省認定の経営革新等支援機関である株式会社イチドキリにお任せください。 イチドキリは、エンジニア出身の代表を含むプロフェッショナルチームが、補助金申請の書類策定から獲得まで伴走する、IT・AI系開発企業に特化した補助金コンサルティング会社です。
事業アイデアの検討から伴走し、適切な補助金選定と申請支援まで対応します。着手金0円・完全成功報酬制で、採択されなければ費用は一切発生しません。リスクなく補助金申請に挑戦できます。
アプリ開発の助成金・補助金に関するよくある5つの質問
アプリ開発で助成金・補助金を活用する際に、多くの事業者が抱える疑問を5つのQ&A形式でまとめました。申請前に知っておくべき重要なポイントを押さえ、スムーズな資金調達を実現しましょう。
Q1. アプリ開発の外注費用も補助金の対象になりますか?
A. はい、アプリ開発の外注費用は多くの補助金で対象となります。 ただし、補助金の種類によって対象範囲や条件が異なるため注意が必要です。
ものづくり補助金では、システム開発やプログラミングの外注は「機械装置・システム構築費」として計上します。
外注費が補助対象となるには、外注内容や金額が明記された契約書を締結すること、成果物が補助事業者に帰属すること、同一代表者・役員が含まれる企業や資本関係がある企業への外注は対象外となります。公募要領を熟読し、対象経費の範囲を正確に把握しましょう。
Q2. 個人事業主でもアプリ開発に使える助成金はありますか?
A. はい、個人事業主も多くの補助金・助成金を利用できます。 主要な補助金のほとんどが個人事業主を対象としており、開業届を提出していることが条件となります。IT導入補助金は、日本国内で事業を行う中小企業または個人が対象です。
小規模事業者持続化補助金も、個人事業主が利用可能です。個人事業主が補助金を活用する際の注意点は、開業届を税務署に提出していること、確定申告を適切に行っていること、事業実態があり、事業計画が実現可能であることです。法人と比べて審査が厳しくなるケースもありますが、事業の実現性や革新性を明確に示すことで採択の可能性は十分にあります。
Q3. 補助金はいつもらえるのでしょうか?後払い(精算払い)が基本ですか?
A. はい、補助金は原則として後払い(精算払い)です。 事業が計画どおりに実施され、かかった費用を支払ったことが確認されてから、初めて受け取ることができます。
事業の途中で補助金を受け取ることはできず、採択されたとしても、まずは事業者が全額を立て替える必要があります。たとえば、600万円のアプリ開発案件で補助金400万円が採択されても、まずは600万円全額を用意しなければなりません。
資金繰りに不安がある場合は、金融機関に「つなぎ融資」を相談することをお勧めします。補助金は自己負担があり後払いであることから、事前に十分な資金計画を立てておきましょう。
Q4. 複数の補助金に同時に申請することは可能ですか?
A. 異なる事業や異なる費目であれば、複数の補助金に同時に申請することは可能です。 しかし、同一事業・同一費目への重複申請は原則として認められません。申請段階では、複数の補助金を併願することは可能です。
異なる事業や、同じ事業の異なる費目については補助金を併願できます。採択後の併用では、異なる事業それぞれに補助金が採択された場合、別々に利用する形で併用できます。同一事業・同一費目は基本的に併用できません。申請前に各補助金の公募要領を確認し、併用可否を事務局に問い合わせることをお勧めします。
Q5. 補助金の申請代行を依頼するメリットは何ですか?
A. 補助金の申請代行を依頼することで、採択率の向上、時間と労力の削減、専門的なサポートが得られます。 特に初めて補助金を申請する事業者にとって、専門家のサポートは大きなメリットとなります。公募要領の確認、必要書類の収集、申請様式への記入など、複雑な作業を専門家に任せられます。
補助金申請に精通した専門家が事業計画書を作成・ブラッシュアップするため、自社で作成するよりも採択率を高めることができます。申請代行を依頼する際は、実績や専門性、対応の柔軟さ、料金体系を確認し、信頼できる業者を選びましょう。
まとめ:2026年は助成金・補助金活用が経営の分かれ目。専門家と連携し、アプリ開発で事業を加速させよう
2026年は、国が中小企業のデジタル化支援を強化しており、アプリ開発に使える助成金・補助金が多数用意されています。 ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金など、数百万円から数千万円規模の支援を受けられる制度が充実しています。
補助金は返済不要で初期投資リスクを軽減できますが、採択には戦略的なアプローチが必要です。公募要領の読み込み、加点項目の確保、認定経営革新等支援機関との連携が重要なポイントです。まずは最新の公募情報をチェックし、自社に最適な制度を見極めましょう。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。