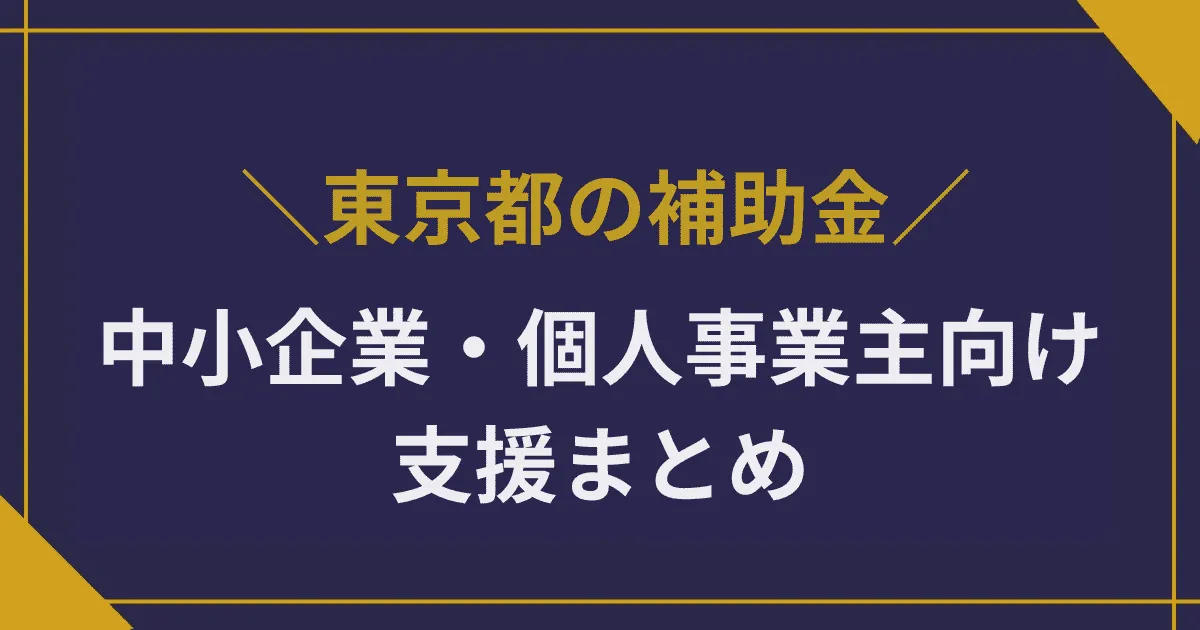事業を推進するうえで大きな壁となるのが資金調達です。特に創業間もない中小企業や個人事業主にとっては、金融機関からの借入だけでは十分な資金を確保できない場合もあります。そこで頼りになるのが、返済義務のない公的支援制度である補助金や助成金です。
国が実施する補助金に加え、東京都では地域の特性や産業振興を目的とした独自の助成制度を設けています。これらをうまく活用することで、設備投資や人材採用、新規サービスの導入といった挑戦を後押しすることが可能です。
ただし制度の種類は多岐にわたり、対象要件や申請のタイミングも異なります。情報を整理せずに臨むと、せっかくのチャンスを逃してしまうことも。本記事では、東京都の補助金・助成金をジャンル別に整理し、制度の特徴や申請の流れをわかりやすく紹介していきます。
- 東京都で実施される補助金の最新動向と活用の基本
- 創業・起業を支援する東京都の補助金
- 設備投資・事業拡大に活用できる補助金
- 販路開拓・マーケティング向け補助金
- 業界特化・エネルギー対策などその他の東京都補助金
- 東京都補助金を確実に活用するための相談先
- まとめ
東京都で実施される補助金の最新動向と活用の基本
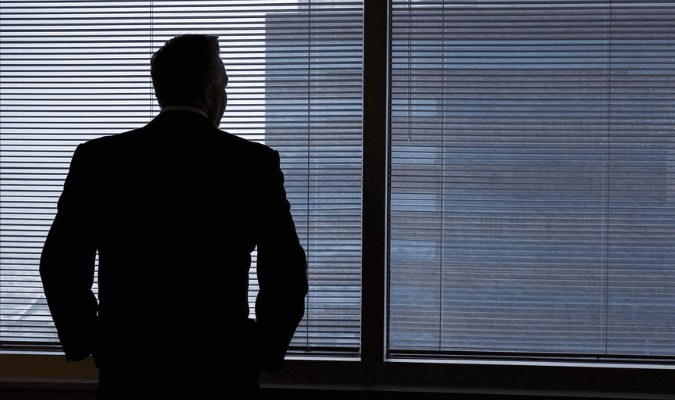
東京都で実施される補助金は、創業期から事業拡大、省エネ対策まで幅広く展開されています。資金繰り改善や新規事業推進に直結する制度が多く、採択されれば返済不要で活用可能です。
まずは補助金の基本と助成金との違いを整理し、活用メリットや申請の基本フローを押さえましょう。
東京都で実施される補助金の特徴
東京都で実施される補助金は、中小企業や個人事業主の成長を後押しする多様な制度で構成されています。主な対象は、創業支援、設備投資、省エネ対策、販路開拓、人材育成など広範囲に及びます。補助金は返済不要で活用でき、採択されれば数十万円から数千万円規模の資金調達が可能です。
東京都は、地域産業の強化や新規事業の創出を重視しており、独自性の高い制度が多数存在します。申請には事業計画書の提出が必須であり、事業の実現性や成長性を数値で示すことが求められます。
また、採択後は経費の証憑管理や実績報告の提出が必要となるため、計画段階から社内体制を整備しておくことが望ましいでしょう。補助金を活用することで、自己資金だけでは難しい投資や事業展開を実現し、地域経済への貢献も期待できます。東京都の補助金は、経営基盤の安定化と新たな成長戦略の実行を後押しする心強い資金源といえるでしょう。
補助金を活用するメリット
補助金の最大の魅力は、返済不要の資金を確保できる点です。資金繰りを圧迫せずに設備導入や広告宣伝を進められ、自己資金や借入に頼らず投資が可能となります。たとえば、製造業では高性能の機械導入による生産性向上が期待でき、小売・サービス業では販促強化やECサイト構築を通じた売上拡大が実現しやすくなります。
さらに、研究開発型の補助金を活用すれば、新製品や新技術の開発スピードを加速させ、競合との差別化にも直結するでしょう。補助金の申請を機に事業計画を整理することで、社内での課題認識が明確化され、長期的な経営改善にも波及します。
採択後は、報告書作成や経費管理を通じて内部統制が整備され、財務面の健全化にもつながります。補助金を適切に活用することで、短期的な資金補填だけでなく、中長期的な企業力強化を実現できるでしょう。
補助金申請の基本フロー
補助金の申請は、情報収集・申請書作成・提出・審査・採択・事後報告という流れで進みます。最初のステップは公募情報の把握です。東京都や中小企業振興公社の公式サイトで最新情報を確認し、募集期間や対象事業を確認しましょう。次に、申請書作成では事業計画を詳細に示し、投資の必要性や将来の効果を数字で示すことが大切です。
審査では計画の実現性や地域経済への貢献度が重視されるため、根拠を明確に示しましょう。採択後は、補助対象経費の支出と報告書の提出が求められます。要件を満たさない支出は補助対象外となるため、領収書の整理や契約書の保管を徹底してください。
申請から交付まで時間がかかることもあるため、資金繰りを考慮した計画的な準備が欠かせません。
補助金申請のフローについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ものづくり補助金の手続きの流れを完全解説|申請から補助金受給までの全ステップ
創業・起業を支援する東京都の補助金

東京都では、起業や事業承継を進める事業者向けに、開業初期費用や販路開拓に役立つ補助金が複数用意されています。創業直後は資金繰りが不安定で、賃料や広告費などの負担が重くなりがちです。
補助金を活用すると、初期費用を軽減しつつ、設備投資や販路拡大に集中できます。ここでは、創業段階や商店街開業、海外展開に関連する代表的な補助金を紹介します。
創業助成事業
創業助成事業は、開業初期に必要な経費を幅広く対象とするため、資金繰りに余裕を持たせながら事業を軌道に乗せやすくなります。賃借料や従業員人件費に加え、広告宣伝費や市場調査費も補助対象に含まれるため、開業直後から販路拡大に注力できます。
器具備品購入費や専門家指導費、産業財産権取得費も助成範囲に含まれるため、製品・サービスの品質向上や知財保護を進めながら事業基盤を整備可能です。助成金は交付決定から6か月経過後に中間払いが可能で、キャッシュフローの安定化にも寄与します。
初めて創業する事業者でも、電子申請により効率的に応募できる点が魅力です。事前に対象経費を整理し、具体的な事業計画を作成することで採択率向上につながり、資金面と経営面の両方で大きな効果を期待できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 都内での創業を計画する個人、または創業5年未満の中小企業(※代表者が通算5年以上の経営経験を有する場合は対象外) |
| 助成対象経費 | 賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費 |
| 助成期間 | 交付決定日から6か月以上、最長2年 |
| 助成限度額 | 上限400万円(事業費・人件費合計は上限300万円、委託費は上限100万円) |
| 助成率 | 経費の3分の2以内 |
| 申請期間 | 令和7年9月29日(月)10:00 ~ 10月8日(水)23:59 |
| 申請方法 | 電子申請(郵送不可) |
商店街起業・承継支援事業
商店街起業・承継支援事業は、東京都内の商店街で新たに店舗を開業する事業者や、既存店舗を承継する事業者を対象とした助成金です。対象となる経費は、店舗の内装工事費、設備購入費、看板製作費など、開業や承継に必要な初期費用が中心です。
開業スケジュールを事前に調整し、助成対象経費や申請条件を正確に確認することが成功への近道です。資金負担の軽減だけでなく、地域に根ざした事業展開をスムーズに進められる点が大きなメリットとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 都内商店街で新規開業する事業者、または店舗を承継する事業者 |
| 助成対象経費 | 店舗内装・外装工事費、設備・備品購入費、看板製作費など |
| 助成率 | 経費の一部(詳細は年度要項による) |
| 助成期間 | 交付決定日から定められた助成対象期間内 |
| 支給方法 | 後払い(対象期間内に発注・納品・支払いが完了した経費が対象) |
| 審査方法 | 書類審査と面接審査の二段階 |
| 交付決定までの期間 | 約4か月 |
設備投資・事業拡大に活用できる補助金

中小企業が生産性向上や事業拡大を目指す際には、設備投資や工場改築に多額の資金が必要になります。東京都では、事業規模の拡大や新製品開発を後押しするための補助金が複数用意されています。
採択されれば、自己資金や借入だけでは難しい大規模投資を現実化でき、事業基盤の強化にもつながるでしょう。ここでは、設備投資や新製品開発に活用しやすい代表的な補助金を紹介します。
経営統合等による産業力強化支援事業
経営統合等による産業力強化支援事業は、都内の中小企業が経営統合や事業承継を契機に、大規模な設備投資を実施する場合に活用できる助成金です。工場の新設や増改築、設備・システムの導入などにかかる経費の一部を補助することで、都内産業の競争力向上とサプライチェーンの維持を後押しします。
助成対象は工場建設費や設備導入費に加え、調査費も含まれ、補助率は最大で2/3、助成額は最大4億円に達します。採択されれば、自己資金では難しい大規模投資が現実となり、長期的な生産力強化や新市場開拓につながるでしょう。事前エントリーやGビズID取得などの準備を早めに進めることが成功の条件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 経営統合(M&A等)を行う都内中小企業(連携枠)/サプライチェーンに大きな影響を与える単体企業(単体枠) |
| 助成対象経費 | 工場建設費、設備・システム導入費、調査費など |
| 助成額・助成率 | 連携枠:最大4億円・2/3以内/単体枠:最大3億円・1/2以内 |
| 助成下限額 | 連携枠:1,000万円/単体枠:5,000万円 |
| 助成対象期間 | 交付決定翌月から最大3年間 |
| 採択予定件数 | 4件程度 |
| 申請方法 | 事前エントリー後、Jグランツによる電子申請 |
| 主な審査 | 書類審査 → 現地調査 → 面接審査 → 採択決定 |
| 申請期間 | 令和7年9月1日(月)~ 10月31日(金)17:00まで |
広域ものづくりネットワーク形成支援事業
広域ものづくりネットワーク形成支援事業は、都内中小企業が主体となり、大手企業への製品・技術提案や自社事業の新規展開に向けて試作品を開発する際に利用できる助成制度です。中核企業として認定を受けた中小企業を中心に、1都10県に所在する協力企業と連携して新製品や技術改良を進めます。
事業では、試作品開発に必要な経費の一部を助成するだけでなく、協力企業の探索や専門家派遣、公社コーディネーターによる伴走支援も受けられる点も特徴です。助成コースは、大手企業等への技術提案を目指す「技術提案コース」と、自社事業の新規展開に取り組む「新事業展開コース」に分かれています。
採択されれば、開発や試験にかかる資金負担を抑えつつ、製品化のスピードを加速させられます。申請前には中核企業認定を取得する必要があるため、スケジュールを逆算した準備が重要です。補助金活用による開発支援と連携強化は、事業拡大と競争力向上につながります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 中核企業認定を受けた都内中小企業(1都10県に協力企業を有すること) |
| 助成対象経費 | 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、直接人件費、産業財産権出願・導入費 |
| 助成額・助成率 | 上限1,500万円/1/2以内(下限50万円) |
| 助成対象期間 | 交付決定日から最長2年間 |
| 助成コース | 技術提案コース/新事業展開コース(併願不可) |
| 申請方法 | GビズIDによるJグランツ電子申請(申請前に中核企業認定が必要) |
| 支援内容 | 協力企業探索、専門家派遣、公社コーディネーターによる伴走支援 |
| 留意点 | 助成金申請の1か月前までに中核企業認定を受ける必要あり |
販路開拓・マーケティング向け補助金
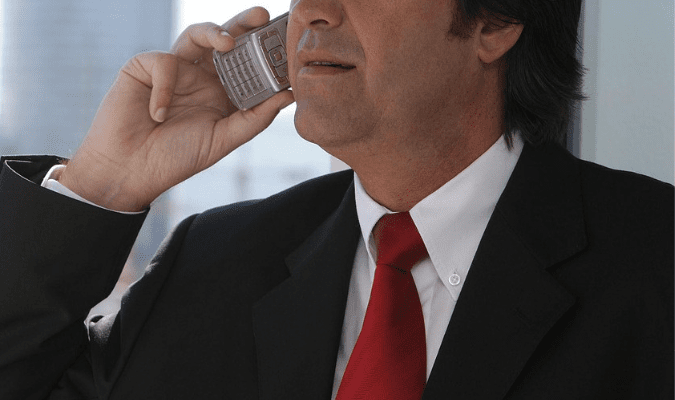
販路開拓や広告宣伝、展示会出展など、販促活動に特化した補助金が東京都では充実しています。自社製品や新サービスを市場へ届けたい中小企業にとって、プロモーション活動に必要な経費の支援は戦略的に不可欠です。
補助金を活用すれば、ECサイト構築や展示会出展などを自己資金に頼らず推進でき、早期の顧客獲得が可能となります。ここでは、販促支援に有用な主要制度を紹介します。
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(販路拡大助成金)
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(販路拡大助成金)は、脱炭素社会の実現を目指す都内中小企業を対象に、販路開拓に必要な経費の一部を助成する制度です。
対象となる事業者は、本店または支店で1年以上継続して事業活動を行う中小企業であり、自社製品として販売する権利を有するゼロエミッション関連商品を扱うことが条件となります。
助成対象経費には、国内外やオンラインでの展示会出展費、EC出店初期登録料、Webサイト制作や改修費、印刷物や動画制作費、広告掲載費などが含まれます。助成率は2/3以内、上限は150万円で、令和7年11月から最長1年1か月間の活動が対象です。
申請にはエントリー後、Jグランツでの電子申請が必要であり、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が求められます。採択されれば、販路拡大に向けた資金負担を軽減でき、環境配慮型商品の市場進出を加速させられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 都内に本店または支店を有し、1年以上事業活動を継続している中小企業 |
| 助成対象商品 | 自社が企画・製造・販売権を持つゼロエミッション関連商品(7分野に該当) |
| 助成対象経費 | 展示会出展費、EC出店初期登録料、Webサイト制作・改修費、印刷物・動画制作費、広告掲載費など |
| 助成額・助成率 | 上限150万円/2/3以内 |
| 助成対象期間 | 令和7年11月1日~令和8年11月30日(最長1年1か月) |
| 申請方法 | エントリー後にJグランツで電子申請(GビズIDプライム必須) |
| 申請期間 | 令和7年8月4日(月)10時~8月29日(金)17時 |
| 主な審査 | 資格審査・書類審査(経理審査を含む) |
また、動画制作を検討している方は、フォーズンへの依頼もおすすめです。
東京の動画制作・映像制作会社フォーズンは、中小企業から大手企業、BtoBからBtoCまで、様々な業種・用途での制作実績を有する東京の動画制作・映像制作会社です。
おすすめの動画・映像制作会社!比較や依頼に役立つ情報まとめといったお役立ち記事も配信しているので、ぜひご覧になってみてください。
シニア・福祉製品・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業
シニア・福祉製品・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業は、高齢者や障害者向けの製品やサービス、パラスポーツ・ユニバーサルデザイン関連製品などを展開する中小企業を対象に、販路開拓費用の一部を支援する制度です。
助成対象となる経費は、国内外やオンライン展示会の出展費用、EC出店初期登録料、Webサイト制作・改修費、印刷物や動画制作費、広告掲載費など幅広く設定されています。助成率は3分の2以内、助成上限は150万円で、採択されると販売促進活動の資金負担を大きく軽減可能です。
申請には事前エントリーが必要で、電子申請はJグランツを通じて行います。エントリーには公社ネットクラブ会員IDが必要であり、電子申請にはGビズIDプライムの取得が必須となります。
採択されると、展示会出展やEC展開などの販路拡大を効率的に進められ、製品やサービスの市場浸透が加速するでしょう。事前にスケジュールや対象経費を明確にし、募集要項を熟読することが成功の条件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 都内の中小企業で、自社が企画・製造し単独販売できるシニア・福祉・パラスポーツ・ユニバーサルデザイン関連製品・サービスを扱う事業者 |
| 助成対象経費 | 展示会出展費(国内・海外・オンライン)、EC出店初期登録料、Webサイト制作・改修費、印刷物・動画制作費、広告掲載費 |
| 助成額・助成率 | 上限150万円/3分の2以内 |
| 助成対象期間 | 第1回:令和7年8月1日~1年1か月以内、第2回:令和8年2月1日~1年1か月以内 |
| 申請方法 | 事前エントリー後にJグランツで電子申請(公社ネットクラブ会員ID+GビズIDプライム必須) |
| 申請期間 | 第1回:令和7年5月12日~5月30日、第2回:令和7年11月10日~11月28日(最終日17時締切) |
| 審査方法 | 資格審査および書類審査(経理審査を含む) |
業界特化・エネルギー対策などその他の東京都補助金

東京都では、医療・エネルギー・脱炭素など、特定分野や社会課題対応に特化した補助金も用意されています。これらの制度は、一般的な創業支援や設備投資補助金ではカバーしきれない分野に対応しており、対象となる事業者にとっては大きな後押しとなるでしょう。
ここでは、業界特化型やエネルギー負担軽減に関する代表的な補助金を紹介します。
第22回 医療機器産業参入促進助成事業
第22回 医療機器産業参入促進助成事業は、都内中小企業が医療機器分野に参入し、開発から事業化までを進める際に活用できる助成制度です。申請には、医療機器製造販売企業と都内ものづくり中小企業が連携し、臨床現場のニーズを踏まえた製品開発を行うことが求められます。
助成には事業化支援と開発着手支援の2区分があり、事業化支援では最大5,000万円、開発着手支援では最大500万円の助成を受けられます。助成率は2/3以内で、最長5年間の長期支援を受けられる点が特徴です。申請前には事前ヒアリングが必須であり、概要説明動画や申請書説明動画の視聴、チェックシートの提出を通じて申請要件を確認します。
採択されれば、試作・評価・臨床試験などの費用負担を軽減し、事業化までの道のりを大きく前進させられます。医療機器市場は参入障壁が高いため、この助成を活用することで資金リスクを抑えつつ、社会的価値の高い事業展開を実現できるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 医療機器製造販売企業+都内ものづくり中小企業の連携体 |
| 助成対象経費 | 医療機器等製品の開発~事業化に必要な経費(試作、評価、臨床試験など) |
| 助成額・助成率 | 事業化支援:上限5,000万円/2/3以内開発着手支援:上限500万円/2/3以内 |
| 助成期間 | 最長5年間 |
| 申請条件 | 事前ヒアリング必須、概要説明動画・申請書説明動画の視聴が必要 |
| 申請方法 | 事前ヒアリング後、Jグランツによる電子申請(GビズIDプライム必須) |
| 主な審査 | 書類審査、現地調査(事業化支援のみ)、面接審査 |
| スケジュール例 | 事前ヒアリング:令和7年7月23日~9月8日申請書提出:9月17日~10月1日面接審査:令和8年1月8日~1月16日交付決定:令和8年3月1日 |
第4回 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金
第4回 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金は、都内で工業用LPガスを使用する中小企業を対象に、燃料費の高騰による経営負担を軽減することを目的とした制度です。
支援金は1事業所あたり10万円で、設備導入や事業拡大を伴わない単純な燃料費補填として利用できます。申請はオンラインまたは郵送で受け付けられ、申請書類の提出後に審査を経て支援金が交付されます。
過去の交付実績がある場合、申請内容を再利用できる簡略化手続きも用意されている点も特徴です。申請対象となるのは、高圧ガス保安法に基づく工業用途でのLPガス使用事業者であり、飲食業や家庭用ガス利用は対象外です。
採択後は、事業所名や所在地などが公表される可能性があります。燃料価格変動の影響を受けやすい製造業や加工業にとって、この支援金は短期的な資金繰り安定化に有効な手段でしょう。申請期限が近づくと審査に時間を要する場合があるため、余裕を持った準備が推奨されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援対象者 | 都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業 |
| 支援金額 | 10万円/事業所 |
| 対象期間 | 令和7年4月~令和7年9月 |
| 申請期間 | 令和7年7月7日(月)~11月30日(日)23:59まで |
| 申請方法 | オンライン申請または郵送申請(当日消印有効) |
| 必要書類 | 申請書、工業用LPガス販売確認書、事業証明書類、身分確認書類など |
| 審査内容 | 書類審査(必要に応じて追加書類提出や現地調査あり) |
| 留意点 | 申請内容に不備や虚偽がある場合は審査中止や返還命令の可能性あり |
第4回 特別高圧電力価格高騰対策支援金
第4回 特別高圧電力価格高騰対策支援金は、東京都内で特別高圧電力を受電する中小企業を対象に、電力価格の上昇による経営負担を軽減することを目的とした支援制度です。特別高圧電力とは、契約電力が2,000kW以上かつ供給電圧が20kV以上の電力を指しますが、契約電力が2,000kW未満でも特別高圧契約であれば対象です。
直接受電する施設には1事業所あたり最大500万円、特別高圧電力を受電する施設のテナントとして入居する事業者には1事業所あたり10万円が交付されます。申請はオンラインまたは郵送で行うことができ、必要書類には申請書、電力契約確認書、事業証明書類などが含まれます。
過去の支援金交付実績がある場合、申請情報の再利用が可能であり、手続きが簡略化される点も利点です。燃料費や電力料金の高騰が経営に与える影響は大きく、支援金の活用によって短期的な資金繰り安定とコスト負担の軽減を図ることができます。申請は余裕を持って準備し、提出期限を遵守することが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援対象者 | 都内で特別高圧電力を受電する中小企業(直接受電またはテナント入居) |
| 支援金額 | 直接受電:500万円/事業所テナント入居:10万円/事業所 |
| 対象期間 | 令和7年4月~令和7年9月 |
| 申請期間 | 令和7年7月7日(月)~11月30日(日)オンライン:23時59分まで/郵送:当日消印有効 |
| 申請方法 | オンライン申請または郵送申請 |
| 必要書類 | 申請書、特別高圧電力契約確認書、事業証明書類、身分確認書類など |
| 審査内容 | 書類審査(必要に応じて追加書類提出や現地調査あり) |
| 留意点 | 虚偽申請は返還命令や違約金対象。関係書類は令和13年3月末まで保存義務あり |
グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業
グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業は、東京都内で再生可能エネルギー由来の水素(グリーン水素)を製造・利用する事業者を対象に、設備導入や関連工事費を全額助成する制度です。
グリーン水素は製造時にCO2を排出しないため、都市の脱炭素化とエネルギー安定供給の両立に貢献します。対象となるのは、登録されたモデルプランを導入する事業者で、製造設備の設置、関連する再エネ発電設備、配管や電気工事などの経費が助成対象です。
補助率は10/10で、ワンパッケージ型の大型設備で最大4億円、通常設備でも2億4,000万円の助成を受けられます。導入後は、発電量や製造量、利用先などを5年間報告し、普及啓発活動にも取り組む必要があります。
採択されれば、次世代エネルギー事業を低リスクで開始でき、脱炭素戦略や水素市場への参入を大きく前進させられるでしょう。設備メーカーとの連携により、さらなる技術開発の促進も期待できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象者 | 登録モデルプランを導入し、都内でグリーン水素を製造・利用する事業者 |
| 助成対象経費 | 設計費、設備費、工事費、諸経費(電気・水道・ガス工事負担金など) |
| 助成額・助成率 | 10/10(全額)ワンパッケージ型:上限4億円(10N㎥/h以上)ワンパッケージ型小型:上限3億3,000万円(10N㎥/h未満)その他大型:上限2億8,000万円その他小型:上限2億4,000万円 |
| 再エネ電力設備 | 水素製造能力1N㎥/hあたり720万円を乗じた額(上限5,400万円) |
| 助成対象期間 | 事業開始から令和8年3月31日まで(予算上限に達し次第終了) |
| 申請方法 | 郵送または持参、一部電子データ提出可 |
| 申請条件 | 製造水素は都内利用、ISO14687-2準拠、5年間の報告義務・普及啓発活動 |
| 公募期間 | モデルプラン:令和7年12月26日まで助成金交付申請:令和8年3月31日まで |
東京都補助金を確実に活用するための相談先
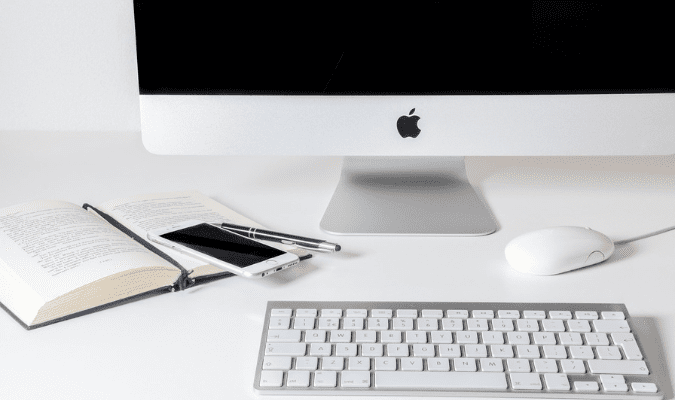
補助金の採択には、情報収集の正確さと申請書類の完成度が重要です。中小企業や個人事業主が自力で対応する場合、申請条件の解釈や必要書類の不備によって不採択となることもあります。
専門的な相談先を活用すると、最新情報の入手や申請書作成の精度向上が期待でき、結果として採択率向上につながるでしょう。ここでは、東京都で活用できる代表的な相談窓口やサポート機関を紹介します。
東京都中小企業振興公社や東京しごと財団の活用
東京都中小企業振興公社は、補助金や助成金の公募情報を公開し、個別相談や申請支援を行っています。公社の相談窓口では、募集要項の確認や対象経費の判断など、初歩的な疑問にも対応してもらえます。
また、東京しごと財団では、人材育成や働き方改革に関する補助金の申請支援を実施しており、研修プランや費用計画の作成に役立つでしょう。公的機関の相談窓口は信頼性が高く、最新情報の入手にも有効です。
活用にあたっては、事前予約や申請書の下書き持参が推奨されます。相談を通じて、自社に合った補助金の選定や計画作成がスムーズに進み、採択可能性の向上につながります。
認定支援機関や専門家に相談するメリット
認定支援機関や補助金申請の専門家に相談すると、事業計画書の作成精度が高まり、採択率が向上しやすくなります。とくに設備投資型や研究開発型の補助金では、事業の将来性や数値計画の説得力が重視されるため、専門的なアドバイスが効果的です。
支援機関は、公募要領の要件確認や必要書類の整理、採択後の実績報告まで幅広く対応します。専門家に依頼する場合は、着手金や成功報酬などの費用体系を確認し、サポート内容を明確にしておくと安心です。外部サポートを受けることで、自社リソースを営業活動や開発に集中でき、時間的・精神的な負担を減らせます。
採択率を高める申請サポートサービスの利用方法
民間の補助金申請サポートサービスを利用する方法もあります。これらのサービスは、申請書作成代行、採択率向上のためのアドバイス、事後報告サポートなどを提供しています。着手金0円・完全成功報酬型のプランを採用している事業者もあり、初期費用を抑えて専門支援を受けられる点が魅力です。
利用の際には、過去の採択実績やサポート範囲を確認し、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。採択率向上に直結するサポートを受けることで、補助金を有効に活用しやすくなります。資金調達や経営改善を加速させたい場合には、有力な選択肢となります。
まとめ
東京都の補助金は、創業期の開業資金から設備投資、販路拡大、省エネ、人材育成まで幅広くカバーしています。返済不要で活用できる資金として、経営改善や新規事業推進に直結し、資金繰りを安定させながら事業成長を加速させられます。補助金をうまく活用することで、自己資金だけでは難しい投資や新たな挑戦に踏み出しやすくなります。
株式会社イチドキリは、東京都内の中小企業を対象に補助金申請をサポートする経営革新等支援機関です。着手金0円・完全成功報酬型で、申請書類の作成から採択後の実績報告、事業計画のブラッシュアップまで幅広く対応します。
過去の採択実績も豊富で、初めての申請でも安心して任せられます。補助金を活用した資金調達や事業拡大を検討中の方は、専門家による個別アドバイスを受けてみてください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県西脇市出身。岡山大学教育学部出身。大手システムインテグレーターでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で副社長兼執行役員を務め、事業再構築補助金を活用した新規事業開発・立ち上げを担当。その後株式会社イチドキリを設立。現在は経済産業省(中小企業庁)認定の経営革新等支援機関として、システム開発に特化した補助金コンサルティング事業を運営。 2016年に「基本情報技術者試験」合格、2024年にGoogle認定資格「Google AI Essentials」、厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」取得。