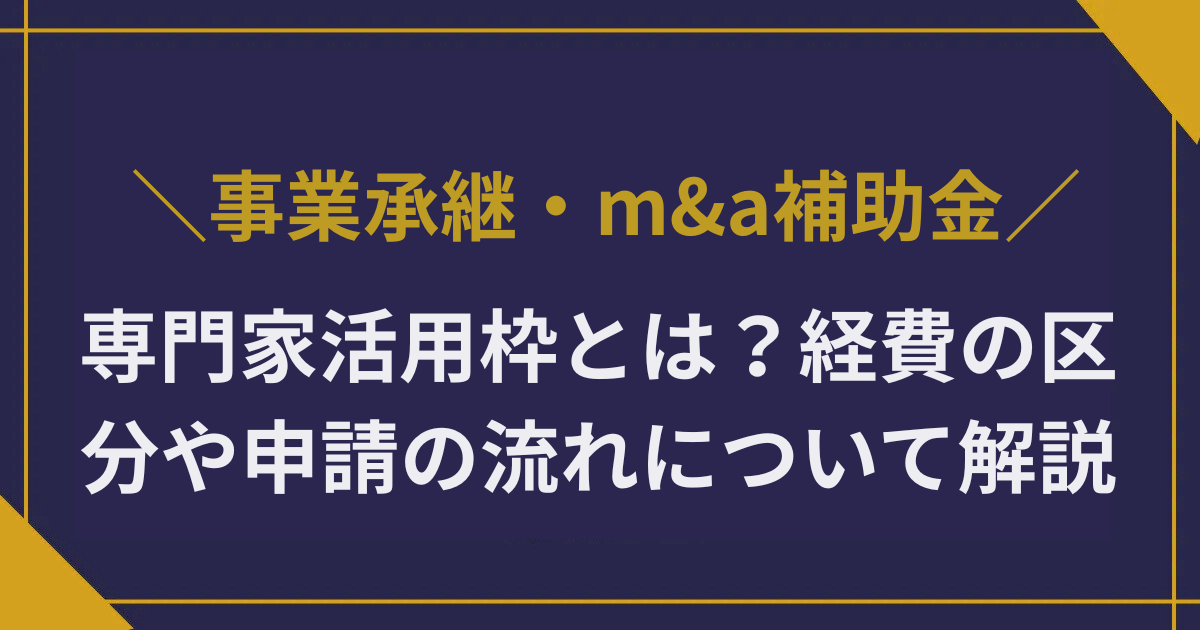中小企業の事業承継やM&Aを後押しする「事業承継・M&A補助金」。本記事では制度の全体像と専門家活用枠に焦点を当て、対象経費や補助率、申請スケジュール、他枠との併用可否まで実務に直結する要点を整理します。
買い手支援類型の100億企業特例、登録専門家の要件、契約締結の適正時期にも触れ、売り手支援型と買い手支援型の活用事例まで確認できる構成です。初めての方でも流れが掴めるようにgBizIDの取得やjGrants提出の留意点も示し、採択に近づく準備手順へ導きます。
- 事業承継・M&A補助金とは
- 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠とは
- 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠の経費の区分と上限額
- 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠のスケジュール
- 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠の事例
- まとめ
事業承継・M&A補助金とは

事業承継・M&A補助金は、事業承継や事業再編等に伴う設備投資や専門家費用、廃業費、PMI関連費用を支援する制度です。令和7年度の13次公募では「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4枠で実施されます。まず全体像を理解してから、自社に合う申請ルートを選ぶことが重要となります。
事業承継・M&A補助金の概要
本補助金は「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4枠で構成されます。承継前の設備更新からM&A時のFA・仲介・DD費用、成立後のPMI、やむを得ない廃業費までを段階別に支援します。
申請は原則電子申請(Jグランツ)のみで、gBizIDプライムの事前取得が必要です。補助率は1/2〜2/3以内、上限は枠と類型により150万円〜2,000万円まで幅があります。まずは自社のフェーズと費用計画を枠に合わせて整理します。
事業承継・M&A補助金の枠の種類
事業承継補助金は、目的や事業規模に応じて複数の枠に分かれています。主なものは「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI実行枠」「廃業・再チャレンジ枠」です。
承継促進枠は新しい事業展開を目的とする企業向け、専門家活用枠はM&A支援を専門家と連携して行う企業向けに設計されています。それぞれの枠で補助対象経費や上限額が異なるため、目的を明確にして最適な類型を選ぶことが大切です。

事業承継・M&A補助金の専門家活用枠とは
専門家活用枠は、M&Aを検討・実施する中小企業が、専門家の助言を受けながら事業引継ぎを進める際に活用できる制度です。M&Aは法務・財務・税務などの専門知識が必要であり、外部専門家の支援を受けることが成功の鍵となります。この補助金を利用することで、専門家への報酬や調査費用などの一部が補助され、負担を軽減しながら安心して取引を進められます。
専門家活用枠の概要
専門家活用枠はM&Aに際して仲介・FAや各種DDなど専門家の支援を受ける中小企業等の費用を補助し、事業承継や事業再編の円滑化を図る仕組みです。
補助対象は補助事業期間内に契約・発注・検収・支払まで完了した経費に限られ、証憑で確認できることが前提となります。M&Aの最終契約や基本合意の締結も期間内の専門家支援に基づく必要があり、手続の順序とエビデンス整備が採択後の要件管理の核心になります。
2つの支援類型と特例が存在する
枠組みは買い手支援類型(I型)と売り手支援類型(II型)の2本柱で設計されています。買い手支援は一律でDD実施を必須としており、売り手支援でも必要性があればDD計上が可能です。[
12次公募以降は買い手支援でPMI推進枠との同時申請が可能となり、過去の補助事業者も事業化状況報告を適正に行っていれば再申請ができます。さらにみなし大企業やみなし同一法人の対象外が明記され、適用可否の線引きが一層明確化しました。
買い手支援類型(I型)100億企業特例について
100億企業特例は将来売上100億円を目指す成長志向の中小企業向けの拡張枠です。上限は2,000万円で、1,000万円まで1/2、超過~2,000万円部分は1/3の補助率となります。
公募時点で「100億宣言」をポータルで公表し、DD実施、譲渡価額5億円以上、シナジーによる生産性向上見込み、地域雇用を牽引する事業見込み、承継従業員の3年以上の雇用維持などを要件とします。通常の買い手支援や売り手支援との同時申請や振替採択は不可であり、戦略と要件適合性の事前設計が鍵となります。
「登録専門家」と「契約締結時期」に留意する
仲介・FA費用はM&A支援機関登録制度の登録事業者に限り補助対象です。採択後の交付申請までに支援専門家の登録が完了している必要があり、未登録の場合は要件不充足となります。
専門家との委託契約は交付決定後の補助事業期間内での締結が必須で、交付前契約や遅滞的な終盤契約は不認定リスクが高まります。
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠の経費の区分と上限額

補助金を最大限活用するためには、どの経費が補助対象となるかを理解しておくことが重要です。対象経費は類型によって異なりますが、共通してM&A実務に必要な専門家費用が含まれます。上限額と補助率を把握し、自社の予算計画と照らし合わせて活用を検討することがポイントです。
補助対象になる経費の区分
対象は①補助事業の遂行に必要と特定できること②補助事業期間内に契約・発注・検収・支払が完了していること③証憑で金額と支払が確認できること、の全てを満たす経費です。仲介・FA費用はM&A支援機関登録事業者への委託のみ対象となります。
交付決定前の契約は不対象となります。PMIなどM&A後の統合費用は対象外です。DD費用は補助額ベースで原則200万円以内ですが、有資格者による財務・税務・法務など複数種を行う場合は種別ごとに200万円まで認められる場合があります。
補助率と上限額
買い手支援類型は補助率2/3以内、売り手支援類型は原則1/2以内で、営業利益率低下や赤字等の要件を満たすと補助上限を2/3へ引き上げ可能です。上限は事業費で600万円、買い手支援でDD上乗せを用いると最大800万円まで拡張できます。M&Aが未実現の場合の上限は300万円となり、買い手支援では原則DD費用のみが対象です。
売り手支援で廃業・再チャレンジ枠を併用する場合は廃業費を最大150万円まで上乗せ可能で、補助率は事業費の補助率に連動します。補助下限額は50万円であり、補助率に応じて75万円または100万円以上の対象経費で申請する必要があります。要件に合致する設計で上限活用を最適化してください。
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠のスケジュール

補助金申請は募集期間が限られており、申請準備には時間を要します。特に専門家契約やgBizIDの取得、見積書の作成には一定の期間が必要です。スケジュールを把握して早めに動くことで、申請漏れを防ぎ、採択の可能性を高められます。
13次公募の申請スケジュール
令和6年度補正予算では、13次公募として専門家活用枠の募集が実施されています。申請受付期間や採択結果の発表時期は中小企業庁および独立行政法人中小企業基盤整備機構の公式サイトで告知されます。申請に必要なgBizIDの取得は1〜2週間かかる場合があるため、早期の準備が推奨されます。事前に募集要項を入手し、書類の不備がないよう注意することが重要です。
申請の流れ
公募要領とWebサイトで要件を確認し、未取得ならgBizIDプライムを取得します。必要書類を整え、jGrantsの申請フォームに情報を入力し、添付資料をアップロードして提出します。差し戻しがあれば期限内に修正します。
採択後は交付申請を行い、交付決定後に専門家契約を締結し事業を開始します。補助事業は原則12ヶ月以内に実施し、検収・支払を完了させたうえで実績報告を提出します。確定検査を経て交付請求を行い、補助金が入金されます。
他の枠との併用について
事業承継・M&A補助金は複数の枠を持ちますが、同一の経費で他の補助金制度と重複して申請することはできません。ただし、異なる目的や費目であれば、他制度との併用が認められるケースもあります。たとえば、M&A支援費を本補助金で申請し、設備投資費を別の補助金で申請することが可能な場合があります。事前に併用可否を確認し、最適な資金計画を立てましょう。
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠の事例
実際の活用事例を知ることで、自社がどのようにこの補助金を活かせるかが具体的に見えてきます。ここでは売り手支援型と買い手支援型の2つのパターンを紹介します。
売り手支援型
売り手支援型では、事業承継やM&Aを通じて企業の存続と雇用維持を目的とする中小企業が補助金の対象となります。実際の事例では、経営者の高齢化や突発的な健康問題をきっかけに、地域経済や従業員の生活を守るため株式譲渡を選択したケースが多く見られます。
補助金を活用することで、M&A仲介会社や専門家への委託費用を補填し、譲渡プロセスを円滑に進められます。例えば、電子部品製造業では代表の病気を機に譲渡を決断し、地域の技術継承を実現しました。
また建設業や運送業では、従業員の雇用確保と取引先維持を重視した承継を行い、経営の安定化に成功しています。このように、売り手支援型は中小企業の事業継続と地域経済の維持に大きく貢献する枠組みといえます。
買い手支援型
買い手支援型は、M&Aを通じて新たな市場開拓や事業拡大を目指す企業が対象となります。専門家活用枠の補助金を利用し、買収検討からデューデリジェンス、契約交渉までの専門家費用を補填できます。実際の事例では、製造業が産業廃棄物処理業を承継し、木材事業のスケール拡大とコスト競争力の強化を実現しました。
また、スポーツ用品小売業では学校販売事業を引き継ぐことで、地域密着型の新たな販路を開拓しています。建設業では優秀な人材や技術を承継し、事業範囲の拡大を達成しました。これらのM&Aに共通するのは、シナジー効果の創出と地域経済・雇用の維持を両立している点です。補助金を活用することで、企業の成長戦略を加速させる有効な手段となります。
まとめ
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠は、中小企業が専門家の力を借りながら安全かつ戦略的に承継・買収を進めるための制度です。売り手・買い手を問わず、M&Aにかかる専門的な費用を軽減できる点が最大の魅力です。補助金の申請は準備期間が必要なため、検討段階から早めに専門家へ相談することが成功の第一歩です。補助制度を有効に活用し、次世代につながる強い経営基盤を築きましょう。
株式会社イチドキリは中小企業庁認定の支援機関。エンジニア出身の補助金プロが着手金0円・完全成功報酬で制度選定から計画・申請まで伴走します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
記事の執筆者

株式会社イチドキリ 代表取締役
徳永 崇志
兵庫県の実家で、競走馬関連事業を展開する中小企業を営む家庭環境で育つ。
岡山大学を卒業後、大手SIerでエンジニアを経験し、その後株式会社リクルート法人営業に携わる。株式会社レアジョブではAIを用いた新規事業の立ち上げに従事し、リリース1年で国内受験者数No.1のテストに導く。株式会社素材図書で役員を務めた後、株式会社イチドキリを設立。中小企業向けに、補助金獲得サポートや新規事業開発や経営企画のサポートをしている。Google認定資格「Google AI Essentials」を2024年に取得済。